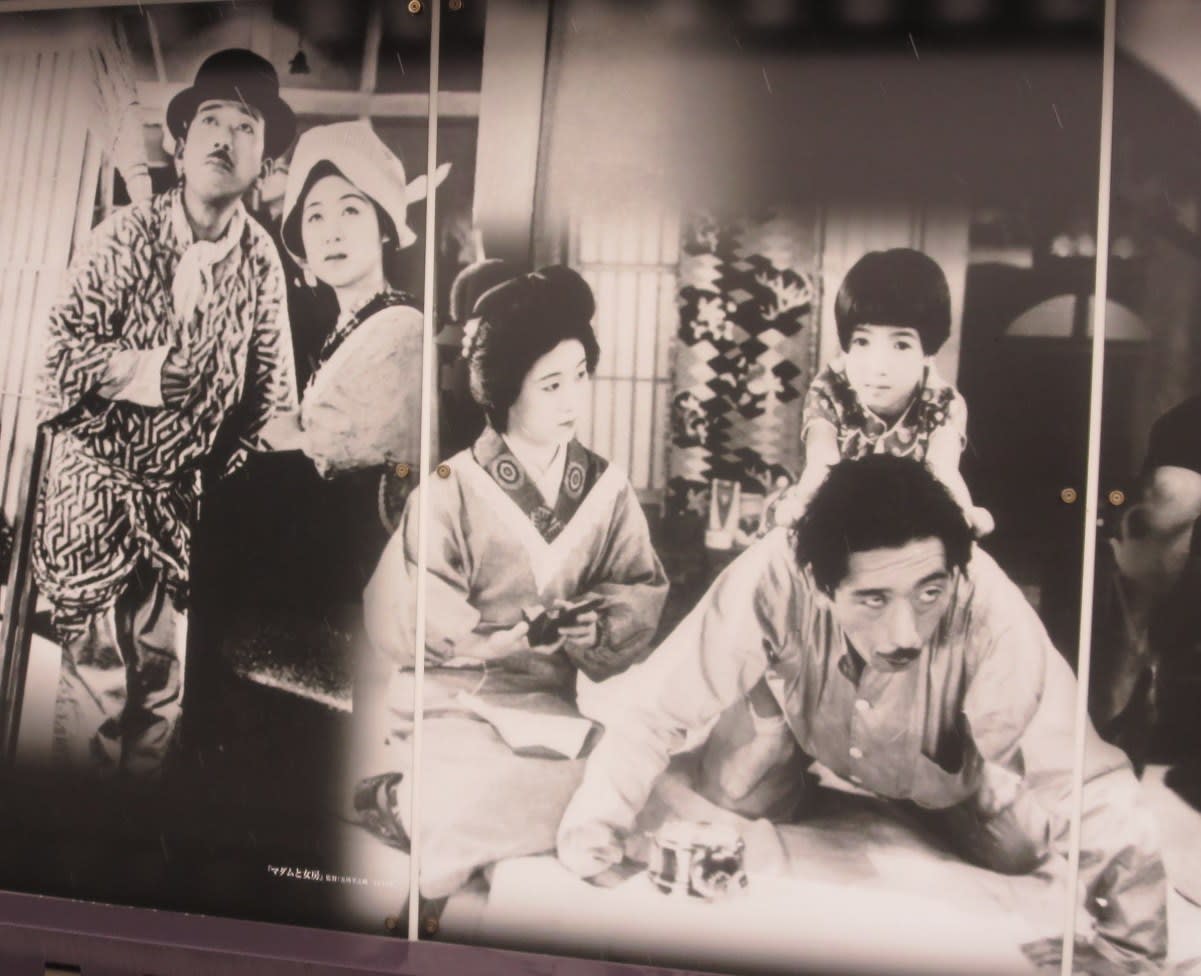五條で旗揚げして代官所を焼討ち、十津川郷士を仲間に引き込んで、総勢1500名程で高取城を攻めるも奪取に失敗、十津川村に退却して立て直しを図ったが叶わず、東吉野村への退陣を余儀なくされた天誅組の末路は如何に…

都の政変以後、逆賊と化した天誅組には、北から彦根藩、南から紀州藩、東から藤堂藩と三方から幕府追討軍が差し向けられ、組はやむなく東吉野村鷲家へ退却する。
今も往時の面影が残る鷲家口の街道筋、電柱さえなければ江戸時代さながらである。

幕府追討軍と壮絶な戦いを繰り広げた天誅組義士の墓は、東吉野村明治谷(みょうじだに)に多く残る。
石垣に沿った小さな墓石は往時東吉野村民が、天誅組を憐れんで葬った時のもの。

村民が建てた墓の前に、明治維新後天誅組の名誉が回復された後、建立された墓石がある。
村と縁もゆかりもない天誅組義士を、手厚く葬った東吉野村の人情はどのようなものだったろうか?

昔の街道は山頂付近の高地を通っていたため、明治谷墓地へは猛烈な急登となる。

幕府追討軍:彦根藩の本陣が置かれた“いかり屋”。
この付近で岡山藩脱藩:藤本鉄石が戦死。果敢に敵陣へ攻め込ん果てたと云う。

いまは「ゆうちょ」になっているこの建物には、幕府追討軍:津の藤堂藩の本陣が置かれた。
この付近で愛知刈谷藩脱藩:松本奎堂が戦死した。
最後は目の見えぬ状態でさまよっているところを討たれた。

土佐藩脱藩:吉村寅太郎は高取城攻めの時、誤って味方の鉄砲で被弾、駕籠でこの地まで逃れてきたが、追討軍の手によって斬首された。
こうして天誅組を主導した3総裁は東吉野村で終焉を迎えた。
弱冠19歳の公家出身の大将:中山忠光は、追討軍の手薄な大阪方面へ逃れた。伴するものは僅か十数人だったと云われる。こうして維新の先駆け天誅組事件は終焉を迎えた。




































































































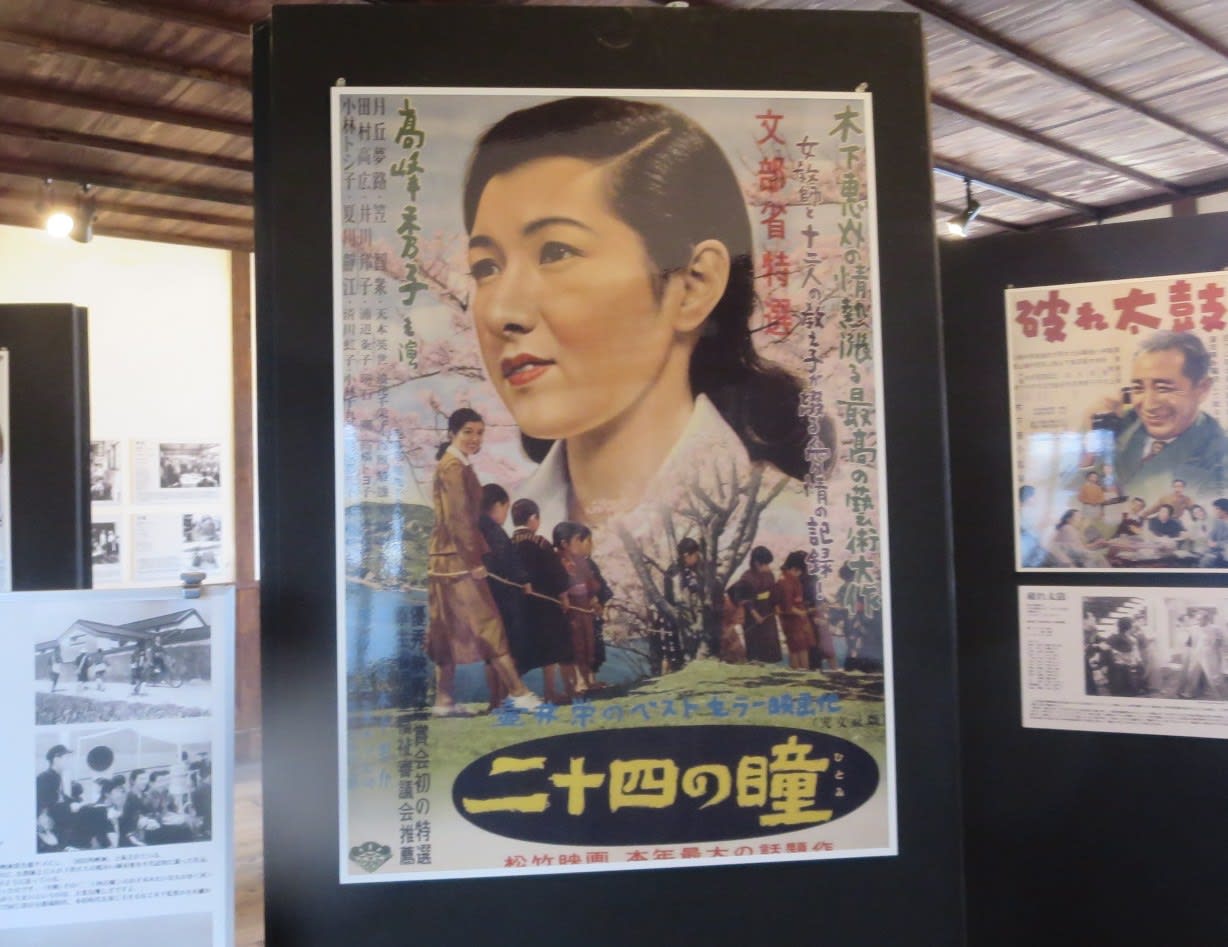




 」と歌われた。
」と歌われた。