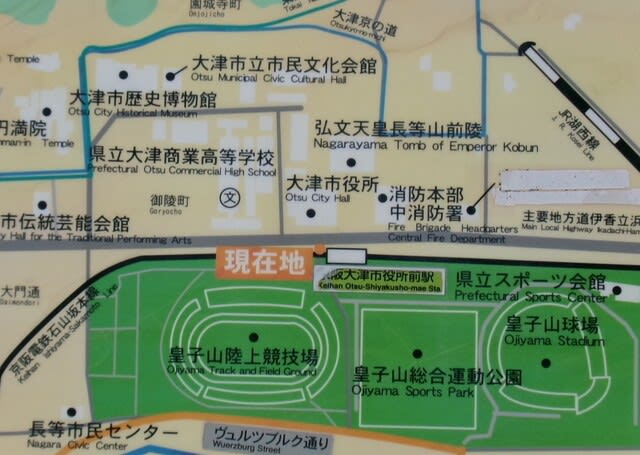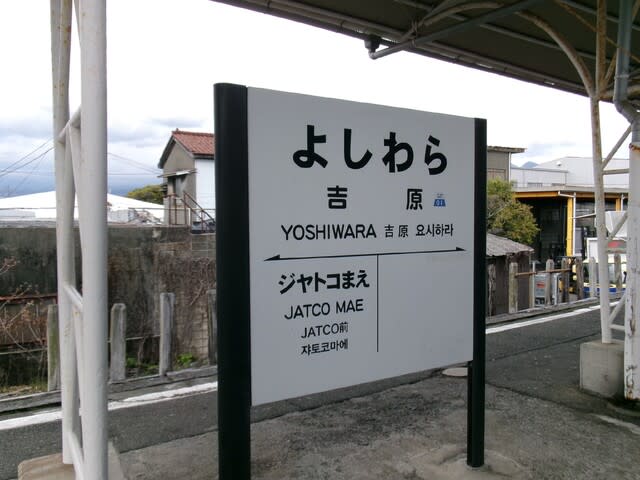薄紫の儚さが漂う藤の花。

強固な藤棚に支えられて保護されています。

長~い房が垂れ下がって、手招きをしているように見えませんか?

長閑な山並みを背景に、「近寄って良~く見てください」と訴えているようです。

一口に藤と言っても、多くの品種があるようで、それぞれに咲き方が違って見えます。

根元は立ち入り禁止となっているので、近くで見える花は多くはありません。

薄曇りの空は格好の引き立て役ですね。

四方八方へ枝をいっぱいに広げて、雄姿を誇示します。

花の形も様々に変化していくのでしょう。
色合いも多様で見る者を飽きさせません。

豪華絢爛、藤娘が根元に立てばさぞかし・・・

あまりにに伸びやかで、フレームに収まり切れない。

これは異種か?ピンクに近い豪華な一房。

可憐な純白の花びらもありました。

地元の方によると、木が老化しているので、年々花房が短くなっていくようだと語っていました。
幹が複雑にくねっている様子をご覧ください。

来年も頑張ってね! エールを送りながらその場を離れました。





























 「菜の花畑に 入日薄れ 見渡す山の端 霞み深し・・・」
「菜の花畑に 入日薄れ 見渡す山の端 霞み深し・・・」