先月の記事に書いた「死を哲学する」の著者=中島義道は、人を尊敬することが苦手ではないかと思うのですが、その師の大森荘蔵(1921~1997)に対しては、同書の中で深い敬意を滲ませています。
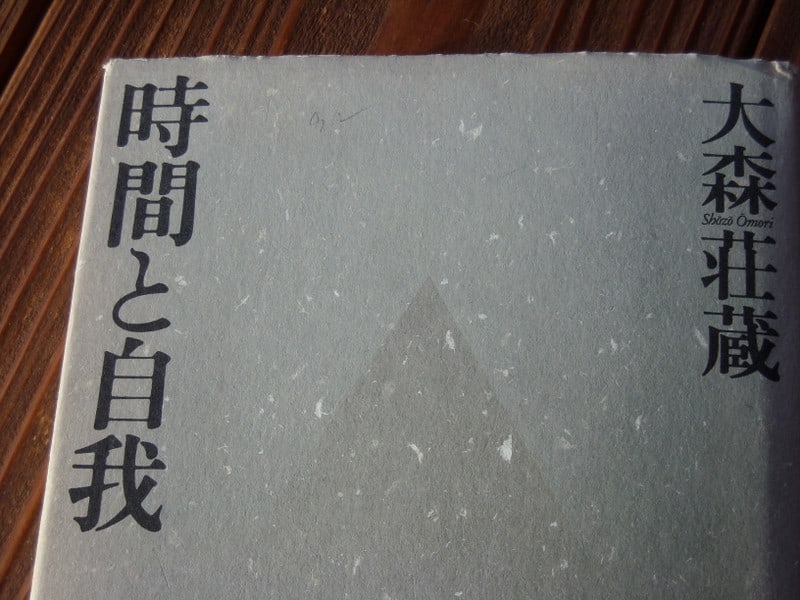 県立図書館から大森荘蔵著「時間と自我」(青土社)を地元の公民館図書室に取り寄せてもらい、借りました。(旧八郷町が先年、石岡市に合併して八郷の名が表舞台から消えたのは誠に残念でしたが、ただ一つ良かったのは、こうした図書取り寄せシステムが機能するようになったことです。)
県立図書館から大森荘蔵著「時間と自我」(青土社)を地元の公民館図書室に取り寄せてもらい、借りました。(旧八郷町が先年、石岡市に合併して八郷の名が表舞台から消えたのは誠に残念でしたが、ただ一つ良かったのは、こうした図書取り寄せシステムが機能するようになったことです。)
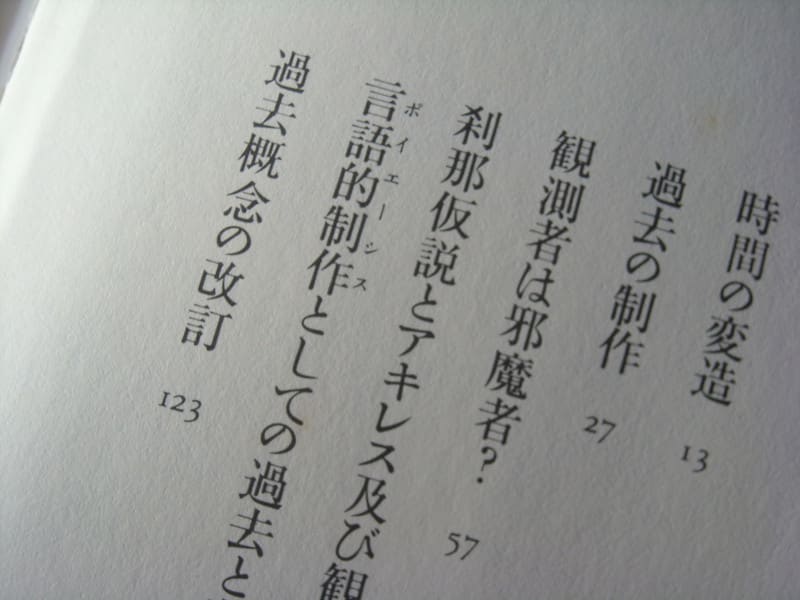 こむずかしいそうなテーマにも拘らず、見事に明快な論理と文章表現力のおかげで、意外に読みやすい本でした。
こむずかしいそうなテーマにも拘らず、見事に明快な論理と文章表現力のおかげで、意外に読みやすい本でした。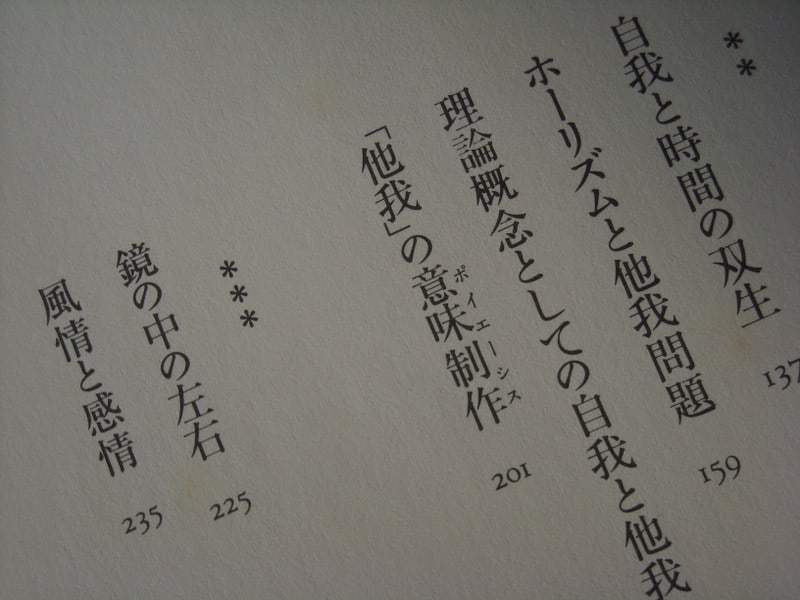
哲学上の問題が・・過去・現在・未来とは何を意味しているのか、人は他人ではないのに何故他人の気持が分かるのか等が・・いわば現実の俎上に引き据えられて、知の高みから捌かれたような読後感があります。痛快とも言える一方、妙に索漠とした気分にもさせられました。
巻末近くになって、オヤ・・と思わせられる部分(P.246)がありました。(文中の「風情」を、著者は「ふうじょう」と読ませています。)
・・音楽の与える風情を音の空間的抽象運動だとみるならば・・その抽象的運動が何かの形で無限に向っての進行であるとき・・人は崇高とでも呼びたいような感動に捕えられるのである。・・視覚においても・・空間的無限が知覚されたり示唆されたりするとき、音楽の感動に類似した感動が与えられる。
これら空間的無限が与える感動と好一対をなすのは遠い昔、遠い過去の想起の中の風情が時間的無限を示唆することで生じる「懐しさ」の情動であろう。
空間的にせよ、時間的にせよ、人が辛うじて無限と接触するとき、現世には珍しい情感に触れるのではないだろうか。それは一言でいえば、世界の無限性に打たれる、ということである。
無限に触れて感動する、というのは、折々に聞かれることではあります。しかし大森荘蔵がそれを語るとなると、聞き捨てにすることは出来ません。このページで大森荘蔵は、「無限」に対して(不用意な、と言って悪ければ)無条件的な「信」を告白しているように、私には思えます。
大森荘蔵にとって無限とは、どういう意味なのでしょう。 それは、言葉でありながら言葉を超えようとするものであり、語り得ないことなのでしょうか・・・









