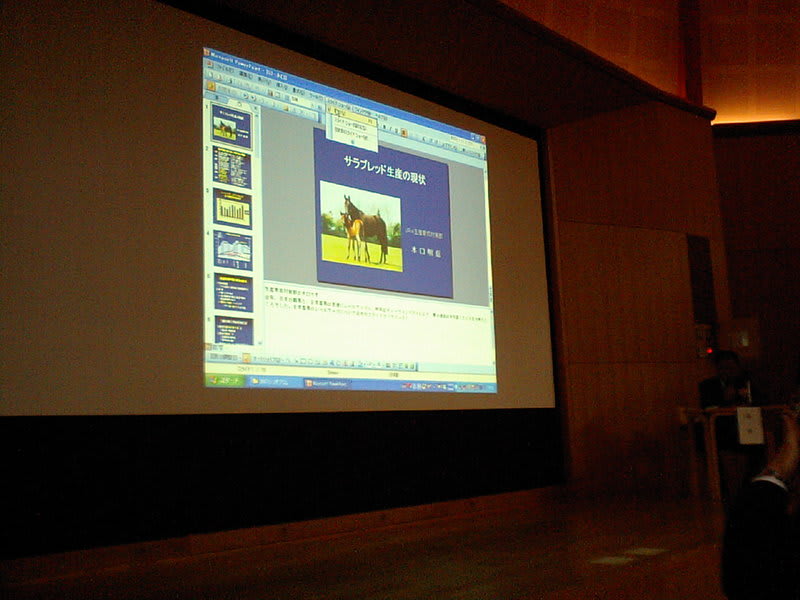ながながとウマ科学会シンポジウム「生産技術を考える」で話した内容を書いている。
ながながとウマ科学会シンポジウム「生産技術を考える」で話した内容を書いている。
まあ、生産地の方で「そんなことよく知っている」という方は読み飛ばしていただきたい。
運動器疾患もけっこうある。
競馬場やトレセンでの診療では、全体の約半数が運動器疾患、ついで疝痛(消化器疾患)だそうだ。
それに比べると、生産地の疾患がいかにバラエティーに富んでいることか。
-
たとえば育成馬の飛節軟腫。
脛骨や距骨の離断性骨軟骨症OCDであることが多い。
X線撮影して関節内に骨軟骨片が見つかると関節鏡手術してそれを取り出すことになる。
関節鏡手術を始めた頃は、軟腫が自然に解消しないか待つだけ待ってから手術をしていたが、今は牧場や馬主さんや調教師さんが「さっさと手術してくれ」と言うようになった。
競走成績まで含めた予後は良好だと思っている。
OCDもDOD(成長期の整形外科的疾患)のひとつだが、もちろんDODへの対応も生産地の獣医師の仕事の一つ。
-
 生産地での馬の死因は、骨折、腸捻転、分娩事故、新生児死で、なかでも骨折はたいへん多い。
生産地での馬の死因は、骨折、腸捻転、分娩事故、新生児死で、なかでも骨折はたいへん多い。
馬が致命的な骨折をすると助けるのはなかなか難しい。
しかし、体重が少ない子馬や、治った後に競走能力を要求されない繁殖雌馬や種雄馬は、骨折治療の対象になる可能性が高い。
だいじな馬を1頭1頭助けることも生産地の獣医師が求められていることではある。
(つづく)
今日は競走馬の Tieback & Ventriculocordectomy 喉頭形成・声嚢声帯切除手術。
その後、高齢の繁殖雌馬の披裂軟骨炎。
呼吸障害がひどいので、緊急に永続的気管切開をした。(右;クリックすると大きくなりますが、頚の部分で気管に![]() 穴 が開いている写真です。馬を押さえていた人は倒れてしまいました。見たくない人はクリックしないように。)
穴 が開いている写真です。馬を押さえていた人は倒れてしまいました。見たくない人はクリックしないように。)
こいつのおかげで今日は昼食ぬき。
その後、競走馬の橈骨剥離骨折の関節鏡手術。
合間に、1歳馬の外傷。
-
もう片付けなければならないだろう。