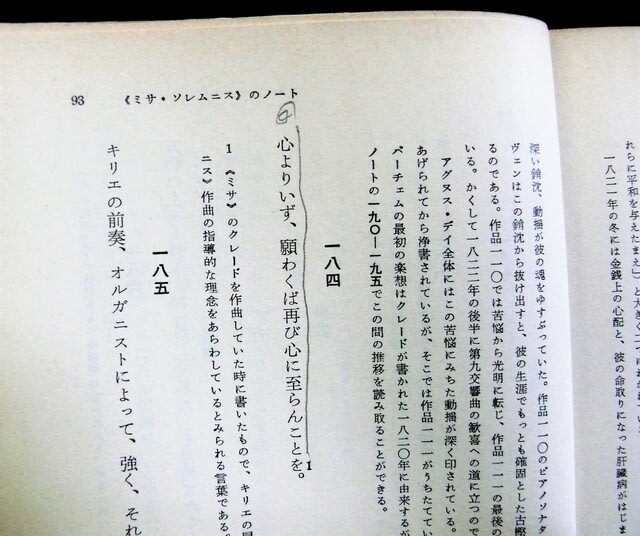<3802> 写俳二百句(141) ヘビイチゴ
蛇苺葉っぱ見る癖いつからか




自選による池田澄子100句の「自句自解」の中に「蛇苺いつも葉っぱを見忘れる」という句が見える。この句を目にしたときはっとした。というのは、私のヘビイチゴに対する見方が花や実もさることながら葉を必ず見るという癖があるからで、この句によってこの無意識とも思える癖に気づかされたからである。ということで、冒頭に掲げた句が生まれたという次第である。
では、この癖は何故、そして、いつごろからかとなるが、思うにそれは山野の草木の花に魅せられ、出かけて写真を撮るようになってからである。草木にはよく似た紛らわしいものがあって間違いやすい。で、観察をより正確にしなければならず、葉にも目を向けるようになったことによる。もちろんヘビイチゴだけではないが、ヘビイチゴでは葉を見ることが癖のごとく普通になった。
なお、ヘビイチゴと名のつくものには、ほかにもヤブヘビイチゴ、ヒメヘビイチゴ、オヘビイチゴが一般によく知られる。加えて、ヘビイチゴによく似て紛らわしいものにキジムシロとミツバツチグリがある。ヘビイチゴとヤブヘビイチゴはヘビイチゴ属の仲間であるが、ヒメヘビイチゴとオヘビイチゴはキジムシロ属で、キジムシロやミツバツチグリの仲間である。ということは、その名に「ヘビイチゴ」とあるが、ヒメヘビイチゴとオヘビイチゴはヘビイチゴとは別種であるということになる。
これらはみな黄色の花と赤い実をつけ、花や実だけでは見分けがつき難い。そこで違いのある葉や花に付随する萼なども加えて見分けるということになる。そして、ここにはヘビイチゴの認識において悩ましい問題が生じて来る。文芸の分野では許容されるが、植物研究における観察の立場では許容出来ないという差異が生じることである。
因みに自解では「一度、摘んでみたいと思いながら実行できていない蛇苺。草叢に赤い実はよく目立つから見ない年はないと言ってよさそう。可愛いなあといつも思って通り過ぎる。ある日ふと、葉っぱを意識したことがなかったこと気付いた。人間の注意力はこんな程度らしい。殆どのモノやコトに気付いていないことにさへ気が付いていないのである。そのことを一句に留めるために、蛇苺の葉に代表になってもらったわけだ」と述べられている。
これは自分が普段如何に注意深さに欠け、物事を意識にかけず見過ごしているかをヘビイチゴの葉っぱをもって句の中に忍ばせているということになる。何か哲学的で、この自解を読んだとき、「ものを認識するには自己の方になにかがなければならぬ。なにかがあるから、むこう側のなにかが分かるのである」という梅原猛の『古典の発見』の言葉が思い出されたのであった。
「なにか」は注意深く見過ごさずにものごとに対し、意識するということの積み重ねによって得ることが出来る。感性だって同じことだろう。ということなどが思い巡らされたのであった。 写真は左から花期のヘビイチゴ、オヘビイチゴ、キジムシロ、ミツバツチグリ。みな春の花で、花だけでは見分けが難しい。しかし、花に葉を加えて見比べると案外簡単に見分けられる。自解の句にヘビイチゴの葉を持ち出しているところは、ヘビイチゴにこういう紛らわしく悩ましい問題のあることを本人は熟知していたのだと思われる。