天王星84年周期として、以前から指摘していることだが、現在は太平洋戦争前夜であり、和歌が流行する。
太平洋戦争前から終戦にかけて短歌が大流行していた。国粋主義による記紀や萬葉への傾倒も大きかったのだろう。戦時中、婦人動員で軍関係に勤務していた人から聞いた話では、休憩時間の楽しみと言えば、上司の軍人を含め、即興の句会をすることだったそうだ。
ドナルドキーンが日本文学に傾倒した大きな切っ掛けは、戦死した日本兵の多くが万葉集を携帯していたことだという。
先日、NHKでSNS上の若者の短歌ブームを特集していた。コロナ禍による若者の疲弊に短歌が癒やしとなっていることに焦点を当てていたが、それに意義はないものの、歴史的観点からは、いささかもの足りない。始めから恣意的にコロナに結びつけている。
コロナは一つの切っ掛け、事象、テーマではあるものの、それが短歌でなければならない理由にはならない。
コロナの無い80年前にも短歌がブームだったことにこそ、短歌でなければならない理由がある。
出演していた歌人は、「短歌で皆が優しくなれる」と話していた。これも全くその通りだと思う。
短歌が流行る時代の共通点は、「ものの言えない社会」だ。「優しくない社会」があるから、短歌でしかものが言えない。
戦前戦中の軍による言論弾圧とそれに同調する世間の抑圧の中で、その当事者をも含め、思いの丈を漏らす語法は短歌でしかなかった。
閉塞のただ中
失われた30年で生まれた閉塞状況は、失敗を恐れ萎縮する大人と、その教育によって手足をもがれて盆栽化した若者が、ネットによる自警団を形成し、少しでも異質な言動をピラニアのように集って抹殺する、言葉狩りと相まって、戦前以上の警察国家になっている。
短歌は日常会話から離れた異空間の独白だ。直接誰かに話しかける言葉ではないから、聞いた人も、その独白に直接攻撃できない。短歌には短歌で返さなければ空振りする。
直接ものが言えない独裁者には、比喩的に意見を述べるが、それでも命がけだ。京都人の「いけず」な会話も、外来の権力者への、「当たり障り」を避ける伝統で、直接会話しか出来ない人々は理解も反論もできず、「何か知らん腹が立つ!」と言うことになる。これも伝統の京都だ。
もともと和歌は、言いにくい思いを伝える口説き手段として、歌垣などで歌われたものだから、相手を怒らせない機能がある。和歌のみならず、歌は独自空間の中にあるので、中に入れば理解し合えるが、直接相手を刺激しない。宗教のような世界だ。
告白して断られれば、お互いに辛いが、歌に歌で答えれば、角は立たない。
SNS上に直接考えを上げれば、攻撃される場合でも、和歌の衣を着て上げれば、解釈のクッションがあるので、攻撃できない。
冷静なコミュニケーションが出来るツールとしての短歌は、素晴らしい伝統だが、一方で、直接考えを表明することが避けられる文化でもある。
そして、その文化が周期的に呼び起こされることは、「ええじゃないか」同様に、日本人が、自ら閉塞社会に落ち込んでいく性を持っていることの証しだろう。











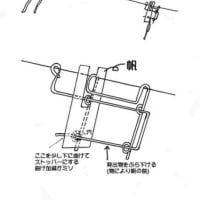






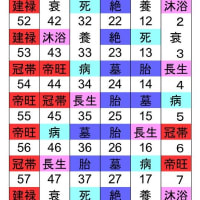
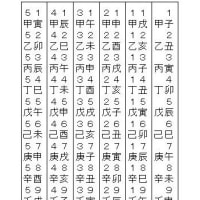
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます