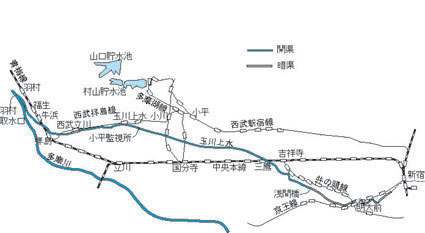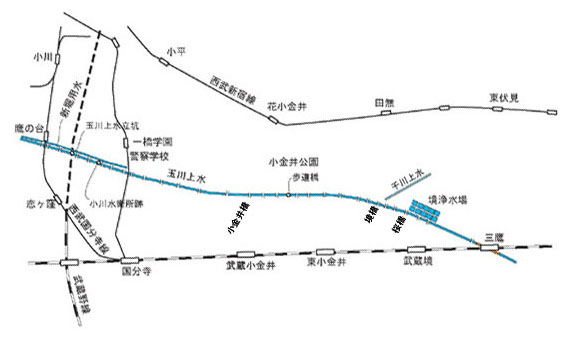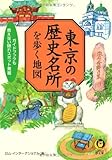本年の初詣は、先日2016年初詣・大國魂神社に書いたとおり、1月2日に府中の大國魂神社に詣でました。そのとき、昨年のお守りや破魔矢などをお焚き上げで納めるのを忘れていました。
1月4日、事務所は定休日ですが、仕事がたて込んでいたので休日出勤と相成りました。そこで、出勤の途上で、わが家の氏神である和泉熊野神社に詣で、お焚き上げを納めてくることにしました。
《和泉熊野神社》
和泉熊野神社は、神田川沿いにあります。神田川と井の頭通りの交点からほんの少し下流に進んだところです。


和泉熊野神社はウィキによると、
『社伝によれば、文永4年(1267年)に紀州の熊野神社の分霊を祀ったのが当神社の創建である。』
とのことです。
勤務する事務所は荻窪駅の近くであり、昼休みに歩いて巡れるご近所には3つの神社があります。4日の昼休み、これら3つの神社もお参りしてきました。
《天沼八幡神社》


天沼八幡神社はウィキによると、
『旧天沼村字中谷戸の鎮守で天正年間(1573年 - 1591年)の創建と伝えられている。』
とあります。
境内ではちょうど、巫女さんと小さな子供が楽しそうにお話ししていました(下写真)。

《天沼熊野神社》


天沼熊野神社は、荻窪駅からは一番遠く、北東方向にあります。ウィキによると、
『社伝によれば神護景雲2年(768年)に東海道巡察使が武蔵国に来たときに、氏神を勧請し別当を置いたのがはじまりと伝えられている。また別の説では、元弘3年(1333年)に新田義貞が北条高時を討つために鎌倉へ軍を進める途中、当地に布陣し、社殿を創設したとも伝えられている。』
とあります。

本殿の左に大きな切り株が鎮座しています。ウィキには、『境内には、直径2mにも及ぶ大杉の切株がある。これは社伝によれば、この大杉は新田義貞がこの地に陣をしいた際、戦勝を祈願して手植えしたものと伝えられている。近隣の古老達はこの杉を『心願成就の杉』などと呼び大切にしてきたが、昭和17年(1942年)に枯死したため伐採され、今では切り株のみが残っている。』と記されています。
《荻窪白山神社》
荻窪駅の北側、JRと平行に走る商店街は「白山通り」と名付けられています。その名の由来は、この商店街の西にある白山神社です。


入口の鳥居をくぐると(左上写真)、北に向かって木々の下を参道が延々と続きます(右上写真)。やっと本殿が見えてきました(下写真)。


荻窪白山神社はウィキによると、
『旧下荻窪村の鎮守。当神社の創建は、社伝によると文明年間(1469年~1486年)に関東管領上杉顕定の家来中田加賀守が、屋敷内に五社権現社を奉齋したのにはじまる。』
とあります。
こうして、1月2日の大國魂神社に続き、1月4日には和泉熊野神社、天沼八幡神社、天沼熊野神社、荻窪白山神社を巡り、お参りしてきました。
1月4日、事務所は定休日ですが、仕事がたて込んでいたので休日出勤と相成りました。そこで、出勤の途上で、わが家の氏神である和泉熊野神社に詣で、お焚き上げを納めてくることにしました。
《和泉熊野神社》
和泉熊野神社は、神田川沿いにあります。神田川と井の頭通りの交点からほんの少し下流に進んだところです。


和泉熊野神社はウィキによると、
『社伝によれば、文永4年(1267年)に紀州の熊野神社の分霊を祀ったのが当神社の創建である。』
とのことです。
勤務する事務所は荻窪駅の近くであり、昼休みに歩いて巡れるご近所には3つの神社があります。4日の昼休み、これら3つの神社もお参りしてきました。
《天沼八幡神社》


天沼八幡神社はウィキによると、
『旧天沼村字中谷戸の鎮守で天正年間(1573年 - 1591年)の創建と伝えられている。』
とあります。
境内ではちょうど、巫女さんと小さな子供が楽しそうにお話ししていました(下写真)。

《天沼熊野神社》


天沼熊野神社は、荻窪駅からは一番遠く、北東方向にあります。ウィキによると、
『社伝によれば神護景雲2年(768年)に東海道巡察使が武蔵国に来たときに、氏神を勧請し別当を置いたのがはじまりと伝えられている。また別の説では、元弘3年(1333年)に新田義貞が北条高時を討つために鎌倉へ軍を進める途中、当地に布陣し、社殿を創設したとも伝えられている。』
とあります。

本殿の左に大きな切り株が鎮座しています。ウィキには、『境内には、直径2mにも及ぶ大杉の切株がある。これは社伝によれば、この大杉は新田義貞がこの地に陣をしいた際、戦勝を祈願して手植えしたものと伝えられている。近隣の古老達はこの杉を『心願成就の杉』などと呼び大切にしてきたが、昭和17年(1942年)に枯死したため伐採され、今では切り株のみが残っている。』と記されています。
《荻窪白山神社》
荻窪駅の北側、JRと平行に走る商店街は「白山通り」と名付けられています。その名の由来は、この商店街の西にある白山神社です。


入口の鳥居をくぐると(左上写真)、北に向かって木々の下を参道が延々と続きます(右上写真)。やっと本殿が見えてきました(下写真)。


荻窪白山神社はウィキによると、
『旧下荻窪村の鎮守。当神社の創建は、社伝によると文明年間(1469年~1486年)に関東管領上杉顕定の家来中田加賀守が、屋敷内に五社権現社を奉齋したのにはじまる。』
とあります。
こうして、1月2日の大國魂神社に続き、1月4日には和泉熊野神社、天沼八幡神社、天沼熊野神社、荻窪白山神社を巡り、お参りしてきました。