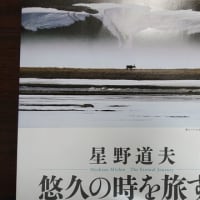菅首相は就任の際、国民に「先ずは自助を」と求めました。これを承け、今日の朝日新聞朝刊に3名の方の意見が掲載されました。その中のひとり、NPO法人「暮らしネット・えん」代表理事を務める小島美里さんの言葉が目に留まりました。
「私たちは健康、職業、受け継いだ資産など色々な要素によって支えられているから自立・自助できる。どれかを持っていなかったり、失ったりすることは『自己責任』ではないはずです。何かの要素を失っても、代わる支えさえあれば自立できる。『自立のための支援』を誰もが受けられる社会にして欲しいと願います。」
私は総理の「自助」発言があった時、「さぼってないで頑張れよ」みたいな性悪説に近い見方を感じました。でも、頑張っているんだけど大変な人は結構いるんじゃないかと思います。例えば、このコロナ禍の下、苦しんでいる大学生は多く、「高等教育無償化プロジェクトFREE」の調査によると5人にひとりが学業の断念を考えているそうです。
「高等教育無償化プロジェクトFREE」代表の岩崎詩都香さんはこう言っています。
「学生は、コロナ禍によって突然困窮したわけではありません。授業料などの学費を稼ぐためにアルバイトをしたり、多額の奨学金を借りたりしている状況がもともとあった。そのうえにコロナ禍が起き、アルバイトをがんばることさえ許されなくなりました。国立大学の授業料の標準額は53万5800円で、半世紀前と比べて45倍くらいに上がっています。私立は平均で100万円近い。一方、非正規雇用が増えたりして、高い学費を負担できる家庭は少なくなっている。そのため、自分の稼ぎだけで学費を出している学生は少なくないし、稼ぐために休学している人もいます。アルバイト漬けで体を壊したり、学業に専念できなかったりするのは本人にとってももったいないし、社会にとっても損です。」

こういった学生に「自助」を求めるのは酷でしょう。「共助」と言っても、家族も疲弊しています。そもそも「共助」があれば「自助」が強く求められることはなく、最低限の生活水準の維持においては順番が逆ではないかと思います。「がんばることさえ許されな」い現状があるから、小島美里さんの言葉は説得力があります。
「はたらけど はたらけど猶 わが生活(くらし) 楽にならざり ぢつと手を見る」
石川啄木の有名な歌です。働いても働いても、なお、ギリギリで生きている人たち、そんな人に「先ずは自助を」と突き放すような社会にならないことを願います。
「私たちは健康、職業、受け継いだ資産など色々な要素によって支えられているから自立・自助できる。どれかを持っていなかったり、失ったりすることは『自己責任』ではないはずです。何かの要素を失っても、代わる支えさえあれば自立できる。『自立のための支援』を誰もが受けられる社会にして欲しいと願います。」
私は総理の「自助」発言があった時、「さぼってないで頑張れよ」みたいな性悪説に近い見方を感じました。でも、頑張っているんだけど大変な人は結構いるんじゃないかと思います。例えば、このコロナ禍の下、苦しんでいる大学生は多く、「高等教育無償化プロジェクトFREE」の調査によると5人にひとりが学業の断念を考えているそうです。
「高等教育無償化プロジェクトFREE」代表の岩崎詩都香さんはこう言っています。
「学生は、コロナ禍によって突然困窮したわけではありません。授業料などの学費を稼ぐためにアルバイトをしたり、多額の奨学金を借りたりしている状況がもともとあった。そのうえにコロナ禍が起き、アルバイトをがんばることさえ許されなくなりました。国立大学の授業料の標準額は53万5800円で、半世紀前と比べて45倍くらいに上がっています。私立は平均で100万円近い。一方、非正規雇用が増えたりして、高い学費を負担できる家庭は少なくなっている。そのため、自分の稼ぎだけで学費を出している学生は少なくないし、稼ぐために休学している人もいます。アルバイト漬けで体を壊したり、学業に専念できなかったりするのは本人にとってももったいないし、社会にとっても損です。」

「5人に1人退学検討」の危機:【SDGs ACTION!】朝日新聞デジタル
困窮する学生への支援を訴えてきた「FREE」。コロナ禍で学生の状況は一層深刻になっています。「高等教育の意味」を問い直すよう訴えています。
【SDGs ACTION!】朝日新聞デジタル
こういった学生に「自助」を求めるのは酷でしょう。「共助」と言っても、家族も疲弊しています。そもそも「共助」があれば「自助」が強く求められることはなく、最低限の生活水準の維持においては順番が逆ではないかと思います。「がんばることさえ許されな」い現状があるから、小島美里さんの言葉は説得力があります。
「はたらけど はたらけど猶 わが生活(くらし) 楽にならざり ぢつと手を見る」
石川啄木の有名な歌です。働いても働いても、なお、ギリギリで生きている人たち、そんな人に「先ずは自助を」と突き放すような社会にならないことを願います。