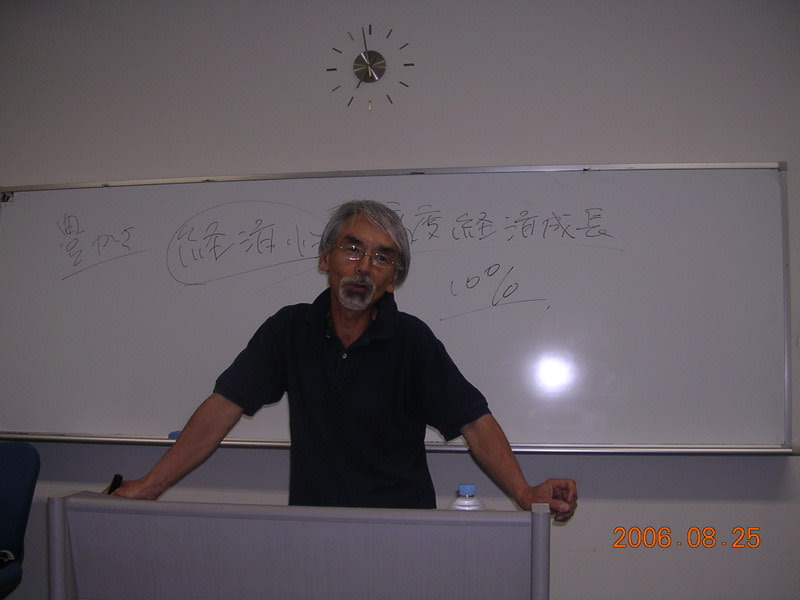久しぶりに参加出来ました、4月の大有研の世話人会。
まずは、夏に行われる農塾などのイベントについて。今年も私が農塾を担当させて頂くことになり、今いろいろと考えております。 まだ詳細は決まっていませんが、
第一回は、前代表の尾崎さんの有機農業推進法について、
第二回は、若者が動かす、広がる、有機の輪
第三回は、有機的に体をきれいに整える。
第四回は、畑に出て、土とオーガニックで遊ぼう!!
これからもっと具体的にブラッシュアップしたいと思っていますが、有機農業を広めるということは、畑だけに留まったものではないと私自身は考えています。今回の農塾では、いろんな角度から有機を見つめたいと思っています。 後は有機農業運動の我が師、全国有機農業団体協議会の尾崎零さんが講師になっての、有機農業推進法(ちゃんとした法律としてみとめらてたのですよ。)についてのお勉強。この活動は有機農業を広めるだけじゃなくて、生産者と消費者の距離を縮めてくれる可能性を秘めていますね。この距離感がとても大切だと思っています。
後は有機農業運動の我が師、全国有機農業団体協議会の尾崎零さんが講師になっての、有機農業推進法(ちゃんとした法律としてみとめらてたのですよ。)についてのお勉強。この活動は有機農業を広めるだけじゃなくて、生産者と消費者の距離を縮めてくれる可能性を秘めていますね。この距離感がとても大切だと思っています。
その後、雨の中、久しぶりにフットサルに。体重たかったけど、楽しかったっス。 体調が底になった時程フットサルに参加して、酸欠になって、バテバテになって、自分の体を追い込みます。これくらいで甘えてんじゃねえよ、という感じでしょうか。とても良い気分転換になります。
 この日の遅めの夕食は、特別に以前から行きたかった星山シェフのバロッタさんへ。
この日の遅めの夕食は、特別に以前から行きたかった星山シェフのバロッタさんへ。
感想としては、食材がとてもしっかりしている。調理法はとてもシンプルだけど、余分なことをしないので、食べていて、ストレスがありません。必要なことはちゃんとして、余分な事しない←これが実はとても難しくて、この部分の見極めが料理人のセンスの違いになるのかな、と思います。
星山さんのやさしい人柄も、お店の魅力ですね。スタッフも充実して、これからますます楽しみです。(画像は、今月のあまから手帳の表紙を飾る、ビーツを使ったパスタです。)
そうそうたまたま私達の食事中に、イ・ヴェンティテェッリの浅井さんが来店された。
同じ魚菜の会の会員ということで、少しお話させて頂き、ワインまで頂いてしまいました。短い時間でしたが、料理に対する情熱がビシビシ伝わって来ました。。
最近のいろいろな意味での不調をようやく消化し、また自分の糧に出来るような感覚が戻ってきた。たくさんの刺激を受けた一日。また、初心に戻って、頑張るでーー!!