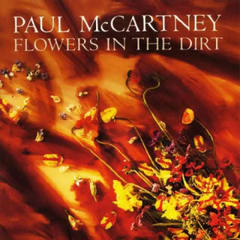1990年代に入って音楽シーンは大きく歪もうとしていた。それまで全盛を誇っていた明るく楽しいポップスが衰退し、代わりにワケのわからんラップやどれを聴いてもみな同じに聞こえる黒人コーラス、そしてただウルサイだけのグランジ・オルタナ系ロックが台頭してきて、更に追い打ちをかけるようにビルボード・ホット100 の集計方法がコロコロ変わって迷走しまくった結果、ヒットチャート自体が急速にその魅力を失っていった。このように音楽シーンが歪んでくると、一番ワリを食うのがマトモな音楽をやっているアーティスト達で、いくつかの例外を除き、80年代に活躍した連中をも含めたベテラン勢は苦戦を強いられた。当然ポールも例外ではなく、アルバムもかつてのようなミリオンセラー連発とはいかなかったが、90年の “ゲット・バック・ツアー” や 91年の MTV アンプラグドですっかり自信を取り戻し、信頼できるバンド・メンバー達との結束を固めたポールは迷うことなく自らの信じる道を進み始めた。そして出来上がったのが93年リリースの「オフ・ザ・グラウンド」である。
アルバムの第一印象は “アンプラグド的な要素の強いシンプルなバンド・サウンド” というべきもので、MTV アンプラグドの成果を活かしながら「フラワーズ・イン・ザ・ダート」の路線を更に推し進めたような感じがする。だからビートルズやウイングスのようなスリリングな展開は希薄だが、さりげなく良い曲が一杯詰まったフレンドリーなアルバムになっていると思う。
私がダントツに好きなのは 1st シングルになった③「ホープ・オブ・デリヴァランス」で、MTV アンプラグドで味をしめたアコギ中心の軽快なポップ・ナンバーになっており、ポールなメロディーが次から次へと出るわ出るわのワンコソバ状態だ(^o^)丿 更にダメ押しとばかりに繰り出されるノリノリのハンドクラッピングにポールの一人追っかけ二重唱と、サウンド・プロダクションの面でも徹底的に作り込まれている。これはもう90年代ポール屈指の大名曲だろう。因みに私はポールの好不調をこのようなキャッチーでノリの良い曲がササッと書けるかどうかで判断している。
ライブ感溢れる⑥「バイカー・ライク・アン・アイコン」も素晴らしい。バイク野郎を追っかける少女を歌った歌詞を、僕とフリオと校庭にいるような(笑)イントロからタイトなバンド・サウンドに乗せて一気呵成に歌うストーリーテラー、ポールがカッコイイ!この手の疾走系ロックンロールが好きな私には堪えられない1曲だ。今にして思えば 80年代の不調時には③や⑥のような曲が皆無だった。素晴らしいバンド仲間を得てポールはすっかり好調の波に乗ったと言えよう。
アルバム冒頭を飾るタイトル曲①「オフ・ザ・グラウンド」も非常に良く出来たナンバーで、爽やかなバック・コーラス、これがあるとないとでは大違いのハンド・クラッピング、縦横無尽に暴れまくるスライド・ギターと、オーヴァーダビングを重ねて非常に重厚なサウンドに仕上げている。イントロからラウドなギターとヘヴィーなリズムが炸裂する②「ルッキング・フォー・チェンジズ」は①をハードにしたようなナンバーで、キャッチーなサビのメロディーもインパクト大だし、演奏自体もノリノリだ。ただ、動物実験による虐待を痛烈に皮肉った陳腐な歌詞はちょっと...(>_<) この頃からポールの歌詞には環境保護や動物愛護といったメッセージ・ソングが増えてきて、ちょうど70年代前半のジョージの宗教モノと同じで、時々その押しつけがましさが鬱陶しく感じられるのが玉にキズだ。
⑦「ピース・イン・ザ・ネイバーフッド」はミディアム・テンポでグイグイ突き進むグルーヴィーなナンバーで、ポールらしいメロディーが楽しめる。もう少しアレンジを工夫して短くまとめれば傑作になったかもしれない。⑩「ゲット・アウト・オブ・マイ・ウェイ」はチャック・ベリーの「ジョニー・ビー・グッド」を裏返しにしたような軽快なロックンロールで、単品としてはエエねんけど、アルバムの流れの中ではちょっと浮いてるような感じがする。⑫「カモン・ピープル」は何となくアルバム「レッド・ローズ・スピードウェイ」を想わせる曲想を持った佳曲で、後半部のビートリィな盛り上がりは圧巻だ。あと、シークレット・トラックとしてラストに「コズミカリー・コンシャス」という曲が入っており、これが何とビートルズ時代にインドで書かれたという。何とも不思議なグルーヴを持った曲で、いかにも “あの時代” を彷彿とさせる雰囲気を醸し出している。まぁポールのことだから、これからも“デビュー前に作った曲” や “ビートルズ時代に書いた未発表曲” がいくらでも出てきそうでファンとしてはめっちゃ楽しみだ。
Paul McCartney - Hope Of Deliverance
アルバムの第一印象は “アンプラグド的な要素の強いシンプルなバンド・サウンド” というべきもので、MTV アンプラグドの成果を活かしながら「フラワーズ・イン・ザ・ダート」の路線を更に推し進めたような感じがする。だからビートルズやウイングスのようなスリリングな展開は希薄だが、さりげなく良い曲が一杯詰まったフレンドリーなアルバムになっていると思う。
私がダントツに好きなのは 1st シングルになった③「ホープ・オブ・デリヴァランス」で、MTV アンプラグドで味をしめたアコギ中心の軽快なポップ・ナンバーになっており、ポールなメロディーが次から次へと出るわ出るわのワンコソバ状態だ(^o^)丿 更にダメ押しとばかりに繰り出されるノリノリのハンドクラッピングにポールの一人追っかけ二重唱と、サウンド・プロダクションの面でも徹底的に作り込まれている。これはもう90年代ポール屈指の大名曲だろう。因みに私はポールの好不調をこのようなキャッチーでノリの良い曲がササッと書けるかどうかで判断している。
ライブ感溢れる⑥「バイカー・ライク・アン・アイコン」も素晴らしい。バイク野郎を追っかける少女を歌った歌詞を、僕とフリオと校庭にいるような(笑)イントロからタイトなバンド・サウンドに乗せて一気呵成に歌うストーリーテラー、ポールがカッコイイ!この手の疾走系ロックンロールが好きな私には堪えられない1曲だ。今にして思えば 80年代の不調時には③や⑥のような曲が皆無だった。素晴らしいバンド仲間を得てポールはすっかり好調の波に乗ったと言えよう。
アルバム冒頭を飾るタイトル曲①「オフ・ザ・グラウンド」も非常に良く出来たナンバーで、爽やかなバック・コーラス、これがあるとないとでは大違いのハンド・クラッピング、縦横無尽に暴れまくるスライド・ギターと、オーヴァーダビングを重ねて非常に重厚なサウンドに仕上げている。イントロからラウドなギターとヘヴィーなリズムが炸裂する②「ルッキング・フォー・チェンジズ」は①をハードにしたようなナンバーで、キャッチーなサビのメロディーもインパクト大だし、演奏自体もノリノリだ。ただ、動物実験による虐待を痛烈に皮肉った陳腐な歌詞はちょっと...(>_<) この頃からポールの歌詞には環境保護や動物愛護といったメッセージ・ソングが増えてきて、ちょうど70年代前半のジョージの宗教モノと同じで、時々その押しつけがましさが鬱陶しく感じられるのが玉にキズだ。
⑦「ピース・イン・ザ・ネイバーフッド」はミディアム・テンポでグイグイ突き進むグルーヴィーなナンバーで、ポールらしいメロディーが楽しめる。もう少しアレンジを工夫して短くまとめれば傑作になったかもしれない。⑩「ゲット・アウト・オブ・マイ・ウェイ」はチャック・ベリーの「ジョニー・ビー・グッド」を裏返しにしたような軽快なロックンロールで、単品としてはエエねんけど、アルバムの流れの中ではちょっと浮いてるような感じがする。⑫「カモン・ピープル」は何となくアルバム「レッド・ローズ・スピードウェイ」を想わせる曲想を持った佳曲で、後半部のビートリィな盛り上がりは圧巻だ。あと、シークレット・トラックとしてラストに「コズミカリー・コンシャス」という曲が入っており、これが何とビートルズ時代にインドで書かれたという。何とも不思議なグルーヴを持った曲で、いかにも “あの時代” を彷彿とさせる雰囲気を醸し出している。まぁポールのことだから、これからも“デビュー前に作った曲” や “ビートルズ時代に書いた未発表曲” がいくらでも出てきそうでファンとしてはめっちゃ楽しみだ。
Paul McCartney - Hope Of Deliverance