今日も首都圏は好天が続きました。地図愛好者グル
ープの例会で、神奈川県民の水源のひとつ、津久井湖
のそばにある城山(津久井城跡)に出かけました。

明日も出かける予定があるので、詳細レポートは別途
とし、数枚の写真のみ紹介します。
JR横浜線の橋本駅からバスに乗り、津久井湖畔の
クラブ前バス停で下車しました。
津久井湖を背にした南に向かい、ちょっとした峠を越
えて、県立津久井湖城山公園の西端、パークセンター
に入ります。
ここから丹沢山塊の蛭ヶ岳と塔ヶ岳の間に馬の形の
雪型が見えました。
城山に上がる遊歩道の途中の、展望広場まで上がっ
て見た雪型です。写真中央部ですが分かりますか?

展望広場の木のベンチで昼食にしました。
さらに城坂を上がり、車坂を上がれば頂上に行ける
のですが、皆さんは、もう雪型を見たからと満足され、
帰るとのこと。それではと記念撮影を。

私は山頂に上がることにして、ここで皆さんと別れま
した。車坂(男坂)を上がって飯縄神社への分岐となる
峠に出て、西にちょっと上がると城山(375m)山頂。
山頂は、津久井城の本曲輪(くるわ)跡。木の間越し
に、雲が増え逆光となっものの、丹沢山塊もよく見え、
雪型もまだ確認できました。

西北側は、津久井湖の上流が見下ろせます。

さらに場所を少し移動すると東方の展望も得られ、
はるか新宿など都心のビル群も確認できました。

写真ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、遠方
のグリーンの帯の上です。
飯縄神社を経て北に下り、津久井湖畔の「花の苑地」
と呼ぶ、桜の多いエリアに出て、地元産品などを販売す
る津久井湖観光センターにも寄りました。
さらにバスの往路だった国道413号から県道506号
へ。町田街道を経てJR横浜線の北隣駅、相原駅まで
歩き、16時半近くに着きました。
ープの例会で、神奈川県民の水源のひとつ、津久井湖
のそばにある城山(津久井城跡)に出かけました。
明日も出かける予定があるので、詳細レポートは別途
とし、数枚の写真のみ紹介します。
JR横浜線の橋本駅からバスに乗り、津久井湖畔の
クラブ前バス停で下車しました。
津久井湖を背にした南に向かい、ちょっとした峠を越
えて、県立津久井湖城山公園の西端、パークセンター
に入ります。
ここから丹沢山塊の蛭ヶ岳と塔ヶ岳の間に馬の形の
雪型が見えました。
城山に上がる遊歩道の途中の、展望広場まで上がっ
て見た雪型です。写真中央部ですが分かりますか?

展望広場の木のベンチで昼食にしました。
さらに城坂を上がり、車坂を上がれば頂上に行ける
のですが、皆さんは、もう雪型を見たからと満足され、
帰るとのこと。それではと記念撮影を。

私は山頂に上がることにして、ここで皆さんと別れま
した。車坂(男坂)を上がって飯縄神社への分岐となる
峠に出て、西にちょっと上がると城山(375m)山頂。
山頂は、津久井城の本曲輪(くるわ)跡。木の間越し
に、雲が増え逆光となっものの、丹沢山塊もよく見え、
雪型もまだ確認できました。

西北側は、津久井湖の上流が見下ろせます。

さらに場所を少し移動すると東方の展望も得られ、
はるか新宿など都心のビル群も確認できました。

写真ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、遠方
のグリーンの帯の上です。
飯縄神社を経て北に下り、津久井湖畔の「花の苑地」
と呼ぶ、桜の多いエリアに出て、地元産品などを販売す
る津久井湖観光センターにも寄りました。
さらにバスの往路だった国道413号から県道506号
へ。町田街道を経てJR横浜線の北隣駅、相原駅まで
歩き、16時半近くに着きました。












































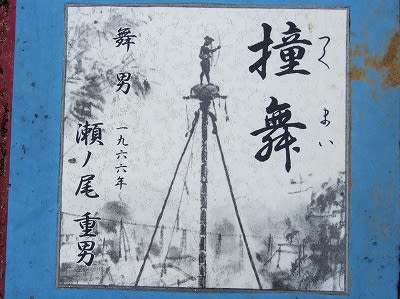













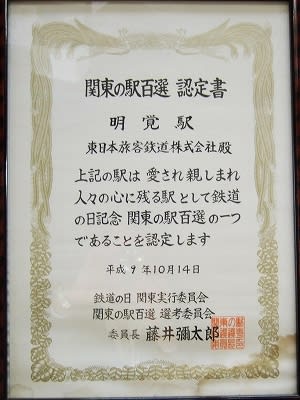









 。
。




































