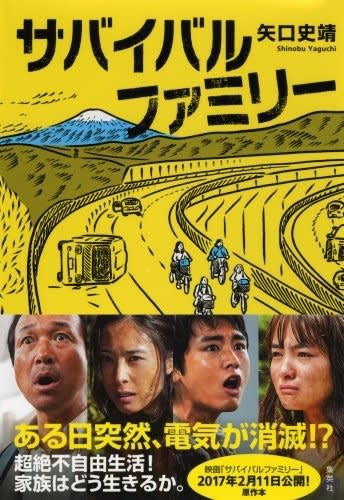阿部さんは好きな俳優でもあるし
ふと目に止まったこのタイトルにも惹かれ、
レンタルでDVDを借りてきて家で鑑賞。
元々はドラマの脚本家の方の初監督作品とのことで
やっぱりどこかコメディータッチのTVドラマのようだけど
作りに反して内容は結構リアルでシリアス。
子どもが巣立った後の50代夫婦の実態がそこにあった。
ラストがちょいとお気楽極楽だけどね(^^;
調べてみると、原作は重松清さんとのこと。
なるほど、リアルでシリアスな内容は重松さんでしたか。
「ファイレス」という、3組の夫婦が描かれた小説のうち
1組の夫婦の話を脚本にして映画化したようだ。
小ネタ満載でかなり笑えるけれど
果たして笑って済ませていい内容なのかと
鑑賞後考えたしまった。
夫はともかく、この作品中の妻の感じ方は
コメディにしてもいいのかもしれないけれど。
おそらく原作にあったと思われる、心に止まるセリフがいくつか。
「いま私たちがこだわるべきなのは
正しいことではなく優しさなのではないでしょうか。
戦争のように、正しいことと正しいことはぶつかるけど
優しいことと優しいことはぶつからない」
「夫婦で決めてきたことは
いま思い出してみて正しかったかどうかわからない。
でも、もし間違っていても
あいつ(妻)なら笑い飛ばしてくれる。
(そういう相手をオレは選んだんだ)」
特に前者は夫婦や家族だけの話じゃない。
社会全般や、政治、外交、人間関係にも言えること。