「仰げば尊し」を旧仮名づかいで書きますと「あふげばたふとし」となります。昔の子弟関係は、現代とはややおもむきが異なり、仰ぎ見て尊敬される師と、頭をたれて教えを聞く謙虚な弟子という関係であったと、教師役を多く演じた俳優の武田鉄矢氏も憧れをこめて語っています。「頭(こうべ)を挙(あ)げて山月を望み、頭を低(た)れて故郷を思う」という李白の詩「静夜思」の情景を思い起こします。
以下は、嘗て、卒業式の定番として歌われた「仰げば尊し」に関する話です。従来この歌は、明治初期に、文部省音楽取調掛、高遠藩士の子弟、伊澤修二の作詞・作曲いわれていました。伊澤は、貧しい家で育った後、東京帝大に進みました。アメリカ留学中、ベル研究所で、友人の金子堅太郎と共に日本人で初めて、電話器を使ったということです。従って、世界で最初に電話器で話された言語は日本語であったそうです。金子堅太郎は、後に外交官となり、伊藤博文総理の命で、アメリカ大統領と大学の同窓という縁をたぐって日露戦争の終結交渉に貢献しました。
「仰げば尊し」の原曲についてはわかっておらず、長い間、小学校唱歌集における「最大の謎」とされて来ました。ところが最近になって、一橋大学名誉教授の桜井雅人氏が、この歌の曲の出典を突き止め、アメリカで19世紀後半に初めて世に出た「Song for the Close of School」、所謂「卒業の歌」の旋律が、「仰げば尊し」の原曲であることが判明しました。原歌には「師の恩」「身を立て、名をあげ」という歌詞は無いそうですが、私は日本の「仰げば尊し」の歌詞、曲、共に愛着を感じます。
1.仰げば尊し 我が師の恩
教(をしへ)の庭にも はや幾年(いくとせ)
思へばいと疾(と)し この年月(としつき)
今こそ別れめ いざさらば
2.互(たがひ)に睦みし 日ごろの恩
別るる後(のち)にも やよ忘るな
身を立て名をあげ やよ励めよ
今こそ別れめ いざさらば
3、朝夕馴(なれ)にし 学びの窓
蛍の灯火 積む白雪
忘るる間(ま)ぞなき ゆく年月
今こそ別れめ いざさらば
以下は、嘗て、卒業式の定番として歌われた「仰げば尊し」に関する話です。従来この歌は、明治初期に、文部省音楽取調掛、高遠藩士の子弟、伊澤修二の作詞・作曲いわれていました。伊澤は、貧しい家で育った後、東京帝大に進みました。アメリカ留学中、ベル研究所で、友人の金子堅太郎と共に日本人で初めて、電話器を使ったということです。従って、世界で最初に電話器で話された言語は日本語であったそうです。金子堅太郎は、後に外交官となり、伊藤博文総理の命で、アメリカ大統領と大学の同窓という縁をたぐって日露戦争の終結交渉に貢献しました。
「仰げば尊し」の原曲についてはわかっておらず、長い間、小学校唱歌集における「最大の謎」とされて来ました。ところが最近になって、一橋大学名誉教授の桜井雅人氏が、この歌の曲の出典を突き止め、アメリカで19世紀後半に初めて世に出た「Song for the Close of School」、所謂「卒業の歌」の旋律が、「仰げば尊し」の原曲であることが判明しました。原歌には「師の恩」「身を立て、名をあげ」という歌詞は無いそうですが、私は日本の「仰げば尊し」の歌詞、曲、共に愛着を感じます。
1.仰げば尊し 我が師の恩
教(をしへ)の庭にも はや幾年(いくとせ)
思へばいと疾(と)し この年月(としつき)
今こそ別れめ いざさらば
2.互(たがひ)に睦みし 日ごろの恩
別るる後(のち)にも やよ忘るな
身を立て名をあげ やよ励めよ
今こそ別れめ いざさらば
3、朝夕馴(なれ)にし 学びの窓
蛍の灯火 積む白雪
忘るる間(ま)ぞなき ゆく年月
今こそ別れめ いざさらば










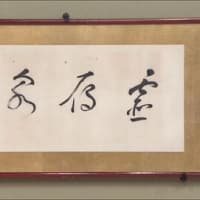



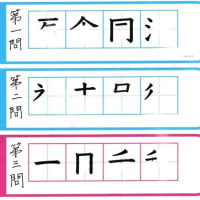










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます