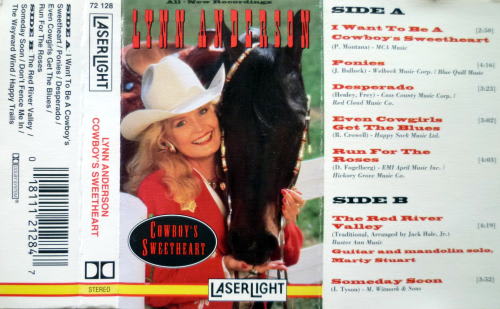Eddie Dean (3)
米国盤 Sutton Records SSU-333 Eddie Dean / I Dreamed of a Hillbilly Heaven
(1)Hillbilly Heaven (2)Love The Way You Say It (3) Banks of The Old Rio Grande (4)Impatient Blues (5)Tangled Lies (6)Iowa Rose (7)Walk Beside Me (8)Katmandu (9)Make Believe (10) Seeds Of Doubt
今日のレコードはすこしマニアック、Suttonレコードというマイナーレコード会社が発売したもので作りも粗末で、曲名だけで何のクレジットもなく解説もなくて訳がわからないもの(smile)。ただ、Eddie Dean というカウボーイ&カントリー歌手名だけを私は知っていたのでアメリカの中古レコード屋さんのカタログの隅っこに各2ドルと載っていたからピンと反応して彼のレコード3枚同時に買ったのでした......船便で3ヵ月くらいかかった時代。音はよくなくてもジャケットだけは粗雑でも雰囲気があってよかった(smile) でも重要な曲が1曲入っていた,.....たったそれだけで満足100%(^^) 名前の通った歌手なのにレコードの粗末さよ......と思ったものです。歌い方は正統派、今では失なわれてしまった昔のカントリーの良さが溢れている...と私自身は感じています。
ところで"夢に見たヒリビリー天国"ですが、アイデアの勝利といえる曲...ヒットしたりしなくても記憶に残る曲といえるでしょう。スティールギターにのって語りがほとんどですが、ヒリビリー天国の夢をみる...そこにいるのがウィル・ロジャース、ジミー・ロジャース、ハンク・ウィリアムズ......そして Red Foley、Ernest Tubb、Gene Autry、 Roy Acuff、Eddie Arnold、Tex Ritter、 Roy Rogersと名前が出てきて 次にエディ・ディーン...と自分の名前のあるところでびっくりして目が覚める。皆んなビッグスター揃いの中に自分が......という驚き! good idea ! この歌が作られた頃はほとんどの人が存命だったはずですが当のEddie Deanを含めて今ではみ〜んなHillbilly Heavenにいます。
このレコード、間違ってもCDなったりはしないでしょうけど(3) Banks of The Old Rio Grande 、(6)Iwoa Rose 、(7)Walk Beside Me、マイナー調の(8)katmandu など雰囲気のある佳曲で、ジム・リーヴスとかレックス・アレンといった昔のカントリー歌手が好きな人達には受けると思うんだけどなぁ......バーボン・ウィスキーを飲みながら聴くカントリー(^^)















 Mel Tillis が亡くなった 1932年~2017年11月19日フロリダ州出身 85歳
Mel Tillis が亡くなった 1932年~2017年11月19日フロリダ州出身 85歳 


 次回に続く
次回に続く