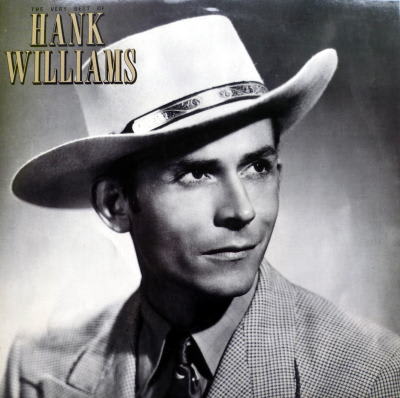肥前 平戸城を訪ねて
平成27年5月28日(木)に博多から高速バスに乗り長崎県佐世保へ~そこから普通バスに乗り換えて平戸まで日帰り旅行に行った。気楽な一人旅で目的は平戸城、松浦(まつら)氏6万1千石の城下町散策と戦国~江戸時代初期にイギリス、オランダ他との南蛮貿易で栄えた歴史の街としての平戸を巡る目的だった。6ヶ月にわたった治療が終了して開放された気分があって海の見える由緒あるところに行きたい・・・・・ということで選んだ場所。 さんざん歩き回るつもりで でっかいおにぎり3個を作って他にキャラメル2箱と乾パンを持っていざ出陣。
博多から朝6時のバスに乗って平戸までは4時間近くかかりました。昔は本土側の田平町からフェリーに乗って平戸港まで渡っていたようですが年に出来た平戸大橋でつながって車で行くことが出来るようになっています。港町とお城が一体になって独特の雰囲気を感じます(地図で青い湾の右手が平戸城で黄色い地帯が市街地)。お城に一番近いところでバスを降りて市役所側(港側)道路から早速登城・・・・・両側が石垣の傾斜のゆるい階段を上っていくと先方に白い鳥居が見えてさらに行くと石垣、右手に白壁のやぐら(乾櫓)が見えてお城らしい雰囲気になってきます。



さらに道なりに登って行くと右側に立ち木と平行な高石垣に乗っかった地蔵坂櫓が見え、すぐに北虎口門の正面に出ます。北虎口門をくぐる前に右側に地蔵坂櫓門が塀で連なっているのがわかります。



門をくぐる前に塀沿いに地蔵坂櫓の方に行って振り返って北虎口門とすぐ横の狸門を移した写真。それから北虎口門をくぐるとすぐ左手に狸櫓があります。


さらに登って行くと本丸前門があって、くぐって道なりに行くと天守閣に出る階段に出た。階段を登りきると右手に天守閣が聳え立っている。



正面から見る天守閣、天主の向こう側には平戸港と市街地があります。 横から見た天守閣の写真も撮って天主内に・・・・中には展示物があって見学。天守閣最上階から本土側を見ると下方に木に囲まれた懐柔櫓が見え、その先は本土側との境の海だ、あいにく曇り空で青い海に写らなかったのが残念・・・・でもなかなかの絶景でこんなに近くに海の見えるお城は珍しいのでは。 平戸城の由来については 「 平戸城( 別名 亀岡城 )は平戸藩主松浦30代松浦 棟(ただす)公により宝永元年(1704)の築城によるもので、山鹿流の縄張りによる日本唯一の平山城であります。明治維新後は荒廃し、わずかに北虎口門と狸櫓が保存されておりましたが、昭和35年(1960)10月天守閣を始め、各櫓の復元に着手し、昭和37年完成いたしました。」 と書いてありました。
山鹿流というのは山鹿素行(1622~1685)が唱えた兵学の一派で、赤穂浪士で有名な播州赤穂の浅野家が影響を受けたことでも知られていますが、江戸初期の平戸の殿様 松浦鎮信が素行に傾倒して弟子となり、平戸藩の藩学になったということです。殿様は山鹿素行を平戸に迎えたかったのに出来ず、素行は 弟(義昌)と自分の息子(高基)を推薦して仕えさせたとのことで、以後連綿として続き 江戸期を通じて山鹿流兵学の家元は平戸藩にあったということだそうです。



天守閣の最上階から見た平戸港(左が最深部、2枚目が港出口、右が外界へ通じる瀬戸で真ん中の小さな島は黒子島という、さらに右手は本土が見えるのです)と市街地。 ここにポルトガル、イギリス、オランダ船が入港して長崎以前の南蛮貿易の拠点だった・・・・・湾の大きさは当時とそんなに大差はないのではないかな? 長崎に比べると手狭で長崎のミニチュア版という感じだ。



天守閣を降りてより奥のほうに歩いていくと見奏櫓という二層の櫓があった。見奏櫓側から見た天守閣石垣。


天守閣を後にもと来た道をたどって北虎口門の手前から場内を左方向に行くと城内からみた地蔵坂櫓に出る、中は平戸地方で使われた昔の民具が展示されていた。さらに城内を道なりに行くと三層の乾櫓 前に出た。 中は売店になっていて腰の曲がったおばあちゃんがひとり店番をしていた、入り口にデーンと自動販売機と白いアイスクリームボックスが設置されているのでどんな角度から撮っても江戸時代の雰囲気には撮れなかったのが残念。


さらに行くと城内は広い平地になっていて大きな亀岡神社がありました。神社前を素通りして歩いていくと城跡にはよくある色々な記念碑や顕彰碑が立っています。その中で興味を惹かれた碑がひとつあったので写す・・・・・「 志士 沖 禎介君 」 と書いてある石碑。途中にあった別な登城口の石垣。
知らなかったので沖 禎介(1874~1904)について調べてみると、平戸出身の人で明治期の諜報活動家、日露戦争が勃発すると民間人ながら陸軍の諜報機関に協力し横川省三等と諜報活動に従事してロシア軍の輸送鉄道爆破を計画して捕らえられ横川とともにハルピン郊外でロシア軍に処刑された・・・・・とある。 最期に臨んで二人の堂々たる態度にロシアの軍人達も感服したらしいです。昔の大陸浪人、日露戦争秘話ともいえる・・・・・映画 「 二百三高地 」 にも出ていた人物のようです。



さらに進んでいくと平戸城一の丸大手門付近の石垣群に出くわしたので何枚か撮影。鬱蒼とした木々の中にある苔むした石垣群は建物はなくても古城の趣きが十分に伝わってくる雰囲気である。



そうするうちにバスで平戸大橋からやって来た時の道路に出た。そこから左へお城の外周をまわる形で歩いていくと猶興館高校(昔の藩校の流れか?)の正門前にでた。城門なのか由緒ありそうな門で高校全体が古びた石垣で囲われているので平戸城内にあるといってもいいのだと思う。



高校の周囲の石垣を歩いていくと別な登城口に出くわしたのでまたそこから登城して行った。すると真ん中に相撲の土俵がある大きな広場に出て、隅っこにさっき天守閣から見下ろした二層の懐柔櫓が立っていた。そこから後上方を見上げると先ほど天守閣の奥にあった見奏櫓が聳えていた。
平戸城の印象ですが、石垣もそんなに高くはないけれど市街地に近いところにあるお城としては古城としての雰囲気が十分の好きなお城でした(smile)



広場でゆっくり腹ごしらえをして再度一の丸大手門側に歩いて行き城外へ出てお城周辺を歩いていき最初の登城口へ舞い戻ったのでした。そこはちょうど近くに市役所の建物があるところで幸橋(眼鏡橋)のお城側たもとです。お城側から市街地の方へ橋を渡ってから眼鏡橋を撮影、お城側を見ると右手の茶色い建物が市役所。



市役所の建物と眼鏡橋の脇に1927(昭和2)年に建立されたという「英国商館遺址の碑」というのが立っています。イギリスの商館が平戸にあったことを示す記念碑のようです。碑には ”商館開設当初の11名の商館員の名前と、1613~1623年の間この地の向こう岸にあった英国商館およびその館員、ならびに貿易に従事したすべての人々の記念のために ” と英文で書かれているそうです・・・・・イギリスが商館を置いたのは短期間だったのですね。ちょうど反対側には実物のオランダ船錨が展示されていました、”1952( 昭和27 )年に川内港から引き上げられたもの ” と書いてありました。



さて、眼鏡橋から湾沿いに湾出口の方に歩いていくといくつかの碑が立っています。
ポルトガル船来航を記念する碑、碑文に曰く ”1550(天文19)年に来航したポルトガル船は1564(永禄7)年長崎福田浦を寄港地とするまでの間、ほぼ毎年平戸に来航していた。ここ入港比定地は1561(永禄4)年宮ノ前事件と呼ばれるポルトガル船員と平戸住民との間におこった紛争事件の現場でもある ”・・・・とのこと。
じゃがたら娘の像の碑文には ”17世紀初頭、平戸にオランダ商館、イギリス商館が設置され、三浦按針(ウィリアム・アダムズ)をはじめ多数の外国人が往来し、繁栄を極めた。幕府の鎖国政策とキリシタン弾圧は島原の乱1637(寛永14)年後ますます激しくなり、1639(寛永16)年平戸、長崎の外国人に関係のある男女32名がジャガタラ(ジャワ)に追放され、平戸から出航し二度と日本に帰れなかったのである。この像は、ジャガタラより望郷の念をジャガタラ文に託す娘の姿をしのび、1965(昭和40)年に建立した ”・・・・と書いてありました。 ”日本こいしや こいしや~ ” で始まる切なくなるような文です(涙)




港から山手の方に入っていくと 「 松浦記念館 」 という博物館があります。まるでお城のような石垣構えの大きな屋敷で殿様の別邸であったところとか。 松浦氏の大名としての鎧兜、奥方のお輿など展示品がたくさんでした。見学のあと正面階段をおりて右手に30m位歩くと「 六角井戸 」というのがありました。 井戸の型が在来の日本のものと異なるところから唐人関係、倭寇関係遺跡として伝承されている・・・・・とのこと。
」


そこから松浦歴史館正面階段に戻って今度は左手の方に行くと「 按針坂 」なる標識に出合って登ってゆくと平戸湾と対岸の平戸城が遠望できます。



道なりに上がっていくとフランシスコ・ザビエル(1506~1552)の記念碑があり、さらに頂上まで行くと三浦按針(ウィリアム・アダムス1564~1620)の墓がありました。
ザビエルの碑の隣に古びた石版があって ”聖フランシスコ・ザべりオ師四度往来し、布教に努めた由緒のこの地に聖師来訪四百年記念に當り余徳を慕って此の碑を建つ ”・・・・と書いてあります。
三浦按針の碑には ”三浦按針(ウィリアム・アダムズ)は、初めて日本に来たイギリス人で、1600(慶長5)年オランダ船デ・リーフデ号の航海長として豊後(大分)に漂着した。その後徳川家康は、彼を外交顧問として今の神奈川県横須賀市に住まわせ、250石を与え召し抱えた。慶長年間、オランダ、イギリスが通商を許され平戸に商館を設置するようになったのは按針の力によるところが大であったといわれる。 後に平戸イギリス商館長コックスのもとに活躍し、1620(元和6)年平戸で病死した。墓地は定かでないが、1954(昭和29)年三浦按針の墓を建立した。夫婦塚は、1964(昭和39)年生誕400年にあたり、イギリスの妻の墓地より婦人の霊魂の象徴として小石を取り寄せ、アダムズの墓に合葬し夫婦塚としたものである。”・・・・・と書いてあります。
かなり以前に ”将軍(SHOGUN)” というアメリカ映画を見たことがありますがひょっとしてこの三浦按針がモデルだったのかなあ、ストーリーは忘れてしまったけれどまた見てみたいなぁ




頂上から海の方に降りてゆくと「 オランダ塀 」で有名な坂に出ます(振り返って撮った写真)、降りてゆくと右手に石垣の入り口があって中はオランダ商館跡地で小さな広場になっていました。
「 オランダ塀 」 の説明があって ”石段に沿って続く漆喰で塗り固められた塀は通称オランダ塀と呼ばれています。1609年から1641年までのあいだこの塀の東側にオランダ商館が置かれていました。商館を外から覗かれないために、また延焼などから守るためにこの塀が設けられました。塀の高さは約2m、底辺の幅は約70cmあります。商館当時の様子を知ることのできる数少ない遺構のひとつです ”・・・・とのこと。
オランダ商館跡の石版には ” 大航海時代の冒険者たち その礎の上に今の私たちはある 眠り給え ここを小さき和蘭として ” と書いてあり、小さな和蘭国旗とたずさわった全ての商館員の名前と年代が刻まれてありました。



海岸沿いの道路まで出て左手の方に行く(湾の出口の方)とすぐ左手に「オランダ井戸」が2つ残っており、中を覗くといまだに水をたたえています(凄い!)。 そこから上を見るとさっき降りてきたオランダ塀が見えます。さらに道路沿いに歩いて行くとオランダ商館倉庫跡の広場がありました、何んにもないけれどココが日本の西洋への小さな窓口だったのか・・・・・と司馬遼太郎さん的に思いを馳せると感慨深いものです。



さらに先に行くとオランダ商館1639年築造倉庫を復元した白い建物がありました。端の方にはオランダ国旗がなびいています。古い故図を見ると本来なら海岸からすぐのところに建っていたのでしょうが、今は海岸線に道路が走っているので海側から見て道路の向こう側に立てられています。商館員がいるわけではないですが昔あった建物の再現を見ると こうだったのかな・・・・と想像しますね。 中には展示物等があるらしいのですが帰りのバス時間が押し迫っていて見れなかったのが残念。
そこから湾出口まで歩いていくと「 常燈の鼻 」 といういわゆる灯台の明かりの役割をした大きな行灯(あんどん)が岸壁の石垣上にありました、1616(元和2)年に設置されたこれも昔からのものなんだそうです。 そこまで行って海岸べりを引き返すと、ちょうどさっきの復元オランダ商館前あたりの海に下りていく 「 オランダ埠頭 」 と呼ぶ階段がありました。オランダ船から上陸したり物を陸揚げしたりする時に使われた当時の姿をそのままとどめているものだそうです。 そこに座って3個目のおにぎりを食べ、下まで降りて裸足になって足を海につけた、心地よい冷たさ(smile)。



小紀行も終わりに近くなって平戸の古い町並みへと引き返していった。平戸は18年くらい前に一度来たことがあって今回が2度目だった、幾分かモダンになったかもしれないけれど古風な町並みは残っていた。何か英国商館がらみのイベントがあるのか日本/イギリスのミニ国旗を飾っているお店が多かった。


帰ってから少し後悔したことがある。司馬遼太郎さんの「街道をゆく」第11巻に平戸のことが沢山載っているのを知って読んでいけばよかったと思った・・・・・吉田松陰が21歳の時平戸を訪ねて54日間滞在し、山鹿流本家で兵学の仕上げをすべく訪ねた・・・・・とのこと。実際 吉田松陰が滞在した場所も残っているらしい。
平戸には外国人が長く住んでいたのに外人墓地みたいなのがないのはどうしてだろう-と思っていましたが、司馬さんの本を読んでなるほどと納得したことがあります・・・・・徳川初期に事件があった・・・・殿様の死で殉死をしなかったことを責められた家臣の一人がうらんで逃走し、幕府に ” 松浦家は切支丹である ” と密告したために大騒ぎになり平戸中の外国関連のものをほとんど取り壊したのであろう・・・・・とのこと等。
正直半日では見切れなかったのでいつかもう1度訪ねようと思う・・・・それくらい平戸には歴史が詰まっていた。平戸は行くのには不便ですが歴史好きの人にはお奨めの処です。