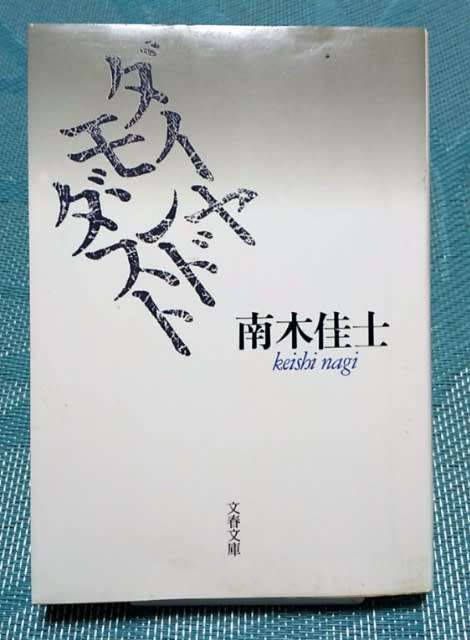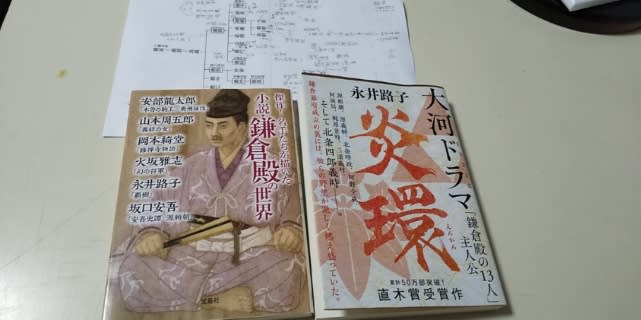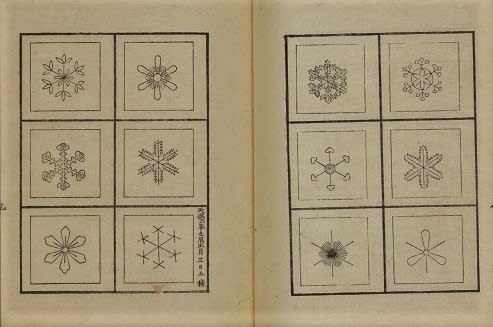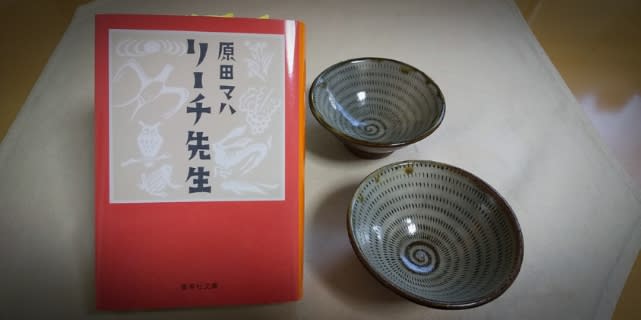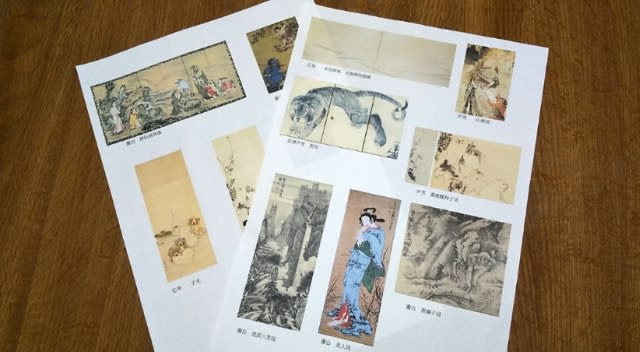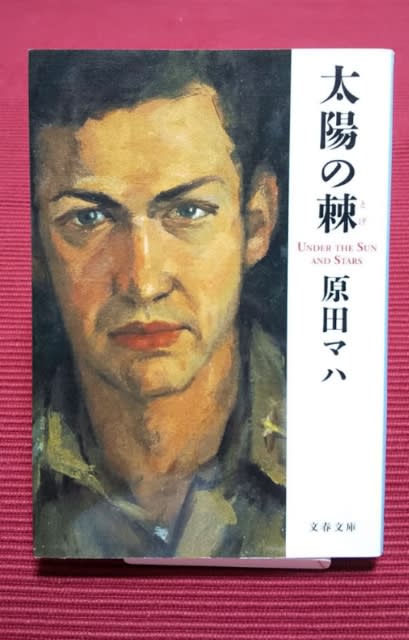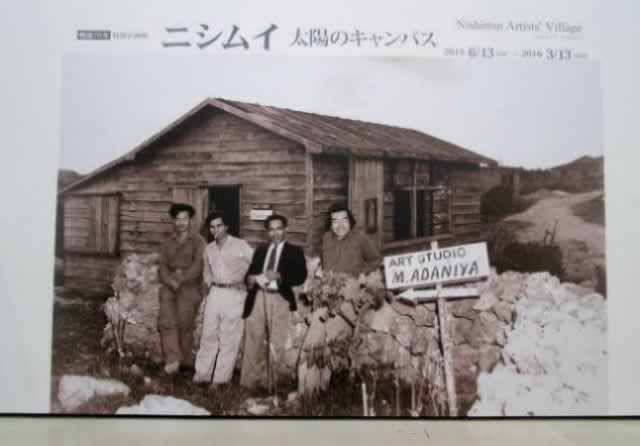将棋には全く無縁な私はメディアを賑わす羽生さんや藤井さんの華やかな表の知識があるくらいでした。
サークルの仲間からこの本が回ってきて「将棋はわからないから」とパスしかかったときに、先にこの本を呼んだ友人の「面白かった!何回も涙が出る場面があった」という感想に、「それでは・・・」と未知の分野の開拓のつもりで借りた本です。
ところが面白くて止められず、ちょうど一日中雨ということもあり一気に読んでしまいました。
まず「奨励会」。これには昇段規定があり、一段ずつ登って三段になると、鬼の三段リーグが待っています。30~40人が半年かけて18局のリーグ戦を戦います。その内上位2名のみが四段に昇段し「棋士」になります。26歳が年齢の壁。このとき四段になれない場合は「退会」という鉄の掟があります。
★瀬川晶司『泣き虫しょったんの奇跡』講談社文庫
(カバーが2枚もかけてあったのは、映画化されたからです)
瀬川棋士(6段)の激動の半生記です。物語の始まりは、61年ぶりに実現したプロ編入試験将棋の第1局に敗れた時の記者会見から始まります。1局に敗れただけで30社の記者会見がなぜ行われたか・・・。この答えは、その数十年前から始まった著者のプロ棋士への困難な長い長い道のりの物語にあります。
将棋の世界は間口は狭くともあまりにも奥が深くて、裏表紙に書かれた紹介文をそのまま載せておきます。
『あきらめなければ夢は必ずかなう!中学選手権で優勝した男は、年齢制限のため26歳にしてプロ棋士の夢を断たれた。将棋と縁を切った彼はいかにして絶望から這い上がり、将棋を再開したか。アマ名人優勝など活躍後、彼を支えた人たちと一緒に将棋界に起こした奇跡。生い立ちから決戦まで秘話満載』
とても心に残っっているのは、5年生の時の担任・苅間澤大子先生との出会いです。それまでの4年間は自分の意志で何かをしたこともなく、成績も冴えない自信のない子でした。40歳過ぎの先生が生徒の自己紹介の翌日には全員のあだ名と名前を覚えていたこと、実験や算数の分数計算に用意されたお菓子は最後に生徒の胃に収まったこと、職員会議で問題になっても全く気にしないこと、保護者向けの学級通信を毎日発行したこと、どんな目立たない子でも必ず通信のエピソードに登場させたこと、等など5年生の子供は先生の公平さをちゃんと見抜いていました。
些細なことでもとにかく子供をほめたこと。これがどんなに子供に意欲を持たせるか、瀬川少年(セガショ-)は5年生で密度の高い1年間を送ることになります。
苦手な作文なのに先生に「才能があるね」と褒められて、突然熱い血が通い始めた感覚を持ちます。作品をほめられた僕が生まれて初めて「書きたい」と思って書いた作文が家族をも驚かせるほどの力作になったのです。
不思議なことに詩や作文をほめられた僕は、ほかのことに対してもやる気が出てきたのです。ある時先生はモジリアニの絵を逆さまにして模写させたのです。クラスで一番よく描けていたのが僕でした。
『逆さまの世界では、普段の絵の得手不得手は関係なくなり、ただ絵をよく見ることが求められた。そしていまにして思えば、何かをよく見ることに、僕はこの頃から少し長けていたのかもしれない』。国語だけでなく少年の成績は飛躍的に上がりました。
ある日、突然にクラスに将棋ブームが起こり、クラスでも強い方になっていきます。先生は『セガショーが強いのは、将棋に熱中しているからよね。勉強じゃなくてもいい、運動じゃなくてもいいのよ。どんなことでもいいから、それに熱中して、上手になったことがある人は、いつか必ずそのことが役に立つ日がきます。そういう人は間違いなく幸せをつかむことができます』『だからね、セガショー。君はそのままでいいの。今のままで十分。だいじょうぶよ』
僕が2学期中のホームルームの目標に将棋大会を提案したものの、女子はほとんど将棋ができないのです。『何とかしなさい、セガショー』の先生の要求に、放課後の教室で駒コマの動かし方から教え続け、遂に全員参加の将棋大会にこぎつけました。もうリーダーシップのある瀬川君・・・になっていました。先生の、目にも見えない子供の小さな才能の芽を見逃さず、掘り起こし、誉める、誉める、誉めることの大切さが人間を育てたのです。
父親から『好きなことを一生懸命にやることはいいことだ。だけど運動もした方ががいいぞ』の一言。4年生までの僕ならそのまま聞き流していたはず。しかし「僕、これから毎日2キロはしる」と宣言し実行します。将棋に夢中になってからの僕は、4年生の時の僕とはまるで別人のようになりました。
『5年生の一年間で、子供も親も、大きく変わったということだ。たったの一年だったとは思えないほど、苅間澤先生と過ごした一年間はたくさんのものを与えてくれた。それは僕だけでなく、あの教室にいた子どもたちすべてが感じていることなのだろう』。
奨励会の3段リーグに失敗して、鉄の掟の26歳という年齢制限で将棋界から引退に追い込まれた僕。それから大学、会社勤め…、なのにまた性懲りもなくプロ入りの試験将棋を行う嘆願書を出し、マスコミをも巻き込む挑戦をしました。その1局目がいきなり負けてしまった……。
その重圧に押しつぶされそうになっていた僕を救ってくれたのが、舞い込んだ一枚のドラえもんのハガキでした。ドラえもんの絵の上に書かれた文字は『だいじょうぶ。きっと良い道が拓かれます』。差出人はひらがなで「かりまさわひろこ」。
『嗚咽でのどが震え、文面が涙で見えなくなる。それをぬぐっては何度も読み返す。そのたびにまた、新しい涙があふれてくる。そうだった。すべてはこの人のおかげだった』。
25年ぶりに、先生は僕が大好きだったドラえもんにメッセージを託し、励ましてくれたのです。「だいじょうぶ。きっと良い道が拓かれます」と。
『先生に教えられたことをすっかり忘れていた。いつの間にか僕は僕でなくなっていた。僕は僕に戻ろう。僕は僕でいいのだから。心にできた固い岩を解かしきるまで、僕は泣き続けた』。
25年ぶりに先生からもらう「だいじょうぶ」。『何が何でも勝たねばならないという強迫観念にとらわれ、自分を見失っていた僕は、少学5年生の時と同じように、すべてを肯定されることで救われた』のです。『僕は僕のままでいい。試験がどんな結果になろうとも、それが僕にとって「よい道」なのだ。先生はそう言っているのだと思った』。
『先生はハガキに自分の住所を書いていなかった。返事の気遣いをさせまいとする配慮からだろう。それでも何とかして夢がかなったことを報告したい。そして心からお礼をいいたいと思っている』
後日譚として、最後のほうに苅間澤先生のことが出てきました。プロ試験に合格した後、先生にお礼の手紙を出したけど返事がなかったとのこと。代わって出版社の人が訪ねると『瀬川君にとって私は過去の人。そんなことに気を遣うより、ほかにやるべきことがあるはずです。夢を手にしたあとは、夢を本物にするためのつらさや苦しさがあるのだから』と。
実は先生も、35歳で教師になられたとのこと。結婚しても夢があきらめられず、30歳過ぎて大学に通いはじめ、35歳で教員試験に合格したのだそうです。
『先生は毎日、夢をかなえた喜びを感じながら教壇に立っていたのでしょう。だから先生の授業は、僕の心にいつまでも残っているのでしょう。そんな先生に出会えた僕は、幸せです』。
これだけでなく、息詰まるような「奨励会」の競争と友情。幼馴染の将棋のライバルとの交流等、どれをとっても迫力があります。湿っぽくなく駒を指すときのような乾いた響きの感じがするおすすめの1冊です。
読んだ感想はまず、文章が分かりやすく上手いと言うことです。てらいがなく、直球と言うところかな。グローブにバシッと快音が響く感じです。
ちょっと長いブログになったのは、久しぶりにパソコン入力したからです。