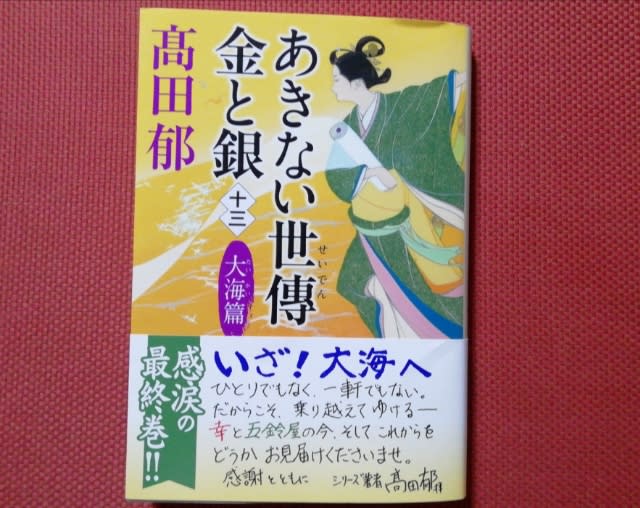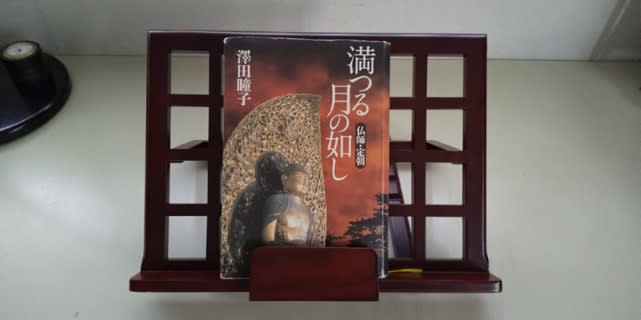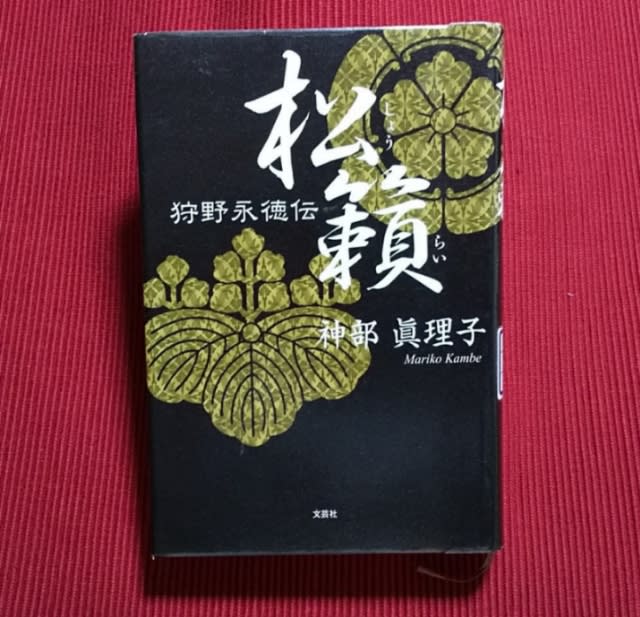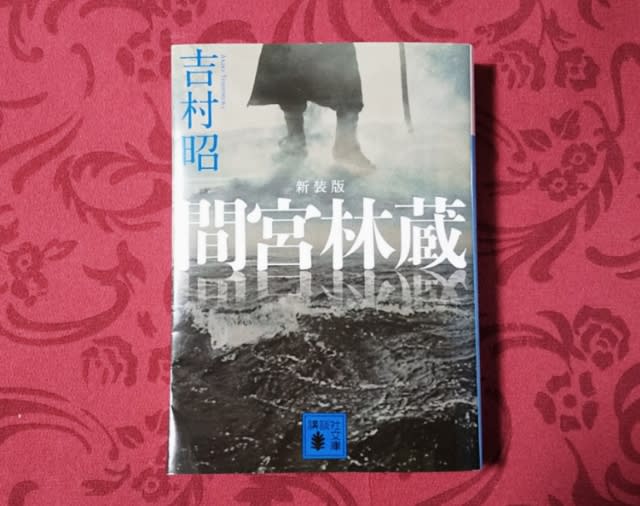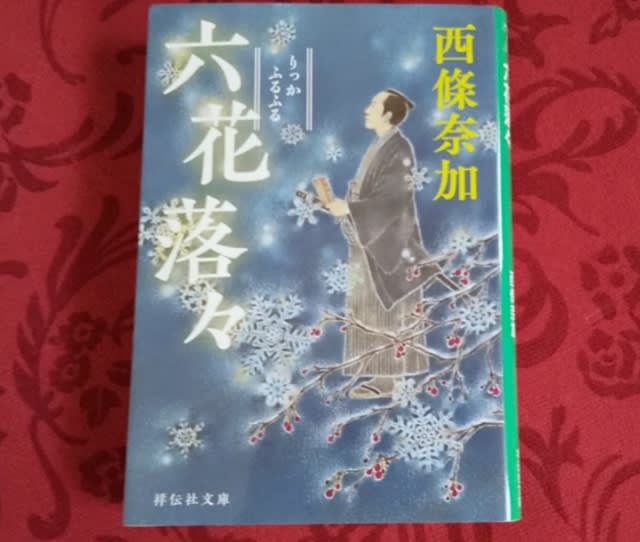来年のNHK大河『どうする家康』のキャストを見ただけで期待が持てます。
家康→松本潤、酒井忠次→大森南朋、本多正信→松山ケンイチ、本多忠勝→山田裕貴、榊原康政→杉野遥亮、井伊直政→板垣李光人、石川数正→松重豊、織田信長→岡田准一、築山殿→有村架純、豊臣秀吉→ムロツヨシ、今川義元→野村萬斎、武田信玄→阿部寛・・・。
この顔ぶれなら歴史の流れを掴んでドラマを見ないともったいない。それも関ヶ原以前の若い頃の家康を描くと聞いたので、それに合いそうな本を選んで読みました。

『天下 家康伝』上・下巻 火坂雅志著
『覇王の家』上・下巻 司馬遼太郎著
『関ヶ原』上・中・下巻 司馬遼太郎著
この中で「出番」が多いのが本多正信。「徳川四天王」には入りませんが、謀略と算盤勘定で家康の信任を得て以心伝心の盟友として常に側に居ます。「四天王」には嫉妬されていたようです。
経歴も三河一向一揆(家康の三大危機の一つ)で、家康を離れて一揆側につき敵として戦い袂を分かちますが、数年間の流浪の末に家康に帰参を許されます。過去にこだわらない家康の心の広さに感謝し、以前にも増して心底尽くしたと言われています。
経歴も三河一向一揆(家康の三大危機の一つ)で、家康を離れて一揆側につき敵として戦い袂を分かちますが、数年間の流浪の末に家康に帰参を許されます。過去にこだわらない家康の心の広さに感謝し、以前にも増して心底尽くしたと言われています。
武田信玄の言った言葉が「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」。唐の頭とは珍しい兜、平八は忠勝のことです。小身の家康には不釣り合いなほどの優れた武将だと、忠勝の活躍を誉めた言葉です。
生涯で57回の戦いに参戦し1度も傷を追わず「ただ、勝つのみ」の本多忠勝は「徳川四天王」の一人です。天下三名槍一つ「蜻蛉切」を愛用。刃長さ43㎝、柄の長さも6m。
三河武士には「知略」よりも「武勇」を尊ぶ風習があります。正信が知略なら、忠勝は武勇。同じ本多でも親子でも親戚でもなく、仲は良くなかったようです。
三河風土に根付いている三河武士団の結束の固さ、異常なほどの忠誠心。それが小牧長久手の戦いで秀吉に勝つ原動力になったのです。
「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」の家康の心のうちに分け入って、司馬さんはそれを分かりやすく描いています。鳴くまでどころか、鳴くのを押さえていた忍耐強さもしっかり見えてきます。
そんな三河家臣団の話が、司馬さんの歯切れのいい文章で綴られ、リズムさえ感じられて分厚いページでも飽きずに読めました。