国を動かすには、標語や掛け声が必要だ。(言葉の御旗、言霊立国)
今回、安倍政権は、自ら四文字熟語を叫んだわけでも無いが、いつの間にか、「アベノミクス」が標語になってしまった。
おそらく、史上初のカタカナ標語だろう。
この春始まったNHK新番組「伝えてピカッチ」は、なかなか面白い。
ことに、粘土細工は新手の「ジェスチャー」だ。
このゲームの一つに、カタカナ語を使わないでヒントを出す連想ゲームがあるが、若い子ほど苦戦する。
カタカナ語が氾濫しているから思いついたゲームだろうが、思惑通りで、制作はニヤリだ。
それにしても、グローバル化だ。近頃は言葉を日本語に翻訳して入ってこなくなった。映画のタイトルもほとんどそのままだし、歌の歌い方まで、わざわざ外国訛風の変な日本語だ。
カタカナ語は、和語や漢語のように「意味」を理解して覚えるのではなく、音と現象を直結させて覚える。
例えば「合コン」は、「合同コンパ」の短縮で、日本人は「合同」の意味は嫌でも解ってしまうが、「コンパ」の意味は深くは考えないだろう。
コンパは「company」が元で、仲間や会社の意味ぐらい理解するが、「company」と聞いた瞬間、comやconが「纏める合わせる繋ぐ」のようなニュアンスで、panyから「おしなべて」のようなニュアンスを感じることなど、全く無いだろう。
日本語で育った日本人が「合」「同」の意味を感じて「合同」を理解するように、英語で育った人は、たまたま同じような意味の「company」を、「com」「pany」の意味を感じて理解する。しかし、「godo」と聞いても固有名詞の音としてしか覚えない。
つまり、異国語は、理解して覚えるのではなく、直観的に何かありがたい「価値」がありそうなものとして受け入れる。
欧米人も[KWARATE]や[SUKIYAKI]は、何となくカッコ良い響きで覚える。「空手」「すき焼き」の意味まで考えない。
このように、カタカナ語とは、日本人にとって問答無用で価値を受け入れる薬用カプセルだ。中味を知れば口にしないようなものでも、ツルリと飲んでしまう。
グローバル化で、カタカナ語が氾濫していることは、日本社会がそれだけ、深く考えなくなったと言うことなのかも知れない。
深く考えなくても、言葉数が減るわけでもない。むしろ言葉が軽くなった分だけ、ためらいなく溢れることになる。
一世風靡の掛け声が、四文字熟語からカタカナ語になった日本。
スローガンを海外にまで共有することのメリット、デメリット。
ムード、ムードで、深く考えない、イケイケ景気。
いいのかな、いいのかな、何が何だか、マンボウ・ジャンボウ、さっぱりわからん
わてほんまによういわんわ、わてほんまによういわんわ











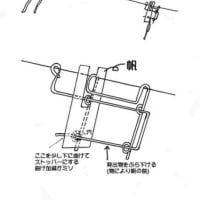






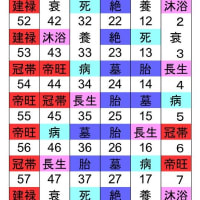
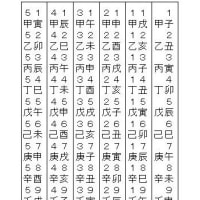
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます