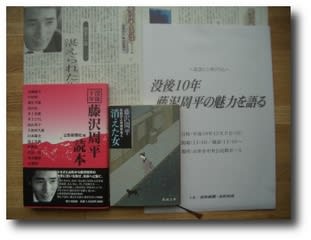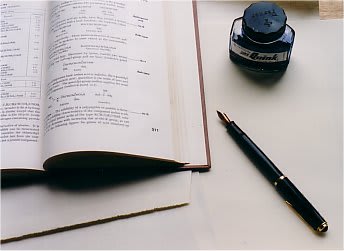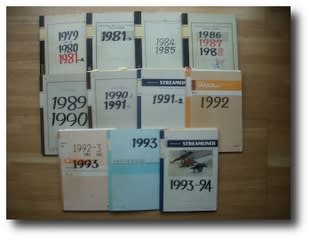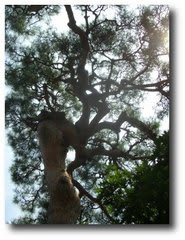山形新聞社は、藤沢周平没後十年を記念して、昨年一年間、特集を企画しました。同紙夕刊に掲載された記事内容はたいへん充実したもので、新しい発見も多く、連載を毎回楽しみにしておりました。当「電網郊外散歩道」でも、そのつど記事にしておりますが、せっかくの特集を、単行本にしてほしいものだと願っておりました。このたび、仙台市の書肆である荒蝦夷社から発売された『没後十年 藤沢周平読本』は、まさに本特集を1冊にまとめたもので、読み応えがあります。
構成と内容は、次の通りです。
第1章 私が選ぶ藤沢作品ベスト12 (高橋義夫)
用心棒日月抄/春秋山伏記/義民が駆ける/三屋清左衛門残日録/回転の門/蝉しぐれ/一茶/雲奔る/橋ものがたり/隠し剣秋風抄/詩塵/漆の実のみのる国
第2章 藤沢作品の表現世界 (中村明)
風/姿/女/剣/心/食/顔/笑/喩/視/始/終
第3章 藤沢周平 その生涯の追憶 (蒲生芳郎)
出会いの頃/同人誌時代/療養生活/妻の発病と死/「溟い海」で新人賞/直木賞受賞後/転機の『用心棒日月抄』/多忙な日々/昭和五十年代の豊熟期/『蝉しぐれ』前後/歴史小説/実りの時期
第4章 藤沢周平を語る
畠山弘/井上史雄/井上ひさし/高山秀子/久保田久雄/山本陽史/池上冬樹/牧野房/佐伯一麦/東谷慶昭/佐藤賢一
第5章 藤沢作品と私 49人の方々の短い文章
第6章 シンポジウム 没後十年 藤沢周平の魅力を語る
第1章と第3章は、新聞掲載時によく読みましたし、何度か感想や紹介を書きました。また、第6章のシンポジウムにも参加して、本ブログでも記事にしました。(*)
しかし、今日の単行本化によって、あらためて感心したのは、第2章の表現論です。藤沢周平の文章を、表現の面から分析し紹介して、実に興味深いものです。なるほど、と頷きます。本書のように単行本化されることにより、年間の特集の全体像が見えてきます。
そして、やはり第3章、「藤沢周平 その生涯の追憶」は、やはり見事な内容です。同級生、文学仲間の一人として、プライベートなことも知っている立場にあるはずですが、これまで積極的には公にすることがなかった事実もあります。たぶん、娘の展子さんや家族の周辺の人々が、没後十年を経て少しずつ語るようになってきたことに力を得て、作家の秘密にそっと触れているのでしょう。このあたりの、情のある姿勢が、初期短編集の公刊に関連するその内容とともに、心を打つものがあります。
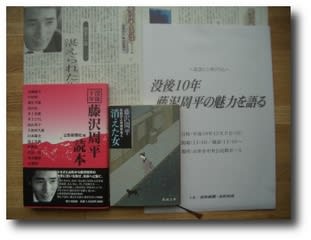
構成と内容は、次の通りです。
第1章 私が選ぶ藤沢作品ベスト12 (高橋義夫)
用心棒日月抄/春秋山伏記/義民が駆ける/三屋清左衛門残日録/回転の門/蝉しぐれ/一茶/雲奔る/橋ものがたり/隠し剣秋風抄/詩塵/漆の実のみのる国
第2章 藤沢作品の表現世界 (中村明)
風/姿/女/剣/心/食/顔/笑/喩/視/始/終
第3章 藤沢周平 その生涯の追憶 (蒲生芳郎)
出会いの頃/同人誌時代/療養生活/妻の発病と死/「溟い海」で新人賞/直木賞受賞後/転機の『用心棒日月抄』/多忙な日々/昭和五十年代の豊熟期/『蝉しぐれ』前後/歴史小説/実りの時期
第4章 藤沢周平を語る
畠山弘/井上史雄/井上ひさし/高山秀子/久保田久雄/山本陽史/池上冬樹/牧野房/佐伯一麦/東谷慶昭/佐藤賢一
第5章 藤沢作品と私 49人の方々の短い文章
第6章 シンポジウム 没後十年 藤沢周平の魅力を語る
第1章と第3章は、新聞掲載時によく読みましたし、何度か感想や紹介を書きました。また、第6章のシンポジウムにも参加して、本ブログでも記事にしました。(*)
しかし、今日の単行本化によって、あらためて感心したのは、第2章の表現論です。藤沢周平の文章を、表現の面から分析し紹介して、実に興味深いものです。なるほど、と頷きます。本書のように単行本化されることにより、年間の特集の全体像が見えてきます。
そして、やはり第3章、「藤沢周平 その生涯の追憶」は、やはり見事な内容です。同級生、文学仲間の一人として、プライベートなことも知っている立場にあるはずですが、これまで積極的には公にすることがなかった事実もあります。たぶん、娘の展子さんや家族の周辺の人々が、没後十年を経て少しずつ語るようになってきたことに力を得て、作家の秘密にそっと触れているのでしょう。このあたりの、情のある姿勢が、初期短編集の公刊に関連するその内容とともに、心を打つものがあります。