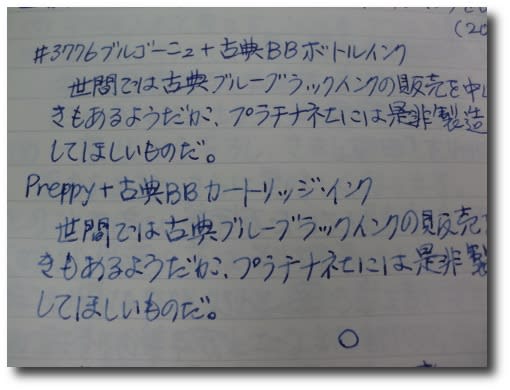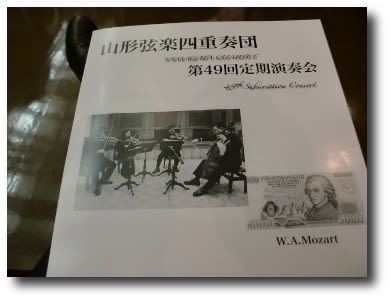新潮文庫で、宮城谷昌光著『楽毅』第四巻を読みました。
趙国内における沙丘の乱により主父が死に、楽毅は迷いを捨てて魏に移ります。首都の大梁において、法家の一人である李老子の門に入ります。「武のみに生きることにむなしさをおぼえました」という楽毅の言葉に真情を見た李老子のはからいで入門を許され、高弟の条有を通じて季進や単余などの協力を得ることとなります。魏にあっては守備隊の伍長に過ぎない里袁にも再会し、ようやく妻と子と一緒の生活を楽しむ中にも、中華の風は吹き止みません。斉の湣王は、愚かにも斉の柱石であるはずの孟嘗君を魏に追いやってしまいます。魏王は大喜びでしょう。魏に到着した孟嘗君は、ひそかに楽毅宅を訪ね、楽毅の意中を確かめると、昭王に、燕王への使者として楽毅を推挙します。
孟嘗君の推挙と犀首の肯諾を得て、魏王の正使として燕に赴いた楽毅は、かつての好敵手・趙与の示唆により、趙の奉陽君(李兌)を聘問し、その面識を得ます。そして燕国に入ると、これが驚くべき厚遇でした。いぶかしむ楽毅主従らでしたが、実は燕王の意図は楽毅本人にありました。斉に父を殺され、国土を蹂躙された過去を持つ燕の昭王は、大国斉への復讐を願っており、趙の侵略に抗し、中山国の滅亡を防ぐために奮闘した将軍・楽毅の力を欲していたのでした。魏王の臣下ではなく客に過ぎない楽毅に対して、昭王は楽毅が燕にとどまってくれなければ魏王への返書は書かぬと宣言します。楽毅は王の熱意にうたれ、魏王には妻子を人質として差し出す形で誠意を示し、燕と魏の交誼を成立させて、自らは燕にとどまることとします。かつて中山の将軍であった楽毅を昭王に面謁させた郭隗から、楽毅の承諾を聞いた昭王は、念願がかなったことに喜びますが、楽毅は王の宿願を果たすためには趙と結ことが肝要であることを提言し、雪路を踏んで趙に向かいます。
ここからの楽毅の外交は、見事と言うしかありません。主父を殺害したという負い目を抱える趙の恵文王は、燕の昭王の書翰に心の通う情義を感じ、また使者である楽毅が中山王に示した忠節を信頼し、燕と趙の会盟を約束し、二城を献じます。ただし、昭王に復命する際に人質として太子を趙に送ってはどうかと示唆したことで、わがままな太子がカチンと来たことは、楽毅には予想外でした。太子が楽毅を誹謗したことは、昭王を激怒させますが、逆に楽毅が妻子を魏王の人質としていることを知り、昭王は使者を魏に遣わして、妻子を楽毅のもとに返します。昭王の思いやりに触れた楽毅は、感激したことでしょう。
燕王の絶大なる信頼と太子の敵意の間にあって、楽毅は昭王の治世の間に斉への復讐の事業をなそうと計略を進めます。斉の湣王の暴虐と魏の孟嘗君の存在が楽毅の大きな戦略を助ける結果となります。そして、この後の楽毅の謀計は、ついに大国斉の大半を燕の支配下に置くことになり、昭王の大望はついに果たされるのですが、その過程の描き方は実に綿密です。それぞれの国の王や宰相、将軍と民の感情などが表され、軍事の物語としての重厚さを感じさせますが、一方で昭王の急逝に伴う太子の即位によって、楽毅の偉業が潰えてしまう様などは、思わず無常を感じてしまいます。と同時に、趙王に厚遇される晩年に、思わず安堵するのも確かです。
○
以前、北海道出張の前後に読み始めた記憶がありますが、再読三読、読み返すたびに読後感は爽快なものがあります。『孟嘗君』『太公望』などに並ぶ、作者の代表的な作品でありましょう。余談ですが、作品の終わり頃になるとやけに端折ってしまう傾向が否めない作者の通例にはよらず、最後まで力の入った物語となっていると感じます。
趙国内における沙丘の乱により主父が死に、楽毅は迷いを捨てて魏に移ります。首都の大梁において、法家の一人である李老子の門に入ります。「武のみに生きることにむなしさをおぼえました」という楽毅の言葉に真情を見た李老子のはからいで入門を許され、高弟の条有を通じて季進や単余などの協力を得ることとなります。魏にあっては守備隊の伍長に過ぎない里袁にも再会し、ようやく妻と子と一緒の生活を楽しむ中にも、中華の風は吹き止みません。斉の湣王は、愚かにも斉の柱石であるはずの孟嘗君を魏に追いやってしまいます。魏王は大喜びでしょう。魏に到着した孟嘗君は、ひそかに楽毅宅を訪ね、楽毅の意中を確かめると、昭王に、燕王への使者として楽毅を推挙します。
孟嘗君の推挙と犀首の肯諾を得て、魏王の正使として燕に赴いた楽毅は、かつての好敵手・趙与の示唆により、趙の奉陽君(李兌)を聘問し、その面識を得ます。そして燕国に入ると、これが驚くべき厚遇でした。いぶかしむ楽毅主従らでしたが、実は燕王の意図は楽毅本人にありました。斉に父を殺され、国土を蹂躙された過去を持つ燕の昭王は、大国斉への復讐を願っており、趙の侵略に抗し、中山国の滅亡を防ぐために奮闘した将軍・楽毅の力を欲していたのでした。魏王の臣下ではなく客に過ぎない楽毅に対して、昭王は楽毅が燕にとどまってくれなければ魏王への返書は書かぬと宣言します。楽毅は王の熱意にうたれ、魏王には妻子を人質として差し出す形で誠意を示し、燕と魏の交誼を成立させて、自らは燕にとどまることとします。かつて中山の将軍であった楽毅を昭王に面謁させた郭隗から、楽毅の承諾を聞いた昭王は、念願がかなったことに喜びますが、楽毅は王の宿願を果たすためには趙と結ことが肝要であることを提言し、雪路を踏んで趙に向かいます。
ここからの楽毅の外交は、見事と言うしかありません。主父を殺害したという負い目を抱える趙の恵文王は、燕の昭王の書翰に心の通う情義を感じ、また使者である楽毅が中山王に示した忠節を信頼し、燕と趙の会盟を約束し、二城を献じます。ただし、昭王に復命する際に人質として太子を趙に送ってはどうかと示唆したことで、わがままな太子がカチンと来たことは、楽毅には予想外でした。太子が楽毅を誹謗したことは、昭王を激怒させますが、逆に楽毅が妻子を魏王の人質としていることを知り、昭王は使者を魏に遣わして、妻子を楽毅のもとに返します。昭王の思いやりに触れた楽毅は、感激したことでしょう。
燕王の絶大なる信頼と太子の敵意の間にあって、楽毅は昭王の治世の間に斉への復讐の事業をなそうと計略を進めます。斉の湣王の暴虐と魏の孟嘗君の存在が楽毅の大きな戦略を助ける結果となります。そして、この後の楽毅の謀計は、ついに大国斉の大半を燕の支配下に置くことになり、昭王の大望はついに果たされるのですが、その過程の描き方は実に綿密です。それぞれの国の王や宰相、将軍と民の感情などが表され、軍事の物語としての重厚さを感じさせますが、一方で昭王の急逝に伴う太子の即位によって、楽毅の偉業が潰えてしまう様などは、思わず無常を感じてしまいます。と同時に、趙王に厚遇される晩年に、思わず安堵するのも確かです。
○
以前、北海道出張の前後に読み始めた記憶がありますが、再読三読、読み返すたびに読後感は爽快なものがあります。『孟嘗君』『太公望』などに並ぶ、作者の代表的な作品でありましょう。余談ですが、作品の終わり頃になるとやけに端折ってしまう傾向が否めない作者の通例にはよらず、最後まで力の入った物語となっていると感じます。