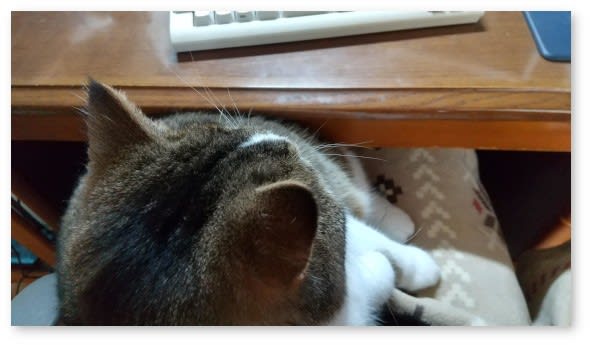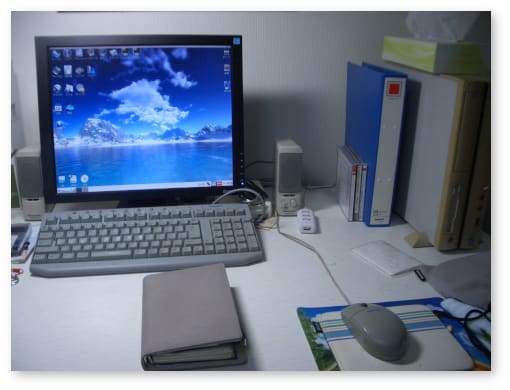8月のはてなブログ「電網郊外散歩道」記事更新リストです。
【8月】
2025/08/23 愛用の万年筆プラチナ#3776ブルゴーニュに古典BBインクを補充
2025/08/22 農家はほんとにお天気次第〜今年の桃「あかつき」を振り返る
2025/08/21 川中島白桃の収穫期が近づき、反射シートを敷く
2025/08/20 スケジュール管理の過去・現在・未来
2025/08/19 舘神龍彦『手帳と日本人』を読む
2025/08/18 再びスパゲッティ・ボロネーゼを作る
2025/08/17 日曜夜のNHK-FMはオッコ・カム指揮で山響のシベリウス(1)
2025/08/16 鳥獣保護管理法と生類憐れみの令と殺生戒〜クマ襲撃事件に思う
2025/08/15 今年も慌ただしくお盆の日々が過ぎていく〜花火大会が終わって
2025/08/14 お盆もボクには関係ない
2025/08/13 "It's OK"というメッセージが最後の輝きとなっても
2025/08/12 お盆前のスーパーには
2025/08/11 YouTubeでドヴォルザークの弦楽四重奏曲「アメリカ」を聴く
2025/08/10 へぇ〜、山形市は文具店が充実している街なのか!
2025/08/09 國本知里『クリエイターのためのChatGPT活用大全』を読む
2025/08/08 山形弦楽四重奏団第96回定期演奏会でモーツァルト、ドヴォルザーク、ベートーヴェンを聴く
2025/08/07 雨の合間に桃「あかつき」を収穫し初出荷となる
2025/08/06 門井慶喜『東京、はじまる』を読む
2025/08/05 ようやく小雨が降った
2025/08/04 山響第326回定期演奏会でバルトーク、サン=サーンス、シューマンを聴く
2025/08/03 インク切れJetstreamの芯交換と汚れたグリップを洗浄してみた結果
2025/08/02 晩生種の桃にパルス・スプリンクラーで散水する
2025/08/01 日照りの影響はモモの大きさにも現れている
◯
goo ブログのサービスが停止すると、引越ししなかった(できなかった)ブログはやがて消滅します。それは仕方のないことではありますが、長年ブログを綴っていると、今はもう更新が途絶えているけれど強く印象に残っているブログというものがあります。サービス終了によって跡形もなく消えてしまう前に、ブラウザのブックマーク「sleeping」の中から、goo ブログを中心にいくつかをリストアップしてみましょう。
「クラシック音楽のひとりごと」 goo ブログ mozart1889 さんのブログ。当初は Doblog で継続していましたが、Doblog がHDDのバックアップ障害でサービス停止に追い込まれた後、goo ブログに移行しました。「ガハハ」という笑い声を入れながら関西弁で綴るクラシック音楽の記事は親しみ深いものでした。島の支店に単身で転勤した後、2011年にぷっつりと更新が止まり、病気で倒れたか事故にあったかと心配しましたが、ついに再開されることはありませんでした。
静かな場所 goo ブログ お子さんが障碍を持ち、ご自身も難しい病気と戦いながら、心折れそうになる奥様を支えつつ、尊敬するバーンスタインを中心にクラシック音楽と仕事や日々の出来事を記事に綴っていました。2022年5月の投稿を最後に更新が途絶えました。おそらくはご病気の悪化で亡くなられたのではないかと想像しています。勇気を持って生きる姿に読む側が励まされるような、静かで温かいブログでした。心からご冥福をお祈りいたします。