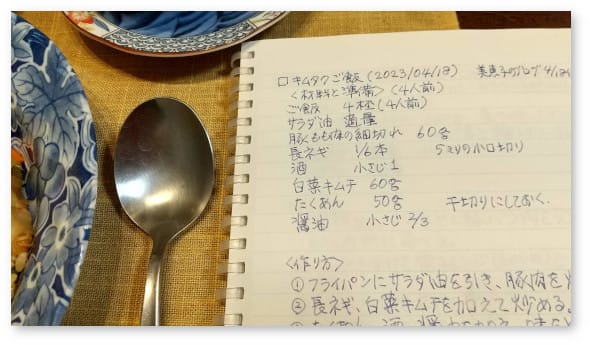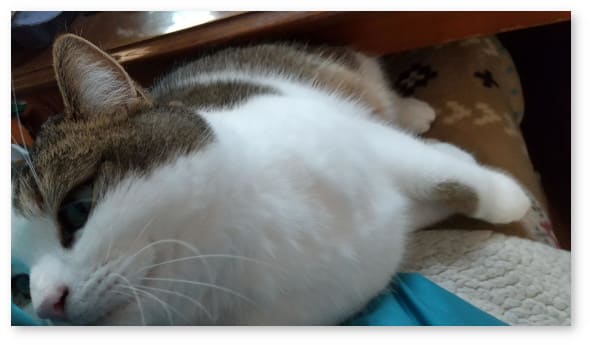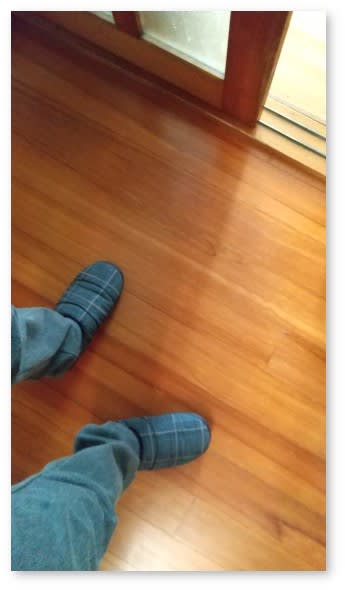先日、給湯器が故障し、お風呂や台所、洗面所等のお湯が使えなくなりました。リフォーム業者を通じて点検修理を依頼したところ、給湯器内部のボイラーの配管接合部から水漏れしたのが原因とのこと。給湯器内部の故障は10年保証のため無償修理となるそうで、昨日、ようやく修理が完了しました。


ボイラーの湯沸かし缶本体とバーナーセット、電磁ポンプ、温度ヒューズ、電源ケース、感電装置などの交換となり、サービスショップの人が午後いっぱいかかって直してくれました。幸いにお天気が良かったから大丈夫だったものの、野外での作業は大変だったことでしょう。休憩時に差し入れた缶コーヒー等の飲み物の中からトマトジュースを選んだサービスマンは、健康意識が高い人だったのかも(^o^)/

設定も元通りにしてもらい、台所や洗面所で自由にお湯が使えていつでもお風呂に入れる生活の便利さ、ありがたさを感じました。もう一つ、設備の不具合が起こったときに、リフォームを担当した業者を通して相談することの大切さを感じました。10年保証で無償修理というサービスはありがたい。建てっぱなし、売りっぱなしではないスタイルは、2016年に築250年の古民家をリフォームした我が家にとっては大切な要件のように感じます。