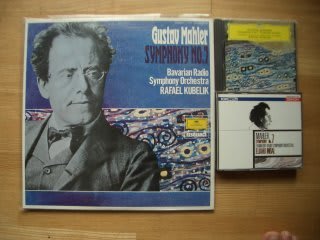地元紙「山形新聞」夕刊には、木曜日に藤沢周平の没後10年を記念する特集記事が掲載されています。この内容がたいへん充実していることは、以前書いた(*)とおりです。今週は、作家の池上冬樹氏が黒土監督の映画「蝉しぐれ」を取り上げ、ひとつだけ、「原作と異なる場面がクライマックスにある」ことを指摘しています。
原作では、最終章「蝉しぐれ」において、藩主と死別した40代のお福さまが、今は郡奉行となり牧助左衛門を名乗る文四郎に手紙を送り、二人は二十数年ぶりに再会します。そして、例の「あのひとの白い胸など見なければよかった」という場面になりますが、黒土監督の映画「蝉しぐれ」ではこのシーンを描くことを避け、原作にない、駕籠の格子から目で最後の別れをする場面としています。池上冬樹氏はこの選択を支持し、藤沢周平が原作でなぜ生々しい男女の抱擁と接吻の場面を描いたのか、「海鳴り」の愛の形や「逢びき」等の洋画(恋愛映画)の結末の影響などとして、その要因を推測しています。
ここからは私の考えです。実は、黒土三男監督は、映画「蝉しぐれ」を制作する前にも、NHKの金曜時代劇「蝉しぐれ」の脚本を書いています。このときは、お福様と助左衛門の対面に続く濡れ場を、かなり象徴的ではありますが、しっかりと描いていました。しかし、視聴者の反応は二分されたようです。黒土監督はこのことを頭に入れて、ラストの別れの場面を構想したのではないか。
原作は文芸作品ですので、読者が一人で場面を想像し、ひそやかに楽しむことができます。したがって、どんなに色っぽい場面であろうと、かまいません。ところが、テレビや映画は、リアルで生々しい。そこでは、原作と同じように再現することが、必ずしも原作の味わいを生かすことにはならない場合が出てくるからではないでしょうか。原作から初恋の要素を切り出して見せた黒土監督の映像作品「蝉しぐれ」は、原作に流れる、美しい人妻たる矢田淑江の色香や、中年になって再会したお福様への「愛憐の情」など、物語の厚みを構成する多様な要素をそぎ落とすことで、成り立っているように思います。
(*):藤沢周平の転機~蒲生芳郎氏の追憶より
原作では、最終章「蝉しぐれ」において、藩主と死別した40代のお福さまが、今は郡奉行となり牧助左衛門を名乗る文四郎に手紙を送り、二人は二十数年ぶりに再会します。そして、例の「あのひとの白い胸など見なければよかった」という場面になりますが、黒土監督の映画「蝉しぐれ」ではこのシーンを描くことを避け、原作にない、駕籠の格子から目で最後の別れをする場面としています。池上冬樹氏はこの選択を支持し、藤沢周平が原作でなぜ生々しい男女の抱擁と接吻の場面を描いたのか、「海鳴り」の愛の形や「逢びき」等の洋画(恋愛映画)の結末の影響などとして、その要因を推測しています。
ここからは私の考えです。実は、黒土三男監督は、映画「蝉しぐれ」を制作する前にも、NHKの金曜時代劇「蝉しぐれ」の脚本を書いています。このときは、お福様と助左衛門の対面に続く濡れ場を、かなり象徴的ではありますが、しっかりと描いていました。しかし、視聴者の反応は二分されたようです。黒土監督はこのことを頭に入れて、ラストの別れの場面を構想したのではないか。
原作は文芸作品ですので、読者が一人で場面を想像し、ひそやかに楽しむことができます。したがって、どんなに色っぽい場面であろうと、かまいません。ところが、テレビや映画は、リアルで生々しい。そこでは、原作と同じように再現することが、必ずしも原作の味わいを生かすことにはならない場合が出てくるからではないでしょうか。原作から初恋の要素を切り出して見せた黒土監督の映像作品「蝉しぐれ」は、原作に流れる、美しい人妻たる矢田淑江の色香や、中年になって再会したお福様への「愛憐の情」など、物語の厚みを構成する多様な要素をそぎ落とすことで、成り立っているように思います。
(*):藤沢周平の転機~蒲生芳郎氏の追憶より