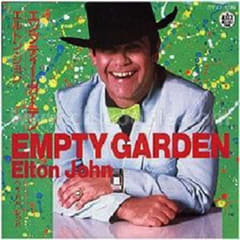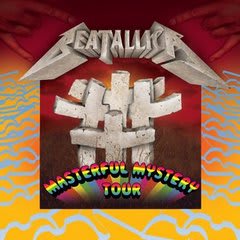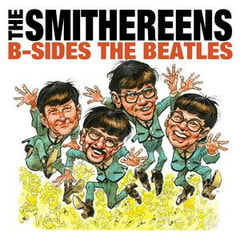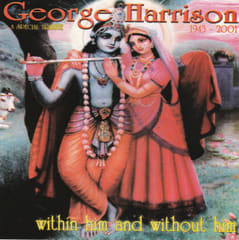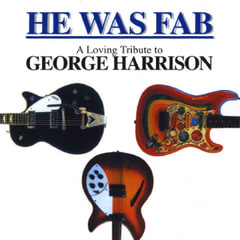少し前にネットでマーク・チャップマンの仮釈申請却下のニュースを読んだ。仮釈やと?ナメとんのか!心神喪失だか何だか知らないが、あのクサレ外道がまだ塀の中で、しかも三食付きでのうのうと生きていること自体許し難いのに、仮釈で出して自由にシャバの空気を吸わせるなんて絶対にあってはならない。私的にはゴルゴ13 にでも依頼して即刻射殺してほしいくらいのレベルだ。あの忌まわしい事件から30年経った今でも、12月8日になるとジョンを失った悲しみと共に奴に対する怒りが沸々と込み上げてくるのを抑えられない。怒りなどという言葉では生ぬるいこの気持ちはこの30年間変わっていないのだが、ブログで恨みつらみを延々と並べ立てるワケにもいかないので、今日は彼への追悼ソングの中で最も心に沁みたエルトン・ジョンの「エンプティ・ガーデン」を聴いて心を鎮めることにしよう。
私が初めてエルトン・ジョンという名前を耳にしたのは洋楽を聴き始めてすぐの頃で、彼のアルバム「キャプテン・ファンタスティック・アンド・ザ・ブラウン・ダート・カウボーイ」が全米アルバムチャートで初登場1位を記録したと音楽誌で大ニュースになっていた。アルバムチャート初登場1位なんて今では珍しくも何ともないが、当時としては前人未到の快挙だったようで、 “そんなに凄いアルバムやったら聴いてみよう” とLPを買ってきて聴いてみたのだが、毒にも薬にもならんような退屈な内容で、私にはどこがエエのかサッパリ分からなかった。その後エルトンの参加で話題になった「心の壁、愛の橋」やMSGでのジョンとの共演ライヴ・シングルも聴いたが、結局エルトン・ジョンの良さは分からずじまいだった。
そんな私が彼に瞠目したのは1982年、いつものように「ベスト・ヒット・USA」を見ていた時のこと、この「エンプティ・ガーデン」がチャート急上昇曲ということで紹介されたのだ。ビデオ・クリップに付けられた字幕の日本語訳を見ながらエルトンの歌声を聴いていた私は、不覚にも感動で目頭が熱くなってしまった。エルトンと公私共に仲の良かったジョンを “a gardener(庭師)” に例えたバーニー・トーピンの歌詞が圧倒的に、超越的に、芸術的に素晴らしい;
ここで何が起きたんだろう?
夕暮れ時のニューヨーク
僕は何も生えてない庭を見つけた
ここには誰が住んでたんだろう?
その人は立派な庭師だったに違いない
涙を刈り取り、良い作物を育てた
でも今はそうじゃない
一匹の虫が庭を食い散らかしてしまったんだ
何のためにあるんだろう?
赤褐色のドアに面した
この荒れ果てた小さな庭は
歩道の割れ目からはもう何も生えてこない
ここには誰が住んでたんだろう?
その人は立派な庭師だったに違いない
涙を刈り取り、良い作物を育てたんだ
僕らは驚き、愕然とした
彼の代わりになる人なんて誰もいない
ドアをノックしてるのに 誰も出てくれない
一日中ずっとドアをノックしてるのに
呼び続けてるんだ
ヘイ、ジョニー 一緒に遊ぼうぜ、ってね
涙にくれながら
こう言う人々もいる 若い頃の彼は最高の仕事をしたと
でももし彼がそれを聞いたら
人は年齢を重ねて成長していくものだと言っただろう
その人は立派な庭師だったに違いない
涙を刈り取り、良い作物を育てた
僕らは今 雨を願う そして雨粒一つ一つの音が
君の名前に聞こえるんだ
ジョニー もう一緒に遊べないのかい? この空っぽの君の庭で...
特にサビの I’ve been knocking but no one answers... の部分はビートルズ・ファンなら涙なしには聴けないだろう。バーニー・トーピンの天才ここに極まれり、と言いたくなる大傑作だ。
そしてこのジョンへの哀悼の想いに満ち溢れた歌詞を切々と歌い上げるエルトンのヴォーカルがこれまた素晴らしい。彼のまるで慟哭のように響く歌声が、その歌詞の一言一言が私の心をビンビン震わせるのだ。そこには私を失望させた「キャプテン・ファンタスティック」で聞かれた虚構のかけらもなく、ただただ深いバラッド性があった。私はこの曲を聴いて初めてエルトン・ジョンの良さを理解できた気がした。
その後の私は初期の大名曲「ユア・ソング」やダイアナ妃に捧げられた「キャンドル・イン・ザ・ウインド」(←元々はマリリン・モンローの事を歌った曲やけど...)を聴くに至って “エルトンの神髄はバラッドにあり” を確信したのだが、そのきっかけとなったのが数あるジョンの追悼曲の中で一番好きなこの「エンプティ・ガーデン」なのだ。
Elton John- Empty Garden (with lyrics and The Beatles pics)
私が初めてエルトン・ジョンという名前を耳にしたのは洋楽を聴き始めてすぐの頃で、彼のアルバム「キャプテン・ファンタスティック・アンド・ザ・ブラウン・ダート・カウボーイ」が全米アルバムチャートで初登場1位を記録したと音楽誌で大ニュースになっていた。アルバムチャート初登場1位なんて今では珍しくも何ともないが、当時としては前人未到の快挙だったようで、 “そんなに凄いアルバムやったら聴いてみよう” とLPを買ってきて聴いてみたのだが、毒にも薬にもならんような退屈な内容で、私にはどこがエエのかサッパリ分からなかった。その後エルトンの参加で話題になった「心の壁、愛の橋」やMSGでのジョンとの共演ライヴ・シングルも聴いたが、結局エルトン・ジョンの良さは分からずじまいだった。
そんな私が彼に瞠目したのは1982年、いつものように「ベスト・ヒット・USA」を見ていた時のこと、この「エンプティ・ガーデン」がチャート急上昇曲ということで紹介されたのだ。ビデオ・クリップに付けられた字幕の日本語訳を見ながらエルトンの歌声を聴いていた私は、不覚にも感動で目頭が熱くなってしまった。エルトンと公私共に仲の良かったジョンを “a gardener(庭師)” に例えたバーニー・トーピンの歌詞が圧倒的に、超越的に、芸術的に素晴らしい;
ここで何が起きたんだろう?
夕暮れ時のニューヨーク
僕は何も生えてない庭を見つけた
ここには誰が住んでたんだろう?
その人は立派な庭師だったに違いない
涙を刈り取り、良い作物を育てた
でも今はそうじゃない
一匹の虫が庭を食い散らかしてしまったんだ
何のためにあるんだろう?
赤褐色のドアに面した
この荒れ果てた小さな庭は
歩道の割れ目からはもう何も生えてこない
ここには誰が住んでたんだろう?
その人は立派な庭師だったに違いない
涙を刈り取り、良い作物を育てたんだ
僕らは驚き、愕然とした
彼の代わりになる人なんて誰もいない
ドアをノックしてるのに 誰も出てくれない
一日中ずっとドアをノックしてるのに
呼び続けてるんだ
ヘイ、ジョニー 一緒に遊ぼうぜ、ってね
涙にくれながら
こう言う人々もいる 若い頃の彼は最高の仕事をしたと
でももし彼がそれを聞いたら
人は年齢を重ねて成長していくものだと言っただろう
その人は立派な庭師だったに違いない
涙を刈り取り、良い作物を育てた
僕らは今 雨を願う そして雨粒一つ一つの音が
君の名前に聞こえるんだ
ジョニー もう一緒に遊べないのかい? この空っぽの君の庭で...
特にサビの I’ve been knocking but no one answers... の部分はビートルズ・ファンなら涙なしには聴けないだろう。バーニー・トーピンの天才ここに極まれり、と言いたくなる大傑作だ。
そしてこのジョンへの哀悼の想いに満ち溢れた歌詞を切々と歌い上げるエルトンのヴォーカルがこれまた素晴らしい。彼のまるで慟哭のように響く歌声が、その歌詞の一言一言が私の心をビンビン震わせるのだ。そこには私を失望させた「キャプテン・ファンタスティック」で聞かれた虚構のかけらもなく、ただただ深いバラッド性があった。私はこの曲を聴いて初めてエルトン・ジョンの良さを理解できた気がした。
その後の私は初期の大名曲「ユア・ソング」やダイアナ妃に捧げられた「キャンドル・イン・ザ・ウインド」(←元々はマリリン・モンローの事を歌った曲やけど...)を聴くに至って “エルトンの神髄はバラッドにあり” を確信したのだが、そのきっかけとなったのが数あるジョンの追悼曲の中で一番好きなこの「エンプティ・ガーデン」なのだ。
Elton John- Empty Garden (with lyrics and The Beatles pics)