2012年10月2日(火)
連れ合いと、JR上越線の群馬総社(ぐんまそうじや)駅周辺にある古墳めぐりに出
かけた。10時47分に群馬総社駅に着く。
駅前の車道を南進し、県道107号との交差点際の諏訪神社へ。天正18(1590)
年に諏訪頼永が総社領主となり、信州の諏訪神社を勧請したのがはじめとか。

社殿は上社(かみしや)、下社(しもしや)を合わせており、三間社と呼ぶ東西に拝礼
場がある特殊な構造。境内には、百庚申や二十二夜塔などがある。
県道に出て左折、すぐ先で南への路地を入ると、最初の総社二子山古墳(国史跡)が
ある。6世紀の築造とされ全長は約90m、この地域では最後の前方後円墳だという。

桜の古木に覆われた墳丘へヒガンバナの咲く方墳側から上り、丘頂を進んで円墳側から
下りた。そばに、黒瓦の光るりっぱな民家がある。

南側の市立六中と天狗岩用水に挟まれた愛宕山(あたごやま)古墳へ。墳丘には広葉樹
と下草が生い茂り、上がれない。南から東へと下を一周して古墳際の駐車場に戻った。

古墳の規模は一辺56mの大型方墳で、いま面影は無いが幅18mの周濠を巡らせてい
たという。
県道に戻って東進して、天狗岩用水を越える。橋際に「群馬水力発電発祥の地」の説明
板がある。下に少しだけ残るレンガ積みが、明治27(1895)年5月、県内最初の水
力を利用した総社発電所の取水口跡だという。

さらに、ここは天狗岩用水の立石橋に設置した、総社城下町の西木戸跡だったとの説明
板もあった。
天狗岩用水は、総社城主秋元長朝(あきもとながとも)が慶長7(1602)年から3
年かけて完成したもの。用水のお陰で領内の水田が広がり、6千石から1万石の豊かな土
地になり、領民はのち、長朝に感謝を込めて秋元氏の菩提寺である光厳寺に「力田遺愛碑
(りょくでんいあいのひ)」を建てたという。
次の交差点を北に入り、その次の通りの突き当たりにある元景寺(げんけいじ)に行く。
秋元長朝が天正15(1587)年に総社城主となり、その年に逝去した父景朝の菩提の
ために開創したもの。

広い境内には、本堂を中心に鐘楼の無い鐘楼堂、五千石用水の守り神、羽階(はがい)
権現堂、前橋市内最古という応永の石仏↓、天満天神宮、水子地蔵尊、天明3(1783)
年の浅間山大噴火で嬬恋方面から利根川を流された惨死者を供養する供養塔など、歴史的
なものが多く、幼稚園も設置されている。

本堂の背後、利根川右岸堤防を見下ろす広い墓域の中心に秋元氏墓地があり、宝篋印塔
(ほうきよういんとう)が立つ。

右隣には、淀君の墓と伝えられる墓が、左隣には秋元景朝の墓がある。
墓地は利根川の右岸高台にある勝山城跡で、雲に隠さた赤城山や、子持山、小野子山、
榛名山などが望まれる。墓地を回った後、鐘楼堂のそばで昼食をし、梅の古木の並ぶ参道
を進んで山門を出た。
南に向かい、鍵の手のところで県道107号に入り、三国(みくに)街道の総社宿だっ
たあたりに進む。当時の宿並みは約1.2㎞あり、街路に面して短冊形の屋敷が左右に
120軒前後ずつ並んでいたという。
郵便局の手前に、総社大明宮があった。総社領主秋元長朝が伊勢神宮を勧請(かんじょ
う)したもの。のちの寛政3(1791)年に造営した伊勢の内宮遙拝殿(ないくうよう
はいでん)は、12本の丸柱の門構えという珍しい構造である。

すぐ近くの神社とは反対側の三差路際に、古い大きな商家らしい建物がある。何の家か
は、その後回ったに総社資料館で分かった。

その前に、神社側の三差路を左折して、神社の背後200mほどにある遠見山古墳に行く。
畑に囲まれた墳丘長約70mの古墳は、五世紀後半の前方後円墳。総社城の遠見に使われた
ので遠見山古墳と呼ばれており、総社古墳群の中でも最古のものという。

三差路に戻り、すぐ先の反対側の三差路に進む。天狗岩用水の堀割沿いに北に入ると、総
社資料館があった。街道に面した先ほどの大きな建物の主、旧本間酒店の酒造用の2棟を利
用したものである。

館内には、総社古墳群からの出土品や複製品、歴史を示すパネル、この後回った山王廃寺
の出土品、本間酒店の酒造用品、前橋特産のこけしなどが展示されていた。

別棟には古い農具や家具などが並び、小学生の体験学習にも利用されているようだ(入場
無料)。

天狗岩用水の下流側、公民館の広い駐車場の南に回り、7世紀末と推定される蛇穴山(じ
ゃけつさん)古墳(国史跡)へ。一辺39mの方墳で、墳丘は二段構造になっている。

南面の石室は羨道(せんどう)が無く、玄門と玄室だけの特殊な構造。天井、奥壁、左右
壁とも見事に加工された1枚の巨岩で、当時の石材加工技術の優秀さが知れる。玄門から中
に入って内部も見られる。

古墳前の流れは五千石用水。慶長12(1607)年頃、総社鉱泉付近の天狗岩用水から
引水され、潅漑地域が五千石に達することからその名が呼ばれるようになったとか。城の内
堀には不可欠な用水で、後には宿場町に利用されて防火用水にもなったという。

蛇穴山古墳から、駐車場と道路を隔ててすぐ西側にある宝塔山(ほうとうざん)古墳(国
史跡)に回る。

一辺約55m、高さ11mあり、三段に築造された方墳で、県内古墳の最終末期、7世紀
末から8世紀初頭のものと見られ、方墳としては全国的に見ても大きなものらしい。

北東から石段を上がり、左に回り込むと墳丘上に総社領主秋元氏の歴代墓地がある。その
あたりからは、東方に群馬県庁など前橋市の中心街が望まれる。

南面には横穴式石室があり、羨道、前室、玄室に分かれている。石室の壁面には精巧に加
工した切石が使われ、随所に切組積みの手法が見られ、それらは最高水準を示すという。
玄室にある家型石棺は、底部が格狭間(ごうざま)という形にくり抜かれていて、古墳への
仏教文化の影響を物語っているようだ。

宝塔山古墳の西北側に接して、光厳寺(こうがんじ)がある。光厳寺は総社城内の西南隅
近くに位置し、城主秋元長朝が母の菩提寺として慶長12(1607)年に造営したもの。

本柱が門の中心線から前方にずれていて、江戸初期かそれ以前の建立と推定されるという
薬医門の横から境内に入った。中心に文政3(1820)年再建の大本堂↑があり、右手に
文化9年(1812)再建という、朱塗り神殿風の秋元家御廟所(ごびようしよ)が並んで
いる。

その間に立つ高さ4.17m、安山岩製七層の東覚寺層塔は、室町時代の特徴をよく表し
ていて、もと総惣社町井の東覚寺にあったものと伝えられるという。
光厳寺を出て南側の県道6号を西へ、JR線路を跨道橋で越えて次のY字路を南西に入る。
幅広い産業道路を横断すると、平行して五千石堰(ごせんごくぜき)用水が流れ、すぐに
八幡川の山王橋を渡る。

五千石堰用水は、天狗岩用水より以前から存在していたことなどが、橋のそばの説明板に
記されていた。

橋から200m余り、十字路際の小公園に古い双体道祖神が立ち、南側には、五千石堰用
水で水死した子どもの供養と災難予防のため、宝暦年代(1751~64)に建立されたら
しい、山王子育地蔵尊が小さい社に祭られている。
その十字路を西に200m足らず進んで日枝(ひえ)神社に行く。境内はそう広くはない
が、この周辺は国史跡の山王廃寺跡である。

山王廃寺は約1300年前この地に建てられ、講堂を中心に回廊を巡らせ、中に五重塔や
金堂が、講堂の背後には僧坊があったと推定されているという。

境内には、ほかでは鳥取県の大寺廃寺のみという石製の鴟尾(しび)↑、山王廃寺五重塔
の心柱根巻石(しんばしらねまきいし)や塔心礎(とうしんそ)が、屋根付きの建物に保存
されている。寺の建立時期は、出土瓦などから7世紀末の白鳳期頃と考えられるようだ。
社殿の周辺には、元禄8(1695)年の庚申塔など18基の古い石造物が並んでいた。

周辺の民家は、何れも広い敷地に大きな建物が立っていて、生活のゆとりが感じられる。

産業道路に戻りそばのバス停で時刻を見たが、しばらくバスは無い。産業道路を北へ進ん
で日進電機の北を回り、16時12分に群馬総社駅に戻った。
(天気 晴後曇、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 前橋、歩行地 前橋市、歩数
16,700)

にほんブログ村
連れ合いと、JR上越線の群馬総社(ぐんまそうじや)駅周辺にある古墳めぐりに出
かけた。10時47分に群馬総社駅に着く。
駅前の車道を南進し、県道107号との交差点際の諏訪神社へ。天正18(1590)
年に諏訪頼永が総社領主となり、信州の諏訪神社を勧請したのがはじめとか。

社殿は上社(かみしや)、下社(しもしや)を合わせており、三間社と呼ぶ東西に拝礼
場がある特殊な構造。境内には、百庚申や二十二夜塔などがある。
県道に出て左折、すぐ先で南への路地を入ると、最初の総社二子山古墳(国史跡)が
ある。6世紀の築造とされ全長は約90m、この地域では最後の前方後円墳だという。

桜の古木に覆われた墳丘へヒガンバナの咲く方墳側から上り、丘頂を進んで円墳側から
下りた。そばに、黒瓦の光るりっぱな民家がある。

南側の市立六中と天狗岩用水に挟まれた愛宕山(あたごやま)古墳へ。墳丘には広葉樹
と下草が生い茂り、上がれない。南から東へと下を一周して古墳際の駐車場に戻った。

古墳の規模は一辺56mの大型方墳で、いま面影は無いが幅18mの周濠を巡らせてい
たという。
県道に戻って東進して、天狗岩用水を越える。橋際に「群馬水力発電発祥の地」の説明
板がある。下に少しだけ残るレンガ積みが、明治27(1895)年5月、県内最初の水
力を利用した総社発電所の取水口跡だという。

さらに、ここは天狗岩用水の立石橋に設置した、総社城下町の西木戸跡だったとの説明
板もあった。
天狗岩用水は、総社城主秋元長朝(あきもとながとも)が慶長7(1602)年から3
年かけて完成したもの。用水のお陰で領内の水田が広がり、6千石から1万石の豊かな土
地になり、領民はのち、長朝に感謝を込めて秋元氏の菩提寺である光厳寺に「力田遺愛碑
(りょくでんいあいのひ)」を建てたという。
次の交差点を北に入り、その次の通りの突き当たりにある元景寺(げんけいじ)に行く。
秋元長朝が天正15(1587)年に総社城主となり、その年に逝去した父景朝の菩提の
ために開創したもの。

広い境内には、本堂を中心に鐘楼の無い鐘楼堂、五千石用水の守り神、羽階(はがい)
権現堂、前橋市内最古という応永の石仏↓、天満天神宮、水子地蔵尊、天明3(1783)
年の浅間山大噴火で嬬恋方面から利根川を流された惨死者を供養する供養塔など、歴史的
なものが多く、幼稚園も設置されている。

本堂の背後、利根川右岸堤防を見下ろす広い墓域の中心に秋元氏墓地があり、宝篋印塔
(ほうきよういんとう)が立つ。

右隣には、淀君の墓と伝えられる墓が、左隣には秋元景朝の墓がある。
墓地は利根川の右岸高台にある勝山城跡で、雲に隠さた赤城山や、子持山、小野子山、
榛名山などが望まれる。墓地を回った後、鐘楼堂のそばで昼食をし、梅の古木の並ぶ参道
を進んで山門を出た。
南に向かい、鍵の手のところで県道107号に入り、三国(みくに)街道の総社宿だっ
たあたりに進む。当時の宿並みは約1.2㎞あり、街路に面して短冊形の屋敷が左右に
120軒前後ずつ並んでいたという。
郵便局の手前に、総社大明宮があった。総社領主秋元長朝が伊勢神宮を勧請(かんじょ
う)したもの。のちの寛政3(1791)年に造営した伊勢の内宮遙拝殿(ないくうよう
はいでん)は、12本の丸柱の門構えという珍しい構造である。

すぐ近くの神社とは反対側の三差路際に、古い大きな商家らしい建物がある。何の家か
は、その後回ったに総社資料館で分かった。

その前に、神社側の三差路を左折して、神社の背後200mほどにある遠見山古墳に行く。
畑に囲まれた墳丘長約70mの古墳は、五世紀後半の前方後円墳。総社城の遠見に使われた
ので遠見山古墳と呼ばれており、総社古墳群の中でも最古のものという。

三差路に戻り、すぐ先の反対側の三差路に進む。天狗岩用水の堀割沿いに北に入ると、総
社資料館があった。街道に面した先ほどの大きな建物の主、旧本間酒店の酒造用の2棟を利
用したものである。

館内には、総社古墳群からの出土品や複製品、歴史を示すパネル、この後回った山王廃寺
の出土品、本間酒店の酒造用品、前橋特産のこけしなどが展示されていた。

別棟には古い農具や家具などが並び、小学生の体験学習にも利用されているようだ(入場
無料)。

天狗岩用水の下流側、公民館の広い駐車場の南に回り、7世紀末と推定される蛇穴山(じ
ゃけつさん)古墳(国史跡)へ。一辺39mの方墳で、墳丘は二段構造になっている。

南面の石室は羨道(せんどう)が無く、玄門と玄室だけの特殊な構造。天井、奥壁、左右
壁とも見事に加工された1枚の巨岩で、当時の石材加工技術の優秀さが知れる。玄門から中
に入って内部も見られる。

古墳前の流れは五千石用水。慶長12(1607)年頃、総社鉱泉付近の天狗岩用水から
引水され、潅漑地域が五千石に達することからその名が呼ばれるようになったとか。城の内
堀には不可欠な用水で、後には宿場町に利用されて防火用水にもなったという。

蛇穴山古墳から、駐車場と道路を隔ててすぐ西側にある宝塔山(ほうとうざん)古墳(国
史跡)に回る。

一辺約55m、高さ11mあり、三段に築造された方墳で、県内古墳の最終末期、7世紀
末から8世紀初頭のものと見られ、方墳としては全国的に見ても大きなものらしい。

北東から石段を上がり、左に回り込むと墳丘上に総社領主秋元氏の歴代墓地がある。その
あたりからは、東方に群馬県庁など前橋市の中心街が望まれる。

南面には横穴式石室があり、羨道、前室、玄室に分かれている。石室の壁面には精巧に加
工した切石が使われ、随所に切組積みの手法が見られ、それらは最高水準を示すという。
玄室にある家型石棺は、底部が格狭間(ごうざま)という形にくり抜かれていて、古墳への
仏教文化の影響を物語っているようだ。

宝塔山古墳の西北側に接して、光厳寺(こうがんじ)がある。光厳寺は総社城内の西南隅
近くに位置し、城主秋元長朝が母の菩提寺として慶長12(1607)年に造営したもの。

本柱が門の中心線から前方にずれていて、江戸初期かそれ以前の建立と推定されるという
薬医門の横から境内に入った。中心に文政3(1820)年再建の大本堂↑があり、右手に
文化9年(1812)再建という、朱塗り神殿風の秋元家御廟所(ごびようしよ)が並んで
いる。

その間に立つ高さ4.17m、安山岩製七層の東覚寺層塔は、室町時代の特徴をよく表し
ていて、もと総惣社町井の東覚寺にあったものと伝えられるという。
光厳寺を出て南側の県道6号を西へ、JR線路を跨道橋で越えて次のY字路を南西に入る。
幅広い産業道路を横断すると、平行して五千石堰(ごせんごくぜき)用水が流れ、すぐに
八幡川の山王橋を渡る。

五千石堰用水は、天狗岩用水より以前から存在していたことなどが、橋のそばの説明板に
記されていた。

橋から200m余り、十字路際の小公園に古い双体道祖神が立ち、南側には、五千石堰用
水で水死した子どもの供養と災難予防のため、宝暦年代(1751~64)に建立されたら
しい、山王子育地蔵尊が小さい社に祭られている。
その十字路を西に200m足らず進んで日枝(ひえ)神社に行く。境内はそう広くはない
が、この周辺は国史跡の山王廃寺跡である。

山王廃寺は約1300年前この地に建てられ、講堂を中心に回廊を巡らせ、中に五重塔や
金堂が、講堂の背後には僧坊があったと推定されているという。

境内には、ほかでは鳥取県の大寺廃寺のみという石製の鴟尾(しび)↑、山王廃寺五重塔
の心柱根巻石(しんばしらねまきいし)や塔心礎(とうしんそ)が、屋根付きの建物に保存
されている。寺の建立時期は、出土瓦などから7世紀末の白鳳期頃と考えられるようだ。
社殿の周辺には、元禄8(1695)年の庚申塔など18基の古い石造物が並んでいた。

周辺の民家は、何れも広い敷地に大きな建物が立っていて、生活のゆとりが感じられる。

産業道路に戻りそばのバス停で時刻を見たが、しばらくバスは無い。産業道路を北へ進ん
で日進電機の北を回り、16時12分に群馬総社駅に戻った。
(天気 晴後曇、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 前橋、歩行地 前橋市、歩数
16,700)
にほんブログ村


















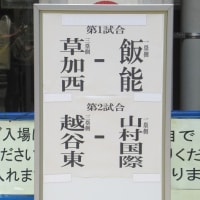





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます