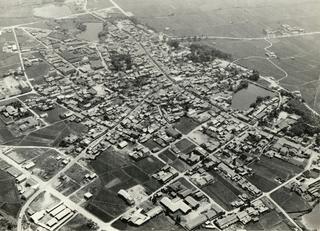加東市を西の高岡から社を通り、北東の鴨川へと横断して丹波へと抜けていく国道372号線。上三草、山口辺りは源平の古戦場で知られる三草山があり、その山麓には県下最大級の土堰堤を誇る昭和池があります。
この谷には三草川が流れ、現国道と並行するように旧街道の京街道が通っています。そして、街道沿いには馬瀬、山口、上三草、三草と集落があります。その旧街道の上三草と山口の境あたりに三草山へ通じる分かれ道があり、その三叉路の脇に2本の石柱が立っていました。一本は昭和池入口の(写真右)、もう一本は道標でした(写真左)。
道標には「右 ほつけ山」「左 お深山くめ」と刻まれています。
この街道は西国巡礼の巡礼道で、西国二十五番の御嶽山清水寺(加東市)から社を通り、二十六番の法華山一乗寺(加西市)へと通じています。お深山は加東市松沢にある東福寺で、久米を抜けて松沢へと通じています。ともに霊場巡りの人々への大切な道しるべとなっていたのでしょう。東福寺はこのブログでも最近弁財天祭り、護摩焚くを紹介しました。