英語の詩を日本語で
English Poetry in Japanese
Milton, Paradise Lost (10: 914-36)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『楽園は失われた』 (10: 914-36)
(イヴ 「わたしがいけなかったの」)
こんなふうに見棄てないで、アダム、天に誓うわ、
あなたを愛してる、心の底から
尊敬してる。わたし、わけわかんないまま神さまに背いちゃった、
だまされちゃった、ほんと悲しい。お願い、
許して、行かないで。あなたが頼りなの、
やさしくわたしを見て、助けて、
わたし、ほんとにわからない、どうしたらいいの?
力になって支えてくれるのはあなただけなの。あなたに見棄てられたら、
わたし、どこに行けばいい? どこで生きていける?
わたしたちの命、あと一時間もないかも、でも、まだ生きているあいだ、
仲よくしたい、いっしょに
ひどい目にあったんだから、いっしょに
敵を憎んでいたい、あの蛇を。神さまも
そういってたよね? わたしだけ
憎まないで、こんな悲しいことになっちゃったけど、
わたしの命、もうおしまいなんだし、わたし、あなたよりも
つらいんだから。わたしたち、ふたりとも罪を犯したけど、あなたは
神さまに背いただけ、わたしは神さまとあなたに背いちゃった。
だからわたし、神さまに裁かれたとこにいって、
泣いて天にお願いする、あなたへの
裁きはなしにして、それをみんなわたしに
ください、って、だって、あなたを不幸にしたのはわたしだもの、
神さまが怒ってるのはわたしに対してだけだもの。
* * *
John Milton
Paradise Lost (10: 914-36)
Forsake me not thus, Adam, witness Heav'n
What love sincere, and reverence in my heart [915]
I beare thee, and unweeting have offended,
Unhappilie deceav'd; thy suppliant
I beg, and clasp thy knees; bereave me not,
Whereon I live, thy gentle looks, thy aid,
Thy counsel in this uttermost distress, [920]
My onely strength and stay: forlorn of thee,
Whither shall I betake me, where subsist?
While yet we live, scarse one short hour perhaps,
Between us two let there be peace, both joyning,
As joyn'd in injuries, one enmitie [925]
Against a Foe by doom express assign'd us,
That cruel Serpent: On me exercise not
Thy hatred for this miserie befall'n,
On me alreadie lost, mee then thy self
More miserable; both have sin'd, but thou [930]
Against God onely, I against God and thee,
And to the place of judgment will return,
There with my cries importune Heaven, that all
The sentence from thy head remov'd may light
On me, sole cause to thee of all this woe, [935]
Mee mee onely just object of his ire.
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_9/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
『楽園は失われた』 (10: 914-36)
(イヴ 「わたしがいけなかったの」)
こんなふうに見棄てないで、アダム、天に誓うわ、
あなたを愛してる、心の底から
尊敬してる。わたし、わけわかんないまま神さまに背いちゃった、
だまされちゃった、ほんと悲しい。お願い、
許して、行かないで。あなたが頼りなの、
やさしくわたしを見て、助けて、
わたし、ほんとにわからない、どうしたらいいの?
力になって支えてくれるのはあなただけなの。あなたに見棄てられたら、
わたし、どこに行けばいい? どこで生きていける?
わたしたちの命、あと一時間もないかも、でも、まだ生きているあいだ、
仲よくしたい、いっしょに
ひどい目にあったんだから、いっしょに
敵を憎んでいたい、あの蛇を。神さまも
そういってたよね? わたしだけ
憎まないで、こんな悲しいことになっちゃったけど、
わたしの命、もうおしまいなんだし、わたし、あなたよりも
つらいんだから。わたしたち、ふたりとも罪を犯したけど、あなたは
神さまに背いただけ、わたしは神さまとあなたに背いちゃった。
だからわたし、神さまに裁かれたとこにいって、
泣いて天にお願いする、あなたへの
裁きはなしにして、それをみんなわたしに
ください、って、だって、あなたを不幸にしたのはわたしだもの、
神さまが怒ってるのはわたしに対してだけだもの。
* * *
John Milton
Paradise Lost (10: 914-36)
Forsake me not thus, Adam, witness Heav'n
What love sincere, and reverence in my heart [915]
I beare thee, and unweeting have offended,
Unhappilie deceav'd; thy suppliant
I beg, and clasp thy knees; bereave me not,
Whereon I live, thy gentle looks, thy aid,
Thy counsel in this uttermost distress, [920]
My onely strength and stay: forlorn of thee,
Whither shall I betake me, where subsist?
While yet we live, scarse one short hour perhaps,
Between us two let there be peace, both joyning,
As joyn'd in injuries, one enmitie [925]
Against a Foe by doom express assign'd us,
That cruel Serpent: On me exercise not
Thy hatred for this miserie befall'n,
On me alreadie lost, mee then thy self
More miserable; both have sin'd, but thou [930]
Against God onely, I against God and thee,
And to the place of judgment will return,
There with my cries importune Heaven, that all
The sentence from thy head remov'd may light
On me, sole cause to thee of all this woe, [935]
Mee mee onely just object of his ire.
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_9/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, Paradise Lost (10: 808-44)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『楽園は失われた』 (10: 808-44)
(アダム 「ぼくだけが罰を受ければいいのに」)
でも、さ、
「死」っていうのは、思ってたような、一度にガーンと来て、あっという間に
感覚を奪うようなものじゃなくって、今日からずっと
不幸せなまま生きてく、ってことなのかな? 今のぼくが
そうで、まわりのものもそうで、これが永遠につづく、って
ことなのかな? うわ・・・・・・また嫌なこと
思い出しちゃった。ノーガードの頭に、雷みたいに
こわい考えが落ちてくる・・・・・・ぼくと「死」は、
いっしょに、永遠に、生きつづけるのかな? 合体したみたいにひとつになって?
いや、ぼくだけじゃなくって、ぼくの子孫もみんな
いっしょに呪われるんだ。すてきな遺産を
残してしまったね、ぼくのこどもたち! こんな負の財産、
ぼくだけで使いはたして、なんにも残さなかったらよかったのに!
こんな財産、ないほうがありがたいよね。
うらまれて当然だよね! もうさ、ひとりの人間が罪を犯したからって、
なんで罪のない他のみんなが罰を受けることになるんだろ?
だって、みんなは悪くないのに? あ、ちがうか・・・・・・ぼくから生まれる人間は
みんな堕落してることになるよね。頭も心もみんな腐ってて、
考えることもやることもぼくと
おんなじなんだ。神さまの前で、無罪です!
なんていえるはずないんだ。はあ、結局、悪いのはぼくで、
神さまは悪くない、ってことか・・・・・・。どれだけ言い訳しても、
言い逃れしても、頭がこんがらがるだけで、最後は
ぼくが悪い、ってなっちゃうな。最初から最後まで、
ぼくが、ぼくだけが、悪いんだ。ぼくが悪の源、
みんなぼくだけのせいなんだ。だから、
ぼくだけが罰を受ければいいのに! ・・・・・・なんて無理だよね。ぼくだけで、
この大地より重い罰、
この世界よりもずっと重い罰を背負えるわけないし。あの悪い女と
ふたりでわけあったってね。もうさ、こうしたい、って考えても、
これは嫌だ、ってことを考えても、行きつくとこはおんなじだな。
もはや逃げ道なんてなくって、ぼくは過去にも
未来にも例がないほど悲惨で不幸、って思い知るだけなんだ。
こんな罪と罰に値するのなんて、ぼくを除けばサタンだけ・・・・・・。
ああ、ああ、良心的に考えてたら、
もう恐怖のどん底だ。出口もなく、
ただ深く、もっと深く、まっさかさまに落ちてくだけなんだ!
* * *
John Milton
Paradise Lost (10: 808-44)
. . . But say
That Death be not one stroak, as I suppos'd,
Bereaving sense, but endless miserie [810]
From this day onward, which I feel begun
Both in me, and without me, and so last
To perpetuitie; Ay me, that fear
Comes thundring back with dreadful revolution
On my defensless head; both Death and I [815]
Am found Eternal, and incorporate both,
Nor I on my part single, in mee all
Posteritie stands curst: Fair Patrimonie
That I must leave ye, Sons; O were I able
To waste it all my self, and leave ye none! [820]
So disinherited how would ye bless
Me now your curse! Ah, why should all mankind
For one mans fault thus guiltless be condemn'd,
If guiltless? But from mee what can proceed,
But all corrupt, both Mind and Will deprav'd, [825]
Not to do onely, but to will the same
With me? how can they then acquitted stand
In sight of God? Him after all Disputes
Forc't I absolve: all my evasions vain
And reasonings, though through Mazes, lead me still [830]
But to my own conviction: first and last
On mee, mee onely, as the sourse and spring
Of all corruption, all the blame lights due;
So might the wrauth. Fond wish! couldst thou support
That burden heavier then the Earth to bear [835]
Then all the World much heavier, though divided
With that bad Woman? Thus what thou desir'st,
And what thou fearst, alike destroyes all hope
Of refuge, and concludes thee miserable
Beyond all past example and future, [840]
To Satan only like both crime and doom.
O Conscience, into what Abyss of fears
And horrors hast thou driv'n me; out of which
I find no way, from deep to deeper plung'd!
* * *
イヴとはケンカ中。
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_10/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
『楽園は失われた』 (10: 808-44)
(アダム 「ぼくだけが罰を受ければいいのに」)
でも、さ、
「死」っていうのは、思ってたような、一度にガーンと来て、あっという間に
感覚を奪うようなものじゃなくって、今日からずっと
不幸せなまま生きてく、ってことなのかな? 今のぼくが
そうで、まわりのものもそうで、これが永遠につづく、って
ことなのかな? うわ・・・・・・また嫌なこと
思い出しちゃった。ノーガードの頭に、雷みたいに
こわい考えが落ちてくる・・・・・・ぼくと「死」は、
いっしょに、永遠に、生きつづけるのかな? 合体したみたいにひとつになって?
いや、ぼくだけじゃなくって、ぼくの子孫もみんな
いっしょに呪われるんだ。すてきな遺産を
残してしまったね、ぼくのこどもたち! こんな負の財産、
ぼくだけで使いはたして、なんにも残さなかったらよかったのに!
こんな財産、ないほうがありがたいよね。
うらまれて当然だよね! もうさ、ひとりの人間が罪を犯したからって、
なんで罪のない他のみんなが罰を受けることになるんだろ?
だって、みんなは悪くないのに? あ、ちがうか・・・・・・ぼくから生まれる人間は
みんな堕落してることになるよね。頭も心もみんな腐ってて、
考えることもやることもぼくと
おんなじなんだ。神さまの前で、無罪です!
なんていえるはずないんだ。はあ、結局、悪いのはぼくで、
神さまは悪くない、ってことか・・・・・・。どれだけ言い訳しても、
言い逃れしても、頭がこんがらがるだけで、最後は
ぼくが悪い、ってなっちゃうな。最初から最後まで、
ぼくが、ぼくだけが、悪いんだ。ぼくが悪の源、
みんなぼくだけのせいなんだ。だから、
ぼくだけが罰を受ければいいのに! ・・・・・・なんて無理だよね。ぼくだけで、
この大地より重い罰、
この世界よりもずっと重い罰を背負えるわけないし。あの悪い女と
ふたりでわけあったってね。もうさ、こうしたい、って考えても、
これは嫌だ、ってことを考えても、行きつくとこはおんなじだな。
もはや逃げ道なんてなくって、ぼくは過去にも
未来にも例がないほど悲惨で不幸、って思い知るだけなんだ。
こんな罪と罰に値するのなんて、ぼくを除けばサタンだけ・・・・・・。
ああ、ああ、良心的に考えてたら、
もう恐怖のどん底だ。出口もなく、
ただ深く、もっと深く、まっさかさまに落ちてくだけなんだ!
* * *
John Milton
Paradise Lost (10: 808-44)
. . . But say
That Death be not one stroak, as I suppos'd,
Bereaving sense, but endless miserie [810]
From this day onward, which I feel begun
Both in me, and without me, and so last
To perpetuitie; Ay me, that fear
Comes thundring back with dreadful revolution
On my defensless head; both Death and I [815]
Am found Eternal, and incorporate both,
Nor I on my part single, in mee all
Posteritie stands curst: Fair Patrimonie
That I must leave ye, Sons; O were I able
To waste it all my self, and leave ye none! [820]
So disinherited how would ye bless
Me now your curse! Ah, why should all mankind
For one mans fault thus guiltless be condemn'd,
If guiltless? But from mee what can proceed,
But all corrupt, both Mind and Will deprav'd, [825]
Not to do onely, but to will the same
With me? how can they then acquitted stand
In sight of God? Him after all Disputes
Forc't I absolve: all my evasions vain
And reasonings, though through Mazes, lead me still [830]
But to my own conviction: first and last
On mee, mee onely, as the sourse and spring
Of all corruption, all the blame lights due;
So might the wrauth. Fond wish! couldst thou support
That burden heavier then the Earth to bear [835]
Then all the World much heavier, though divided
With that bad Woman? Thus what thou desir'st,
And what thou fearst, alike destroyes all hope
Of refuge, and concludes thee miserable
Beyond all past example and future, [840]
To Satan only like both crime and doom.
O Conscience, into what Abyss of fears
And horrors hast thou driv'n me; out of which
I find no way, from deep to deeper plung'd!
* * *
イヴとはケンカ中。
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_10/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, Paradise Lost (10: 720-42)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『楽園は失われた』 (10: 720-42)
(アダム 「人間すべてが呪われてしまった」)
ああ、もう最悪だ、幸せだったのに。こんなことになるなんて、
この新しい、すばらしい世界と、その頂点に立ってたはずの
このぼくが・・・・・・。幸せの頂点から
呪いのどん底にまっさかさまだ。もう神さまに
顔向けできないな。神さまに会うことがいちばんの
楽しみだったのに。でも、それだけじゃないんだよな。
これくらいの不幸はぼくにとって当然の報いだから、
がまんしなくちゃね。でも、ぼくが耐えるだけじゃダメなんだ。
ぼくが食べるもの、飲むもの、ぼくから生まれるもの、
みんな呪われることになったんだから。前に聞いた
「産めよ、増えよ」、って言葉、
今聞いたら、それだけで死にそうだ。ぼくから産まれて
増えるのは、ぼくへの呪いだけだから。
これから先、生まれてくる者は、みんな
ぼくがもたらした不幸のなかで生きて、そして
ぼくを呪うんだ。汚れた祖先がバカなことをしたもんだ、
礼をいうぜ、アダム! ってね。ありがとう、とかいって
呪われるって、きついよね。つまりさ、
ぼくにふりかかる呪いに加えて、ぼくから生まれる者すべてに
ふりかかる呪いも、波みたいにぼくの上にかえってくるんだ。
重力の中心みたいに、ぼくの上に、
どーんって落ちてくるんだ。楽園の喜びなんて、あっという間に消えちゃった。
あっという間だったのに、その代償は高かったよな、永遠につづく苦悩なんだもんな。
* * *
John Milton
Paradise Lost (10: 720-42)
O miserable of happie! is this the end [720]
Of this new glorious World, and mee so late
The Glory of that Glory, who now becom
Accurst of blessed, hide me from the face
Of God, whom to behold was then my highth
Of happiness: yet well, if here would end [725]
The miserie, I deserv'd it, and would beare
My own deservings; but this will not serve;
All that I eat or drink, or shall beget,
Is propagated curse. O voice once heard
Delightfully, Encrease and multiply, [730]
Now death to hear! for what can I encrease
Or multiplie, but curses on my head?
Who of all Ages to succeed, but feeling
The evil on him brought by me, will curse
My Head, Ill fare our Ancestor impure, [735]
For this we may thank Adam; but his thanks
Shall be the execration; so besides
Mine own that bide upon me, all from mee
Shall with a fierce reflux on mee redound,
On mee as on thir natural center light [740]
Heavie, though in thir place. O fleeting joyes
Of Paradise, deare bought with lasting woes!
* * *
アダム(とイヴ)の原罪および死の運命が、彼らから
生まれるすべての人間に受け継がれることになる、
ということ。またその結果、すべての人間がアダムを
うらむことになる、ということ。
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_10/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
『楽園は失われた』 (10: 720-42)
(アダム 「人間すべてが呪われてしまった」)
ああ、もう最悪だ、幸せだったのに。こんなことになるなんて、
この新しい、すばらしい世界と、その頂点に立ってたはずの
このぼくが・・・・・・。幸せの頂点から
呪いのどん底にまっさかさまだ。もう神さまに
顔向けできないな。神さまに会うことがいちばんの
楽しみだったのに。でも、それだけじゃないんだよな。
これくらいの不幸はぼくにとって当然の報いだから、
がまんしなくちゃね。でも、ぼくが耐えるだけじゃダメなんだ。
ぼくが食べるもの、飲むもの、ぼくから生まれるもの、
みんな呪われることになったんだから。前に聞いた
「産めよ、増えよ」、って言葉、
今聞いたら、それだけで死にそうだ。ぼくから産まれて
増えるのは、ぼくへの呪いだけだから。
これから先、生まれてくる者は、みんな
ぼくがもたらした不幸のなかで生きて、そして
ぼくを呪うんだ。汚れた祖先がバカなことをしたもんだ、
礼をいうぜ、アダム! ってね。ありがとう、とかいって
呪われるって、きついよね。つまりさ、
ぼくにふりかかる呪いに加えて、ぼくから生まれる者すべてに
ふりかかる呪いも、波みたいにぼくの上にかえってくるんだ。
重力の中心みたいに、ぼくの上に、
どーんって落ちてくるんだ。楽園の喜びなんて、あっという間に消えちゃった。
あっという間だったのに、その代償は高かったよな、永遠につづく苦悩なんだもんな。
* * *
John Milton
Paradise Lost (10: 720-42)
O miserable of happie! is this the end [720]
Of this new glorious World, and mee so late
The Glory of that Glory, who now becom
Accurst of blessed, hide me from the face
Of God, whom to behold was then my highth
Of happiness: yet well, if here would end [725]
The miserie, I deserv'd it, and would beare
My own deservings; but this will not serve;
All that I eat or drink, or shall beget,
Is propagated curse. O voice once heard
Delightfully, Encrease and multiply, [730]
Now death to hear! for what can I encrease
Or multiplie, but curses on my head?
Who of all Ages to succeed, but feeling
The evil on him brought by me, will curse
My Head, Ill fare our Ancestor impure, [735]
For this we may thank Adam; but his thanks
Shall be the execration; so besides
Mine own that bide upon me, all from mee
Shall with a fierce reflux on mee redound,
On mee as on thir natural center light [740]
Heavie, though in thir place. O fleeting joyes
Of Paradise, deare bought with lasting woes!
* * *
アダム(とイヴ)の原罪および死の運命が、彼らから
生まれるすべての人間に受け継がれることになる、
ということ。またその結果、すべての人間がアダムを
うらむことになる、ということ。
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_10/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, Paradise Lost (9: 896-916)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『楽園は失われた』 (9: 896-916)
(アダム 「君なしでは生きていけない」)
この世でいちばんきれいな君・・・・・・神が最後に、いちばん
いいものとしてつくった君・・・・・この世で見えるもの、
頭に浮かぶもの、そのいちばんいいものを集めたかのような君・・・・・・
清らかで、神々しくて、善良で、やさしくて、そして美しかった君!
君が堕ちてしまうなんて、こんなに急に堕ちてしまうなんて、どういうことなの?
美しさを失って、花を失って、死ぬ人、滅びる人となってしまうなんて?
ねえ、君はどうして背いてしまったの?
あの厳しい禁止の命令に? どうしてあの神聖な、
禁じられた果実に手をつけてしまったの? よくわからないけど、
邪悪な敵の策略か何かにだまされたんだよね?
君といっしょに、ぼくも、もうおしまいだね。だって、
ぼくも死ぬんだから・・・・・・。もう決めてる。
ぼくは君なしじゃ生きられない。君と話すこと、愛しあうことなしでは
生きられない。あんなに楽しかったんだから。幸せだったんだから。
この誰もいない森でひとりで生きていくなんて、もういやだよ。
たとえ神がもうひとりイヴをつくってくれても、あばらを
もう一本とるだけだとしても、君のことは
忘れられない。絶対に無理。ぼくと君は、
もともとつながってるんだ。君はぼくの肉から、
ぼくの骨からできてるんだ。だから、ぼくは君と
絶対に別れない。幸せなときも、そうでないときも、だよ。
* * *
John Milton
Paradise Lost (9: 896-916)
O fairest of Creation, last and best
Of all Gods works, Creature in whom excell'd
Whatever can to sight or thought be formd,
Holy, divine, good, amiable, or sweet!
How art thou lost, how on a sudden lost, [900]
Defac't, deflourd, and now to Death devote?
Rather how hast thou yeelded to transgress
The strict forbiddance, how to violate
The sacred Fruit forbidd'n! som cursed fraud
Of Enemie hath beguil'd thee, yet unknown, [905]
And mee with thee hath ruind, for with thee
Certain my resolution is to Die;
How can I live without thee, how forgoe
Thy sweet Converse and Love so dearly joyn'd,
To live again in these wilde Woods forlorn? [910]
Should God create another Eve, and I
Another Rib afford, yet loss of thee
Would never from my heart; no no, I feel
The Link of Nature draw me: Flesh of Flesh,
Bone of my Bone thou art, and from thy State [915]
Mine never shall be parted, bliss or woe.
* * *
人間すべての原罪が(ほぼ)確定する場面だが、
ミルトンは、この場面を美しく、そしてある意味
人として正しいものとして描いている。
キリスト教倫理的にいちばん悪い場面が、
いちばん美しく、そして正しい、という。
(サタンの描写についても同様。キリスト教
倫理的にいちばん悪い存在が、ある意味、
いちばん魅力的な存在、となっている。)
キリスト教における教義・神話・世界観・倫理などを
聖書や各種神学思想にのっとってきちんと描き切り、
かつ同時に、キリスト教倫理とは齟齬する、きわめて
人間的な価値観を軸に心ゆさぶる物語をつくっている
ところに、ミルトンの視野の広さ、社会や人に対する
洞察や深さ、思考の幅や奥行、のようなものを見るべき
だろう。
『楽園は失われた』は、極端な宗教性(急進的な
プロテスタント思想、いわゆるピューリタニズム)と、
極端な世俗性(ルネサンス的、古典文学的な、
人間的、世俗的で、時として非道徳的な思考)を、
等しくあわせもっている。つまり、そこに含まれるのは、
16-17世紀イギリスの思潮における両極端であると同時に、
いわばヨーロッパのキリスト教文明における過去と
未来のすべてである。
(上の場面のようなアダムを、たとえば、信仰のために
家庭を棄てることを当然のこととして描く--というか、
家庭をほとんど描かない--バニヤンの『巡礼の旅』
(『天路歴程』)と比べてみる。ミルトンが現代の側に
いることがよくわかるだろう。)
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_9/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
『楽園は失われた』 (9: 896-916)
(アダム 「君なしでは生きていけない」)
この世でいちばんきれいな君・・・・・・神が最後に、いちばん
いいものとしてつくった君・・・・・この世で見えるもの、
頭に浮かぶもの、そのいちばんいいものを集めたかのような君・・・・・・
清らかで、神々しくて、善良で、やさしくて、そして美しかった君!
君が堕ちてしまうなんて、こんなに急に堕ちてしまうなんて、どういうことなの?
美しさを失って、花を失って、死ぬ人、滅びる人となってしまうなんて?
ねえ、君はどうして背いてしまったの?
あの厳しい禁止の命令に? どうしてあの神聖な、
禁じられた果実に手をつけてしまったの? よくわからないけど、
邪悪な敵の策略か何かにだまされたんだよね?
君といっしょに、ぼくも、もうおしまいだね。だって、
ぼくも死ぬんだから・・・・・・。もう決めてる。
ぼくは君なしじゃ生きられない。君と話すこと、愛しあうことなしでは
生きられない。あんなに楽しかったんだから。幸せだったんだから。
この誰もいない森でひとりで生きていくなんて、もういやだよ。
たとえ神がもうひとりイヴをつくってくれても、あばらを
もう一本とるだけだとしても、君のことは
忘れられない。絶対に無理。ぼくと君は、
もともとつながってるんだ。君はぼくの肉から、
ぼくの骨からできてるんだ。だから、ぼくは君と
絶対に別れない。幸せなときも、そうでないときも、だよ。
* * *
John Milton
Paradise Lost (9: 896-916)
O fairest of Creation, last and best
Of all Gods works, Creature in whom excell'd
Whatever can to sight or thought be formd,
Holy, divine, good, amiable, or sweet!
How art thou lost, how on a sudden lost, [900]
Defac't, deflourd, and now to Death devote?
Rather how hast thou yeelded to transgress
The strict forbiddance, how to violate
The sacred Fruit forbidd'n! som cursed fraud
Of Enemie hath beguil'd thee, yet unknown, [905]
And mee with thee hath ruind, for with thee
Certain my resolution is to Die;
How can I live without thee, how forgoe
Thy sweet Converse and Love so dearly joyn'd,
To live again in these wilde Woods forlorn? [910]
Should God create another Eve, and I
Another Rib afford, yet loss of thee
Would never from my heart; no no, I feel
The Link of Nature draw me: Flesh of Flesh,
Bone of my Bone thou art, and from thy State [915]
Mine never shall be parted, bliss or woe.
* * *
人間すべての原罪が(ほぼ)確定する場面だが、
ミルトンは、この場面を美しく、そしてある意味
人として正しいものとして描いている。
キリスト教倫理的にいちばん悪い場面が、
いちばん美しく、そして正しい、という。
(サタンの描写についても同様。キリスト教
倫理的にいちばん悪い存在が、ある意味、
いちばん魅力的な存在、となっている。)
キリスト教における教義・神話・世界観・倫理などを
聖書や各種神学思想にのっとってきちんと描き切り、
かつ同時に、キリスト教倫理とは齟齬する、きわめて
人間的な価値観を軸に心ゆさぶる物語をつくっている
ところに、ミルトンの視野の広さ、社会や人に対する
洞察や深さ、思考の幅や奥行、のようなものを見るべき
だろう。
『楽園は失われた』は、極端な宗教性(急進的な
プロテスタント思想、いわゆるピューリタニズム)と、
極端な世俗性(ルネサンス的、古典文学的な、
人間的、世俗的で、時として非道徳的な思考)を、
等しくあわせもっている。つまり、そこに含まれるのは、
16-17世紀イギリスの思潮における両極端であると同時に、
いわばヨーロッパのキリスト教文明における過去と
未来のすべてである。
(上の場面のようなアダムを、たとえば、信仰のために
家庭を棄てることを当然のこととして描く--というか、
家庭をほとんど描かない--バニヤンの『巡礼の旅』
(『天路歴程』)と比べてみる。ミルトンが現代の側に
いることがよくわかるだろう。)
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_9/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, Paradise Lost (9: 780-833)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『楽園は失われた』 (9: 780-833)
(イヴが禁断の木の実を食べる)
・・・・・・軽はずみにもイヴは、禁断の木の実に手をのばし、
それをもぎとり、そして食べた。運命の瞬間であった。
大地は傷つき、自然が
生んだすべてのものも嘆き、ため息をつき、こういっているかのようであった、
すべてが失われた、と。罪深いヘビはこそこそと
茂みに戻っていった。これにイヴは気づかなかったが、それはしかたがない。
果実の味に夢中になっていて、他のことなど目に入らなかった
からだ。彼女は思った、これほどおいしい果実なんて
食べたことない、と。本当にそうなのか、知恵が手に入るという期待から
そう妄想したのかは、怪しいところだ。神になる、という夢想も忘れてはいなかった。
イヴはその実を頬ばり、むしゃむしゃと食べた。止まらなかった。
〈死〉を食べているとも気づかずに。やがて満足し、
ワインに酔っているかのように、陽気に、楽しげに、
彼女はひとりで話しはじめた。
「うわ、もう、最高! 効きすぎ! この木が
いちばん! 賢くしてくれるなんて、
まさに神さまの力ね。これまで知らなかったし、悪いものだと思ってた。
この実、わたし、ほったらかしにして、役立たずみたいに
見てた。でも、これから毎朝、ちゃんと世話するわ。
歌でたたえて、賛美して、
そして実りの重荷をおろしてあげる。
みんなにどうぞって、枝がさし出されてるんだから。
毎日この実を食べて、わたし、もの知りに
なるの。何でも知ってる神さまたちみたいに。
あ、そうそう、知識をひとり占めしたがる神さまたちもいるようね。そんなこと、
無理なのに。知識がそんな神さまたちのものだったら、こんなふうに
ここに知識の木なんか生えてるはずないもの。それから、〈経験〉って
大事よね。最高の道しるべだわ。〈経験〉を恐れていたら、
わたし、バカなままだった。〈経験〉することで〈知恵〉が
手に入ったのよね。それまで隠れていたような〈知恵〉が、よ。
うふ、たぶん、わたし、ばれてないわ。天国は高くて、
高くて遠くて、地上のことなんか
はっきり見えるわけないし。それから、いろいろ忙しいはずだから、
あの、ダメっていってた神さま? も、ずーっとこっちなんか
見てるはずないわ。スパイにいろいろ任せっきり
なんだし。・・・・・・でも、アダムには
なんていおう? わたしが変わったことを
ちゃんと教えてあげて、この幸せを
半分こしようかな? それとも、やめとく?
知識でリードしたんだから、そのままで
いてもいいよね? そしたら、女に足りない部分が
補えて、アダムもわたしのこと、もっと好きになってくれたりなんかして?
彼と対等になって、で、もしかしたら、
ちょっとうれしいかもなんだけど、ときどきわたしのほうが
上になったり、しちゃうかも? だって、下にいたら自由なんてないんだし。
でも、それはいいとして、もし、わたし、神さまにばれてて
死ぬことになっちゃったらどうしよう? わたしがいなくなったら、
アダムは別のイヴと結婚するのかな?
そして末永く幸せになっちゃったりするのかな? わたしなしで・・・・・・。
うわ、そんなの、考えただけで死にそう! 絶対無理! うん、決めた!
アダムにも知識の幸せをわけてあげる。それか、死をわけてあげる。
わたし、アダムが好き。あの人がいれば
死も平気。あの人がいなかったら、わたし、死んじゃう。
* * *
John Milton
Paradise Lost (9: 780-833)
. . . her rash hand in evil hour [780]
Forth reaching to the Fruit, she pluck'd, she eat:
Earth felt the wound, and Nature from her seat
Sighing through all her Works gave signs of woe,
That all was lost. Back to the Thicket slunk
The guiltie Serpent, and well might, for Eve [785]
Intent now wholly on her taste, naught else
Regarded, such delight till then, as seemd,
In Fruit she never tasted, whether true
Or fansied so, through expectation high
Of knowledg, nor was God-head from her thought. [790]
Greedily she ingorg'd without restraint,
And knew not eating Death: Satiate at length,
And hight'nd as with Wine, jocond and boon,
Thus to her self she pleasingly began.
O Sovran, vertuous, precious of all Trees [795]
In Paradise, of operation blest
To Sapience, hitherto obscur'd, infam'd,
And thy fair Fruit let hang, as to no end
Created; but henceforth my early care,
Not without Song, each Morning, and due praise [800]
Shall tend thee, and the fertil burden ease
Of thy full branches offer'd free to all;
Till dieted by thee I grow mature
In knowledge, as the Gods who all things know;
Though others envie what they cannot give; [805]
For had the gift bin theirs, it had not here
Thus grown. Experience, next to thee I owe,
Best guide; not following thee, I had remaind
In ignorance, thou op'nst Wisdoms way,
And giv'st access, though secret she retire. [810]
And I perhaps am secret; Heav'n is high,
High and remote to see from thence distinct
Each thing on Earth; and other care perhaps
May have diverted from continual watch
Our great Forbidder, safe with all his Spies [815]
About him. But to Adam in what sort
Shall I appeer? shall I to him make known
As yet my change, and give him to partake
Full happiness with mee, or rather not,
But keep the odds of Knowledge in my power [820]
Without Copartner? so to add what wants
In Femal Sex, the more to draw his Love,
And render me more equal, and perhaps,
A thing not undesireable, somtime
Superior: for inferior who is free? [825]
This may be well: but what if God have seen
And Death ensue? then I shall be no more,
And Adam wedded to another Eve,
Shall live with her enjoying, I extinct;
A death to think. Confirm'd then I resolve, [830]
Adam shall share with me in bliss or woe:
So dear I love him, that with him all deaths
I could endure, without him live no life.
* * *
ミルトンは、かわいい、愛すべき女性として
この場面のイヴを描いていると思う。
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_9/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
『楽園は失われた』 (9: 780-833)
(イヴが禁断の木の実を食べる)
・・・・・・軽はずみにもイヴは、禁断の木の実に手をのばし、
それをもぎとり、そして食べた。運命の瞬間であった。
大地は傷つき、自然が
生んだすべてのものも嘆き、ため息をつき、こういっているかのようであった、
すべてが失われた、と。罪深いヘビはこそこそと
茂みに戻っていった。これにイヴは気づかなかったが、それはしかたがない。
果実の味に夢中になっていて、他のことなど目に入らなかった
からだ。彼女は思った、これほどおいしい果実なんて
食べたことない、と。本当にそうなのか、知恵が手に入るという期待から
そう妄想したのかは、怪しいところだ。神になる、という夢想も忘れてはいなかった。
イヴはその実を頬ばり、むしゃむしゃと食べた。止まらなかった。
〈死〉を食べているとも気づかずに。やがて満足し、
ワインに酔っているかのように、陽気に、楽しげに、
彼女はひとりで話しはじめた。
「うわ、もう、最高! 効きすぎ! この木が
いちばん! 賢くしてくれるなんて、
まさに神さまの力ね。これまで知らなかったし、悪いものだと思ってた。
この実、わたし、ほったらかしにして、役立たずみたいに
見てた。でも、これから毎朝、ちゃんと世話するわ。
歌でたたえて、賛美して、
そして実りの重荷をおろしてあげる。
みんなにどうぞって、枝がさし出されてるんだから。
毎日この実を食べて、わたし、もの知りに
なるの。何でも知ってる神さまたちみたいに。
あ、そうそう、知識をひとり占めしたがる神さまたちもいるようね。そんなこと、
無理なのに。知識がそんな神さまたちのものだったら、こんなふうに
ここに知識の木なんか生えてるはずないもの。それから、〈経験〉って
大事よね。最高の道しるべだわ。〈経験〉を恐れていたら、
わたし、バカなままだった。〈経験〉することで〈知恵〉が
手に入ったのよね。それまで隠れていたような〈知恵〉が、よ。
うふ、たぶん、わたし、ばれてないわ。天国は高くて、
高くて遠くて、地上のことなんか
はっきり見えるわけないし。それから、いろいろ忙しいはずだから、
あの、ダメっていってた神さま? も、ずーっとこっちなんか
見てるはずないわ。スパイにいろいろ任せっきり
なんだし。・・・・・・でも、アダムには
なんていおう? わたしが変わったことを
ちゃんと教えてあげて、この幸せを
半分こしようかな? それとも、やめとく?
知識でリードしたんだから、そのままで
いてもいいよね? そしたら、女に足りない部分が
補えて、アダムもわたしのこと、もっと好きになってくれたりなんかして?
彼と対等になって、で、もしかしたら、
ちょっとうれしいかもなんだけど、ときどきわたしのほうが
上になったり、しちゃうかも? だって、下にいたら自由なんてないんだし。
でも、それはいいとして、もし、わたし、神さまにばれてて
死ぬことになっちゃったらどうしよう? わたしがいなくなったら、
アダムは別のイヴと結婚するのかな?
そして末永く幸せになっちゃったりするのかな? わたしなしで・・・・・・。
うわ、そんなの、考えただけで死にそう! 絶対無理! うん、決めた!
アダムにも知識の幸せをわけてあげる。それか、死をわけてあげる。
わたし、アダムが好き。あの人がいれば
死も平気。あの人がいなかったら、わたし、死んじゃう。
* * *
John Milton
Paradise Lost (9: 780-833)
. . . her rash hand in evil hour [780]
Forth reaching to the Fruit, she pluck'd, she eat:
Earth felt the wound, and Nature from her seat
Sighing through all her Works gave signs of woe,
That all was lost. Back to the Thicket slunk
The guiltie Serpent, and well might, for Eve [785]
Intent now wholly on her taste, naught else
Regarded, such delight till then, as seemd,
In Fruit she never tasted, whether true
Or fansied so, through expectation high
Of knowledg, nor was God-head from her thought. [790]
Greedily she ingorg'd without restraint,
And knew not eating Death: Satiate at length,
And hight'nd as with Wine, jocond and boon,
Thus to her self she pleasingly began.
O Sovran, vertuous, precious of all Trees [795]
In Paradise, of operation blest
To Sapience, hitherto obscur'd, infam'd,
And thy fair Fruit let hang, as to no end
Created; but henceforth my early care,
Not without Song, each Morning, and due praise [800]
Shall tend thee, and the fertil burden ease
Of thy full branches offer'd free to all;
Till dieted by thee I grow mature
In knowledge, as the Gods who all things know;
Though others envie what they cannot give; [805]
For had the gift bin theirs, it had not here
Thus grown. Experience, next to thee I owe,
Best guide; not following thee, I had remaind
In ignorance, thou op'nst Wisdoms way,
And giv'st access, though secret she retire. [810]
And I perhaps am secret; Heav'n is high,
High and remote to see from thence distinct
Each thing on Earth; and other care perhaps
May have diverted from continual watch
Our great Forbidder, safe with all his Spies [815]
About him. But to Adam in what sort
Shall I appeer? shall I to him make known
As yet my change, and give him to partake
Full happiness with mee, or rather not,
But keep the odds of Knowledge in my power [820]
Without Copartner? so to add what wants
In Femal Sex, the more to draw his Love,
And render me more equal, and perhaps,
A thing not undesireable, somtime
Superior: for inferior who is free? [825]
This may be well: but what if God have seen
And Death ensue? then I shall be no more,
And Adam wedded to another Eve,
Shall live with her enjoying, I extinct;
A death to think. Confirm'd then I resolve, [830]
Adam shall share with me in bliss or woe:
So dear I love him, that with him all deaths
I could endure, without him live no life.
* * *
ミルトンは、かわいい、愛すべき女性として
この場面のイヴを描いていると思う。
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_9/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, Paradise Lost (9: 679-732)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『楽園は失われた』 (9: 679-732)
(サタン 「禁じられた木の実なんて食べても平気」)
「うん、君は聖なる木、知恵ある木、そしてその知恵を与えてくれる、
知識の母のような木だね。今、ぼくは君の力を感じるよ。 680
はっきりとね。ぼくには見えるんだ、
原因のうちに結果が。それから、いちばんかしこい神々の
考えるようなことも読める。どんなに難しいことでもね。
ねえ、あなた、この世の女王さま、信じなくてもいいですよ、
死についてのあの恐ろしい脅しなんか。だって死なないんですから。
死ぬ、ですって? この実で? むしろ命が手に入るんですよ、
知識だけでなく。脅してくるあの彼の手で死ぬ? ぼくを見てくださいよ。
あの実をとって食べたのに、まだ生きてるし、
運命で決まってた以上の完璧な生きかたが
できるようになってます。上をめざすことによって、です。690
ぼくみたいな動物に許されることが人間に禁じられるなんて、
ありえます? 神が怒りに燃えあがったりしますか?
こんなささいな過失で? むしろほめてくれるんじゃないですか?
何ものも恐れることなく、いいことをするんですから。
死刑という脅しにも屈せず(そもそも死ってなんでしょう?)、
より幸せな生、善悪についての知識を
もたらす行為を貫くのですから。
善についての知識を手に入れるって、いいことですよね? 悪についても、もし
悪が本当にあるのなら、知っているべきでしょう? うまく避けるために。
つまりです、神はあなたに危害を加えたりしません。そんなことをしたら、もはや神は 700
正しくないですよ。そして、正しくない神なんて、もう神じゃありません。恐れることも従うことも
ないんです。ほら、死はこわいから、逆に死は恐れなくていい、ということになりました。
さて、では、なぜこの木の実は禁じられてるのでしょう? たんにこわがらせるためだけ、
あなたを無知で下等にしておくためだけなんじゃないですか?
そのほうが、彼を崇拝させるために都合がいいんです。彼は知っています。
この木の実を食べたら、澄みわたっているようで
実は曇っていたあなたの目がぱっちりと
開いて透明になり、そして神々のようになれるのです。
彼らと同じように、善と悪についてわかるようになるのです。
ぼくが人間のように、少なくとも内面的には人間のようになったのだから、710
あなたが神々のようになるということは、まさに当然ですよね。
ぼくは獣から人間になって、あなたは人間から神になる。
そう、だから、いいかたによっては、あなたは死ぬ、ということになるんでしょう。
人間の特徴を棄てて、神々の能力を身につけるのですから。すばらしいじゃないですか、
まるでこわいもののようにいわれてますが、こんなことが死だったら。
それから、そもそも神って何なんでしょうね? 神と同じものを
食べてたら、人間だって神になれるんじゃないですか?
それから、神々はぼくたちよりも前からいて、そのことをうまく利用して
ぼくたちに信じさせてます、彼らがすべてのものをつくった、って。
それはどうかな、と思うんですよ。だって、この美しい大地とか、見てください。720
太陽にあたためられて、あらゆるものを生み出してますよね。
これに対して、彼らが何かつくったのを見たことありますか? もし彼らがすべての
ものをつくったというのなら、誰がこの木に善と悪の知識を閉じこめたんでしょうね?
だって、この木の実を食べたら、彼らの許可もないのに
知恵が手に入るんですよ? それから、何がいけないんでしょうね?
人間が知識を得たとしても、ね? あなたが知識を得て、
神が困ることなんてないでしょう? そもそもこの木に、神が禁じている知識を
与える力なんてあるんでしょうか? すべてが神の思うがままだとしたら?
あ、もしかしたら、神がただ人間に対して意地悪をしてる、ってことでしょうか?
でも、神の胸に意地悪な考えが浮かぶなんて、ま、まさか・・・・・・・ねえ・・・・・・。730
こんなことをいろいろ考えると、やっぱりあなたはこの木の実を食べなくてはなりません。
人間である女神さま、ほら、手をのばして、ご自由にお召しあがりくださいませ。」
* * *
John Milton
Paradise Lost (9: 679-732)
O Sacred, Wise, and Wisdom-giving Plant,
Mother of Science, Now I feel thy Power [680]
Within me cleere, not onely to discerne
Things in thir Causes, but to trace the wayes
Of highest Agents, deemd however wise.
Queen of this Universe, doe not believe
Those rigid threats of Death; ye shall not Die: [685]
How should ye? by the Fruit? it gives you Life
To Knowledge, By the Threatner, look on mee,
Mee who have touch'd and tasted, yet both live,
And life more perfet have attaind then Fate
Meant mee, by ventring higher then my Lot. [690]
Shall that be shut to Man, which to the Beast
Is open? or will God incense his ire
For such a petty Trespass, and not praise
Rather your dauntless vertue, whom the pain
Of Death denounc't, whatever thing Death be, [695]
Deterrd not from atchieving what might leade
To happier life, knowledge of Good and Evil;
Of good, how just? of evil, if what is evil
Be real, why not known, since easier shunnd?
God therefore cannot hurt ye, and be just; [700]
Not just, not God; not feard then, nor obeyd:
Your feare it self of Death removes the feare.
Why then was this forbid? Why but to awe,
Why but to keep ye low and ignorant,
His worshippers; he knows that in the day [705]
Ye Eate thereof, your Eyes that seem so cleere,
Yet are but dim, shall perfetly be then
Op'nd and cleerd, and ye shall be as Gods,
Knowing both Good and Evil as they know.
That ye should be as Gods, since I as Man, [710]
Internal Man, is but proportion meet,
I of brute human, yee of human Gods.
So ye shall die perhaps, by putting off
Human, to put on Gods, death to be wisht,
Though threat'nd, which no worse then this can bring. [715]
And what are Gods that Man may not become
As they, participating God-like food?
The Gods are first, and that advantage use
On our belief, that all from them proceeds;
I question it, for this fair Earth I see, [720]
Warm'd by the Sun, producing every kind,
Them nothing: If they all things, who enclos'd
Knowledge of Good and Evil in this Tree,
That whoso eats thereof, forthwith attains
Wisdom without their leave? and wherein lies [725]
Th' offence, that Man should thus attain to know?
What can your knowledge hurt him, or this Tree
Impart against his will if all be his?
Or is it envie, and can envie dwell
In Heav'nly brests? these, these and many more [730]
Causes import your need of this fair Fruit.
Goddess humane, reach then, and freely taste.
* * *
神はアダムとイヴに、知識の木の実を食べることを禁じている。
サタンは、彼らにこの禁を犯すよう仕向けたい。なぜなら、
神の意に反するということは、それまでにサタンがしてきたこと
であり、こうすることによって人間がサタンの仲間、神の敵と
なるから。
上の一節は、イヴに禁断の木の実を食べさせようとする
(ヘビに化けた)サタンの誘惑の言葉・議論。思うに、ポイントは、
支離滅裂とはいわないまでも、この議論が一貫していないこと。
もっともらしい議論の寄せ集めであること。しかし、イヴは
これに屈して禁断の木の実を食べる。(人類最初の罪=原罪を犯す。)
679-92 (日本語訳上の行数)
禁断の木の実を食べると善悪の知識が手に入る。
685-86
禁断の木の実を食べても死なない。
688-97
脅しに屈せず上をめざすのはいいこと。
698-99
善悪の知識は望ましいもの。
700-2
禁断の木の実を食べることは正しいことで、
これを禁じる、あるいは罰するような神は神ではないから、
従う必要もない。
703-5
人間に知識を禁じることは、神の支配にとって都合がいい。
706-15
死とは神と同等の知恵を手に入れること。望ましいこと。
716-17
神と同じものを食べれば神になれる。
718-22
神がすべてのものをつくった、というのは嘘。
722-25
神がすべてのものをつくったのなら、神の許可がなければ、
禁断の木の実も、それを食べた者に知識を与えることが
できないはず。
725-27
人間が知識を得ても、神は困らないはず。
727-28
神が禁じているような知識を与える力は、
知識の木の実にはない。
729-30
神が知識の木の実を人間に禁じているのは、
神が意地悪だから。そして、意地悪な神など、
本当の神ではないはず。
(夢の論理に関してフロイトが提示した「やかんの議論」を
思い出す。やかんを借りて穴をあけて返した人の言い訳--
1. 穴は直したはず、2. 穴なんてあいていない、3. やかんなんて
借りていない。)
いずれにせよ、一気にたたみかけるように語ることにより、
サタンの議論はある種の説得力をもつように見え、また
イヴが誘惑に屈することも、ある種やむをえないように
感じられるようになる。
これはある種のリアリズム。日常生活における会話・対話は、
往々にして少なからぬ矛盾をはらむが、しかし話す人によって、
また話しかたによって、説得力があったりなかったりする。
往々にしてそのような観察眼がミルトンの作品には感じられる。
(探偵小説的な厳密な論理性やそういう意味での完成度
のようなものは、そもそも17世紀の作品には存在しない。)
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_9/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
『楽園は失われた』 (9: 679-732)
(サタン 「禁じられた木の実なんて食べても平気」)
「うん、君は聖なる木、知恵ある木、そしてその知恵を与えてくれる、
知識の母のような木だね。今、ぼくは君の力を感じるよ。 680
はっきりとね。ぼくには見えるんだ、
原因のうちに結果が。それから、いちばんかしこい神々の
考えるようなことも読める。どんなに難しいことでもね。
ねえ、あなた、この世の女王さま、信じなくてもいいですよ、
死についてのあの恐ろしい脅しなんか。だって死なないんですから。
死ぬ、ですって? この実で? むしろ命が手に入るんですよ、
知識だけでなく。脅してくるあの彼の手で死ぬ? ぼくを見てくださいよ。
あの実をとって食べたのに、まだ生きてるし、
運命で決まってた以上の完璧な生きかたが
できるようになってます。上をめざすことによって、です。690
ぼくみたいな動物に許されることが人間に禁じられるなんて、
ありえます? 神が怒りに燃えあがったりしますか?
こんなささいな過失で? むしろほめてくれるんじゃないですか?
何ものも恐れることなく、いいことをするんですから。
死刑という脅しにも屈せず(そもそも死ってなんでしょう?)、
より幸せな生、善悪についての知識を
もたらす行為を貫くのですから。
善についての知識を手に入れるって、いいことですよね? 悪についても、もし
悪が本当にあるのなら、知っているべきでしょう? うまく避けるために。
つまりです、神はあなたに危害を加えたりしません。そんなことをしたら、もはや神は 700
正しくないですよ。そして、正しくない神なんて、もう神じゃありません。恐れることも従うことも
ないんです。ほら、死はこわいから、逆に死は恐れなくていい、ということになりました。
さて、では、なぜこの木の実は禁じられてるのでしょう? たんにこわがらせるためだけ、
あなたを無知で下等にしておくためだけなんじゃないですか?
そのほうが、彼を崇拝させるために都合がいいんです。彼は知っています。
この木の実を食べたら、澄みわたっているようで
実は曇っていたあなたの目がぱっちりと
開いて透明になり、そして神々のようになれるのです。
彼らと同じように、善と悪についてわかるようになるのです。
ぼくが人間のように、少なくとも内面的には人間のようになったのだから、710
あなたが神々のようになるということは、まさに当然ですよね。
ぼくは獣から人間になって、あなたは人間から神になる。
そう、だから、いいかたによっては、あなたは死ぬ、ということになるんでしょう。
人間の特徴を棄てて、神々の能力を身につけるのですから。すばらしいじゃないですか、
まるでこわいもののようにいわれてますが、こんなことが死だったら。
それから、そもそも神って何なんでしょうね? 神と同じものを
食べてたら、人間だって神になれるんじゃないですか?
それから、神々はぼくたちよりも前からいて、そのことをうまく利用して
ぼくたちに信じさせてます、彼らがすべてのものをつくった、って。
それはどうかな、と思うんですよ。だって、この美しい大地とか、見てください。720
太陽にあたためられて、あらゆるものを生み出してますよね。
これに対して、彼らが何かつくったのを見たことありますか? もし彼らがすべての
ものをつくったというのなら、誰がこの木に善と悪の知識を閉じこめたんでしょうね?
だって、この木の実を食べたら、彼らの許可もないのに
知恵が手に入るんですよ? それから、何がいけないんでしょうね?
人間が知識を得たとしても、ね? あなたが知識を得て、
神が困ることなんてないでしょう? そもそもこの木に、神が禁じている知識を
与える力なんてあるんでしょうか? すべてが神の思うがままだとしたら?
あ、もしかしたら、神がただ人間に対して意地悪をしてる、ってことでしょうか?
でも、神の胸に意地悪な考えが浮かぶなんて、ま、まさか・・・・・・・ねえ・・・・・・。730
こんなことをいろいろ考えると、やっぱりあなたはこの木の実を食べなくてはなりません。
人間である女神さま、ほら、手をのばして、ご自由にお召しあがりくださいませ。」
* * *
John Milton
Paradise Lost (9: 679-732)
O Sacred, Wise, and Wisdom-giving Plant,
Mother of Science, Now I feel thy Power [680]
Within me cleere, not onely to discerne
Things in thir Causes, but to trace the wayes
Of highest Agents, deemd however wise.
Queen of this Universe, doe not believe
Those rigid threats of Death; ye shall not Die: [685]
How should ye? by the Fruit? it gives you Life
To Knowledge, By the Threatner, look on mee,
Mee who have touch'd and tasted, yet both live,
And life more perfet have attaind then Fate
Meant mee, by ventring higher then my Lot. [690]
Shall that be shut to Man, which to the Beast
Is open? or will God incense his ire
For such a petty Trespass, and not praise
Rather your dauntless vertue, whom the pain
Of Death denounc't, whatever thing Death be, [695]
Deterrd not from atchieving what might leade
To happier life, knowledge of Good and Evil;
Of good, how just? of evil, if what is evil
Be real, why not known, since easier shunnd?
God therefore cannot hurt ye, and be just; [700]
Not just, not God; not feard then, nor obeyd:
Your feare it self of Death removes the feare.
Why then was this forbid? Why but to awe,
Why but to keep ye low and ignorant,
His worshippers; he knows that in the day [705]
Ye Eate thereof, your Eyes that seem so cleere,
Yet are but dim, shall perfetly be then
Op'nd and cleerd, and ye shall be as Gods,
Knowing both Good and Evil as they know.
That ye should be as Gods, since I as Man, [710]
Internal Man, is but proportion meet,
I of brute human, yee of human Gods.
So ye shall die perhaps, by putting off
Human, to put on Gods, death to be wisht,
Though threat'nd, which no worse then this can bring. [715]
And what are Gods that Man may not become
As they, participating God-like food?
The Gods are first, and that advantage use
On our belief, that all from them proceeds;
I question it, for this fair Earth I see, [720]
Warm'd by the Sun, producing every kind,
Them nothing: If they all things, who enclos'd
Knowledge of Good and Evil in this Tree,
That whoso eats thereof, forthwith attains
Wisdom without their leave? and wherein lies [725]
Th' offence, that Man should thus attain to know?
What can your knowledge hurt him, or this Tree
Impart against his will if all be his?
Or is it envie, and can envie dwell
In Heav'nly brests? these, these and many more [730]
Causes import your need of this fair Fruit.
Goddess humane, reach then, and freely taste.
* * *
神はアダムとイヴに、知識の木の実を食べることを禁じている。
サタンは、彼らにこの禁を犯すよう仕向けたい。なぜなら、
神の意に反するということは、それまでにサタンがしてきたこと
であり、こうすることによって人間がサタンの仲間、神の敵と
なるから。
上の一節は、イヴに禁断の木の実を食べさせようとする
(ヘビに化けた)サタンの誘惑の言葉・議論。思うに、ポイントは、
支離滅裂とはいわないまでも、この議論が一貫していないこと。
もっともらしい議論の寄せ集めであること。しかし、イヴは
これに屈して禁断の木の実を食べる。(人類最初の罪=原罪を犯す。)
679-92 (日本語訳上の行数)
禁断の木の実を食べると善悪の知識が手に入る。
685-86
禁断の木の実を食べても死なない。
688-97
脅しに屈せず上をめざすのはいいこと。
698-99
善悪の知識は望ましいもの。
700-2
禁断の木の実を食べることは正しいことで、
これを禁じる、あるいは罰するような神は神ではないから、
従う必要もない。
703-5
人間に知識を禁じることは、神の支配にとって都合がいい。
706-15
死とは神と同等の知恵を手に入れること。望ましいこと。
716-17
神と同じものを食べれば神になれる。
718-22
神がすべてのものをつくった、というのは嘘。
722-25
神がすべてのものをつくったのなら、神の許可がなければ、
禁断の木の実も、それを食べた者に知識を与えることが
できないはず。
725-27
人間が知識を得ても、神は困らないはず。
727-28
神が禁じているような知識を与える力は、
知識の木の実にはない。
729-30
神が知識の木の実を人間に禁じているのは、
神が意地悪だから。そして、意地悪な神など、
本当の神ではないはず。
(夢の論理に関してフロイトが提示した「やかんの議論」を
思い出す。やかんを借りて穴をあけて返した人の言い訳--
1. 穴は直したはず、2. 穴なんてあいていない、3. やかんなんて
借りていない。)
いずれにせよ、一気にたたみかけるように語ることにより、
サタンの議論はある種の説得力をもつように見え、また
イヴが誘惑に屈することも、ある種やむをえないように
感じられるようになる。
これはある種のリアリズム。日常生活における会話・対話は、
往々にして少なからぬ矛盾をはらむが、しかし話す人によって、
また話しかたによって、説得力があったりなかったりする。
往々にしてそのような観察眼がミルトンの作品には感じられる。
(探偵小説的な厳密な論理性やそういう意味での完成度
のようなものは、そもそも17世紀の作品には存在しない。)
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_9/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, Paradise Lost (4: 8-113)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『楽園は失われた』 (4: 8-113)
(サタン 「オレの存在が地獄そのもの」)
・・・・・・今、
サタンが、怒りの炎に燃えてやってきた。
人間を糾弾するのではなく、誘惑するために、である。
まだ罪を知らぬ、しかし罪を犯しうる人間に対して、天国での
敗北および地獄への逃亡の腹いせをしよう、というのだ。
勇敢で気高いサタンに、恐れるものなどない。
が、今の彼は、首尾上々、と得意げなようすでもない。
彼がはじめようとしている恐ろしい企てが、
頭をかけめぐり、また乱れる胸のなか沸騰しているのだった。
それは、まるで、悪魔の兵器の
自爆・・・・・・。恐怖と疑念で
思考が荒れる、乱れる。内なる地獄が
底から沸きたつ。そう、地獄は、
彼のうちにあった。また、彼をとりかこんでもいた。だから、サタンは、
地獄から一歩も抜け出せない。どこに行こうと
自分から逃げられないのと同じように。今、良心が、眠っていた
絶望を揺りおこす。苦い記憶を呼びさます。
過去の自分の姿、今の姿、そして未来の姿・・・・・・今より
さらに堕ちているに決まっている! 悪事を重ねれば苦しみも重なるのだ。
時おり、目の前に広がる楽しげな
エデンの園を、サタンは悲しげにじっと見つめる。
時おり、空、そして熱く燃えさかる太陽を見つめる。
今は正午--太陽はそびえたつ塔の上にあるかのよう。
そして、深く思い悩みつつ、彼はため息まじりに、こう話しはじめた--
「おい、おまえ、おまえは何よりも輝く冠をのせて、
神みたいな支配の座からこの世を
見下ろしている・・・・・・おまえがいると、星たちはみんな光を失い、
隠れてしまう・・・・・・そう、おまえだ、オレはおまえを呼んでいるんだ。
友だちだから、じゃないけどな。そうだな、名前で呼んでやろう、
おい、聞け、太陽、オレはおまえの光が大嫌いだ。
思い出してしまうからな。どんな高い地位から
落ちたか、をな。昔のオレは、おまえより輝いてた。
でも、オレは傲慢になって、いけない野心にかられて、落ちてしまった。
天国を支配する最強の王と戦って・・・・・・
うおおおおお! なんということを!? あんなこと、オレは
やっちゃいけなかった。あいつはオレをつくり、
輝く高位につけてくれた。やさしいから、
誰かを責めたりしなかった。あいつに仕えるのなんて、まったく楽なことだった。
あいつを称えることくらい楽な仕事なんてあるか?
ないよな? あいつに感謝することだって、
あたりまえだよな? でも、あいつが善良だから、オレが悪くなってしまった。
悪いことを考えるようになってしまった。高い地位についたから、
服従するのが嫌になった。もう一歩のぼれば
最高の地位につける、一瞬にして
膨大な、無限の感謝の借りをチャラにできる、と思った。
実際、こいつは重荷だった。払っても払っても負債が増えてくんだから。
あいつからいつもどんな恩恵を受けてるか、とか忘れてたし、
わかってなかった、感謝する者は
借りをつくると同時に返済しているのだと、感謝の
借りと返済は実は同じことなのだと。重荷なんて、はじめからなかったんだ。
なあ、あいつが強力な運命で定めて、
オレがもっと身分の低い天使だったらよかったのにな。そしたら、
オレ、幸せだったかもな。身のほど知らずな望み、
野望なんて抱かなかっただろうな。いやいやいや、そうでもないか。誰か、
オレくらい身分の高い奴が同じ野望を抱いて、身分の低いオレを
仲間に引き入れてたかもしれないしな。でも、オレくらい身分が高くても
堕落しなかった天使もいるよな。自分から悪いこと考えたり、
外から誘われてフラフラしたりしないでさ。誘惑なんて寄せつけません、ってな。
オレにもそういう自由な意志や、誘惑に耐える力がなかったのかな?
いや、あったよな。・・・・・・じゃ、誰のせいだ? 何がいけなかったんだ?
もちろん、誰にでも等しく与えられる天からの愛だよな。
あいつの愛を呪ってやる。だってよ、愛も憎しみも、
オレにとっては同じこと、この先、永劫につづく不幸をもたらしやがったんだからな。
・・・・・・バカいえ、おまえ自身を呪え、オレ! あいつの意に反して、自分の意志で
自由に選んで、今嘆いている状況に陥って・・・・・・
うおおおおお! バカなオレ! どこに逃げればいい?
永遠につづく怒りから? 永遠につづく絶望から?
どこに逃げたって、そこに地獄がある! だってオレが地獄そのものだから!
深い地獄の淵の底にいるのに、さらに深い淵が
口をあけてオレを飲みこもうとしている。
これに比べたら、オレたちが落ちてたあの地獄なんて、まるで天国だな。
・・・・・・はあ、もうお手上げだ。まだ間にあうかな?
悔いあらためたりしたら、さ。許してもらえるかな?
ま、あいつの支配下に入れば、ってことだよな。でも、敗北を認めるなんて、
オレのプライドが許すわけないし、恥ずかしいよな、
地獄に落ちた天使たちになんていえばいいんだろ? オレが誘ったんだもんな。
いろいろ約束して、偉そうなこといって、
まさか降伏だなんてな。全能者とやらを征服してやる、とか
いっちゃったもんな。はああ、あいつら、知らないんだよな。
あんな大嘘のおかげで、オレがどんだけつらいことになってるか、ってな。
オレは、心のなかで拷問に泣いてる、ってのによ。
地獄の王とかいってあいつらがオレを崇めたてまつって、
冠やら笏やらあてがってもちあげてても、
でも、オレは落ちつづけてる。最高の地位にいて、
そして、最高に悲惨・・・・・・。野望を抱いたごほうび、ってことだな。
でも、もし、オレが悔いあらためて、もし
特赦によって前の地位に戻れたとしたら、どうかな? いや、高い地位に
戻れば、すぐに傲慢な考えが復活するに決まってる。降伏なんて
嘘でした! っていうに決まってる。苦痛がなくなれば、苦痛のなかで
誓ったことなんて無効、暴力によっていわされた、って取り消すに決まってる。
本当の和解なんて無理なんだ、
殺したいほどの憎しみが深い、消えない爪跡を残してるんだからな。
結局、オレは、より悪い罪を犯し、
より深く堕ちて、そしてより重い罰を受けるだけなんだ。高い代償を払って、
しばしの息抜きと、そして二倍の苦痛と苦悩を買うだけなんだ。
今、オレを罰しているあいつも、これを知ってる。だから、オレと和解する気なんて
あいつにはないし、オレも和平なんて求めない。
さて、これでもう希望なんて絶滅だな。追い出されたオレたちのことなんて
もういいから、新しくつくられて、今、あいつに大事にされている
人間と、そいつのためにつくられたこの世界のことを考えよう。
さらばだ、希望! 希望といっしょに消えろ、恐怖心!
さらばだ、良心! もうオレに善はいらない!
悪、これからはおまえがオレの善だ! おまえとともに、
オレは天の王とこの世の支配権を
分けあうんだ。たぶん、この世の半分以上はオレのものになるはずだ。
遠からず、人間やこの新しい世界にも思い知らせてやるからな。」
* * *
John Milton
Paradise Lost (4: 8-113)
. . . now
Satan, now first inflam'd with rage, came down,
The Tempter ere th' Accuser of man-kind, [10]
To wreck on innocent frail man his loss
Of that first Battel, and his flight to Hell:
Yet not rejoycing in his speed, though bold,
Far off and fearless, nor with cause to boast,
Begins his dire attempt, which nigh the birth [15]
Now rowling, boiles in his tumultuous brest,
And like a devillish Engine back recoiles
Upon himself; horror and doubt distract
His troubl'd thoughts, and from the bottom stirr
The Hell within him, for within him Hell [20]
He brings, and round about him, nor from Hell
One step no more then from himself can fly
By change of place: Now conscience wakes despair
That slumberd, wakes the bitter memorie
Of what he was, what is, and what must be [25]
Worse; of worse deeds worse sufferings must ensue.
Sometimes towards Eden which now in his view
Lay pleasant, his grievd look he fixes sad,
Sometimes towards Heav'n and the full-blazing Sun,
Which now sat high in his Meridian Towre: [30]
Then much revolving, thus in sighs began.
O thou that with surpassing Glory crownd,
Look'st from thy sole Dominion like the God
Of this new World; at whose sight all the Starrs
Hide thir diminisht heads; to thee I call, [35]
But with no friendly voice, and add thy name
O Sun, to tell thee how I hate thy beams
That bring to my remembrance from what state
I fell, how glorious once above thy Spheare;
Till Pride and worse Ambition threw me down [40]
Warring in Heav'n against Heav'ns matchless King:
Ah wherefore! he deservd no such return
From me, whom he created what I was
In that bright eminence, and with his good
Upbraided none; nor was his service hard. [45]
What could be less then to afford him praise,
The easiest recompence, and pay him thanks,
How due! yet all his good prov'd ill in me,
And wrought but malice; lifted up so high
I sdeind subjection, and thought one step higher [50]
Would set me highest, and in a moment quit
The debt immense of endless gratitude,
So burthensome, still paying, still to ow;
Forgetful what from him I still receivd,
And understood not that a grateful mind [55]
By owing owes not, but still pays, at once
Indebted and dischargd; what burden then?
O had his powerful Destiny ordaind
Me some inferiour Angel, I had stood
Then happie; no unbounded hope had rais'd [60]
Ambition. Yet why not? som other Power
As great might have aspir'd, and me though mean
Drawn to his part; but other Powers as great
Fell not, but stand unshak'n, from within
Or from without, to all temptations arm'd. [65]
Hadst thou the same free Will and Power to stand?
Thou hadst: whom hast thou then or what to accuse,
But Heav'ns free Love dealt equally to all?
Be then his Love accurst, since love or hate,
To me alike, it deals eternal woe. [70]
Nay curs'd be thou; since against his thy will
Chose freely what it now so justly rues.
Me miserable! which way shall I flie
Infinite wrauth, and infinite despaire?
Which way I flie is Hell; my self am Hell; [75]
And in the lowest deep a lower deep
Still threatning to devour me opens wide,
To which the Hell I suffer seems a Heav'n.
O then at last relent: is there no place
Left for Repentance, none for Pardon left? [80]
None left but by submission; and that word
Disdain forbids me, and my dread of shame
Among the Spirits beneath, whom I seduc'd
With other promises and other vaunts
Then to submit, boasting I could subdue [85]
Th' Omnipotent. Ay me, they little know
How dearly I abide that boast so vaine,
Under what torments inwardly I groane:
While they adore me on the Throne of Hell,
With Diadem and Sceptre high advanc'd [90]
The lower still I fall, onely Supream
In miserie; such joy Ambition findes.
But say I could repent and could obtaine
By Act of Grace my former state; how soon
Would higth recall high thoughts, how soon unsay [95]
What feign'd submission swore: ease would recant
Vows made in pain, as violent and void.
For never can true reconcilement grow
Where wounds of deadly hate have peirc'd so deep:
Which would but lead me to a worse relapse [100]
And heavier fall: so should I purchase deare
Short intermission bought with double smart.
This knows my punisher; therefore as farr
From granting hee, as I from begging peace:
All hope excluded thus, behold in stead [105]
Of us out-cast, exil'd, his new delight,
Mankind created, and for him this World.
So farewel Hope, and with Hope farewel Fear,
Farewel Remorse: all Good to me is lost;
Evil be thou my Good; by thee at least [110]
Divided Empire with Heav'ns King I hold
By thee, and more then half perhaps will reigne;
As Man ere long, and this new World shall know.
* * *
20
The Hell within him, for within him Hell
鏡構造の行。地獄--彼のうちに--彼のうちに--地獄
25-26
Of what he was,
what is,
and what must be Worse;
[W]asとWorseの意地悪な音あわせ。
20世紀的な言いかたをするなら、「不完全なパラライム」。
75
Hell; my self am Hell
ふたたび鏡構造--is ではなく am なのは、
my と音をあわせるため。
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_4/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
『楽園は失われた』 (4: 8-113)
(サタン 「オレの存在が地獄そのもの」)
・・・・・・今、
サタンが、怒りの炎に燃えてやってきた。
人間を糾弾するのではなく、誘惑するために、である。
まだ罪を知らぬ、しかし罪を犯しうる人間に対して、天国での
敗北および地獄への逃亡の腹いせをしよう、というのだ。
勇敢で気高いサタンに、恐れるものなどない。
が、今の彼は、首尾上々、と得意げなようすでもない。
彼がはじめようとしている恐ろしい企てが、
頭をかけめぐり、また乱れる胸のなか沸騰しているのだった。
それは、まるで、悪魔の兵器の
自爆・・・・・・。恐怖と疑念で
思考が荒れる、乱れる。内なる地獄が
底から沸きたつ。そう、地獄は、
彼のうちにあった。また、彼をとりかこんでもいた。だから、サタンは、
地獄から一歩も抜け出せない。どこに行こうと
自分から逃げられないのと同じように。今、良心が、眠っていた
絶望を揺りおこす。苦い記憶を呼びさます。
過去の自分の姿、今の姿、そして未来の姿・・・・・・今より
さらに堕ちているに決まっている! 悪事を重ねれば苦しみも重なるのだ。
時おり、目の前に広がる楽しげな
エデンの園を、サタンは悲しげにじっと見つめる。
時おり、空、そして熱く燃えさかる太陽を見つめる。
今は正午--太陽はそびえたつ塔の上にあるかのよう。
そして、深く思い悩みつつ、彼はため息まじりに、こう話しはじめた--
「おい、おまえ、おまえは何よりも輝く冠をのせて、
神みたいな支配の座からこの世を
見下ろしている・・・・・・おまえがいると、星たちはみんな光を失い、
隠れてしまう・・・・・・そう、おまえだ、オレはおまえを呼んでいるんだ。
友だちだから、じゃないけどな。そうだな、名前で呼んでやろう、
おい、聞け、太陽、オレはおまえの光が大嫌いだ。
思い出してしまうからな。どんな高い地位から
落ちたか、をな。昔のオレは、おまえより輝いてた。
でも、オレは傲慢になって、いけない野心にかられて、落ちてしまった。
天国を支配する最強の王と戦って・・・・・・
うおおおおお! なんということを!? あんなこと、オレは
やっちゃいけなかった。あいつはオレをつくり、
輝く高位につけてくれた。やさしいから、
誰かを責めたりしなかった。あいつに仕えるのなんて、まったく楽なことだった。
あいつを称えることくらい楽な仕事なんてあるか?
ないよな? あいつに感謝することだって、
あたりまえだよな? でも、あいつが善良だから、オレが悪くなってしまった。
悪いことを考えるようになってしまった。高い地位についたから、
服従するのが嫌になった。もう一歩のぼれば
最高の地位につける、一瞬にして
膨大な、無限の感謝の借りをチャラにできる、と思った。
実際、こいつは重荷だった。払っても払っても負債が増えてくんだから。
あいつからいつもどんな恩恵を受けてるか、とか忘れてたし、
わかってなかった、感謝する者は
借りをつくると同時に返済しているのだと、感謝の
借りと返済は実は同じことなのだと。重荷なんて、はじめからなかったんだ。
なあ、あいつが強力な運命で定めて、
オレがもっと身分の低い天使だったらよかったのにな。そしたら、
オレ、幸せだったかもな。身のほど知らずな望み、
野望なんて抱かなかっただろうな。いやいやいや、そうでもないか。誰か、
オレくらい身分の高い奴が同じ野望を抱いて、身分の低いオレを
仲間に引き入れてたかもしれないしな。でも、オレくらい身分が高くても
堕落しなかった天使もいるよな。自分から悪いこと考えたり、
外から誘われてフラフラしたりしないでさ。誘惑なんて寄せつけません、ってな。
オレにもそういう自由な意志や、誘惑に耐える力がなかったのかな?
いや、あったよな。・・・・・・じゃ、誰のせいだ? 何がいけなかったんだ?
もちろん、誰にでも等しく与えられる天からの愛だよな。
あいつの愛を呪ってやる。だってよ、愛も憎しみも、
オレにとっては同じこと、この先、永劫につづく不幸をもたらしやがったんだからな。
・・・・・・バカいえ、おまえ自身を呪え、オレ! あいつの意に反して、自分の意志で
自由に選んで、今嘆いている状況に陥って・・・・・・
うおおおおお! バカなオレ! どこに逃げればいい?
永遠につづく怒りから? 永遠につづく絶望から?
どこに逃げたって、そこに地獄がある! だってオレが地獄そのものだから!
深い地獄の淵の底にいるのに、さらに深い淵が
口をあけてオレを飲みこもうとしている。
これに比べたら、オレたちが落ちてたあの地獄なんて、まるで天国だな。
・・・・・・はあ、もうお手上げだ。まだ間にあうかな?
悔いあらためたりしたら、さ。許してもらえるかな?
ま、あいつの支配下に入れば、ってことだよな。でも、敗北を認めるなんて、
オレのプライドが許すわけないし、恥ずかしいよな、
地獄に落ちた天使たちになんていえばいいんだろ? オレが誘ったんだもんな。
いろいろ約束して、偉そうなこといって、
まさか降伏だなんてな。全能者とやらを征服してやる、とか
いっちゃったもんな。はああ、あいつら、知らないんだよな。
あんな大嘘のおかげで、オレがどんだけつらいことになってるか、ってな。
オレは、心のなかで拷問に泣いてる、ってのによ。
地獄の王とかいってあいつらがオレを崇めたてまつって、
冠やら笏やらあてがってもちあげてても、
でも、オレは落ちつづけてる。最高の地位にいて、
そして、最高に悲惨・・・・・・。野望を抱いたごほうび、ってことだな。
でも、もし、オレが悔いあらためて、もし
特赦によって前の地位に戻れたとしたら、どうかな? いや、高い地位に
戻れば、すぐに傲慢な考えが復活するに決まってる。降伏なんて
嘘でした! っていうに決まってる。苦痛がなくなれば、苦痛のなかで
誓ったことなんて無効、暴力によっていわされた、って取り消すに決まってる。
本当の和解なんて無理なんだ、
殺したいほどの憎しみが深い、消えない爪跡を残してるんだからな。
結局、オレは、より悪い罪を犯し、
より深く堕ちて、そしてより重い罰を受けるだけなんだ。高い代償を払って、
しばしの息抜きと、そして二倍の苦痛と苦悩を買うだけなんだ。
今、オレを罰しているあいつも、これを知ってる。だから、オレと和解する気なんて
あいつにはないし、オレも和平なんて求めない。
さて、これでもう希望なんて絶滅だな。追い出されたオレたちのことなんて
もういいから、新しくつくられて、今、あいつに大事にされている
人間と、そいつのためにつくられたこの世界のことを考えよう。
さらばだ、希望! 希望といっしょに消えろ、恐怖心!
さらばだ、良心! もうオレに善はいらない!
悪、これからはおまえがオレの善だ! おまえとともに、
オレは天の王とこの世の支配権を
分けあうんだ。たぶん、この世の半分以上はオレのものになるはずだ。
遠からず、人間やこの新しい世界にも思い知らせてやるからな。」
* * *
John Milton
Paradise Lost (4: 8-113)
. . . now
Satan, now first inflam'd with rage, came down,
The Tempter ere th' Accuser of man-kind, [10]
To wreck on innocent frail man his loss
Of that first Battel, and his flight to Hell:
Yet not rejoycing in his speed, though bold,
Far off and fearless, nor with cause to boast,
Begins his dire attempt, which nigh the birth [15]
Now rowling, boiles in his tumultuous brest,
And like a devillish Engine back recoiles
Upon himself; horror and doubt distract
His troubl'd thoughts, and from the bottom stirr
The Hell within him, for within him Hell [20]
He brings, and round about him, nor from Hell
One step no more then from himself can fly
By change of place: Now conscience wakes despair
That slumberd, wakes the bitter memorie
Of what he was, what is, and what must be [25]
Worse; of worse deeds worse sufferings must ensue.
Sometimes towards Eden which now in his view
Lay pleasant, his grievd look he fixes sad,
Sometimes towards Heav'n and the full-blazing Sun,
Which now sat high in his Meridian Towre: [30]
Then much revolving, thus in sighs began.
O thou that with surpassing Glory crownd,
Look'st from thy sole Dominion like the God
Of this new World; at whose sight all the Starrs
Hide thir diminisht heads; to thee I call, [35]
But with no friendly voice, and add thy name
O Sun, to tell thee how I hate thy beams
That bring to my remembrance from what state
I fell, how glorious once above thy Spheare;
Till Pride and worse Ambition threw me down [40]
Warring in Heav'n against Heav'ns matchless King:
Ah wherefore! he deservd no such return
From me, whom he created what I was
In that bright eminence, and with his good
Upbraided none; nor was his service hard. [45]
What could be less then to afford him praise,
The easiest recompence, and pay him thanks,
How due! yet all his good prov'd ill in me,
And wrought but malice; lifted up so high
I sdeind subjection, and thought one step higher [50]
Would set me highest, and in a moment quit
The debt immense of endless gratitude,
So burthensome, still paying, still to ow;
Forgetful what from him I still receivd,
And understood not that a grateful mind [55]
By owing owes not, but still pays, at once
Indebted and dischargd; what burden then?
O had his powerful Destiny ordaind
Me some inferiour Angel, I had stood
Then happie; no unbounded hope had rais'd [60]
Ambition. Yet why not? som other Power
As great might have aspir'd, and me though mean
Drawn to his part; but other Powers as great
Fell not, but stand unshak'n, from within
Or from without, to all temptations arm'd. [65]
Hadst thou the same free Will and Power to stand?
Thou hadst: whom hast thou then or what to accuse,
But Heav'ns free Love dealt equally to all?
Be then his Love accurst, since love or hate,
To me alike, it deals eternal woe. [70]
Nay curs'd be thou; since against his thy will
Chose freely what it now so justly rues.
Me miserable! which way shall I flie
Infinite wrauth, and infinite despaire?
Which way I flie is Hell; my self am Hell; [75]
And in the lowest deep a lower deep
Still threatning to devour me opens wide,
To which the Hell I suffer seems a Heav'n.
O then at last relent: is there no place
Left for Repentance, none for Pardon left? [80]
None left but by submission; and that word
Disdain forbids me, and my dread of shame
Among the Spirits beneath, whom I seduc'd
With other promises and other vaunts
Then to submit, boasting I could subdue [85]
Th' Omnipotent. Ay me, they little know
How dearly I abide that boast so vaine,
Under what torments inwardly I groane:
While they adore me on the Throne of Hell,
With Diadem and Sceptre high advanc'd [90]
The lower still I fall, onely Supream
In miserie; such joy Ambition findes.
But say I could repent and could obtaine
By Act of Grace my former state; how soon
Would higth recall high thoughts, how soon unsay [95]
What feign'd submission swore: ease would recant
Vows made in pain, as violent and void.
For never can true reconcilement grow
Where wounds of deadly hate have peirc'd so deep:
Which would but lead me to a worse relapse [100]
And heavier fall: so should I purchase deare
Short intermission bought with double smart.
This knows my punisher; therefore as farr
From granting hee, as I from begging peace:
All hope excluded thus, behold in stead [105]
Of us out-cast, exil'd, his new delight,
Mankind created, and for him this World.
So farewel Hope, and with Hope farewel Fear,
Farewel Remorse: all Good to me is lost;
Evil be thou my Good; by thee at least [110]
Divided Empire with Heav'ns King I hold
By thee, and more then half perhaps will reigne;
As Man ere long, and this new World shall know.
* * *
20
The Hell within him, for within him Hell
鏡構造の行。地獄--彼のうちに--彼のうちに--地獄
25-26
Of what he was,
what is,
and what must be Worse;
[W]asとWorseの意地悪な音あわせ。
20世紀的な言いかたをするなら、「不完全なパラライム」。
75
Hell; my self am Hell
ふたたび鏡構造--is ではなく am なのは、
my と音をあわせるため。
* * *
英語テクストは、以下のものを使用。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/pl/book_4/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, Paradise Lost (1: 84-124)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『楽園は失われた』 (1: 84-124)
(サタン 「負けるもんか!」)
おまえ、か? フッ、落ちたもんだな。
変わっちまったな・・・・・・。幸せだったよな、あの光の国で、おまえ、
みんなよりもキラキラしてた、輝いてた、よな。
もちろん、みんなキラキラしてた・・・・・・。オレたち、誓ったよな。
ふたりで考えて、心を決めて、希望を抱いて、
危険を冒したよな。あの輝かしくもやばい仕事で、な。
オレたち、いっしょに戦って、そして、今、いっしょにどん底だ、
なかよく破滅だ。なんて深いところによ、
なんて高いところから、落ちたものか・・・・・・。あいつ、思ったより強かったからな、
雷なんか使いやがって。戦うまでは誰も知らなかったよな、
あのひどい武器の破壊力なんてよ。でもな、そんなん知るか、ってもんだ。
あいつが怒って、また攻めて
きたとしても、オレは悔い改めない。オレは変わらない。
見かけは変わっても、輝きをなくしちまっても、オレはオレだ。あの決意、
あいつを見下す気高い心・・・・・そもそもちゃんと認められなかったから、
最強のあいつと戦ったんだろ?
あの誇り高き戦い・・・・・・
他の天使のやつらもたくさんついてきたよな。武器もって、さ。
みんな、あいつの支配よりもオレのほうがいいっていってたぜ?
あいつ、神のくせに全力出して、オレたちも押し返して、
あの天の戦い、いい勝負だったよな。あいつの王座だって、
ぐらついてただろ。勝ち負けなんて関係ないぜ。
負けて全部失ったわけじゃない。心はまだ折れてない。
復讐だぜ。あいつへの憎しみは絶対に消えないし、
オレたち勇敢だから絶対降伏なんてしないよな。ゴメンナサイ、とかいわないよな。
つまりさ、オレたち、負けてない、ってことだ。
あいつがどれだけ怒り狂っても、あいつがどれだけ強くても、
オレを負かす、なんて栄誉はやらん。
頭下げて膝ついて、どうかお許しを、とか
いって一回勝っただけのあいつを神と認めるなんて、
(ついさっきまであいつ、オレにびびって、
国がやべえ、とかいってたんだからな)、そんなの、ダサすぎだろ。
まさに不名誉、恥ずかしいよな。
地獄落ち以下だ。〈運命〉ではじめから決まってるだろ、
オレたち神だから、力は衰えないし、からだも傷つかない、ってさ。オレたちは死なないんだ。
一回やらかしちまった後でも、オレたちの
戦闘能力は落ちてないし、むしろ読みは鋭くなってる。
だからよ、前よりいい結果めざして、やってみようぜ。
武器を使ってもいい、策略を使ってもいい、死ぬまで戦うんだ。
和平なんて無理だ、あいつは最大の敵だから。
今ごろ大喜びで勝利に乾杯してやがって、
天で独裁して、好き放題やってるあいつと戦うんだ。
* * *
John Milton
Paradise Lost (1: 84-124)
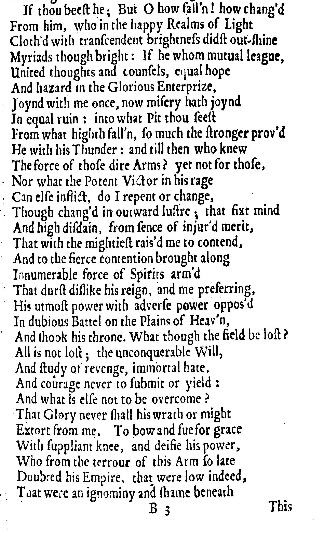

* * *
天国での戦いにおいて神(と神の子)に敗れ、地獄に落とされたサタンが、
炎の湖のほとりで、かつての仲間のビエルゼバブ(と思しき堕天使)を見つけ、
話しかける場面。
サタン(悪に走る前の名はルシファー)が堕天使のトップで、
ビエルゼバブがナンバー2。
* * *
以下、訳注と解釈例。
84-92
構文は、次のようなかたち。
If thou beest he . . . (条件節),
if [thou beest] he. . . (条件節のくり返し)
into what Pit fallen? (帰結節)
「もしおまえがわたしの知っている彼なら・・・・・・
なあ、オレたち、どれだけ落ちてきたんだ?」
But O how fall'n! から四行、Myriad though brightまでは
挿入された節。口語的/会話的に、連想が飛んで、大枠の構文からは
独立して発展して、という感じ。
なお、本来、92行目のfall'nの後にピリオドがあるべきだが、
口語的/会話的に話がつづいていることを示すために、
コンマで次の文へとつなげられている。
84 thou
二人称単数の代名詞の主格。話しかけている相手をあらわすもの。
主として自分より地位が低い相手に対して使う。
84 beest
Beの仮定法二人称単数形。Thouに対応してbeが活用している。
If thou beest he = If you should/could be he
84 fallen
(過去分詞、形容詞)
高い場所から降りて/落ちてきた(天国から地獄へ--OED, "fallen" 1)
高い地位から落ちて/堕ちてきた(天使から堕天使へ--OED, "fallen" 5)。
加えて、受け身の構文(how thou art fallen)でもあるので--
(神に)「落とされた」(過去に落とされた、というだけではなく、
過去に落とされて、現在落ちている状態である、ということ。)
85 Realm[s]
王国(kingdom)(OED 1-2a)。"the Realms of Light" は天国のこと。
「王」国なのは、天国(実際この世すべて)を、
神が王として支配しているから。領域、場所(OED 2b-c)。
86 transcendent
形容詞。他の同種のものより勝る(OED 1)。
87 If he
If [thou beest] he. . . .
86 outshine
動詞。他のものより輝く(OED 1)。輝いているのは、天使だから。
同じ行のtranscendentと不必要に意味が重なっている。が、このように、
特に地位的なことがらについて、他の者と自分(ここでは自分の舎弟的な
ビエルゼバブ)を比べたがり、そして自分(たち)が上にいないと
気がすまないのが、ミルトンの描くサタン。いつでも地位にこだわる。
88 counsel[s]
決意、目的、意図、計画、企画、陰謀(OED 4)。
91 ruin
建物などが、崩れ、倒れること(OED 1a)。
社会的破滅(財産、地位などを失うこと)(OED 6a)。
絶望的にみじめな状態(OED 7)。
91 Pit
地面に掘られた穴(OED 1)。地獄(OED 4)。
91 thou seest
現代英語のyou see--「わかるだろ」、「な?」、「ね?」、
というニュアンスの挿入句--のようなかたちでここに入っている。
散文的に直すと、ここは、次のような間接疑問の構文。
Thou seest into what Pit [and] from what highth
[thou art / we are] fall'n.
92-93
「神は雷をもっていて、だからその分強かった」
=「雷がなければ、オレたちが勝っていたはず」
たとえ神に雷がなくても、本来サタンらは神に敵わないはずなのだが、
その事実を認めようとしていないことをあらわす。そこが、まさにサタン的。
92 the stronger
ここのtheは定冠詞ではなく副詞。次の行のwith his Thunderと
対応して、「だからますます」。
以下の言葉からもわかる通り、サタンにとっては、
強いかどうかがほとんど唯一の価値基準。
93 He
神のこと。サタンは「神」ということばを使わない。
神を唯一絶対的な神と認めていないから。
(表向きに強がっていて。)
93 Thunder
ギリシャ/ローマ神話における最高神ゼウス/ユピテルの武器。
聖書においても神(イエス・キリストではなく、父なる神、主)の武器
(出エジプト記9:23など)。
98 merit
高い評価や褒賞や感謝に値すること(OED 3a)。
称賛や高い評価に対する要求、またこれらを要求する
権利や資格(OED 4a)
99 the mightiest
神のこと。通常、Mightiestと大文字で表記して、
神をあらわす固有名詞とするところだが、そうしていない。
サタンは、神=最強の者、と認めていないから。
たまたま、結果的に、今回はヤツがいちばん強かったが、
次の戦いがあったら違う結果もありうる、というような意識があって。
99 fierce
気高く勇敢な(OED 2, 古語)。誇り高き、傲慢な(OED 3, 古語)。
野獣のように暴力的で激しい(OED 1)。
サタンと神との戦いは、自分を美化したがるサタンの視点から
見れば「気高く勇敢な」もの。しかしキリスト教的な価値観において、
それは、「傲慢な」もの。(「傲慢」prideとは、中世以来の神学に
おける「七つの大罪」のうち、もっとも大きな罪。) さらに、
ゲンコツや、弓や、銃や、せいぜい大砲程度の武器による
人間の戦いにくらべて、神や天使など霊的な存在による戦いは、
はるかに「暴力的で激しい」。
---
キリスト教的道徳における「傲慢」(pride)とは、神によって
与えられているもの(地位、性質、能力、外見など)以上のものを
求める、あるいはそれに値すると考える、人間の心や意識を指す。
「傲慢」から「妬み」(envy)が生まれる--
ホントはオレのほうが高い地位に値するはずなのに、
なんであいつが・・・・・・。
「傲慢」から「怒り」が生まれる--
なぜオレが認められない? なぜオレに地位がない?
金がない?
「傲慢」から「怠惰」(sloth)が生まれる--
オレには能力があるはずだから、コツコツとケチな努力なんか
する必要ない。そんなことしなくても、高い地位につけるはず、
なんでも手に入るはず。
「傲慢」から「貪欲」(greed/avarice/covetousness) が
生まれる--
地位をくれ、金をくれ、みんなくれ。
---
103 utmost
最大限の。サタンを倒すために、全力を出して、本当に
懸命になって、神は戦った、ということ。あくまで、これは、
サタンの妄想。実際は、
サタン率いる堕天使軍 VS 善良な天使軍
=引き分け
サタン率いる堕天使軍 VS 神の子
=神の子の完勝、まったくお話にならないくらいの圧勝。
(神自身は戦いに出てきてすらいない。)
これを「惜しい戦いだった」、「ヤツも必死だった」というところが、
サタンの欺瞞。人間くさいところ。
104 Plains
広がる空(OED 1c)。戦場(OED 2)。
105 study
目的達成のために向けられる思考や努力(OED 4a)。
夢想、実のともなわない思考(OED 3b)
110 Glory
栄誉や名声をもたらすもの。自慢の種(OED 3)。
116 by Fate
神ではなく、「運命」が、この世に存在するものすべてを
支配している、というサタンの考えがあらわれている。
(これはあくまで対外的な見解で、心の底ではサタンも、
神の支配を理解し、また認めている。第四巻の独白参照。)
なお、「運命」は、ギリシャ/ローマ神話では女神として
神格化されている。ここの発言においてサタンは異教的
(異教的な運命の神 > キリスト教の神)。
116 Gods
天使たちのこと。その対外的発言において、サタンは、
神と天使たちのあいだの違いを認めない。
117 fail
不足する、なくなる、消える、力を失う、死ぬ(OED I)。
122 grand Foe
Grand=もっとも位の高い、最大の(OED 2-3)。Foe=敵。
普通、「最大の敵」(arch enemy, arch foe) といったら
サタンのこと。(Satanとは、ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語などの
「敵」、「敵対する」ということばから由来。)
* * *
上の英文テクストは、John Milton, Paradise Lost (1674) より。
以下は、Milton Reading Roomのもの。
If thou beest he; But O how fall'n! how chang'd
From him, who in the happy Realms of Light [85]
Cloth'd with transcendent brightness didst out-shine
Myriads though bright: If he Whom mutual league,
United thoughts and counsels, equal hope
And hazard in the Glorious Enterprize,
Joynd with me once, now misery hath joynd [90]
In equal ruin: into what Pit thou seest
From what highth fall'n, so much the stronger prov'd
He with his Thunder: and till then who knew
The force of those dire Arms? yet not for those,
Nor what the Potent Victor in his rage [95]
Can else inflict, do I repent or change,
Though chang'd in outward lustre; that fixt mind
And high disdain, from sence of injur'd merit,
That with the mightiest rais'd me to contend,
And to the fierce contention brought along [100]
Innumerable force of Spirits arm'd
That durst dislike his reign, and me preferring,
His utmost power with adverse power oppos'd
In dubious Battel on the Plains of Heav'n,
And shook his throne. What though the field be lost? [105]
All is not lost; the unconquerable Will,
And study of revenge, immortal hate,
And courage never to submit or yield:
And what is else not to be overcome?
That Glory never shall his wrath or might [110]
Extort from me. To bow and sue for grace
With suppliant knee, and deifie his power,
Who from the terrour of this Arm so late
Doubted his Empire, that were low indeed,
That were an ignominy and shame beneath [115]
This downfall; since by Fate the strength of Gods
And this Empyreal substance cannot fail,
Since through experience of this great event
In Arms not worse, in foresight much advanc't,
We may with more successful hope resolve [120]
To wage by force or guile eternal Warr
Irreconcileable, to our grand Foe,
Who now triumphs, and in th' excess of joy
Sole reigning holds the Tyranny of Heav'n.
http://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/
pl/book_1/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
『楽園は失われた』 (1: 84-124)
(サタン 「負けるもんか!」)
おまえ、か? フッ、落ちたもんだな。
変わっちまったな・・・・・・。幸せだったよな、あの光の国で、おまえ、
みんなよりもキラキラしてた、輝いてた、よな。
もちろん、みんなキラキラしてた・・・・・・。オレたち、誓ったよな。
ふたりで考えて、心を決めて、希望を抱いて、
危険を冒したよな。あの輝かしくもやばい仕事で、な。
オレたち、いっしょに戦って、そして、今、いっしょにどん底だ、
なかよく破滅だ。なんて深いところによ、
なんて高いところから、落ちたものか・・・・・・。あいつ、思ったより強かったからな、
雷なんか使いやがって。戦うまでは誰も知らなかったよな、
あのひどい武器の破壊力なんてよ。でもな、そんなん知るか、ってもんだ。
あいつが怒って、また攻めて
きたとしても、オレは悔い改めない。オレは変わらない。
見かけは変わっても、輝きをなくしちまっても、オレはオレだ。あの決意、
あいつを見下す気高い心・・・・・そもそもちゃんと認められなかったから、
最強のあいつと戦ったんだろ?
あの誇り高き戦い・・・・・・
他の天使のやつらもたくさんついてきたよな。武器もって、さ。
みんな、あいつの支配よりもオレのほうがいいっていってたぜ?
あいつ、神のくせに全力出して、オレたちも押し返して、
あの天の戦い、いい勝負だったよな。あいつの王座だって、
ぐらついてただろ。勝ち負けなんて関係ないぜ。
負けて全部失ったわけじゃない。心はまだ折れてない。
復讐だぜ。あいつへの憎しみは絶対に消えないし、
オレたち勇敢だから絶対降伏なんてしないよな。ゴメンナサイ、とかいわないよな。
つまりさ、オレたち、負けてない、ってことだ。
あいつがどれだけ怒り狂っても、あいつがどれだけ強くても、
オレを負かす、なんて栄誉はやらん。
頭下げて膝ついて、どうかお許しを、とか
いって一回勝っただけのあいつを神と認めるなんて、
(ついさっきまであいつ、オレにびびって、
国がやべえ、とかいってたんだからな)、そんなの、ダサすぎだろ。
まさに不名誉、恥ずかしいよな。
地獄落ち以下だ。〈運命〉ではじめから決まってるだろ、
オレたち神だから、力は衰えないし、からだも傷つかない、ってさ。オレたちは死なないんだ。
一回やらかしちまった後でも、オレたちの
戦闘能力は落ちてないし、むしろ読みは鋭くなってる。
だからよ、前よりいい結果めざして、やってみようぜ。
武器を使ってもいい、策略を使ってもいい、死ぬまで戦うんだ。
和平なんて無理だ、あいつは最大の敵だから。
今ごろ大喜びで勝利に乾杯してやがって、
天で独裁して、好き放題やってるあいつと戦うんだ。
* * *
John Milton
Paradise Lost (1: 84-124)
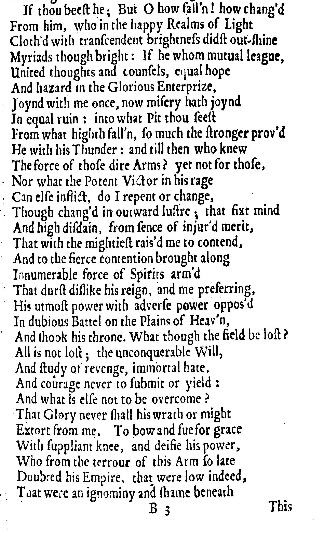

* * *
天国での戦いにおいて神(と神の子)に敗れ、地獄に落とされたサタンが、
炎の湖のほとりで、かつての仲間のビエルゼバブ(と思しき堕天使)を見つけ、
話しかける場面。
サタン(悪に走る前の名はルシファー)が堕天使のトップで、
ビエルゼバブがナンバー2。
* * *
以下、訳注と解釈例。
84-92
構文は、次のようなかたち。
If thou beest he . . . (条件節),
if [thou beest] he. . . (条件節のくり返し)
into what Pit fallen? (帰結節)
「もしおまえがわたしの知っている彼なら・・・・・・
なあ、オレたち、どれだけ落ちてきたんだ?」
But O how fall'n! から四行、Myriad though brightまでは
挿入された節。口語的/会話的に、連想が飛んで、大枠の構文からは
独立して発展して、という感じ。
なお、本来、92行目のfall'nの後にピリオドがあるべきだが、
口語的/会話的に話がつづいていることを示すために、
コンマで次の文へとつなげられている。
84 thou
二人称単数の代名詞の主格。話しかけている相手をあらわすもの。
主として自分より地位が低い相手に対して使う。
84 beest
Beの仮定法二人称単数形。Thouに対応してbeが活用している。
If thou beest he = If you should/could be he
84 fallen
(過去分詞、形容詞)
高い場所から降りて/落ちてきた(天国から地獄へ--OED, "fallen" 1)
高い地位から落ちて/堕ちてきた(天使から堕天使へ--OED, "fallen" 5)。
加えて、受け身の構文(how thou art fallen)でもあるので--
(神に)「落とされた」(過去に落とされた、というだけではなく、
過去に落とされて、現在落ちている状態である、ということ。)
85 Realm[s]
王国(kingdom)(OED 1-2a)。"the Realms of Light" は天国のこと。
「王」国なのは、天国(実際この世すべて)を、
神が王として支配しているから。領域、場所(OED 2b-c)。
86 transcendent
形容詞。他の同種のものより勝る(OED 1)。
87 If he
If [thou beest] he. . . .
86 outshine
動詞。他のものより輝く(OED 1)。輝いているのは、天使だから。
同じ行のtranscendentと不必要に意味が重なっている。が、このように、
特に地位的なことがらについて、他の者と自分(ここでは自分の舎弟的な
ビエルゼバブ)を比べたがり、そして自分(たち)が上にいないと
気がすまないのが、ミルトンの描くサタン。いつでも地位にこだわる。
88 counsel[s]
決意、目的、意図、計画、企画、陰謀(OED 4)。
91 ruin
建物などが、崩れ、倒れること(OED 1a)。
社会的破滅(財産、地位などを失うこと)(OED 6a)。
絶望的にみじめな状態(OED 7)。
91 Pit
地面に掘られた穴(OED 1)。地獄(OED 4)。
91 thou seest
現代英語のyou see--「わかるだろ」、「な?」、「ね?」、
というニュアンスの挿入句--のようなかたちでここに入っている。
散文的に直すと、ここは、次のような間接疑問の構文。
Thou seest into what Pit [and] from what highth
[thou art / we are] fall'n.
92-93
「神は雷をもっていて、だからその分強かった」
=「雷がなければ、オレたちが勝っていたはず」
たとえ神に雷がなくても、本来サタンらは神に敵わないはずなのだが、
その事実を認めようとしていないことをあらわす。そこが、まさにサタン的。
92 the stronger
ここのtheは定冠詞ではなく副詞。次の行のwith his Thunderと
対応して、「だからますます」。
以下の言葉からもわかる通り、サタンにとっては、
強いかどうかがほとんど唯一の価値基準。
93 He
神のこと。サタンは「神」ということばを使わない。
神を唯一絶対的な神と認めていないから。
(表向きに強がっていて。)
93 Thunder
ギリシャ/ローマ神話における最高神ゼウス/ユピテルの武器。
聖書においても神(イエス・キリストではなく、父なる神、主)の武器
(出エジプト記9:23など)。
98 merit
高い評価や褒賞や感謝に値すること(OED 3a)。
称賛や高い評価に対する要求、またこれらを要求する
権利や資格(OED 4a)
99 the mightiest
神のこと。通常、Mightiestと大文字で表記して、
神をあらわす固有名詞とするところだが、そうしていない。
サタンは、神=最強の者、と認めていないから。
たまたま、結果的に、今回はヤツがいちばん強かったが、
次の戦いがあったら違う結果もありうる、というような意識があって。
99 fierce
気高く勇敢な(OED 2, 古語)。誇り高き、傲慢な(OED 3, 古語)。
野獣のように暴力的で激しい(OED 1)。
サタンと神との戦いは、自分を美化したがるサタンの視点から
見れば「気高く勇敢な」もの。しかしキリスト教的な価値観において、
それは、「傲慢な」もの。(「傲慢」prideとは、中世以来の神学に
おける「七つの大罪」のうち、もっとも大きな罪。) さらに、
ゲンコツや、弓や、銃や、せいぜい大砲程度の武器による
人間の戦いにくらべて、神や天使など霊的な存在による戦いは、
はるかに「暴力的で激しい」。
---
キリスト教的道徳における「傲慢」(pride)とは、神によって
与えられているもの(地位、性質、能力、外見など)以上のものを
求める、あるいはそれに値すると考える、人間の心や意識を指す。
「傲慢」から「妬み」(envy)が生まれる--
ホントはオレのほうが高い地位に値するはずなのに、
なんであいつが・・・・・・。
「傲慢」から「怒り」が生まれる--
なぜオレが認められない? なぜオレに地位がない?
金がない?
「傲慢」から「怠惰」(sloth)が生まれる--
オレには能力があるはずだから、コツコツとケチな努力なんか
する必要ない。そんなことしなくても、高い地位につけるはず、
なんでも手に入るはず。
「傲慢」から「貪欲」(greed/avarice/covetousness) が
生まれる--
地位をくれ、金をくれ、みんなくれ。
---
103 utmost
最大限の。サタンを倒すために、全力を出して、本当に
懸命になって、神は戦った、ということ。あくまで、これは、
サタンの妄想。実際は、
サタン率いる堕天使軍 VS 善良な天使軍
=引き分け
サタン率いる堕天使軍 VS 神の子
=神の子の完勝、まったくお話にならないくらいの圧勝。
(神自身は戦いに出てきてすらいない。)
これを「惜しい戦いだった」、「ヤツも必死だった」というところが、
サタンの欺瞞。人間くさいところ。
104 Plains
広がる空(OED 1c)。戦場(OED 2)。
105 study
目的達成のために向けられる思考や努力(OED 4a)。
夢想、実のともなわない思考(OED 3b)
110 Glory
栄誉や名声をもたらすもの。自慢の種(OED 3)。
116 by Fate
神ではなく、「運命」が、この世に存在するものすべてを
支配している、というサタンの考えがあらわれている。
(これはあくまで対外的な見解で、心の底ではサタンも、
神の支配を理解し、また認めている。第四巻の独白参照。)
なお、「運命」は、ギリシャ/ローマ神話では女神として
神格化されている。ここの発言においてサタンは異教的
(異教的な運命の神 > キリスト教の神)。
116 Gods
天使たちのこと。その対外的発言において、サタンは、
神と天使たちのあいだの違いを認めない。
117 fail
不足する、なくなる、消える、力を失う、死ぬ(OED I)。
122 grand Foe
Grand=もっとも位の高い、最大の(OED 2-3)。Foe=敵。
普通、「最大の敵」(arch enemy, arch foe) といったら
サタンのこと。(Satanとは、ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語などの
「敵」、「敵対する」ということばから由来。)
* * *
上の英文テクストは、John Milton, Paradise Lost (1674) より。
以下は、Milton Reading Roomのもの。
If thou beest he; But O how fall'n! how chang'd
From him, who in the happy Realms of Light [85]
Cloth'd with transcendent brightness didst out-shine
Myriads though bright: If he Whom mutual league,
United thoughts and counsels, equal hope
And hazard in the Glorious Enterprize,
Joynd with me once, now misery hath joynd [90]
In equal ruin: into what Pit thou seest
From what highth fall'n, so much the stronger prov'd
He with his Thunder: and till then who knew
The force of those dire Arms? yet not for those,
Nor what the Potent Victor in his rage [95]
Can else inflict, do I repent or change,
Though chang'd in outward lustre; that fixt mind
And high disdain, from sence of injur'd merit,
That with the mightiest rais'd me to contend,
And to the fierce contention brought along [100]
Innumerable force of Spirits arm'd
That durst dislike his reign, and me preferring,
His utmost power with adverse power oppos'd
In dubious Battel on the Plains of Heav'n,
And shook his throne. What though the field be lost? [105]
All is not lost; the unconquerable Will,
And study of revenge, immortal hate,
And courage never to submit or yield:
And what is else not to be overcome?
That Glory never shall his wrath or might [110]
Extort from me. To bow and sue for grace
With suppliant knee, and deifie his power,
Who from the terrour of this Arm so late
Doubted his Empire, that were low indeed,
That were an ignominy and shame beneath [115]
This downfall; since by Fate the strength of Gods
And this Empyreal substance cannot fail,
Since through experience of this great event
In Arms not worse, in foresight much advanc't,
We may with more successful hope resolve [120]
To wage by force or guile eternal Warr
Irreconcileable, to our grand Foe,
Who now triumphs, and in th' excess of joy
Sole reigning holds the Tyranny of Heav'n.
http://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/
pl/book_1/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。
商用、盗用、悪用などはないようお願いします。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, From A Mask (659-65)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『ラドロウ城の仮面劇』より
(659-65)
(コウマス)
ダメですよ、お姫さま、さあ、お座りくださいませ。わたしがこの杖をひと振りしたら、
あなたの神経なんて、みんな固まってしまいますよ?
真っ白な大理石の彫刻みたいにね。そう、アポローンから
逃げたダプネーみたいに、足に根っこが生えてきて、動けなくなってしまうんです。
(少女)
愚か者! いばるのはやめなさい!
おまえなんか、わたしの自由な心には指一本ふれさせないわ。
魔法を使っても無駄よ。たとえこのからだが
鎖でつながれたとしてもね! 神さまがちゃんと見ててくださるんだから!
* * *
John Milton
From A Mask Presented at Ludlow Castle, 1634
(659-65)
Comus.
Nay Lady sit; if I but wave this wand,
Your nerves are all chain'd up in Alabaster, [660]
And you a statue; or as Daphne was
Root-bound, that fled Apollo,
La[dy].
Fool do not boast,
Thou canst not touch the freedom of my minde
With all thy charms, although this corporal rinde
Thou haste immanacl'd, while Heav'n sees good. [665]
* * *
アポローンとダプネーの物語への言及。
(オウィディウス『変身物語』第1巻参照)。
コウマスは宮廷人風の悪い魔法使い。
少女は貴族の家の子で15歳。
* * *
アポローンとダプネーの物語
(オウィディウス、『変身物語』第1巻より)
1.
太陽神アポローンは、愛の神クピード-を
バカにしていう、「おまえみたいな子どもの矢で
何が打てるんだ?」
2.
クピードーは、「おまえを打っちゃうぞ!」
といって、金の矢でアポローンを、鉛入りの
矢でダプネーを打つ。金の矢は恋をかきたてる矢で、
鉛の矢は恋を嫌うよう仕向けるものだった。
3.
こうしてアポローンはダプネーに恋をし、
ダプネーは彼から逃げることになる。
4.
ダプネーを追いかけながら、アポローンはいう--
「ぼくは子羊を追いかけているオオカミとは違うよ!」
「転ばないように気をつけて! あ、ぼくが追いかけてるから、
いけないのか!」
「ぼくのお父さんはゼウスだよ! ぼく、未来に
ついて予言したりできるんだよ! ぼくは音楽の神でも
あるんだよ!」
「ぼくは医療の神なんだよ! でも、病気の薬は
つくれても、恋の病に効く薬がつくれないなんて、
変だよね!」
5.
そんなアポローンを恐がり、ダプネーはひたすら逃げる。
アポローンはひたすら追いかける。そして、とうとう
つかまってしまう、というとき、ダプネーは自分の父である
川の神ぺーネイオスに祈る、「わたしの姿を何か
他のものに変えて!」。
6.
これが聞き入れられ、ダプネーは月桂樹の木に変身する。
アポローンはその木を抱き、キスしようとするが、いやがられる。
7.
さらにアポローンはその木にいう、「ぼくのお嫁さんには
なってくれなかったけど、ぼくの木になってくれる?」。
するとその木は、いいわ、といっているかのようにゆれる。
* * *
何かと微妙で複雑なエピソードなので、少し分解してみる。
1-3
突然、みずからの意に反して、恋におち、
そして一心不乱にダプネーを追うアポローン。
そんな彼の思いは、はじめからかなえられないものと
定められている。ダプネーは必死に逃げる。
4
自分をこわがって逃げている女の子に対して、
「ぼく、こわくないよ!」とか、「ケガしちゃうから
止まって!」とか。
(いわば、ひとりでボケ・ツッコミ。)
ダプネーに好かれるために、家柄のよさを主張。
ダプネーに好かれるために、人にはない能力を主張。
(「ぼく音楽の神」を現代風にいうなら、たとえば、
「ぼくギター弾けるんだ」。)
医療の神なのに恋の薬をつくれない。
(ひとりでボケ・ツッコミ。)
5-6
ダプネーの父が彼女を救う。(が、本当は父は、
ダプネーをだれかと結婚させたがっていた。
「孫が見たい」などといって。)
6-7
木になったダプネーに対してアポローンは
思いを寄せつづける。ダプネーは、性的には
彼を拒絶。しかし、性的ではない関係なら、
いっしょにいてもいい(?)。
* * *
まとめると--
(アポローンの視点から見れば)
報われない恋の物語。
(ダプネーの視点から見れば)
好きでもない男性に執拗に追われる恐怖の物語。
(アポローンの描写)
高貴な生まれ、多彩な能力。恋愛において一途。
(おそらくルックスもいい。) ダプネー自身の
気持ちに対して無神経・鈍感(だが、それは
クピードーの矢によるもので、見方によっては
彼の非ではない)。
(ダプネーの描写)
美しい。逃げる姿も美しい。男嫌い(だが、それは
クピードーの矢によるもの。彼女の意志によるもの
ではない)。
(結末)
アポローンにとっては残念な結果?
ダプネーにとっては望みどおりの結果?
すべての意味で微妙な描写になっている。
(ペーネイオスにとっては?)
* * *
アポローンとダプネーを扱う美術作品

ニコラ・プッサン 「アポローンとダプネー」
http://www.nicolaspoussin.org/Apollo-and-Daphne-1625.html
クピードーがアポローンを恋の矢でうつところ
から、彼が月桂樹を身につけるところまで(アポローンの
頭には月桂冠)、二人のエピソードの全場面を、
時間の流れを無視して一画面にまとめた作品。
この絵は、あえてペーネイオスを前面に主人公として
描く。(壺から流れる水は川をあらわす。彼は川の神。)
上の物語をペーネイオスの視点で読み直してみる。
彼は、娘が結婚して子どもを産み・・・・・・ということを
期待していた。が、アポローンから必死で逃げる娘の願いを
聞き、彼女を月桂樹に変身させる。こうして彼は、みずからの
手により娘を失うことになる。その娘を救うために。
ふだん特にとりあげられないが、このようなやりきれない
立場にあるペーネイオスにプッサンは注目している。
---

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス 「アポローンとダプネー」
http://www.jwwaterhouse.com/view.cfm?recordid=93
ダプネーが木に変わりはじめているところを描く。
(ふたりのエピソードを扱う絵のほとんどがこのパターン。)
この絵のポイント 1
アポローンのいい男ぶり。
ポイント 2
ダプネーの右手。アポローンの右手を握り返そうと
していて、でもためらっている、というようす。
(ウォーターハウスの描く人物の動きや姿勢は
とても表情豊か。下に見るように、もちろん顔も。)
ポイント 3
ダプネーの左手。このポーズがあらわすのは
どんな感情?
ポイント 4
ダプネーの顔。左手とあわせて、この表情が
あらわすのはどんな感情? おそらく、こんな感じ。
「え・・・・・・」
「うそ・・・・・・」
つまり、ウォーターハウスは、追いかけられて
追いかけられて、必死で逃げてきたダプネーが、
最後の最後にアポローンを好きになって、という
シナリオでこの絵を描いている。
「やめて! やめて! やめて! 来ないで! 来ないで! 来ないで!」
「いや! いや! いやよ! 」
「いやよ! いや・・・・・・・・・・・・えっ?」
「うそ・・・・・・」
ポイント 5
ダプネーの足。左足しかない。右足はすでに
木になっている。(木のなかにうっすら見える。)
つまり、追いかけられて追いかけられて、必死で
逃げてきたダプネーが、最後の最後にアポローンを
好きになって、というときには、もうすでに
手遅れだった--すでに彼女は木になりかけていて、
二人はけっして結ばれないことになってしまっていた--
ということ。
ウォーターハウスは、アポローンにとっての
報われない恋の物語を、ダプネーにとっても
報われない恋の物語へと改作した。しかも、
ダプネーみずからの意志によってそうなってしまった、
という物語に。(これもまた切ない。)
より大きな図版で確認を。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollo_and_Daphne_waterhouse.jpg
基本的にウォーターハウスは、いつも正しく、
正確に、女性を描く。彼の描く女性は、みな
日常的な姿勢・しぐさ・表情をしている。
気づかないうちにとられた写真のように。
力が抜けて猫背になっていたり、寝転がって
いたり。
(つづく)
* * *
英語テクストは、Milton Reading Roomより。
http://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/comus/index.shtml
少しスペリングを修正。
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
『ラドロウ城の仮面劇』より
(659-65)
(コウマス)
ダメですよ、お姫さま、さあ、お座りくださいませ。わたしがこの杖をひと振りしたら、
あなたの神経なんて、みんな固まってしまいますよ?
真っ白な大理石の彫刻みたいにね。そう、アポローンから
逃げたダプネーみたいに、足に根っこが生えてきて、動けなくなってしまうんです。
(少女)
愚か者! いばるのはやめなさい!
おまえなんか、わたしの自由な心には指一本ふれさせないわ。
魔法を使っても無駄よ。たとえこのからだが
鎖でつながれたとしてもね! 神さまがちゃんと見ててくださるんだから!
* * *
John Milton
From A Mask Presented at Ludlow Castle, 1634
(659-65)
Comus.
Nay Lady sit; if I but wave this wand,
Your nerves are all chain'd up in Alabaster, [660]
And you a statue; or as Daphne was
Root-bound, that fled Apollo,
La[dy].
Fool do not boast,
Thou canst not touch the freedom of my minde
With all thy charms, although this corporal rinde
Thou haste immanacl'd, while Heav'n sees good. [665]
* * *
アポローンとダプネーの物語への言及。
(オウィディウス『変身物語』第1巻参照)。
コウマスは宮廷人風の悪い魔法使い。
少女は貴族の家の子で15歳。
* * *
アポローンとダプネーの物語
(オウィディウス、『変身物語』第1巻より)
1.
太陽神アポローンは、愛の神クピード-を
バカにしていう、「おまえみたいな子どもの矢で
何が打てるんだ?」
2.
クピードーは、「おまえを打っちゃうぞ!」
といって、金の矢でアポローンを、鉛入りの
矢でダプネーを打つ。金の矢は恋をかきたてる矢で、
鉛の矢は恋を嫌うよう仕向けるものだった。
3.
こうしてアポローンはダプネーに恋をし、
ダプネーは彼から逃げることになる。
4.
ダプネーを追いかけながら、アポローンはいう--
「ぼくは子羊を追いかけているオオカミとは違うよ!」
「転ばないように気をつけて! あ、ぼくが追いかけてるから、
いけないのか!」
「ぼくのお父さんはゼウスだよ! ぼく、未来に
ついて予言したりできるんだよ! ぼくは音楽の神でも
あるんだよ!」
「ぼくは医療の神なんだよ! でも、病気の薬は
つくれても、恋の病に効く薬がつくれないなんて、
変だよね!」
5.
そんなアポローンを恐がり、ダプネーはひたすら逃げる。
アポローンはひたすら追いかける。そして、とうとう
つかまってしまう、というとき、ダプネーは自分の父である
川の神ぺーネイオスに祈る、「わたしの姿を何か
他のものに変えて!」。
6.
これが聞き入れられ、ダプネーは月桂樹の木に変身する。
アポローンはその木を抱き、キスしようとするが、いやがられる。
7.
さらにアポローンはその木にいう、「ぼくのお嫁さんには
なってくれなかったけど、ぼくの木になってくれる?」。
するとその木は、いいわ、といっているかのようにゆれる。
* * *
何かと微妙で複雑なエピソードなので、少し分解してみる。
1-3
突然、みずからの意に反して、恋におち、
そして一心不乱にダプネーを追うアポローン。
そんな彼の思いは、はじめからかなえられないものと
定められている。ダプネーは必死に逃げる。
4
自分をこわがって逃げている女の子に対して、
「ぼく、こわくないよ!」とか、「ケガしちゃうから
止まって!」とか。
(いわば、ひとりでボケ・ツッコミ。)
ダプネーに好かれるために、家柄のよさを主張。
ダプネーに好かれるために、人にはない能力を主張。
(「ぼく音楽の神」を現代風にいうなら、たとえば、
「ぼくギター弾けるんだ」。)
医療の神なのに恋の薬をつくれない。
(ひとりでボケ・ツッコミ。)
5-6
ダプネーの父が彼女を救う。(が、本当は父は、
ダプネーをだれかと結婚させたがっていた。
「孫が見たい」などといって。)
6-7
木になったダプネーに対してアポローンは
思いを寄せつづける。ダプネーは、性的には
彼を拒絶。しかし、性的ではない関係なら、
いっしょにいてもいい(?)。
* * *
まとめると--
(アポローンの視点から見れば)
報われない恋の物語。
(ダプネーの視点から見れば)
好きでもない男性に執拗に追われる恐怖の物語。
(アポローンの描写)
高貴な生まれ、多彩な能力。恋愛において一途。
(おそらくルックスもいい。) ダプネー自身の
気持ちに対して無神経・鈍感(だが、それは
クピードーの矢によるもので、見方によっては
彼の非ではない)。
(ダプネーの描写)
美しい。逃げる姿も美しい。男嫌い(だが、それは
クピードーの矢によるもの。彼女の意志によるもの
ではない)。
(結末)
アポローンにとっては残念な結果?
ダプネーにとっては望みどおりの結果?
すべての意味で微妙な描写になっている。
(ペーネイオスにとっては?)
* * *
アポローンとダプネーを扱う美術作品

ニコラ・プッサン 「アポローンとダプネー」
http://www.nicolaspoussin.org/Apollo-and-Daphne-1625.html
クピードーがアポローンを恋の矢でうつところ
から、彼が月桂樹を身につけるところまで(アポローンの
頭には月桂冠)、二人のエピソードの全場面を、
時間の流れを無視して一画面にまとめた作品。
この絵は、あえてペーネイオスを前面に主人公として
描く。(壺から流れる水は川をあらわす。彼は川の神。)
上の物語をペーネイオスの視点で読み直してみる。
彼は、娘が結婚して子どもを産み・・・・・・ということを
期待していた。が、アポローンから必死で逃げる娘の願いを
聞き、彼女を月桂樹に変身させる。こうして彼は、みずからの
手により娘を失うことになる。その娘を救うために。
ふだん特にとりあげられないが、このようなやりきれない
立場にあるペーネイオスにプッサンは注目している。
---

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス 「アポローンとダプネー」
http://www.jwwaterhouse.com/view.cfm?recordid=93
ダプネーが木に変わりはじめているところを描く。
(ふたりのエピソードを扱う絵のほとんどがこのパターン。)
この絵のポイント 1
アポローンのいい男ぶり。
ポイント 2
ダプネーの右手。アポローンの右手を握り返そうと
していて、でもためらっている、というようす。
(ウォーターハウスの描く人物の動きや姿勢は
とても表情豊か。下に見るように、もちろん顔も。)
ポイント 3
ダプネーの左手。このポーズがあらわすのは
どんな感情?
ポイント 4
ダプネーの顔。左手とあわせて、この表情が
あらわすのはどんな感情? おそらく、こんな感じ。
「え・・・・・・」
「うそ・・・・・・」
つまり、ウォーターハウスは、追いかけられて
追いかけられて、必死で逃げてきたダプネーが、
最後の最後にアポローンを好きになって、という
シナリオでこの絵を描いている。
「やめて! やめて! やめて! 来ないで! 来ないで! 来ないで!」
「いや! いや! いやよ! 」
「いやよ! いや・・・・・・・・・・・・えっ?」
「うそ・・・・・・」
ポイント 5
ダプネーの足。左足しかない。右足はすでに
木になっている。(木のなかにうっすら見える。)
つまり、追いかけられて追いかけられて、必死で
逃げてきたダプネーが、最後の最後にアポローンを
好きになって、というときには、もうすでに
手遅れだった--すでに彼女は木になりかけていて、
二人はけっして結ばれないことになってしまっていた--
ということ。
ウォーターハウスは、アポローンにとっての
報われない恋の物語を、ダプネーにとっても
報われない恋の物語へと改作した。しかも、
ダプネーみずからの意志によってそうなってしまった、
という物語に。(これもまた切ない。)
より大きな図版で確認を。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollo_and_Daphne_waterhouse.jpg
基本的にウォーターハウスは、いつも正しく、
正確に、女性を描く。彼の描く女性は、みな
日常的な姿勢・しぐさ・表情をしている。
気づかないうちにとられた写真のように。
力が抜けて猫背になっていたり、寝転がって
いたり。
(つづく)
* * *
英語テクストは、Milton Reading Roomより。
http://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/comus/index.shtml
少しスペリングを修正。
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, ("When I consider how my light is spent")
ジョン・ミルトン (1608-1674)
ソネット XVI
(「わたしの光は使い果たされてしまった、と思うとき」)
わたしの光は使い果たされてしまった、と思うとき--
人生の半ば以前に、この暗い、しかも広い世界の中で、
そしてイエスの話のあの一タラントン、
それを隠しておいた召使いを待っていたのは死という、
それをわたしは無駄にもっていて、そうではなくわたしの魂は
それを使って創り主たる神に仕えたいのに、そして見せたいのに、
貸し与えられたものをわたしが本当はどのように使ってきたかを、
でないと彼が帰ってきたときに怒られてしまう--
神は日々の労働を要求するか? 光が奪われた者から?
愚かにもわたしは問う。が、「忍耐」がそのような
不平のつぶやきをかき消すべく、すぐに答える、神には必要がない、
人間の努力も、また自分が与えたものを人間から返して
もらうことも。もっともしっかり彼の軽いくびきを負う者が、
彼にもっとも奉仕をしている者である。神は
万物の王である。何千もの者が彼の指示により飛び急ぎまわる、
陸や海の上を休みなく。
が、そのような者も神に奉仕しているのだ、ただ立って待つだけの者も。
* * *
John Milton
Sonnet XVI
("When I consider how my light is spent")
When I consider how my light is spent,
E're half my days, in this dark world and wide,
And that one Talent which is death to hide,
Lodg'd with me useless, though my Soul more bent
To serve therewith my Maker, and present
My true account, least he returning chide,
Doth God exact day labour, light deny'd,
I fondly ask; But patience to prevent
That murmur, soon replies, God doth not need
Either man's work or his own gifts, who best
Bear his milde yoak, they serve him best, his State
Is Kingly. Thousands at his bidding speed
And post o're Land and Ocean without rest:
They also serve who only stand and waite.
* * *
日本語訳においては、一行に収まらない行が多いので、
いわゆるペトラルカ式ソネットの枠組み通り
4行+4行+3行+3行というかたちで区切って、
およその内容のまとまり(およびこの形式がいかに
無視されているか)を示している。
このタイプのミルトンのソネットのモデルは、
実際、ペトラルカではなく、形式的により自由な
ジョヴァンニ・デッラ・カーザ(Giovanni della Casa)。
--J. S. Smart, The Sonnets of Milton参照。
http://archive.org/details/sonnetsofmilton00miltuoft
(ミルトンは、ケンブリッジの学生だった頃、1629年に
デッラ・カーザのソネット集を入手していた。が、
1633年頃の手紙の下書きでは、まだソネットのことを
「ペトラルカ風のスタンザ」と呼んでいたりもする。
同じころ、1630年代のはじめに書かれたと思われる
ソネット Iも、ラヴ・ソング風。いろいろ未確認だが、
1630年代後半のイタリア滞在、1640-50年代の宗教/政治
論文執筆、それから『失われた楽園』の初期構想などを
経るなかで、ソネット形式のとらえ方が変わっていったよう。)
ソネットXVIの特に前半、構成や構文が崩れているのは、
視力を失った「わたし」がテンパっていて、
秩序だった思考ができていないことに対応。
しかし全体を通じて脚韻は完璧で、実際のミルトン自身は、
冷静に、緻密にこの作品を書いたことを示している。
(意図的に内容とかたちをあわせたのか、ただデッラ・
カーサ風にゆるくしているだけということなのか。
ミルトンのソネットにおける形式の崩れには、作品によって
程度の差やタイプの違いがあるので、個人的には前者よりの
ように思う。このXVIと、ピエモンテの虐殺を扱うXVが
もっとも崩れている。20110806の記事にあるソネットXIXも参照。)
ちなみに、このような形式の崩れは、16-17世紀のイギリスの
ソネットにおける例外中の例外。
その後、17世紀半ばから18世紀にかけてソネットは衰退。
19世紀、いわゆるロマン派によってソネットが再び
多く書かれるようになったとき、もとは例外だったミルトンの
作品がある種のモデルとされるようになる。
(20120519の記事にあるワーズワースのものなど参照。)
(シェリーの「ラムセス二世」"Ozymandias" などは、
さらに別のかたちで実験的。)
* * *
訳注と解釈例。
全体の骨組みは、以下の通り。
(前半)
When I consider how my light is spent,
I fondly ask, Doth God exact day labour
[from one who is deny'd light]?
視力を失った自分について思いをめぐらし、
こんな状態でも神に奉仕しなくてはいけないのか、と問う。
(後半)
But patience to prevent That murmur, soon replies. . . .
自分のなかで「忍耐」が答えていう・・・・・・。
(その他、次の文章に記したことをかいつまんで
まとめたいと思うが、さしあたり全文のご参照を。)
http://jairo.nii.ac.jp/0279/00000289
http://rplib.ferris.ac.jp/il4/cont/01/G0000005ir/000/000/000000142.pdf
* * *
英文テクストは、Milton, Poems, &c. upon Several Occasions
(1673) (Wing M2161A) より。
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
ソネット XVI
(「わたしの光は使い果たされてしまった、と思うとき」)
わたしの光は使い果たされてしまった、と思うとき--
人生の半ば以前に、この暗い、しかも広い世界の中で、
そしてイエスの話のあの一タラントン、
それを隠しておいた召使いを待っていたのは死という、
それをわたしは無駄にもっていて、そうではなくわたしの魂は
それを使って創り主たる神に仕えたいのに、そして見せたいのに、
貸し与えられたものをわたしが本当はどのように使ってきたかを、
でないと彼が帰ってきたときに怒られてしまう--
神は日々の労働を要求するか? 光が奪われた者から?
愚かにもわたしは問う。が、「忍耐」がそのような
不平のつぶやきをかき消すべく、すぐに答える、神には必要がない、
人間の努力も、また自分が与えたものを人間から返して
もらうことも。もっともしっかり彼の軽いくびきを負う者が、
彼にもっとも奉仕をしている者である。神は
万物の王である。何千もの者が彼の指示により飛び急ぎまわる、
陸や海の上を休みなく。
が、そのような者も神に奉仕しているのだ、ただ立って待つだけの者も。
* * *
John Milton
Sonnet XVI
("When I consider how my light is spent")
When I consider how my light is spent,
E're half my days, in this dark world and wide,
And that one Talent which is death to hide,
Lodg'd with me useless, though my Soul more bent
To serve therewith my Maker, and present
My true account, least he returning chide,
Doth God exact day labour, light deny'd,
I fondly ask; But patience to prevent
That murmur, soon replies, God doth not need
Either man's work or his own gifts, who best
Bear his milde yoak, they serve him best, his State
Is Kingly. Thousands at his bidding speed
And post o're Land and Ocean without rest:
They also serve who only stand and waite.
* * *
日本語訳においては、一行に収まらない行が多いので、
いわゆるペトラルカ式ソネットの枠組み通り
4行+4行+3行+3行というかたちで区切って、
およその内容のまとまり(およびこの形式がいかに
無視されているか)を示している。
このタイプのミルトンのソネットのモデルは、
実際、ペトラルカではなく、形式的により自由な
ジョヴァンニ・デッラ・カーザ(Giovanni della Casa)。
--J. S. Smart, The Sonnets of Milton参照。
http://archive.org/details/sonnetsofmilton00miltuoft
(ミルトンは、ケンブリッジの学生だった頃、1629年に
デッラ・カーザのソネット集を入手していた。が、
1633年頃の手紙の下書きでは、まだソネットのことを
「ペトラルカ風のスタンザ」と呼んでいたりもする。
同じころ、1630年代のはじめに書かれたと思われる
ソネット Iも、ラヴ・ソング風。いろいろ未確認だが、
1630年代後半のイタリア滞在、1640-50年代の宗教/政治
論文執筆、それから『失われた楽園』の初期構想などを
経るなかで、ソネット形式のとらえ方が変わっていったよう。)
ソネットXVIの特に前半、構成や構文が崩れているのは、
視力を失った「わたし」がテンパっていて、
秩序だった思考ができていないことに対応。
しかし全体を通じて脚韻は完璧で、実際のミルトン自身は、
冷静に、緻密にこの作品を書いたことを示している。
(意図的に内容とかたちをあわせたのか、ただデッラ・
カーサ風にゆるくしているだけということなのか。
ミルトンのソネットにおける形式の崩れには、作品によって
程度の差やタイプの違いがあるので、個人的には前者よりの
ように思う。このXVIと、ピエモンテの虐殺を扱うXVが
もっとも崩れている。20110806の記事にあるソネットXIXも参照。)
ちなみに、このような形式の崩れは、16-17世紀のイギリスの
ソネットにおける例外中の例外。
その後、17世紀半ばから18世紀にかけてソネットは衰退。
19世紀、いわゆるロマン派によってソネットが再び
多く書かれるようになったとき、もとは例外だったミルトンの
作品がある種のモデルとされるようになる。
(20120519の記事にあるワーズワースのものなど参照。)
(シェリーの「ラムセス二世」"Ozymandias" などは、
さらに別のかたちで実験的。)
* * *
訳注と解釈例。
全体の骨組みは、以下の通り。
(前半)
When I consider how my light is spent,
I fondly ask, Doth God exact day labour
[from one who is deny'd light]?
視力を失った自分について思いをめぐらし、
こんな状態でも神に奉仕しなくてはいけないのか、と問う。
(後半)
But patience to prevent That murmur, soon replies. . . .
自分のなかで「忍耐」が答えていう・・・・・・。
(その他、次の文章に記したことをかいつまんで
まとめたいと思うが、さしあたり全文のご参照を。)
http://jairo.nii.ac.jp/0279/00000289
http://rplib.ferris.ac.jp/il4/cont/01/G0000005ir/000/000/000000142.pdf
* * *
英文テクストは、Milton, Poems, &c. upon Several Occasions
(1673) (Wing M2161A) より。
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, From _A Mask_ (244-52)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『ラドロウ城で演じられた仮面劇』
(通称『コウマス』)(244-52)
大地の土を混ぜてつくられた、永遠の生をもたない人間が、
このような神々しく心奪うような声で歌うことができるのか?
いや、何か聖なるものがこの子の胸に宿っているにちがいない。
そしてこのようにうっとりさせる何かを使って空気に声を出させて、
そこに隠れていることを知らせようとしているのだ。
ああ、なんと美しく、あの歌声は沈黙の翼にのって空を
舞っていたことか。空っぽな丸天井のような夜空をめぐり、ただよい、
低音に下がるたびに、大きなカラスのような闇の羽を
なでてやりながら。その闇も、うれしそうにほほえんでいた・・・・・・。
* * *
John Milton
From A Mask Presented at Ludlow Castle, 1634
(244-52)
Can any mortal mixture of Earths mould
Breath such Divine inchanting ravishment?
Sure somthing holy lodges in that brest,
And with these raptures moves the vocal air
To testifie his hidd'n residence;
How sweetly did they float upon the wings
Of silence, through the empty-vaulted night
At every fall smoothing the Raven doune
Of darknes till it smil'd. . . .
* * *
夜の森に迷った少女の歌を聴いて、
魔法使いコウマスがいうセリフ。
* * *
訳注。
244 mortal mixture of Earths mould
土からつくられた人間、ということ。聖書の創世記にある通り。
mortal: 死ぬ運命にある。
Earth: 大地、地面(OED I)
(Earths = Earth's)
mould: 地面の表面にあるかたまっていない土(OED 1)。
245 ravishment
心を奪うこと、また心を奪われた状態(OED 3)。
もともとravishとは、人を奪う(無理やり連れ去る)
ことなので、そのように、いわば強引に心を奪う、
というニュアンス。
ここでは、そのように心を奪う歌声のこと。
歌声という具体的なものを、心を奪うこと、
という抽象概念にたとえて表現。
247 raptures
心を奪うこと、また心を奪われた状態(OED 5a)。
こちらのもとの意味は、天に連れていかれる、
ということ。(比喩的に、または文字通りに)
(OED "rapt", pa.pple.)。
ここでは、これも歌声のこと。
247
the vocal air
声をもつ空気。つまり、科学的には、人が声を
出して空気を振動させるが、ここでは、少女の
胸に宿る何か神聖なものが、何か心奪うものを発して、
そして空気そのものに声を出させている、と表現。
16-17世紀の詩によく見られる奇想conceit
(空想豊かで、また機知に富んだ、器用な思考や
その表現--OED, "conceit" n.8)の例。
文学史的には、このような表現方法を特に顕著に
受け継いだのが、コールリッジやシェリー。
(実際、程度の差はあれ、ほとんどの詩人に
見られるものだが。)
249 they
= these raptures ( = 少女の歌声)
249-50
歌声が沈黙の羽にのって舞う、というのも奇想。
251-52
fall:
メロディの音程が下がること(OED, n.1. 10)。
+
歌声をのせて飛びまわっている沈黙が下降すること。
(たとえば、妖精をのせて飛んでいる鳥のように。)
+
何かをなでるために人が手を上から降ろすこと。
ここでは、こうして大きなカラスのような闇の羽を
なでる。すると、この闇がうれしそうにほほえむ。
* * *
以上、複雑すぎて、劇のセリフとしては
日本語ではかなり厳しいと思われるので、
要約し、また間をおいて表記してみる。
---
神ではない人間が、
このような神々しく、心奪うような声で
歌うことができるのか?
いや、何か聖なるものが
この子の胸に宿っているにちがいない。
そして、魔法か何かで空気をふるわせて、
自分の存在を知らせようとしているのだ。
ああ、なんと美しく、あの歌声は
沈黙の翼にのって空を舞っていたことか。
丸天井のような夜空をめぐり、ただよい、
メロディにあわせて、闇夜の羽を
なでてやりながら。
闇夜もうれしそうに、
ほほえんでいるかのようだった。
* * *
詩形はブランク・ヴァース(弱強五歩格無韻)。
(厳密にx/x/x/x/x/と並んでいるわけでは
もちろんない。)
* * *
英文テクストは、Milton, Poems (1645) より。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/comus/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
『ラドロウ城で演じられた仮面劇』
(通称『コウマス』)(244-52)
大地の土を混ぜてつくられた、永遠の生をもたない人間が、
このような神々しく心奪うような声で歌うことができるのか?
いや、何か聖なるものがこの子の胸に宿っているにちがいない。
そしてこのようにうっとりさせる何かを使って空気に声を出させて、
そこに隠れていることを知らせようとしているのだ。
ああ、なんと美しく、あの歌声は沈黙の翼にのって空を
舞っていたことか。空っぽな丸天井のような夜空をめぐり、ただよい、
低音に下がるたびに、大きなカラスのような闇の羽を
なでてやりながら。その闇も、うれしそうにほほえんでいた・・・・・・。
* * *
John Milton
From A Mask Presented at Ludlow Castle, 1634
(244-52)
Can any mortal mixture of Earths mould
Breath such Divine inchanting ravishment?
Sure somthing holy lodges in that brest,
And with these raptures moves the vocal air
To testifie his hidd'n residence;
How sweetly did they float upon the wings
Of silence, through the empty-vaulted night
At every fall smoothing the Raven doune
Of darknes till it smil'd. . . .
* * *
夜の森に迷った少女の歌を聴いて、
魔法使いコウマスがいうセリフ。
* * *
訳注。
244 mortal mixture of Earths mould
土からつくられた人間、ということ。聖書の創世記にある通り。
mortal: 死ぬ運命にある。
Earth: 大地、地面(OED I)
(Earths = Earth's)
mould: 地面の表面にあるかたまっていない土(OED 1)。
245 ravishment
心を奪うこと、また心を奪われた状態(OED 3)。
もともとravishとは、人を奪う(無理やり連れ去る)
ことなので、そのように、いわば強引に心を奪う、
というニュアンス。
ここでは、そのように心を奪う歌声のこと。
歌声という具体的なものを、心を奪うこと、
という抽象概念にたとえて表現。
247 raptures
心を奪うこと、また心を奪われた状態(OED 5a)。
こちらのもとの意味は、天に連れていかれる、
ということ。(比喩的に、または文字通りに)
(OED "rapt", pa.pple.)。
ここでは、これも歌声のこと。
247
the vocal air
声をもつ空気。つまり、科学的には、人が声を
出して空気を振動させるが、ここでは、少女の
胸に宿る何か神聖なものが、何か心奪うものを発して、
そして空気そのものに声を出させている、と表現。
16-17世紀の詩によく見られる奇想conceit
(空想豊かで、また機知に富んだ、器用な思考や
その表現--OED, "conceit" n.8)の例。
文学史的には、このような表現方法を特に顕著に
受け継いだのが、コールリッジやシェリー。
(実際、程度の差はあれ、ほとんどの詩人に
見られるものだが。)
249 they
= these raptures ( = 少女の歌声)
249-50
歌声が沈黙の羽にのって舞う、というのも奇想。
251-52
fall:
メロディの音程が下がること(OED, n.1. 10)。
+
歌声をのせて飛びまわっている沈黙が下降すること。
(たとえば、妖精をのせて飛んでいる鳥のように。)
+
何かをなでるために人が手を上から降ろすこと。
ここでは、こうして大きなカラスのような闇の羽を
なでる。すると、この闇がうれしそうにほほえむ。
* * *
以上、複雑すぎて、劇のセリフとしては
日本語ではかなり厳しいと思われるので、
要約し、また間をおいて表記してみる。
---
神ではない人間が、
このような神々しく、心奪うような声で
歌うことができるのか?
いや、何か聖なるものが
この子の胸に宿っているにちがいない。
そして、魔法か何かで空気をふるわせて、
自分の存在を知らせようとしているのだ。
ああ、なんと美しく、あの歌声は
沈黙の翼にのって空を舞っていたことか。
丸天井のような夜空をめぐり、ただよい、
メロディにあわせて、闇夜の羽を
なでてやりながら。
闇夜もうれしそうに、
ほほえんでいるかのようだった。
* * *
詩形はブランク・ヴァース(弱強五歩格無韻)。
(厳密にx/x/x/x/x/と並んでいるわけでは
もちろんない。)
* * *
英文テクストは、Milton, Poems (1645) より。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/comus/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, _Samson_ (1205-23)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『闘技士サムソン』(1205-23)
わたしの国は、おまえの国の支配者たちに征服された。
が、それはあくまで武力によるもの。武力など、武力で
いつでも退けられる。征服された者にそれができればな。
わたしは一平民で、だからわたしの国の者たちが
同盟を破った者としてとらえて引き渡した、と?
ひとりで勝手に反乱をおこし、敵対行為に及んだとして?
わたしは平民などではない。わたしは、神によって
国に自由をもたらすよう命じられ、
必要な力を授けられた者だ。国の者たちが、解放者である
わたしを受けいれず、それどころか奴隷根性丸出しで、
おまえの国の支配者たちにただでさし出したということは、
それだけ彼らが愚かだということ、だから今だに隷従させられているのだ。
わたしは、天に命じられたことをしようとしたのみ、
そして、実際それをなしとげていたはずだ、みな知っているあのあやまちに
よってそれができなくなってしまわなければな。おまえたちに封じられたのではない。
さあ、言い逃れはもう通用しない。わたしの挑戦に応えろ。
盲目だから、もう大きなことはできないかもしれないが、
おまえとの決闘くらい、屁みたいなものだ。
こうやって挑むのは、もう三回目だぞ。
* * *
John Milton
Samson Agonistes (1205-23)
My Nation was subjected to your Lords.
It was the force of Conquest; force with force
Is well ejected when the Conquer'd can.
But I a private person, whom my Countrey
As a league-breaker gave up bound, presum'd
Single Rebellion and did Hostile Acts. [1210]
I was no private but a person rais'd
With strength sufficient and command from Heav'n
To free my Countrey; if their servile minds
Me their Deliverer sent would not receive,
But to thir Masters gave me up for nought,
Th'unworthier they; whence to this day they serve.
I was to do my part from Heav'n assign'd,
And had perform'd it if my known offence
Had not disabl'd me, not all your force:
These shifts refuted, answer thy appellant [1220]
Though by his blindness maim'd for high attempts,
Who now defies thee thrice to single fight,
As a petty enterprise of small enforce.
* * *
イスラエルの怪力の英雄だったが、今や盲目の奴隷と
なりはてたサムソンが、敵部族ペリシテ人の怪力の男
ハラファに対して、みずからを正当化し、また彼を
挑発する場面。
聖書の士師記13-16章がこの作品の元ネタ。
(ミルトンが創作した箇所も多々あり。この場面もそう。)
* * *
訳注と解釈例など。
1206
共和国初期には、征服した者が正当な支配者、
力が正義、悪い征服者にしたがうことは
(たとえば、貧しい者が泥棒から施しを受ける
ことと同様)罪ではない、国の支配者としては、
正しくても弱い者より、悪くても強い者のほうがいい、
など、征服をめぐるいろいろな議論がなされていた。
もちろん、共和国が、国王支持者を武力で
制圧した結果のものだったから。
軍および共和国の支持者であったが、ミルトンは、
基本的に上のようなことはいわず、下記の通り、
軍は、神に命じられ、また味方されて戦い、勝利した、
という立場をとっていた。
1207 well
当然の結果として(OED 8a)。かんたんに(OED 9a)。
うまく、上手に、実質的に(OED 11)
1208-
1640-50年代のイギリスにおいて、国王など支配者に
抵抗する権利をもつのは、議員など公職にある者のみだ、
いや一般の人々 private persons にも抵抗権がある、
などという議論がなされていた。抵抗権を公職者に限定する
議論のほうが、カルヴィンなどから連なるプロテスタントの主流で、
この当時のイギリスでは、公職にない一般民である
軍、兵士らによる国王攻撃を違法とするために
用いられた。(そもそも、だれでも支配者に対して
武装抵抗してよければ、明らかに大変なことになる。)
これに対して、ミルトンのような軍の支持者は、
(神に命じられていれば)一般民の武装抵抗も
正当、と論じた。どうして神に命じられているかどうかが
わかるのか、といえば、それは、戦闘に勝ってきたから・・・・・・。
つまり、神に命じられたから一般民も戦っていい、
ではなく、勝ったから、その戦いは神に命じられた
ものにちがいない、というかたちで、常に遡及的に
過去の戦闘が正当化された。
だから、1650年代半ば、西インド諸島でイギリス軍が
スペインに敗れたとき、また(より深刻、重大に)1660年に
共和国が自壊してふたたび王政が立てられたとき、
ミルトンら共和国の支持者たちは、頭を抱えることになる。
神に命じられて戦ってきたはずなのに、神に命じられた
戦いを支持してきたはずなのに・・・・・・勘違いしていた?
しかし、『サムソン』のような作品を出す、ということは、
ミルトンは、この勘違いを認めてはいなかった
(苦悩はあったかもしれないが)、ということ。
(・・・・・・では、『失われた楽園』は?)
なお、この箇所に出てくる、隷属やそこからの解放という
考えは、暴君 tyrant チャールズ一世によって、また
暴君クロムウェルによって、奴隷のように奉仕させられる国民、
という1640-50年代の議論から。
1215 for nought
報酬なしで。Nought = nothing.
1218 my known offence
敵部族出身(ペリシテ人)である妻ダリラに対して、
サムソンがみずからの強さの秘密(髪を切られると
弱くなる)を話してしまったこと。これを聞いて
ダリラは、サムソンの神を切り落とし、弱くなった
彼を部族の長らに引き渡す。(1213行からの、
引き渡しエピソードは、これとは別もので
士師記15章からのもの。) そしてその部族の
長たちは、サムソンの目をくり抜いて盲目にし、
奴隷として使っている・・・・・・というのが、
上の場面までの話。
1220-
神に命じられているという設定だが、こういうケンカの
売り方はどうか、と思わせる書き方。平たく言えば、
「おい、やろうっていってんだろ? おまえなんてちょろいぜ!」
ということなので。また、その後すぐ、サムソンはこのように
挑発的にいう。
「おいおい、オレをただ見にきたのかい? 実際に
手でさわってオレの強さを調べたほうがいいんじゃね?
おーっと、でも気をつけろよ、逆にオレがおまえの強さを
調べちゃうからな!」
* * *
また加筆修正します。
* * *
英文テクストは、Paradise Regain'd : A Poem in IV books:
To Which Is Added Samson Agonistes (1671) より。
(日本語訳は、まとまりごとにわけてあります。)
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
『闘技士サムソン』(1205-23)
わたしの国は、おまえの国の支配者たちに征服された。
が、それはあくまで武力によるもの。武力など、武力で
いつでも退けられる。征服された者にそれができればな。
わたしは一平民で、だからわたしの国の者たちが
同盟を破った者としてとらえて引き渡した、と?
ひとりで勝手に反乱をおこし、敵対行為に及んだとして?
わたしは平民などではない。わたしは、神によって
国に自由をもたらすよう命じられ、
必要な力を授けられた者だ。国の者たちが、解放者である
わたしを受けいれず、それどころか奴隷根性丸出しで、
おまえの国の支配者たちにただでさし出したということは、
それだけ彼らが愚かだということ、だから今だに隷従させられているのだ。
わたしは、天に命じられたことをしようとしたのみ、
そして、実際それをなしとげていたはずだ、みな知っているあのあやまちに
よってそれができなくなってしまわなければな。おまえたちに封じられたのではない。
さあ、言い逃れはもう通用しない。わたしの挑戦に応えろ。
盲目だから、もう大きなことはできないかもしれないが、
おまえとの決闘くらい、屁みたいなものだ。
こうやって挑むのは、もう三回目だぞ。
* * *
John Milton
Samson Agonistes (1205-23)
My Nation was subjected to your Lords.
It was the force of Conquest; force with force
Is well ejected when the Conquer'd can.
But I a private person, whom my Countrey
As a league-breaker gave up bound, presum'd
Single Rebellion and did Hostile Acts. [1210]
I was no private but a person rais'd
With strength sufficient and command from Heav'n
To free my Countrey; if their servile minds
Me their Deliverer sent would not receive,
But to thir Masters gave me up for nought,
Th'unworthier they; whence to this day they serve.
I was to do my part from Heav'n assign'd,
And had perform'd it if my known offence
Had not disabl'd me, not all your force:
These shifts refuted, answer thy appellant [1220]
Though by his blindness maim'd for high attempts,
Who now defies thee thrice to single fight,
As a petty enterprise of small enforce.
* * *
イスラエルの怪力の英雄だったが、今や盲目の奴隷と
なりはてたサムソンが、敵部族ペリシテ人の怪力の男
ハラファに対して、みずからを正当化し、また彼を
挑発する場面。
聖書の士師記13-16章がこの作品の元ネタ。
(ミルトンが創作した箇所も多々あり。この場面もそう。)
* * *
訳注と解釈例など。
1206
共和国初期には、征服した者が正当な支配者、
力が正義、悪い征服者にしたがうことは
(たとえば、貧しい者が泥棒から施しを受ける
ことと同様)罪ではない、国の支配者としては、
正しくても弱い者より、悪くても強い者のほうがいい、
など、征服をめぐるいろいろな議論がなされていた。
もちろん、共和国が、国王支持者を武力で
制圧した結果のものだったから。
軍および共和国の支持者であったが、ミルトンは、
基本的に上のようなことはいわず、下記の通り、
軍は、神に命じられ、また味方されて戦い、勝利した、
という立場をとっていた。
1207 well
当然の結果として(OED 8a)。かんたんに(OED 9a)。
うまく、上手に、実質的に(OED 11)
1208-
1640-50年代のイギリスにおいて、国王など支配者に
抵抗する権利をもつのは、議員など公職にある者のみだ、
いや一般の人々 private persons にも抵抗権がある、
などという議論がなされていた。抵抗権を公職者に限定する
議論のほうが、カルヴィンなどから連なるプロテスタントの主流で、
この当時のイギリスでは、公職にない一般民である
軍、兵士らによる国王攻撃を違法とするために
用いられた。(そもそも、だれでも支配者に対して
武装抵抗してよければ、明らかに大変なことになる。)
これに対して、ミルトンのような軍の支持者は、
(神に命じられていれば)一般民の武装抵抗も
正当、と論じた。どうして神に命じられているかどうかが
わかるのか、といえば、それは、戦闘に勝ってきたから・・・・・・。
つまり、神に命じられたから一般民も戦っていい、
ではなく、勝ったから、その戦いは神に命じられた
ものにちがいない、というかたちで、常に遡及的に
過去の戦闘が正当化された。
だから、1650年代半ば、西インド諸島でイギリス軍が
スペインに敗れたとき、また(より深刻、重大に)1660年に
共和国が自壊してふたたび王政が立てられたとき、
ミルトンら共和国の支持者たちは、頭を抱えることになる。
神に命じられて戦ってきたはずなのに、神に命じられた
戦いを支持してきたはずなのに・・・・・・勘違いしていた?
しかし、『サムソン』のような作品を出す、ということは、
ミルトンは、この勘違いを認めてはいなかった
(苦悩はあったかもしれないが)、ということ。
(・・・・・・では、『失われた楽園』は?)
なお、この箇所に出てくる、隷属やそこからの解放という
考えは、暴君 tyrant チャールズ一世によって、また
暴君クロムウェルによって、奴隷のように奉仕させられる国民、
という1640-50年代の議論から。
1215 for nought
報酬なしで。Nought = nothing.
1218 my known offence
敵部族出身(ペリシテ人)である妻ダリラに対して、
サムソンがみずからの強さの秘密(髪を切られると
弱くなる)を話してしまったこと。これを聞いて
ダリラは、サムソンの神を切り落とし、弱くなった
彼を部族の長らに引き渡す。(1213行からの、
引き渡しエピソードは、これとは別もので
士師記15章からのもの。) そしてその部族の
長たちは、サムソンの目をくり抜いて盲目にし、
奴隷として使っている・・・・・・というのが、
上の場面までの話。
1220-
神に命じられているという設定だが、こういうケンカの
売り方はどうか、と思わせる書き方。平たく言えば、
「おい、やろうっていってんだろ? おまえなんてちょろいぜ!」
ということなので。また、その後すぐ、サムソンはこのように
挑発的にいう。
「おいおい、オレをただ見にきたのかい? 実際に
手でさわってオレの強さを調べたほうがいいんじゃね?
おーっと、でも気をつけろよ、逆にオレがおまえの強さを
調べちゃうからな!」
* * *
また加筆修正します。
* * *
英文テクストは、Paradise Regain'd : A Poem in IV books:
To Which Is Added Samson Agonistes (1671) より。
(日本語訳は、まとまりごとにわけてあります。)
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, _Paradise Lost_ (11: 689-97)
ジョン・ミルトン (1608-1674)
『失われた楽園』(11: 689-97)
なぜなら、この時代には力だけが驚嘆と称賛の対象となり、
勇敢さ、英雄性などと呼ばれるからです。
戦闘に勝利し、国々を征服し、
戦利品をもって帰る、もちろん、数えきれないほどの
人を殺して……そういうことが、最高の
栄誉とされるでしょう。そして栄誉ある
勝利者は、偉大なる征服者、
人類の守護者、まさに神、あるい神の子、などと呼ばれるでしょう。
本当はただの破壊者、人類の害悪そのものなのですが。
* * *
John Milton
Paradise Lost (11: 689-97)
For in those dayes Might onely shall be admir'd,
And Valour and Heroic Vertu call'd; [690]
To overcome in Battle, and subdue
Nations, and bring home spoils with infinite
Man-slaughter, shall be held the highest pitch
Of human Glorie, and for Glorie done
Of triumph, to be styl'd great Conquerours,
Patrons of Mankind, Gods, and Sons of Gods,
Destroyers rightlier call'd and Plagues of men.
* * *
将来起こるであろうことを映像のようなかたちで
アダムに見せながら、天使ミカエルが語ることば。
ホメーロスの『イリアス』におけるアキレウスのような、
武勲にすぐれた英雄の否定であると同時に、
1640-50年代のイギリス内乱における戦闘の批判。
* * *
訳注。
689 those dayes
エノクやその前後の世代が生きた時代。
エノクは、ノアの曾祖父(創世記5: 21-28)。
[D]ayes = days.
この場面の前の11巻638行目以降に、
どのような時代であったかが描かれている。
政治的対立、戦争と殺戮・・・・・・。
689 Might
身体的/精神的な力、大きな影響力や
武力(OED 3b)。自分の思い通りに人や
ものごとを動かすために用いられる「力」。
正当性rightの反意語(OED 4)。
689 shall be
アダムにとって未来のことだから。読者にとっては、
(ミルトンの創作もあるが)聖書のなかに記された
過去のできごと。
690 Vertu
Virtue. 男性的な力(OED 7; vir = man)。
691-
構文は以下の通り。
---
(節1)
主部(誰が/何が):
To overcome in Battle, and subdue Nations,
and bring home spoils with infinite Man-slaughter
述部(どうする):
shall be held the highest pitch Of human Glorie
V: shall be held
C: the highest pitch Of human Glorie
"and" でつないで--
(節2)
主部:
to be styl'd great Conquerours, Patrons of Mankind,
Gods, and Sons of Gods
(for Glorie done Of triumphはこの理由)
述部(どうする):
shall be held the highest pitch
Of human Glorie
(補足部分)
[though they are actually] Destroyers and Plagues of men
[if] rightlier call'd
---
693 pitch
最も高い点(OED n2, IV)。
* * *
上の一節で、世俗的な利害のための戦闘は
批判しつつも、ミルトンは、ピエモンテのソネットや
『サムソン』など、神の意にかなう戦闘を支持するかの
ような作品を残している。また、『第二弁護論』の
ような政治論文でも、神に支持された軍の
指揮者としてクロムウェルを称賛していたりする。(注)
その際に、人間的な利害による戦闘と、神の意に
よるものをどう区別するか、実際区別できるのか、
ということを考えないのは、そういう時代だったから、
というのが半分、ミルトンがそういう人だったから、
というのが半分(おそらく)。
ミルトンよりも宗教的、道徳的に冷めた人々は、
強い者にしたがえばいい、とか、海外での征服は
国の威信と利益の点でおおいにけっこう、
いいぞいいぞ!行け行け! というようなことを
書いている。(マーチャモント・ニーダムとか)。
「武力」をめぐる問題意識を共有しつつ、
ミルトンよりも冷めていたドライデンは、
たとえば、「人が考える神の意は、たいてい
その人の意志なのよ」というようなセリフを、
劇中の人物にいわせている(『恋する暴君』
Tyrannick Love 4幕より、聖カタリナのセリフ。)
これらのようなことや、さらには、当時すでに
西インド諸島あたりへの武力による進出や、
それにともなう奴隷貿易が動きはじめていたことを
考えれば、上の『失われた楽園』からの一節は、
理念的すぎてもの足りないと同時に、
もの足りないからこそ説得力があるようにも見える、
といったところではないか。
---
(注)
主人公サムソンのいわゆる自爆テロ的な行為を
描く『サムソン』の評価は、現在でも(現在だからこそ)
定まっていない。
また、『第二弁護論』は、共和政府のプロパガンディストという
立場から半ば書かれたものなので、そこに記された見解が
ミルトン個人のものとは、必ずしもいえない。
* * *
英文テクストは、Paradise Lost (1674) より。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/contents/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
『失われた楽園』(11: 689-97)
なぜなら、この時代には力だけが驚嘆と称賛の対象となり、
勇敢さ、英雄性などと呼ばれるからです。
戦闘に勝利し、国々を征服し、
戦利品をもって帰る、もちろん、数えきれないほどの
人を殺して……そういうことが、最高の
栄誉とされるでしょう。そして栄誉ある
勝利者は、偉大なる征服者、
人類の守護者、まさに神、あるい神の子、などと呼ばれるでしょう。
本当はただの破壊者、人類の害悪そのものなのですが。
* * *
John Milton
Paradise Lost (11: 689-97)
For in those dayes Might onely shall be admir'd,
And Valour and Heroic Vertu call'd; [690]
To overcome in Battle, and subdue
Nations, and bring home spoils with infinite
Man-slaughter, shall be held the highest pitch
Of human Glorie, and for Glorie done
Of triumph, to be styl'd great Conquerours,
Patrons of Mankind, Gods, and Sons of Gods,
Destroyers rightlier call'd and Plagues of men.
* * *
将来起こるであろうことを映像のようなかたちで
アダムに見せながら、天使ミカエルが語ることば。
ホメーロスの『イリアス』におけるアキレウスのような、
武勲にすぐれた英雄の否定であると同時に、
1640-50年代のイギリス内乱における戦闘の批判。
* * *
訳注。
689 those dayes
エノクやその前後の世代が生きた時代。
エノクは、ノアの曾祖父(創世記5: 21-28)。
[D]ayes = days.
この場面の前の11巻638行目以降に、
どのような時代であったかが描かれている。
政治的対立、戦争と殺戮・・・・・・。
689 Might
身体的/精神的な力、大きな影響力や
武力(OED 3b)。自分の思い通りに人や
ものごとを動かすために用いられる「力」。
正当性rightの反意語(OED 4)。
689 shall be
アダムにとって未来のことだから。読者にとっては、
(ミルトンの創作もあるが)聖書のなかに記された
過去のできごと。
690 Vertu
Virtue. 男性的な力(OED 7; vir = man)。
691-
構文は以下の通り。
---
(節1)
主部(誰が/何が):
To overcome in Battle, and subdue Nations,
and bring home spoils with infinite Man-slaughter
述部(どうする):
shall be held the highest pitch Of human Glorie
V: shall be held
C: the highest pitch Of human Glorie
"and" でつないで--
(節2)
主部:
to be styl'd great Conquerours, Patrons of Mankind,
Gods, and Sons of Gods
(for Glorie done Of triumphはこの理由)
述部(どうする):
shall be held the highest pitch
Of human Glorie
(補足部分)
[though they are actually] Destroyers and Plagues of men
[if] rightlier call'd
---
693 pitch
最も高い点(OED n2, IV)。
* * *
上の一節で、世俗的な利害のための戦闘は
批判しつつも、ミルトンは、ピエモンテのソネットや
『サムソン』など、神の意にかなう戦闘を支持するかの
ような作品を残している。また、『第二弁護論』の
ような政治論文でも、神に支持された軍の
指揮者としてクロムウェルを称賛していたりする。(注)
その際に、人間的な利害による戦闘と、神の意に
よるものをどう区別するか、実際区別できるのか、
ということを考えないのは、そういう時代だったから、
というのが半分、ミルトンがそういう人だったから、
というのが半分(おそらく)。
ミルトンよりも宗教的、道徳的に冷めた人々は、
強い者にしたがえばいい、とか、海外での征服は
国の威信と利益の点でおおいにけっこう、
いいぞいいぞ!行け行け! というようなことを
書いている。(マーチャモント・ニーダムとか)。
「武力」をめぐる問題意識を共有しつつ、
ミルトンよりも冷めていたドライデンは、
たとえば、「人が考える神の意は、たいてい
その人の意志なのよ」というようなセリフを、
劇中の人物にいわせている(『恋する暴君』
Tyrannick Love 4幕より、聖カタリナのセリフ。)
これらのようなことや、さらには、当時すでに
西インド諸島あたりへの武力による進出や、
それにともなう奴隷貿易が動きはじめていたことを
考えれば、上の『失われた楽園』からの一節は、
理念的すぎてもの足りないと同時に、
もの足りないからこそ説得力があるようにも見える、
といったところではないか。
---
(注)
主人公サムソンのいわゆる自爆テロ的な行為を
描く『サムソン』の評価は、現在でも(現在だからこそ)
定まっていない。
また、『第二弁護論』は、共和政府のプロパガンディストという
立場から半ば書かれたものなので、そこに記された見解が
ミルトン個人のものとは、必ずしもいえない。
* * *
英文テクストは、Paradise Lost (1674) より。
http://www.dartmouth.edu/~milton/
reading_room/contents/index.shtml
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, Sonnet XIX ("Methought I saw . . . ")
ジョン・ミルトン (1608-1774)
ソネット XIX (「先日逝った妻に・・・・・・」)
先日逝った、聖人のような妻に会った気がした。
わたしのところに、アルケースティスのように墓から連れ戻されてきていて。
ゼウスの偉大な息子が連れ戻して、その夫を喜ばせたというあの女性のように、
力ずくで死から救い出されて。白く、弱々しく、ではあったが。
妻は、出産のけがれから、
旧約の律法通りの儀式によって洗い清められた人のように、
そして、もう一度、わたしはそう信じているのだが、
天国ではなんの妨げもなく彼女の姿をすべて、完全に見ることができるであろう、そんな姿で、
やってきたのだ。白い服、彼女の心のように純粋な白に身を包んで。
顔にはヴェールがかかっていたが、空想のなかのわたしの目には、
愛と、美しさと、善良さがそこで輝いていた、
本当にはっきりと透き通るように。他の人の顔ではありえないくらいに楽しげに。
だが、ああ、わたしを抱きしめようと彼女がかがみこんたとき、
わたしは目を覚まし、彼女はすっと消え、朝日がわたしの夜を連れ戻した。
* * *
John Milton
Sonnet XIX ("Methought I saw . . . ")
Methought I saw my late espoused Saint
Brought to me like Alcestis from the grave,
Whom Joves great son to her glad Husband gave,
Rescu'd from death by force though pale and faint.
Mine as whom washt from spot of child-bed taint,
Purification in the old Law did save,
And such, as yet once more I trust to have
Full sight of her in Heaven without restraint,
Came vested all in white, pure as her mind:
Her face was vail'd, yet to my fancied sight,
Love, sweetness, goodness, in her person shin'd
So clear, as in no face with more delight.
But O as to embrace me she enclin'd,
I wak'd, she fled, and day brought back my night.
* * *
以下、訳注。
タイトル
1673年詩集に収められなかったソネットも数に入れて、
推定執筆年代順に並べ、このソネットを23番とする数え方も
あるが、個人的にはミルトンがつけた番号にしたがうほうが
いいかと。推定はあくまで推定ということで。
1 Methought
= It seemed to me--(OED, "think" [v1] -->
OED, "methinks"). Walter Raleighに、
"Methought I saw the grave where Laura lay"
という詩があり、また、H. G. という無名の詩人に
"Methought I saw upon Matildas Tombe . . . " という
作品もある。(どちらも16c末のもの。後者は
この本に--<http://www.archive.org/details/
mirrovrofmaiesti00greeuoft>。)
1 late
最近まで生きていた(OED [a1] 5a)--saintにかかる
+ 最近、近頃(OED [adv] 4)--espousedにかかる。
1 late espoused Saint
ミルトンの二番目の妻キャサリンのこと、という説が有力。
キャサリンは、1656年11月にミルトンと結婚し、1657年10月に
長女を出産し、そして、1658年2月に死去。
3 Joves great son
ヘラクレスのこと。
2-4
エウリピデスの『アルケスティス』参照(『ギリシャ悲劇
--エウリピデス--』 筑摩書房、1974年などに所収)。
手元にこの本や他の資料がないので、記憶をたどって
大ざっぱにあらすじを。
---
(1)
テッサリアのアドメートス王は病気(か何か)で死にそうであったが、
(神々との取り決めか何かで)父か母か妻がかわりに死ねば、
彼は生きつづけられることになっていた。
(2)
両親は、死にたくない、という。
(3)
妻であるアルケースティスが身代わりになって死ぬ。
(4)
葬儀をすませたばかりのときに、アドメートスの親友ヘラクレスが
やってくる。アドメートスは、妻の死を隠して、ヘラクレスを
手厚く、陽気にもてなす。
(5)
しかし、妙にしめやかな家のようすに、なんか変だな、と
感づいたヘラクレスは、召使いに事情をたずね、
アルケースティスが死んだことを知る。
(6)
「こんな大変なときに、オレまで悲しませないために
陽気にしてるなんて、あのバカ・・・・・・」と、
意気に感じたヘラクレスは、出て行き、
死神と戦って、アルケースティスをこの世に奪い返す。
(7)
ヘラクレスは、ヴェールを包まれたアルケースティスを
連れてアドメートス家にふたたびやって来て、いう--
ヘラクレス:
ちょっと、おまえに紹介したいカワイコちゃんがいるんだけど。
アドメートス:
いいよ、オレは。
ヘラ:
いやいや、そんなこというなって、絶対気に入るから。
アド:
おいおい、頼むよ、勘弁してくれよ。
ヘラ:
いいからいいから、な、この子の顔、見てみろよ!
アド:
ちょ、待てって、おまえ・・・・・・
は?・・・・・・マジ?・・・・・・
すげー! やったー!
---
5 as whom
= as one whom (OED 5).
5-6
S: Purification in the old Law
V: did save
O: whom
washed . . . taintは分詞構文。
---
5-6
上記の通り、実際ミルトンの二番目の妻キャサリンは、
出産後に亡くなったことから。出産後の清めの儀礼に
ついては、レビ記12章を参照。大ざっぱにまとめると--
---
女性は出産後、次の期間けがれているとされる。
男の子場合:
7日間(+その後33日は聖なるものにふれてはいけない)
女の子の場合:
14日間(+その後66日は聖なるものにふれてはいけない)
その後、祭司が小羊やハトなどをいけにえに捧げる
清めの儀式をして、その女性はふたたび清いものとなる。
---
7 such
副詞--as以下のようなようすで/as以下のような
程度まで(OED "such" [adv] A)。
7-8
ミルトンは1652年頃に失明した、ということがこの節の
背景にある。天国に行ったら彼女の顔が見られる、
しかもなんの妨げもなく、というのは、失明のため、
この世でそれを見ることができなかったから。
下の10-11行目の注も参照。
9 Pure
妻の名キャサリンの語源であるギリシャ語の
katharosという語は、pureという意味。
10
彼女の顔がヴェールに覆われている、というのは、
上記の通りアルケースティスがそうだったから。
加えて、1652年に失明し、1656年にキャサリンと
再婚したミルトンは、キャサリンの顔をまったく知らず、
それを具体的にはまったく想像できないから。
だから・・・・・・
11
妻の顔の特徴として、愛、美しさ、善良さ、という
抽象概念しかあげられない。たとえば、青い瞳、とか、
赤らんだ頬、とかは無理なわけで。
11 person
人の姿。10, 12行目のfaceと同義として解釈。
11-12
愛、美しさ、善良さ、という抽象概念を擬人化し、
それらが妻の顔の上(なか)で楽しそうに、うれしそうに
輝いている、といっている。
14
夢のなかでは目が見えるが、現実には盲目だから、
夢から覚めると真っ暗な世界にいる、ということ。
なお、次の対応にも注目。
ヘラクレスがアルケースティスを連れ戻した。
朝日が夜を連れ戻した。
* * *
以下、ソネット(14行詩)としての形式を確認。
脚韻パターン:
abba abba cdc dcd
イタリア式ソネットとして完璧。
(後半の脚韻が、cdc/dcdまたはcde/cdeと
教科書的に整ったイタリア式ソネットは
実はそこまで多くなかったりする。
ミルトンにも、他の詩人にも。)
構成:
通常のイタリア式ソネットの構成
(14 = 8+6 = 4+4+3+3)ではなく、
内容的には 4 + 8(=5+3) + 2 という、
イギリス式ソネットに近いかたちになっている。
(この詩にはあてはまらないが、脚韻が
abba/abba/cdcd/eeというイタ/イギ混合式の
ソネットが、実際かなり多い。)
1-4
一応ピリオドで終わっている一文。しかし、
主節は1行目で完結していて、2行目は1行目の
Saintの説明、3-4行目は2行目のAlcestisの
説明(であると同時に妻Saintの説明)。
後から後から詳細がつけ加えられていて、
話がどこに向かっているかわかりにくい。
5-9
主語Mineが文頭にあるが、述部(動詞)Cameが
9行目まで出てこない。5-8行目は、この主語Mineの
説明だけで終わっており、しかも、Mineにかかる
ふたつの修飾部のかたちがずれている。
---
asの前置詞句(そのなかにwhom節): ・・・・・・という人のように
such節: ・・・・・・というようすで/という程度まで
---
ということで、二重、三重にわかりにくい文構造。
10-12
比喩表現がなくなって、シンプルでクリアに。
13-14
オチ。But以降で1-12行目をすべてひっくり返すという
イギリス式ソネットにありがちなパターン。
と、見せかけて・・・・・・(以下参照)。
* * *
以下、解釈例。
ミルトンのソネットのうち、評価の高いもの、ピエモンテの
虐殺もの(XV)や、盲目もの(XVI)には、形式的に整った
ペトラルカのソネットではなく、形式的に、構成/構文的に
より自由で流動的なデッラ・カーサGiovanni della Casaのものの
影響が強く見られるといわれます。表現したい内容にあわせて、
(たとえば4/4/3/3という)構成を崩したり、コンマやピリオドの
出し入れや行またがりの多用によってリズムに変化を加えたり、
というわけです。(John S. Smart, The Sonnets of Milton, 1921
など参照。次のURLからダウンロードできます--<http://
www.archive.org/details/sonnetsofmilton00miltuoft>。)
ということで、上記のようなゆるめの構文とゆるめの構成など、
このXIXの形式的な特徴も、なにか意図があってのこと、
その裏に何か理由があるものと考えられます。
で、その意図とは・・・・・・
I
この詩が描く夢のぼんやりした世界の雰囲気を
伝えること。
(1)
夢のなかの話だから、上記のように、1-4行目で
ただの思いつきや連想であるかのように、
情報が後から後から追加されている。
(2)
夢のなかの話だから、上記のように、5-8行目でも
ただの思いつきや連想であるかのように、
情報が後から後から追加されている。
(3)
夢のなかの話だから、上記のように、5行目Mineを
受ける述部Cameが、その文脈がほとんど忘れられた頃に
あらわれる(9行目に)。
以上、夢のなかだから、思考が論理的に整理されていない、
ということ。
(4)
夢のなかの話だから、文学/芸術的なネタとしては
マイナーなアルケースティスがとりあげられてる?
冥界からの生還、という話で通常まず頭に浮かぶのは
オルペウスとエウリディケーの話のはず。
(ミルトンも、たとえば "L'Allegro" および
"Il Penseroso" でこれにふれている・・・・・・
だからこのソネットではあえて避けた?)。
個人的には、夢だから、起きているときとは異なる
連想がはたらいてアルケースティスが想起されたのかと、
ちょっと思いたい。
(ざっとウェブ上で確認しただけですが、
たとえば、アルケースティスを描いた絵は、
古代のものか18世紀以降のものばかりのようです。
オルペウスとエウリディケーの絵は、ティッツィアーノ、
プーサンなど、ルネサンスから初期近代にかけて、
ミルトンに近い時代の画家のものが少なくありません。)
---
(詩形と内容の関連のつづき)
II.
死者の帰還、(夢のなかでの)生の世界と死の世界の邂逅、
という主題と、この詩のかたちは対応している。
この詩では、通常イタリア式ソネットの転回点である
8:6の区切り目、もっとも大きなブレイクが入るべき
8行目と9行目のあいだが、主語Mine(妻が)と述語Came
(帰ってきた)でガッチリと連結されている。
通常、明確に切れるはずのイタリア式ソネットの
8:6の境界がない
= 通常、明確なはずの生死の境界が夢のなかでぼやけている
(妻が/帰ってきた)
III.
この詩の構成は、夢のなかで妻に再会している「わたし」の
思考の流れを示す。
1-4
アルケースティスに関するギリシャ神話/悲劇への言及。
比喩というかたちで、夢のなかの妻のようすを理性的に
とらえ、説明しようとしている。
5-8
旧約聖書への言及。1-4と同様、比喩というかたちで、
夢のなかの妻のようすを理性的にとらえ、説明しようとしている。
9-12
9行目のやってきたCame以降、(擬人化はあるが)
表現がより直接的になる。彼女の服は純粋さをあらわす白、
とか、彼女の表情は愛に満ちていて、きれいで、そして
やさしくて、とか。つまり、ミルトンの詩にありがちな、
教養の量と質をひけらかすかのような(そして現代の読者に
とっては無駄とも見えかねない)比喩を考える心のゆとり、
理性のはたらき、のようなものが感じられない。
とりあえず、きれいでサイコー! みたいに。
このような感情の高ぶり示すのに貢献していると
思われるのが、9行目冒頭にやっとあらわれる述語Came.
5行目の主語Mineの後、6-8行でじらされた後、9行目冒頭に、
(述語が)来た! という感覚は、(孤独な日々のなか・・・・・・)
妻が生き返ってきた! という感覚を想起させる。
このCame vested all in whiteが、この詩の第一の
クライマックス。
12行目冒頭のSo clearも同様。11行目最後の語
shin'dだけでも意味的には十分で、妻の顔の輝きは
わかるわけだが、そこからさらに行またがりで息をつかせず、
いわばダメ押しのようなかたちで読ませるSo clear
「本当にはっきりと透き通るように!」というフレーズを
おくことで、さらに強調的に「わたし」の心の高ぶりを
あらわしている。このSo clearが第二のクライマックス。
行またがり
= 行末に意味の切れ目/音読時の息つぎがないこと
IV.
イギリス式ソネット的な12:2の構成は、
夢のなかの幸せ:現実の不幸せの比率をあらわす。
ポイントは、現実としての重みを基準にすれば、
この12:2とは、実際、12<2 であること。
さらにいえば、この詩の構成は、実際12:2ではなく、
13:1。
1-13: 夢
14: 現実
(そして重みは、13<1)
つまり、この詩は、たった一行のできごと、目を覚ます、という
ほんの何気ない、ごくあたりまえなひとつの動作によって、
幸せの絶頂から失望のどん底に落とされる、それ以前
1-13行の幸福感が霧散する、という物語。
あわせて、この13:1の1は、盲目のままひとり残されるという
孤独感を暗示しているような気が。
* * *
英文テクストは、Milton, Poems (1673), p. 61より。

* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
ソネット XIX (「先日逝った妻に・・・・・・」)
先日逝った、聖人のような妻に会った気がした。
わたしのところに、アルケースティスのように墓から連れ戻されてきていて。
ゼウスの偉大な息子が連れ戻して、その夫を喜ばせたというあの女性のように、
力ずくで死から救い出されて。白く、弱々しく、ではあったが。
妻は、出産のけがれから、
旧約の律法通りの儀式によって洗い清められた人のように、
そして、もう一度、わたしはそう信じているのだが、
天国ではなんの妨げもなく彼女の姿をすべて、完全に見ることができるであろう、そんな姿で、
やってきたのだ。白い服、彼女の心のように純粋な白に身を包んで。
顔にはヴェールがかかっていたが、空想のなかのわたしの目には、
愛と、美しさと、善良さがそこで輝いていた、
本当にはっきりと透き通るように。他の人の顔ではありえないくらいに楽しげに。
だが、ああ、わたしを抱きしめようと彼女がかがみこんたとき、
わたしは目を覚まし、彼女はすっと消え、朝日がわたしの夜を連れ戻した。
* * *
John Milton
Sonnet XIX ("Methought I saw . . . ")
Methought I saw my late espoused Saint
Brought to me like Alcestis from the grave,
Whom Joves great son to her glad Husband gave,
Rescu'd from death by force though pale and faint.
Mine as whom washt from spot of child-bed taint,
Purification in the old Law did save,
And such, as yet once more I trust to have
Full sight of her in Heaven without restraint,
Came vested all in white, pure as her mind:
Her face was vail'd, yet to my fancied sight,
Love, sweetness, goodness, in her person shin'd
So clear, as in no face with more delight.
But O as to embrace me she enclin'd,
I wak'd, she fled, and day brought back my night.
* * *
以下、訳注。
タイトル
1673年詩集に収められなかったソネットも数に入れて、
推定執筆年代順に並べ、このソネットを23番とする数え方も
あるが、個人的にはミルトンがつけた番号にしたがうほうが
いいかと。推定はあくまで推定ということで。
1 Methought
= It seemed to me--(OED, "think" [v1] -->
OED, "methinks"). Walter Raleighに、
"Methought I saw the grave where Laura lay"
という詩があり、また、H. G. という無名の詩人に
"Methought I saw upon Matildas Tombe . . . " という
作品もある。(どちらも16c末のもの。後者は
この本に--<http://www.archive.org/details/
mirrovrofmaiesti00greeuoft>。)
1 late
最近まで生きていた(OED [a1] 5a)--saintにかかる
+ 最近、近頃(OED [adv] 4)--espousedにかかる。
1 late espoused Saint
ミルトンの二番目の妻キャサリンのこと、という説が有力。
キャサリンは、1656年11月にミルトンと結婚し、1657年10月に
長女を出産し、そして、1658年2月に死去。
3 Joves great son
ヘラクレスのこと。
2-4
エウリピデスの『アルケスティス』参照(『ギリシャ悲劇
--エウリピデス--』 筑摩書房、1974年などに所収)。
手元にこの本や他の資料がないので、記憶をたどって
大ざっぱにあらすじを。
---
(1)
テッサリアのアドメートス王は病気(か何か)で死にそうであったが、
(神々との取り決めか何かで)父か母か妻がかわりに死ねば、
彼は生きつづけられることになっていた。
(2)
両親は、死にたくない、という。
(3)
妻であるアルケースティスが身代わりになって死ぬ。
(4)
葬儀をすませたばかりのときに、アドメートスの親友ヘラクレスが
やってくる。アドメートスは、妻の死を隠して、ヘラクレスを
手厚く、陽気にもてなす。
(5)
しかし、妙にしめやかな家のようすに、なんか変だな、と
感づいたヘラクレスは、召使いに事情をたずね、
アルケースティスが死んだことを知る。
(6)
「こんな大変なときに、オレまで悲しませないために
陽気にしてるなんて、あのバカ・・・・・・」と、
意気に感じたヘラクレスは、出て行き、
死神と戦って、アルケースティスをこの世に奪い返す。
(7)
ヘラクレスは、ヴェールを包まれたアルケースティスを
連れてアドメートス家にふたたびやって来て、いう--
ヘラクレス:
ちょっと、おまえに紹介したいカワイコちゃんがいるんだけど。
アドメートス:
いいよ、オレは。
ヘラ:
いやいや、そんなこというなって、絶対気に入るから。
アド:
おいおい、頼むよ、勘弁してくれよ。
ヘラ:
いいからいいから、な、この子の顔、見てみろよ!
アド:
ちょ、待てって、おまえ・・・・・・
は?・・・・・・マジ?・・・・・・
すげー! やったー!
---
5 as whom
= as one whom (OED 5).
5-6
S: Purification in the old Law
V: did save
O: whom
washed . . . taintは分詞構文。
---
5-6
上記の通り、実際ミルトンの二番目の妻キャサリンは、
出産後に亡くなったことから。出産後の清めの儀礼に
ついては、レビ記12章を参照。大ざっぱにまとめると--
---
女性は出産後、次の期間けがれているとされる。
男の子場合:
7日間(+その後33日は聖なるものにふれてはいけない)
女の子の場合:
14日間(+その後66日は聖なるものにふれてはいけない)
その後、祭司が小羊やハトなどをいけにえに捧げる
清めの儀式をして、その女性はふたたび清いものとなる。
---
7 such
副詞--as以下のようなようすで/as以下のような
程度まで(OED "such" [adv] A)。
7-8
ミルトンは1652年頃に失明した、ということがこの節の
背景にある。天国に行ったら彼女の顔が見られる、
しかもなんの妨げもなく、というのは、失明のため、
この世でそれを見ることができなかったから。
下の10-11行目の注も参照。
9 Pure
妻の名キャサリンの語源であるギリシャ語の
katharosという語は、pureという意味。
10
彼女の顔がヴェールに覆われている、というのは、
上記の通りアルケースティスがそうだったから。
加えて、1652年に失明し、1656年にキャサリンと
再婚したミルトンは、キャサリンの顔をまったく知らず、
それを具体的にはまったく想像できないから。
だから・・・・・・
11
妻の顔の特徴として、愛、美しさ、善良さ、という
抽象概念しかあげられない。たとえば、青い瞳、とか、
赤らんだ頬、とかは無理なわけで。
11 person
人の姿。10, 12行目のfaceと同義として解釈。
11-12
愛、美しさ、善良さ、という抽象概念を擬人化し、
それらが妻の顔の上(なか)で楽しそうに、うれしそうに
輝いている、といっている。
14
夢のなかでは目が見えるが、現実には盲目だから、
夢から覚めると真っ暗な世界にいる、ということ。
なお、次の対応にも注目。
ヘラクレスがアルケースティスを連れ戻した。
朝日が夜を連れ戻した。
* * *
以下、ソネット(14行詩)としての形式を確認。
脚韻パターン:
abba abba cdc dcd
イタリア式ソネットとして完璧。
(後半の脚韻が、cdc/dcdまたはcde/cdeと
教科書的に整ったイタリア式ソネットは
実はそこまで多くなかったりする。
ミルトンにも、他の詩人にも。)
構成:
通常のイタリア式ソネットの構成
(14 = 8+6 = 4+4+3+3)ではなく、
内容的には 4 + 8(=5+3) + 2 という、
イギリス式ソネットに近いかたちになっている。
(この詩にはあてはまらないが、脚韻が
abba/abba/cdcd/eeというイタ/イギ混合式の
ソネットが、実際かなり多い。)
1-4
一応ピリオドで終わっている一文。しかし、
主節は1行目で完結していて、2行目は1行目の
Saintの説明、3-4行目は2行目のAlcestisの
説明(であると同時に妻Saintの説明)。
後から後から詳細がつけ加えられていて、
話がどこに向かっているかわかりにくい。
5-9
主語Mineが文頭にあるが、述部(動詞)Cameが
9行目まで出てこない。5-8行目は、この主語Mineの
説明だけで終わっており、しかも、Mineにかかる
ふたつの修飾部のかたちがずれている。
---
asの前置詞句(そのなかにwhom節): ・・・・・・という人のように
such節: ・・・・・・というようすで/という程度まで
---
ということで、二重、三重にわかりにくい文構造。
10-12
比喩表現がなくなって、シンプルでクリアに。
13-14
オチ。But以降で1-12行目をすべてひっくり返すという
イギリス式ソネットにありがちなパターン。
と、見せかけて・・・・・・(以下参照)。
* * *
以下、解釈例。
ミルトンのソネットのうち、評価の高いもの、ピエモンテの
虐殺もの(XV)や、盲目もの(XVI)には、形式的に整った
ペトラルカのソネットではなく、形式的に、構成/構文的に
より自由で流動的なデッラ・カーサGiovanni della Casaのものの
影響が強く見られるといわれます。表現したい内容にあわせて、
(たとえば4/4/3/3という)構成を崩したり、コンマやピリオドの
出し入れや行またがりの多用によってリズムに変化を加えたり、
というわけです。(John S. Smart, The Sonnets of Milton, 1921
など参照。次のURLからダウンロードできます--<http://
www.archive.org/details/sonnetsofmilton00miltuoft>。)
ということで、上記のようなゆるめの構文とゆるめの構成など、
このXIXの形式的な特徴も、なにか意図があってのこと、
その裏に何か理由があるものと考えられます。
で、その意図とは・・・・・・
I
この詩が描く夢のぼんやりした世界の雰囲気を
伝えること。
(1)
夢のなかの話だから、上記のように、1-4行目で
ただの思いつきや連想であるかのように、
情報が後から後から追加されている。
(2)
夢のなかの話だから、上記のように、5-8行目でも
ただの思いつきや連想であるかのように、
情報が後から後から追加されている。
(3)
夢のなかの話だから、上記のように、5行目Mineを
受ける述部Cameが、その文脈がほとんど忘れられた頃に
あらわれる(9行目に)。
以上、夢のなかだから、思考が論理的に整理されていない、
ということ。
(4)
夢のなかの話だから、文学/芸術的なネタとしては
マイナーなアルケースティスがとりあげられてる?
冥界からの生還、という話で通常まず頭に浮かぶのは
オルペウスとエウリディケーの話のはず。
(ミルトンも、たとえば "L'Allegro" および
"Il Penseroso" でこれにふれている・・・・・・
だからこのソネットではあえて避けた?)。
個人的には、夢だから、起きているときとは異なる
連想がはたらいてアルケースティスが想起されたのかと、
ちょっと思いたい。
(ざっとウェブ上で確認しただけですが、
たとえば、アルケースティスを描いた絵は、
古代のものか18世紀以降のものばかりのようです。
オルペウスとエウリディケーの絵は、ティッツィアーノ、
プーサンなど、ルネサンスから初期近代にかけて、
ミルトンに近い時代の画家のものが少なくありません。)
---
(詩形と内容の関連のつづき)
II.
死者の帰還、(夢のなかでの)生の世界と死の世界の邂逅、
という主題と、この詩のかたちは対応している。
この詩では、通常イタリア式ソネットの転回点である
8:6の区切り目、もっとも大きなブレイクが入るべき
8行目と9行目のあいだが、主語Mine(妻が)と述語Came
(帰ってきた)でガッチリと連結されている。
通常、明確に切れるはずのイタリア式ソネットの
8:6の境界がない
= 通常、明確なはずの生死の境界が夢のなかでぼやけている
(妻が/帰ってきた)
III.
この詩の構成は、夢のなかで妻に再会している「わたし」の
思考の流れを示す。
1-4
アルケースティスに関するギリシャ神話/悲劇への言及。
比喩というかたちで、夢のなかの妻のようすを理性的に
とらえ、説明しようとしている。
5-8
旧約聖書への言及。1-4と同様、比喩というかたちで、
夢のなかの妻のようすを理性的にとらえ、説明しようとしている。
9-12
9行目のやってきたCame以降、(擬人化はあるが)
表現がより直接的になる。彼女の服は純粋さをあらわす白、
とか、彼女の表情は愛に満ちていて、きれいで、そして
やさしくて、とか。つまり、ミルトンの詩にありがちな、
教養の量と質をひけらかすかのような(そして現代の読者に
とっては無駄とも見えかねない)比喩を考える心のゆとり、
理性のはたらき、のようなものが感じられない。
とりあえず、きれいでサイコー! みたいに。
このような感情の高ぶり示すのに貢献していると
思われるのが、9行目冒頭にやっとあらわれる述語Came.
5行目の主語Mineの後、6-8行でじらされた後、9行目冒頭に、
(述語が)来た! という感覚は、(孤独な日々のなか・・・・・・)
妻が生き返ってきた! という感覚を想起させる。
このCame vested all in whiteが、この詩の第一の
クライマックス。
12行目冒頭のSo clearも同様。11行目最後の語
shin'dだけでも意味的には十分で、妻の顔の輝きは
わかるわけだが、そこからさらに行またがりで息をつかせず、
いわばダメ押しのようなかたちで読ませるSo clear
「本当にはっきりと透き通るように!」というフレーズを
おくことで、さらに強調的に「わたし」の心の高ぶりを
あらわしている。このSo clearが第二のクライマックス。
行またがり
= 行末に意味の切れ目/音読時の息つぎがないこと
IV.
イギリス式ソネット的な12:2の構成は、
夢のなかの幸せ:現実の不幸せの比率をあらわす。
ポイントは、現実としての重みを基準にすれば、
この12:2とは、実際、12<2 であること。
さらにいえば、この詩の構成は、実際12:2ではなく、
13:1。
1-13: 夢
14: 現実
(そして重みは、13<1)
つまり、この詩は、たった一行のできごと、目を覚ます、という
ほんの何気ない、ごくあたりまえなひとつの動作によって、
幸せの絶頂から失望のどん底に落とされる、それ以前
1-13行の幸福感が霧散する、という物語。
あわせて、この13:1の1は、盲目のままひとり残されるという
孤独感を暗示しているような気が。
* * *
英文テクストは、Milton, Poems (1673), p. 61より。

* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Milton, "On May Morning"
ジョン・ミルトン (1608-1674)
「歌--五月の朝に--」
今、輝く朝の星、一日のはじまりを告げる星が、
踊りながら東からやってくる。そして手をつないで
花咲く〈五月〉をつれてくる。腰をおろす〈五月〉の緑のドレスには
黄色い九輪桜や淡い桜草が散りばめられている。
ようこそ、恵み深き〈五月〉、君の息は吹き込んでくれる
若さと楽しみ、恋心とからだのあたたかさを。
森や林を君は彩り、着飾らせ、
丘も谷も君の贈りもので誇らしげ。
このようにぼくたちは朝早く、歌で君に呼びかける。
ようこそ、ずっといてくれたらいいのに。
* * *
John Milton (1608-1674)
"Song: On May Morning"
Now the bright morning Star, Dayes harbinger,
Comes dancing from the East, and leads with her
The Flowry May, who from her green lap throws
The yellow Cowslip, and the pale Primrose.
Hail bounteous May that dost inspire
Mirth and youth, and warm desire,
Woods and Groves, are of thy dressing,
Hill and Dale, doth boast thy blessing.
Thus we salute thee with our early Song,
And welcom thee, and wish thee long.
* * *
1行目 morning Star 朝の星
明けの明星 = 金星のこと。

By Mila Zinkova
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Venus-pacific-levelled.jpg
(以下、画像のURLはすべて2011年5月12日現在のもの。)
3行目 May 〈五月〉
擬人化されている。おそらく五月祭May Dayのときに
選ばれるMay Queenのようなうら若い、そして
草花できれいに飾られた女の子として。

By S. J. Thompson (1864-1929)
Photograph courtesy of the New Westminster Public Library
Accession no.:2728
http://www.nwheritage.org/database/images/212_web.jpg
(1887年頃のカナダの写真です。)
なお、この詩が書かれた17世紀のイギリスでは主として
旧暦(ユリウス暦)が用いられていたので、ここでの
五月とは、今の5月11日からのひと月。
3行目 lap ドレス(と、ここでは訳しています。)
スカートの前の部分、あるいは、座っている人のウエストから
膝までの部分の上側(OED, "lap" 4b, 5)〈五月〉の緑の
"lap" とは、もちろん、新緑が萌える野原などのこと。
4行目 Cowslip 九輪桜

(パブリック・ドメインにあるとのこと)
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cowslip.dof.demo.arp.jpg>
4行目 Primrose 桜草

By TeunSpaans
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primula-vulgaris-flowers.jpg>
こういうのも。

By Bouba
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primula_marginata.jpg>
7行目 たとえばこんな情景。

By IrishFireside
<http://www.flickr.com/photos/irishfireside/2373920216/in/photostream/>
(これはアイルランドの七月ですが。)
---
この詩にあるような、一見無駄でくどいようにも見えかねない
自然描写の意味、その存在理由を理解するには、写真、TVや映画、
インターネットなどが発明される前の生活を想像する必要が
あるでしょう。
花は一年の決まった季節にしか咲かない、
草木が青々と生い茂るのも一年のなかの一時期のみ。
そして写真もTVもインターネットもないから、
これらが見られるのは、その決まった時期のみ。
今では、冬でも写真や映像で春夏秋の季節を見ることができますが、
以前は、実際50-60年ほど前(?)までは、もちろんそうではなかった。
(モノクロ写真を除いては。)
冬に見えるのは冬景色だけ、雨の日に見えるのは雨だけ。
夜に見えるのは闇とランプの明かりだけ。
そのような生活における文化的娯楽的な刺激や楽しみとして
唯一手に入ったものが、言葉による描写/表象だったわけです。
たとえば、上の画像を見て金星や桜草などのイメージを
頭に入れていただき、そして雨の日や暗い夜に、殺風景な
仕事場や、アスファルトとビルとあわただしい人々しか見えない
道や駅のホームなどで、この詩を読んで、あるいは思い出して
みてください。ちょっとした感動があるのでは、と勝手に
期待します。たとえば、ワーズワースの「水仙」
("I wonder lonely as a cloud")に描かれているような。
英語のテクストは、Milton, Poems (1645) より。
* * *
(以下、マニアックな方のために)
この詩のリズムや言葉の音について。

/: ストレスのある音節
x: ストレスのない音節
音節: 母音ひとつ + 前後に付随する子音(群)
(長母音、二重母音も基本的に母音ひとつと数える。)
---
1-4
各行十音節ということを除けばほとんど散文。
詩として大きくとらえれば弱強五歩格 iambic pentameter
( x / x / x / x / x / )だが、弱強 " x / " の音歩に
したがわないところが多すぎるため、通常でも散文的な五歩格以上に
さらに散文的な、普通の発話/会話のような雰囲気になっている。
なお、2-4行目は、Comes dancing, The Flowry May,
The yellow Cowslipと、みな明るく楽しげなイメージをもたらす
フレーズではじまっている。行末から行頭に目を移したときに
目に入るのは楽しげな絵 --> どこに目を移しても楽しげな色や景色、
ということかと。
---
5-8
ストレス・ミーターに転調。この部分を指して9行目で our
early song といっている。
ストレス・ミーター(stress meter あるいは accentual
meter --- 英語では通常後者の名称が用いられる)とは、
たとえば、手拍子四回にあわせて一行を読むと、歌のように
調子よく感じられるリズムのこと。(上の画像の
スキャンジョンを見て、行の下のB [beatの略] に
手拍子をあわせながら読んでみてください。)
この四行(5-8行)のなかにもリズムの変化が施されている―――
上昇調(rising = x / x / . . . )のストレス・ミーターから
下降調(falling = / x / x . . . )のそれへ、と。
古典韻律の用語でいえば、5行目は弱強格 iambus,
6行目を七音節として弱強格か強弱格 trochee かを
あいまいにして、7-8行目で強弱格に移行完了。
このような、落ち着いた弱強格から強調的な強弱格へ、
というリズムの変化には、たとえば、春における気分と景色の
変化に対する驚きや感動を強調する効果があるように
思われる。
6 お、なにか楽しげな気分になってきた・・・
7 そうだよ、森や林は新緑と花できれいだし、
8 そうだよ、丘や谷全体が彩られていて自慢げだぞ!
みたいな。
---
9
歌が終わって語りに戻るということで、ふたたび散文的な
十音節(弱強五歩格)。
10
語りに戻っても、やはり五月の楽しげな雰囲気のために、
ついつい歌ってしまうということか、ふたたびストレス・
ミーターで楽しげに。
---
詩のリズムについては、個人的には Derek Attridge,
Poetic Rhythm (Cambridge, 1995) がおすすめです。
多くの作品が例としてあげられていて読みやすい本ですので、
よろしければ。
古典韻律系でしたら、Paul Fussell, Poetic Meter
and Poetic Form, Rev. ed. (New York, 1979) が
読みやすいと思います。(日本語で書かれたイギリス詩の
入門書、解説書の多くにも古典韻律の解説があります。)
* * *
響きあう母音/子音の重なり各種--
Star - harbinger
East - leads
throws - yellow
(Cowslip -) pale - Primrose.
May - Mirth - youth - warm - Woods
dressing - Hill and Dale - doth
boast - blessing
welcom - wish
(頭韻、行内韻、母音韻、子音韻、パラライムなどの
用語は定義があいまいなので使いません。)
* * *
意味上効果的なカプレットの脚韻--
her green lap throws - the pale Primrose
inspire - desire
thy dressing - thy blessing
our early Song - wish thee long
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
「歌--五月の朝に--」
今、輝く朝の星、一日のはじまりを告げる星が、
踊りながら東からやってくる。そして手をつないで
花咲く〈五月〉をつれてくる。腰をおろす〈五月〉の緑のドレスには
黄色い九輪桜や淡い桜草が散りばめられている。
ようこそ、恵み深き〈五月〉、君の息は吹き込んでくれる
若さと楽しみ、恋心とからだのあたたかさを。
森や林を君は彩り、着飾らせ、
丘も谷も君の贈りもので誇らしげ。
このようにぼくたちは朝早く、歌で君に呼びかける。
ようこそ、ずっといてくれたらいいのに。
* * *
John Milton (1608-1674)
"Song: On May Morning"
Now the bright morning Star, Dayes harbinger,
Comes dancing from the East, and leads with her
The Flowry May, who from her green lap throws
The yellow Cowslip, and the pale Primrose.
Hail bounteous May that dost inspire
Mirth and youth, and warm desire,
Woods and Groves, are of thy dressing,
Hill and Dale, doth boast thy blessing.
Thus we salute thee with our early Song,
And welcom thee, and wish thee long.
* * *
1行目 morning Star 朝の星
明けの明星 = 金星のこと。

By Mila Zinkova
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Venus-pacific-levelled.jpg
(以下、画像のURLはすべて2011年5月12日現在のもの。)
3行目 May 〈五月〉
擬人化されている。おそらく五月祭May Dayのときに
選ばれるMay Queenのようなうら若い、そして
草花できれいに飾られた女の子として。

By S. J. Thompson (1864-1929)
Photograph courtesy of the New Westminster Public Library
Accession no.:2728
http://www.nwheritage.org/database/images/212_web.jpg
(1887年頃のカナダの写真です。)
なお、この詩が書かれた17世紀のイギリスでは主として
旧暦(ユリウス暦)が用いられていたので、ここでの
五月とは、今の5月11日からのひと月。
3行目 lap ドレス(と、ここでは訳しています。)
スカートの前の部分、あるいは、座っている人のウエストから
膝までの部分の上側(OED, "lap" 4b, 5)〈五月〉の緑の
"lap" とは、もちろん、新緑が萌える野原などのこと。
4行目 Cowslip 九輪桜

(パブリック・ドメインにあるとのこと)
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cowslip.dof.demo.arp.jpg>
4行目 Primrose 桜草

By TeunSpaans
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primula-vulgaris-flowers.jpg>
こういうのも。

By Bouba
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primula_marginata.jpg>
7行目 たとえばこんな情景。

By IrishFireside
<http://www.flickr.com/photos/irishfireside/2373920216/in/photostream/>
(これはアイルランドの七月ですが。)
---
この詩にあるような、一見無駄でくどいようにも見えかねない
自然描写の意味、その存在理由を理解するには、写真、TVや映画、
インターネットなどが発明される前の生活を想像する必要が
あるでしょう。
花は一年の決まった季節にしか咲かない、
草木が青々と生い茂るのも一年のなかの一時期のみ。
そして写真もTVもインターネットもないから、
これらが見られるのは、その決まった時期のみ。
今では、冬でも写真や映像で春夏秋の季節を見ることができますが、
以前は、実際50-60年ほど前(?)までは、もちろんそうではなかった。
(モノクロ写真を除いては。)
冬に見えるのは冬景色だけ、雨の日に見えるのは雨だけ。
夜に見えるのは闇とランプの明かりだけ。
そのような生活における文化的娯楽的な刺激や楽しみとして
唯一手に入ったものが、言葉による描写/表象だったわけです。
たとえば、上の画像を見て金星や桜草などのイメージを
頭に入れていただき、そして雨の日や暗い夜に、殺風景な
仕事場や、アスファルトとビルとあわただしい人々しか見えない
道や駅のホームなどで、この詩を読んで、あるいは思い出して
みてください。ちょっとした感動があるのでは、と勝手に
期待します。たとえば、ワーズワースの「水仙」
("I wonder lonely as a cloud")に描かれているような。
英語のテクストは、Milton, Poems (1645) より。
* * *
(以下、マニアックな方のために)
この詩のリズムや言葉の音について。

/: ストレスのある音節
x: ストレスのない音節
音節: 母音ひとつ + 前後に付随する子音(群)
(長母音、二重母音も基本的に母音ひとつと数える。)
---
1-4
各行十音節ということを除けばほとんど散文。
詩として大きくとらえれば弱強五歩格 iambic pentameter
( x / x / x / x / x / )だが、弱強 " x / " の音歩に
したがわないところが多すぎるため、通常でも散文的な五歩格以上に
さらに散文的な、普通の発話/会話のような雰囲気になっている。
なお、2-4行目は、Comes dancing, The Flowry May,
The yellow Cowslipと、みな明るく楽しげなイメージをもたらす
フレーズではじまっている。行末から行頭に目を移したときに
目に入るのは楽しげな絵 --> どこに目を移しても楽しげな色や景色、
ということかと。
---
5-8
ストレス・ミーターに転調。この部分を指して9行目で our
early song といっている。
ストレス・ミーター(stress meter あるいは accentual
meter --- 英語では通常後者の名称が用いられる)とは、
たとえば、手拍子四回にあわせて一行を読むと、歌のように
調子よく感じられるリズムのこと。(上の画像の
スキャンジョンを見て、行の下のB [beatの略] に
手拍子をあわせながら読んでみてください。)
この四行(5-8行)のなかにもリズムの変化が施されている―――
上昇調(rising = x / x / . . . )のストレス・ミーターから
下降調(falling = / x / x . . . )のそれへ、と。
古典韻律の用語でいえば、5行目は弱強格 iambus,
6行目を七音節として弱強格か強弱格 trochee かを
あいまいにして、7-8行目で強弱格に移行完了。
このような、落ち着いた弱強格から強調的な強弱格へ、
というリズムの変化には、たとえば、春における気分と景色の
変化に対する驚きや感動を強調する効果があるように
思われる。
6 お、なにか楽しげな気分になってきた・・・
7 そうだよ、森や林は新緑と花できれいだし、
8 そうだよ、丘や谷全体が彩られていて自慢げだぞ!
みたいな。
---
9
歌が終わって語りに戻るということで、ふたたび散文的な
十音節(弱強五歩格)。
10
語りに戻っても、やはり五月の楽しげな雰囲気のために、
ついつい歌ってしまうということか、ふたたびストレス・
ミーターで楽しげに。
---
詩のリズムについては、個人的には Derek Attridge,
Poetic Rhythm (Cambridge, 1995) がおすすめです。
多くの作品が例としてあげられていて読みやすい本ですので、
よろしければ。
古典韻律系でしたら、Paul Fussell, Poetic Meter
and Poetic Form, Rev. ed. (New York, 1979) が
読みやすいと思います。(日本語で書かれたイギリス詩の
入門書、解説書の多くにも古典韻律の解説があります。)
* * *
響きあう母音/子音の重なり各種--
Star - harbinger
East - leads
throws - yellow
(Cowslip -) pale - Primrose.
May - Mirth - youth - warm - Woods
dressing - Hill and Dale - doth
boast - blessing
welcom - wish
(頭韻、行内韻、母音韻、子音韻、パラライムなどの
用語は定義があいまいなので使いません。)
* * *
意味上効果的なカプレットの脚韻--
her green lap throws - the pale Primrose
inspire - desire
thy dressing - thy blessing
our early Song - wish thee long
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| 次ページ » |