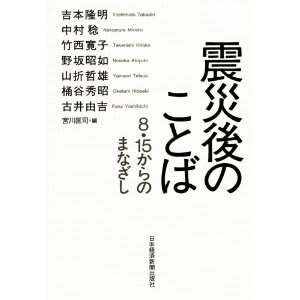第3次『季刊 現代の理論 2012春 VOL30 終刊号 総特集 日本はどこへ?希望はどこに』(明石書店 2012年刊)
第1次『現代の理論』は1959年5月に井汲卓一、長洲一ニ、安東仁兵衛らによって創刊されたが論争は党外でするなという日共中央の圧力で5号をもって停刊。多くの人が60年安保以降日共を脱党し、1964年2月に第2次『現代の理論』が復刊、1989年12月に休刊するまで発行が続いた。第3次『現代の理論』は、2004年6月の創刊準備号に始まり2012年4月の30号を以って終刊することになった。
雑誌の基調がこの国における社会民主主義の深化ということで、かなりナイーブで中庸的なスタンスだったことと、2009年8月の民主党への政権交代で社民主義の実現への期待感が膨らんだ分、民主党政権の現実は衆知のとおりであり、失望感とともに雑誌の寿命を縮めたと思う。
終刊号ということで30数名が寄稿しており、オルタナティブの香りのする論文がないだろうかと通読した。その中で、唯一1本だけ私にとって瞠目すべき論文に遭遇した。稀に自分の中で体系化できないでモヤモヤとしたものがブレイクスルーする時がある。
経済アナリスト山川修氏による『擬制資本の限界から新たな理念構築へ』である。
経済社会を歴史的視点から捉えるのは、経済をメカニカルにしか捉えない近代経済学ではできない。擬制資本を資本主義の最高の発展形態であると同時に資本主義経済の歴史的限界を示しているという山川氏の書きっぷりから見て、氏は宇野経済学をベースにしていると思う。そして、氏は新たな「大きな物語」の構築を呼びかけるのである。
山川氏の展開が、私が発達心理学者の浜田寿美男氏の講演や著作を通じて学んだ「人は、将来の目標のために生きる(勉強と言い換えてもいい)のではなく、自分の持っている力をやりくりしながら、今、ここを全力で生きる以外にない。その結果として成長や目標が達成される場合がある」という「今、ここ」論と通底していたのである。
山川氏は、「未来に向けての現在の運動(マルクスはそれを共産主義という)を、目的達成までの過程と見るべきでない。」なぜなら「自分が生きている間に目的が達成されない場合、現在の運動に虚しさが生じてくる」からであると述べる。さらに「現在の一瞬一瞬を生きるということであり、「いつか、どこか」ではなく、未来の理念に不断に近づこうと努める現在の「今、ここ」を生きることである」という。
他に山川修氏の論文が無いかな?