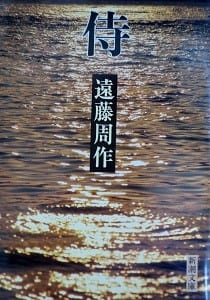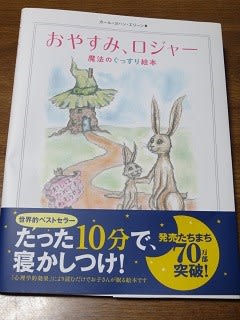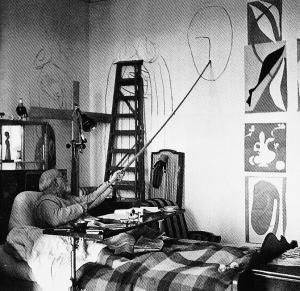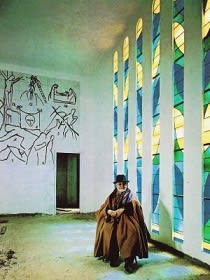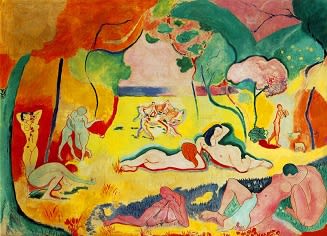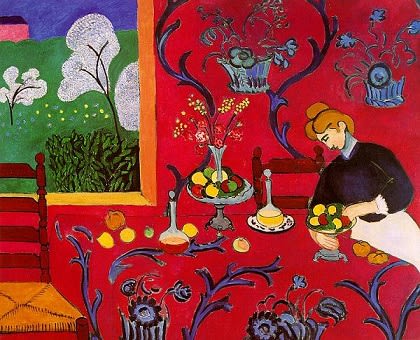上杉鷹山の名前がはっきりと私の心に刻まれたのは、故ケネディ大統領が「尊敬する日本人に鷹山の名前を挙げた」ことを知ったつい最近のことです。アメリカのトップによる高い評価は、日本に居ながら無知だった私には衝撃的でした。そこで先ず読んだのが童門冬二『小説 上杉鷹山』。
そしてまた少し前、北米の大自然の中で凛として生きる主婦のブログで鷹山を描いた藤沢周平『漆の実のみのる国』を知り、これまたアメリカ経由の情報が心に残りました。
江戸時代18世紀半ば、九州南国の小さな藩から東北の上杉家に養子に入った治憲(鷹山)は17歳で9代藩主になります。上杉家は豊臣政権下で景勝の会津藩120万石だったのが、家康に30万石に減封されて米沢に移り、さらに跡継ぎ問題で15万石にまで減らされます。(因みに米沢は家臣・直江兼続の領地で、米沢の町計画の基礎や農業振興の元を作っており、彼は喜んで景勝を迎え入れました。)
代々藩主には吉良上野介の血も流れて武士の格式がことさら重んじられ、また名門の誇りも捨てられず、更には藩士は景勝の時のままの5000人、藩の収支は合わずじまいで借金は16万両(160億円)にも膨らんでいました。
前藩主の重定は領地返上を検討するほど追い込まれていましたが、その時鷹山に託されたのが破たん寸前の藩の改革でした。
ブレーンに選んだのは細井平洲門下生で、いわば米沢藩の保守派とは対立する改革派でした。「大倹約令」を出し自らも実行、武士もクワを持ち開拓地を広げます。
身分制度が秩序だった江戸時代には武士の優位は常識、なかなか理解の得られる改革ではありませんでしたが、少しずつ鷹山の心を共有できる武士が増えていきました。
改革が進みつつある中で、改革派に対抗する重臣7名のいわばクーデターが起き広間に閉じ込められますが、最後は側近と前藩主重定の助けもあり脱出します。愛情と優しさを持つ鷹山でしたが、改革を実行するために7人に対して断固たる意志で厳しい処罰を科しました。
鷹山が行った改革は、漆、桑、楮を100万本ずつ植え、絹糸、和紙、そして漆の実から蝋をとり江戸に売りさばくことでした。しかし不運にも、その頃は西日本から櫨の実のロウソクが安価に出回るようになり計画は失敗。折から浅間山が噴火し「天明の大飢饉」が襲います。藩の収入を上回る損害、餓死者・・・と農村は再び荒れ果て、僅かに成果を出し始めていた改革も水泡に帰しました。
改革では鷹山の存在が大き過ぎ頼られ過ぎること、強硬な改革がうまくいかなかった責任などを考えて藩主を引退し隠居、家定の子・治広が10代藩主になります。
隠居から5年、借金はさらに膨れ上がっていました。鷹山は心を痛めながらも隠居の身分を固く守っていました。
そんな時に、鷹山の復帰を願うかつてのブレーンで引退している竹俣当綱がやってきて、政治の舞台に戻るように、更には莅戸義政を取り立てるように策をとります。
強硬に進めた第1次改革の失敗を冷静に反省し、藩の借金を公開して藩の苦しい状況を共有し藩民の理解を求めます。復帰した鷹山は町民、農民、下級武士からも意見を求める意見箱も設置しました。藩民の知恵と力を合わせて再建する道が開かれたのです。藩政のトップも反対しませんでした。「堰作り」を投書した武士にすべてを任せて実行、水の確保もできました。絹糸は織物に商品化。織り手は武家の子女、商品の流れが始まりました。鷹山はこうして米沢の土地と人に息を吹き込み、大地も人も豊かな藩へと導いていったのです。
ここには書き切れず、複雑な全体が見えてきませんが、2冊共に、藩の置かれた特異な状況、改革の実例、自然環境、幕藩体制、米から通貨へ移り変わろうとする江戸の経済状況など細かく、視野を広げて書いてあります。特に藤沢周平の経済の細かなデータの記述は古文書をやっていると参考になりました。
鷹山の「藩主は藩と領民の安全のためにある」「藩主の贅沢を維持するために、藩と領民があるのではない」という、人権、民主の思想があったことは驚愕でした。
この頃儒学は官学の朱子学と、対する伊藤仁斎、荻生徂徠の三派が主流。細井平洲はそれぞれの長所を採用する折衷派で「訓詁の学識よりも、修身経世の実践を尊ぶ」ものでした。その師の教えを幼い時から学んだという事が、根っこのところで鷹山の思想を形成したものでしょう。
『漆の実のみのる国』を読み終えて、再度『小説・上杉鷹山』を読み直しました。細井門下の竹俣当綱、莅戸(のぞき)善政、木村高広、藁科松柏などの個性的な藩士の能力を見いだし登用したところ、前例の失敗を分析する冷静さなど、鷹山はリーダーとしての手腕を持ち合わせていました。両方を読めばこの中に出てくる名前にもすっかり親しみを覚えました。
『成せば成る、成さねば成らぬ何事も、成らぬは人の成さぬなりけり』有名な鷹山公の言葉です。
ちなみにケネディが鷹山を知ったのは、内村鑑三の5人の『代表的日本人』の英訳の本から。その5人に鷹山が入っていたのです。