 昔、むかしの小学生時代の話。小学校高学年の国語の教科書に出てきた「解体新書」「杉田玄白」「前野良沢」「腑分け」「ターヘル・アナトミア」の文字とその扉絵。数十年を経てもなお頭の片隅にこびりついていました。とにかく苦労して苦労して強い意志だけで歴史的偉業を成し遂げた偉人伝みたいな話だったように記憶しています。
昔、むかしの小学生時代の話。小学校高学年の国語の教科書に出てきた「解体新書」「杉田玄白」「前野良沢」「腑分け」「ターヘル・アナトミア」の文字とその扉絵。数十年を経てもなお頭の片隅にこびりついていました。とにかく苦労して苦労して強い意志だけで歴史的偉業を成し遂げた偉人伝みたいな話だったように記憶しています。
玄白は歴史的にも日の目を見ていますが、なぜか良沢は日の当たらない場所に・・・という疑問がずっとありました。その謎解きをしてくれる本を偶然に書店で見つけました。吉村昭著『冬の鷹』です。正確にはその「偶然」は、ももりさんのブログで吉村昭の書評がよく出てきて、その作家の著作を探していた時に「偶然」に見つけたのです。
..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..
良沢(中津藩医)と玄白(若狭小浜藩医)はそれぞれに解剖図の載っている『ターヘル・アナトミア』の本を所持していました。1771年、医学に志を持つ玄白、良沢、中川淳庵らが骨が原の罪人の腑分けを実見すると、『ターヘル・アナトミア』の解剖図や骨格図と完全に一致しており、それまでの中国から伝わる五臓六腑の解剖図とは全く異なっているのに驚愕を受けます。激しい熱意を持って玄白は、良沢に『ターヘル・アナトミア』の翻訳を提案すると、以前よりオランダ語の翻訳に強い宿願を持っていた良沢も感動をもって賛同します。
良沢はオランダ語が少しはわかるものの、玄白と淳庵はABCからスタートという最悪の条件のもと、「櫓も舵もない船で大海に乗り出す」ことになったのです。頼みの綱は長崎時代に自分でまとめた300語ほど蘭語の記録と、700語ほどの青木昆陽著『和蘭文字略考』と、ピートル・マリンの『仏蘭辞書』だけです。(25年後に、ようやくオランダ語を日本語に訳した6万5千語ほどの「ハルマ和解」ができあがります)
手探りの翻訳は遅々として進みません。たとえば解剖図の「頭」の部分に『het Hoofd is de opperste holligheid.』とあります。良沢の乏しい語学力でわかるのは、Hoofdとisとdeで「頭とは・・・・・也」のみ。数日してやっとマリンの辞書でoppersteという綴りを発見しますが、その語に付記されたオランダ語の説明文もわからず、良沢の苦しみは増すばかりでした。
気を奮い立たせて説明文の単語を一語ずつマリンの仏蘭辞書で探していきます。oppersteという一語を究明するのに説明文が網の目のように広がっていくのです。いたずらに日が過ぎてわかた事は「最も上」ということ。holligheidとhetもやっと解明できて、「上体は頭顱なり」の短い文が初めて出来上がりました。オランダ通詞の力も借りずに、マリンの辞書を使って独力で単語を解明できたことは、良沢に自信と明るさをもたらしました。しかしまだまだこのような作業が249ページ余り続くことになります。ちなみに長崎一の大通詞と言われる人でも、話す方はいいとしても読解力はほとんどなかったとか。
良沢は孤独を好み、他人と共同作業のできない気難しい性格であることを玄白は知り抜いていましたが、良沢の存在なしには翻訳が成功しないこともわかっています。訳語を探して深みに陥った良沢の心身を解きほぐしたり、天性のひらめきで訳語のアドバイスをしたり、展開させたり、良沢も玄白のその能力を評価していました。
こうしてつらく厳しい翻訳作業も2年余りで一応の目途がついたのですが、このときから良沢と玄白の生き方の違いがはっきり浮き出て、それぞれの人生は二つの方向に大きく分かれてしまうとになりますす。
翻訳が終わった段階で玄白は、まず幕府の反応を見るために解剖図のみをまとめた『解体約図』を世に出すことを提案しますが、学究肌の良沢は完全な翻訳ではないことを懸念して自分の名前を出すことを拒否し、玄白が名声を得る手段として翻訳に参加したのだろうと不快感を示します。しかし玄白にすれば、訳語の不備よりもそれまでの東洋医学から西洋医学へ大きく転換し、医学界に大きく寄与する事が大切だと主張して、訳者に良沢の名前はないままに刊行されることになります。
 『解体新書』には、解剖図と人体図も平賀源内の紹介により小野田直武が原画を描き(これは後世に貴重な学術的記録となります)、『解体約図』の評判がよかった1年後の1774年に刊行されます。もちろんここにも良沢の名前は載せないままに。そしていつしか玄白と良沢の交流も途絶えてしまいます。
『解体新書』には、解剖図と人体図も平賀源内の紹介により小野田直武が原画を描き(これは後世に貴重な学術的記録となります)、『解体約図』の評判がよかった1年後の1774年に刊行されます。もちろんここにも良沢の名前は載せないままに。そしていつしか玄白と良沢の交流も途絶えてしまいます。
この鎖国の時代に横文字の混じった書物の出版は禁制で、その罪が自分たちばかりか藩主にまで及ぶ場合もあリ得ると、ここで玄白は慎重な計画をたてます。
玄白の幅広い交流を利用して、将軍家治に本を献上し、別に老中にも献上、さらに公家方へも献上して、賞賛を得て出版は公然と認められました。
『解体新書』の序文を良沢と交流のあった長崎大通詞、吉雄幸左衛門が書き、その中に良沢の努力とその意義を激賞していることで、どうにか良沢も翻訳にかかわったことが世に示されることになります。これ以降、人嫌いの良沢は弟子をとることもせずに、ひたすらオランダ語の翻訳にのめりこんでいきます。
社交的な玄白には学問を乞う人も多く、開いた天真楼塾からは大槻玄沢のような素晴らしい学者が排出し、後継者に娘婿の優秀な伯元を得て、玄白自身は江戸屈指の流行医になり、富は日を追って増していきます。家族や弟子たちに囲まれた華やかで陽光きらめく人生で、歴史の中にもくっきりと名を残しました。した。
他方良沢は、藩主から下賜された蘭書『プラクテーキ』を1年足らずで読み終えますが、それを出版する気などみじんもありません。人を寄せ付けずただオランダ語の翻訳に没頭し、そのことだけに意義を感じている毎日で、患者を得ようという気持ちも薄く、藩医としての収入だけの貧しい生活でした。その上幼い時に亡くした長女に続き長男を亡くし、続いて妻も亡くし、家督を養子に譲ったあとは、一人で借家住まいの孤高な暮らしに入ります。雪に埋もれた借家暮らしの弱り果てた良沢をたった一人残った娘が引き取り、最後はそこで80歳の生涯を終えます。玄白に比べると、目的だけを貫き通した孤独で静かで、家族にも早く分かれてしまった人生でした。
1冊を読み終えてどちらの生き方がいいというものでなく、良沢と玄白があったからこそ『解体新書』は出来上がったのだと思います。。翻訳は良沢中心だったかもしれませんが、それを継続させていったのは玄白の統率力によるものでしょう。それに玄白には翻訳の最中でもイメージを的確に把握するひらめきや考えをまとめる能力があったように思います。玄白の翻訳の参加の動機は、良沢が疑った名声のためばかりでなく、骨が原の腑分けの驚愕が示したように医家としての使命感もそれに負けないくらいあったと思います。しかし、良沢の生き方には胸が詰まるものがあり、やはり良沢は応分の評価がなされていないというところに胸苦しさと悔しさを覚えます。
『解体約図』の出版に際し将軍に献納するときの時代背景として田沼意次や松平定信が登場し、良沢と関係の深かった勤王派の高山彦九郎が登場して、ストーリーに横の広がりが見られます。子供の頃「偉人伝」で読んだ平賀源内が、学究を目指す翻訳グループの間では鼻持ちならぬ人物としてとらえられているのも意外でした。
..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜..:。:.::.*゜:.。:..:*゜
古文書関係の方から、2011年11月26日の西日本新聞のコピーをいただきました。「 『解体新書』より87年も古い解剖書 」 というビックリのタイトルが目に飛び込んできました。
------------------ 内容要約 -------------------------------------------------------------
原三信は初代福岡藩主、黒田長政の藩医を努め、代々襲名し、偉業を継承してきました。6代目が藩命で長崎に留学し、1685年オランダ語による医師免状を受け取り、それには外科医術を学びよく理解した事を認めると書いてあるそうです。1687年にはドイツ人医師レメリンによる解剖書を筆写、解説書も和訳して藩に持ち帰りました。日本初の西洋解剖書『解体新書』よりも三信の写本は87年も早いことになります。
「キリシタンが弾圧され洋書の輸入も禁じられていた時代。原家では免状とともに和訳した解剖書は『一子相伝、門外不出』として錠前の付いたきり箱に厳重に保管してひそかに受け継いできた」ということです。
----------------------------------------------------------------------------------------------
同じ福岡の地で・・・、というのが私には誇らしく思われます。洋書禁止の当時には秘密裡ということもあるでしょうし、名家の秘伝ということも納得できます。このような隠れた資料が続々と出てくるのを待っています。
今、能古博物館で免状や写本が展示されているということです。

 数年前に、平野啓一郎『葬送』(全4巻)を読みました。
数年前に、平野啓一郎『葬送』(全4巻)を読みました。

















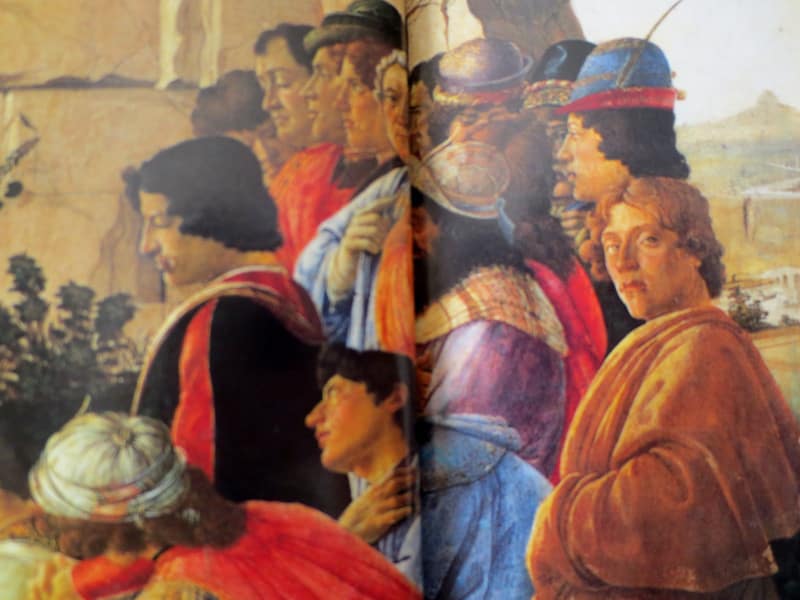

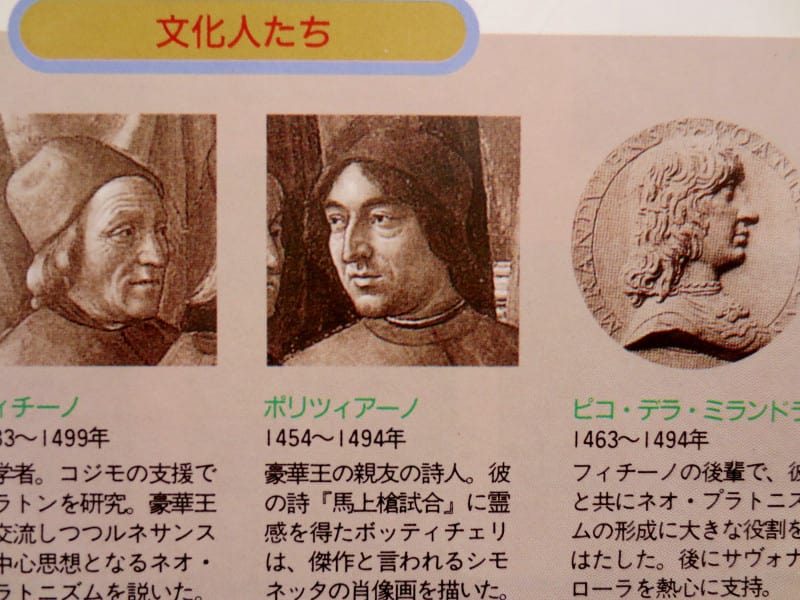




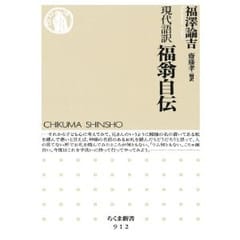
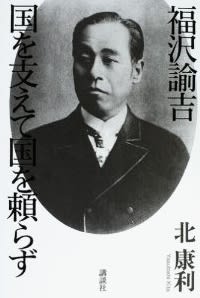


 松田翔太扮する破天荒な雅仁親王(のちの後白河天皇)の登場は度肝を抜くほど印象的でした。その後白河天皇の事を書いた本が
松田翔太扮する破天荒な雅仁親王(のちの後白河天皇)の登場は度肝を抜くほど印象的でした。その後白河天皇の事を書いた本が








