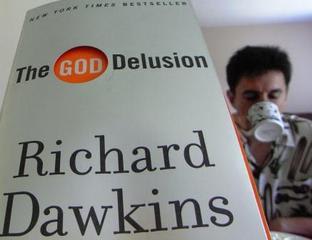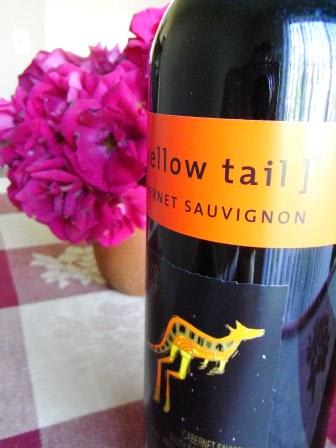1980年。シカゴ市内の何店かのレストランが当時の市長に、7月4日独立記念日にシカゴ市内で「食の祭典」を開こうと持ちかけて始まったのが“Taste of Chicago”。
“build it and they will come(それを作れば彼らはやって来る)”の精神にのっとり、15万ドル(当時のレート$=250円計算で約3,750万円)の予算でスタートしたこの祭典には、初年度には25万人が訪れ、33万ドルの売り上げをあげて大成功のうちに終了した。
初年度のあまりの人出の多さに、翌年からは場所をこれまでのミシガン通りからグラント・パークに移し、以来、“食”のみならず各ジャンルの音楽、加えてファミリーが楽しめるミニ遊園地などのエンターテイメントの要素も加わり、今では“America’s City Picnic”と呼ばれるようになった。
今年で27年目を迎えることとなったこの“Taste of Chicago”。
満を持しての初日、二日目のレポートでござります。
そもそもアメリカで“食”に対する期待はまずもっていない私。
一番のお楽しみはなんと言ってもオールフリーのライブミュージック、そして今が一番美しいシカゴの夏を満喫することにあり。
6月27日(金)
初日は今にもストームが来そうな雲行き。
でもかえってすごしやすく、風が肌に気持ちいい。

摩天楼をバックにこんな自然植物園があることは、あまり知られていない。

地元の人たちは、こうやって喧騒を離れ涼を求めてゆっくりとすごしている


一歩イベント会場に入ると、もうそこはお祭り。
クッキングショーのライブもあってぶらぶらとみているだけでも楽しい。

インターナショナル・パビリオンでMuntu Danceというアフリカンダンスを見る
人間の肉体は、本当に美しい。
そして、いよいよ今日のお目当てチャカ・カーンを見にメインステージへ。
チャカ・カーンはシカゴの黒人街で生まれ育ったローカル歌手なだけに、地元での人気はものすごい。どこを見渡しても、観客は黒人一色。もちろん、アジア系などいやしない。
今日はひとりなので、芝生ではなくフロントステージ席にチャレンジ。開演前30分ほど並んだだけで難なく入れた。

運よく前から10列目くらいに席を見つけることができた。
遠くかなたの芝生席まで埋め尽くした人・人・人・・・

前座をつとめた、Angie Stone

え?これがチャカ・カーン?と目を疑うほど巨大化していたチャカ。
昔(といってももうかれこれ25年も前だけど)から比べると3倍にはなってるかも。
それだけにパワーは増していた。

ステージ横でず~っと観客に手話で歌詞を伝えていた彼女。
アメリカでは、教会に行ってもどこに行ってもかならずといっていいほど手話トランスレーターが舞台の片隅で一語一句を伝えている。
大変な仕事だ。彼女の表情や動きがあまりにも美しくて、見とれてしまう。

Angieと一緒に
最後はもちろん往年のヒット曲↓を全員で歌う。
最後まで見ていたら、思わず電車の時間ぎりぎりになってしまった。
あわててタクシーに飛び乗りプラットフォームに滑り込んだその瞬間、電車が出て行った・・・そして、1時間待ち。
「乗り過ごした~」とPちゃんに泣きの電話を入れ、11時前に家にたどり着いたのであった。
さぁ、下見はバッチリ。
明日はスティービー・ワンダーだ。
(つづく)
“build it and they will come(それを作れば彼らはやって来る)”の精神にのっとり、15万ドル(当時のレート$=250円計算で約3,750万円)の予算でスタートしたこの祭典には、初年度には25万人が訪れ、33万ドルの売り上げをあげて大成功のうちに終了した。
初年度のあまりの人出の多さに、翌年からは場所をこれまでのミシガン通りからグラント・パークに移し、以来、“食”のみならず各ジャンルの音楽、加えてファミリーが楽しめるミニ遊園地などのエンターテイメントの要素も加わり、今では“America’s City Picnic”と呼ばれるようになった。
今年で27年目を迎えることとなったこの“Taste of Chicago”。
満を持しての初日、二日目のレポートでござります。
そもそもアメリカで“食”に対する期待はまずもっていない私。
一番のお楽しみはなんと言ってもオールフリーのライブミュージック、そして今が一番美しいシカゴの夏を満喫することにあり。
6月27日(金)
初日は今にもストームが来そうな雲行き。
でもかえってすごしやすく、風が肌に気持ちいい。

摩天楼をバックにこんな自然植物園があることは、あまり知られていない。

地元の人たちは、こうやって喧騒を離れ涼を求めてゆっくりとすごしている


一歩イベント会場に入ると、もうそこはお祭り。
クッキングショーのライブもあってぶらぶらとみているだけでも楽しい。

インターナショナル・パビリオンでMuntu Danceというアフリカンダンスを見る
人間の肉体は、本当に美しい。
そして、いよいよ今日のお目当てチャカ・カーンを見にメインステージへ。
チャカ・カーンはシカゴの黒人街で生まれ育ったローカル歌手なだけに、地元での人気はものすごい。どこを見渡しても、観客は黒人一色。もちろん、アジア系などいやしない。
今日はひとりなので、芝生ではなくフロントステージ席にチャレンジ。開演前30分ほど並んだだけで難なく入れた。

運よく前から10列目くらいに席を見つけることができた。
遠くかなたの芝生席まで埋め尽くした人・人・人・・・

前座をつとめた、Angie Stone

え?これがチャカ・カーン?と目を疑うほど巨大化していたチャカ。
昔(といってももうかれこれ25年も前だけど)から比べると3倍にはなってるかも。
それだけにパワーは増していた。

ステージ横でず~っと観客に手話で歌詞を伝えていた彼女。
アメリカでは、教会に行ってもどこに行ってもかならずといっていいほど手話トランスレーターが舞台の片隅で一語一句を伝えている。
大変な仕事だ。彼女の表情や動きがあまりにも美しくて、見とれてしまう。

Angieと一緒に
最後はもちろん往年のヒット曲↓を全員で歌う。
最後まで見ていたら、思わず電車の時間ぎりぎりになってしまった。
あわててタクシーに飛び乗りプラットフォームに滑り込んだその瞬間、電車が出て行った・・・そして、1時間待ち。
「乗り過ごした~」とPちゃんに泣きの電話を入れ、11時前に家にたどり着いたのであった。
さぁ、下見はバッチリ。
明日はスティービー・ワンダーだ。
(つづく)












 photo by http://news.sky.com
photo by http://news.sky.com (courtesy by Ac・Rock)
(courtesy by Ac・Rock) (courtesy by Ac・Rock)
(courtesy by Ac・Rock)