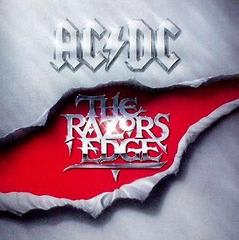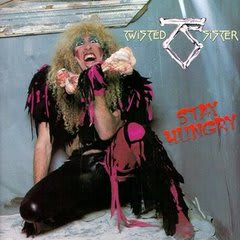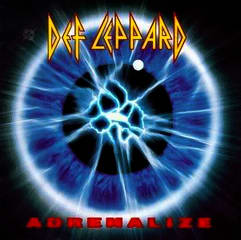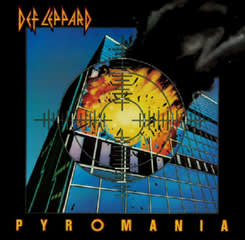この2枚組CD のディスク1が1995年にリリースされたベスト盤「ヴォールト」と選曲・曲順がほぼ同じという “ヒット曲集” なのに対し、ディスク2はさながら “裏ベスト” 的な様相を呈している。選曲に関して言えば、「ナウ」や「ワーク・イット・アウト」を入れるぐらいなら「カミン・アンダー・ファイアー」や「デモリッション・マン」を、カヴァーなら「ノー・マター・ホワット」なんかよりも絶対に「アクション」を入れろよ!とは思うが、こればっかりは個人的な嗜好の問題なので自家製ベストを CD-R に焼いて楽しんでいる。ということで、今日はディスク2からお気に入りのナンバー5曲をピックアップ;
②「レット・イット・ロック」
彼らの 2ndアルバム「ハイ・アンド・ドライ」からはこのベスト盤に6曲も収録されているのだが、その “隠れ名盤” の1曲目を飾っていたのがこの「レット・イット・ロック」だ。バンドが頂点に向かって駆け上がっていく勢いを感じさせるハイスピード・チューンで、プロデューサーが同じロバート・ジョン・マット・ラングということもあって、ラフで荒々しいヴォーカル、ソリッドなギター、パワフルなドラムスから武骨なバック・コーラスに至るまで、同時期に大ヒットしていた AC/DC の「バック・イン・ブラック」を彷彿とさせるものがある。マット・ラングが徹底的に贅肉を削ぎ落としてガチガチに磨き上げたその硬質なサウンドは実にスリリングだ。
Def Leppard - Let It Go
③「ハイ・アンド・ドライ」
2nd アルバムのタイトル曲「ハイ・アンド・ドライ」は、そのヘヴィーな曲想といい、シャープな音作りといい、「バック・イン・ブラック」(1980)に続いてマット・ラングがプロデュースした AC/DC の全米№1アルバム「悪魔の招待状」(1981)に入れたらぴったりハマりそうなタテノリ・ロックだ。古い音源ほどリマスターによる音質向上が目覚ましいのは理の当然だが、手持ちの「ハイ・アンド・ドライ」旧規格CDでは情けないぐらいの薄っぺらい音しか聴けなかっただけに、②③と立て続けに聴いてみてまるで違うテイクを聴いているかのような錯覚に陥ってしまった。ホンマにテクノロジーの進化は凄いわ... (≧▽≦)
Def Leppard - High 'N' Dry #Saturday Night# #HQ#
①「ロック・ロック」
名作「パイロメニア」の1曲目を堂々と飾っていたのがこの「ロック・ロック」という曲。私は一連のビデオ・クリップでレップスを知り、「フォトグラフ」、「ロック・オブ・エイジズ」、「フーリン」といったシングル曲目当てで「パイロメニア」を買ったのだが、いきなり予想もしていなかったこの曲のパワーに圧倒されてブッ飛んだのを今でもよく覚えている。何と言ってもイントロのシンセを切り裂くように炸裂するギラギラしたギターがめちゃくちゃカッコイイし、若き日のジョー・エリオットのハイトーン・シャウトも生々しい。ノリ一発でガンガン攻める姿勢が名演を生んだのだろう。どこを切っても熱いロック・スピリットが迸り出るような、タイトル通りのストレートアヘッドな疾走系ロックンロールだ。
Def Leppard Rock! Rock! Till You Drop Music video
⑧「ウィミン」
この曲は「パイロメニア」の大ヒットを受けて4年ぶりにリリースされた待望のアルバム「ヒステリア」からの 1st シングルということで期待も大きかったのだが、全米チャートでは全くの不発(←何と80位までしか上がらんかった...)に終わってしまい、そのせいか過小評価されているキライがある。まぁ一般ピープルにとってはサウンドが余りにもヘヴィーすぎるし、 “女、女、女なしでは生きられない~♪” などというこっ恥ずかしい歌詞(笑)もラジオではかかりにくいのでシングルには向かないとは思うが、綿密に練り上げられた重厚でスケールのデカいサウンド・プロダクションといい、ブリティッシュ・ロックらしいエモーショナルなギター・ソロといい、私にとっては「ヒステリア」の中で5指に入る愛聴曲。特に後半部の盛り上がりようは凄まじく、幾重にも重なっていくリフレインのヘヴィーネスは痛快無比だ。
Def Leppard - Women
⑩「スラング」
1996年にリリースされたアルバム「スラング」は当時の音楽界を席巻していたグランジ/オルタナ・ロックに迎合したかのようなダークな作風や、収録曲のクオリティーが過去の作品群と比べて遥かに落ちるせいもあってあんまり好きになれないが、このタイトル曲だけは別。最初、ファンキーなリズム・カッティングが生み出すモダンなビートに乗ってジョー・エリオットのラップ調ヴォーカルが飛び出してきた時は “何じゃいコレは...(゜o゜)” と思ったが、何度も聴くうちに脳内リフレインを起こし、 “コレはコレでめっちゃオモロイやん!” とすっかり気に入ってしまった。ラップ/ヒップホップは私が生理的に受け付けない音楽ジャンルの一つなのだが、レップスの手にかかると楽しく聴けてしまうのだからあら不思議... 彼らならではのポップなメロディー・センスと美麗コーラス・ワーク、そして息もつかせぬパワー・コードの波状攻撃が、有象無象の凡百ヒップホップ・ロックとは激しく一線を画すカッコ良いダンサブル・ロック・ナンバーに仕上げているのだ。とにかく騙されたと思ってこの曲をリピート再生してみて下さい... 絶対にハマりまっせ(^o^)丿
Def Leppard - Slang Official Music Video 潤・1996
②「レット・イット・ロック」
彼らの 2ndアルバム「ハイ・アンド・ドライ」からはこのベスト盤に6曲も収録されているのだが、その “隠れ名盤” の1曲目を飾っていたのがこの「レット・イット・ロック」だ。バンドが頂点に向かって駆け上がっていく勢いを感じさせるハイスピード・チューンで、プロデューサーが同じロバート・ジョン・マット・ラングということもあって、ラフで荒々しいヴォーカル、ソリッドなギター、パワフルなドラムスから武骨なバック・コーラスに至るまで、同時期に大ヒットしていた AC/DC の「バック・イン・ブラック」を彷彿とさせるものがある。マット・ラングが徹底的に贅肉を削ぎ落としてガチガチに磨き上げたその硬質なサウンドは実にスリリングだ。
Def Leppard - Let It Go
③「ハイ・アンド・ドライ」
2nd アルバムのタイトル曲「ハイ・アンド・ドライ」は、そのヘヴィーな曲想といい、シャープな音作りといい、「バック・イン・ブラック」(1980)に続いてマット・ラングがプロデュースした AC/DC の全米№1アルバム「悪魔の招待状」(1981)に入れたらぴったりハマりそうなタテノリ・ロックだ。古い音源ほどリマスターによる音質向上が目覚ましいのは理の当然だが、手持ちの「ハイ・アンド・ドライ」旧規格CDでは情けないぐらいの薄っぺらい音しか聴けなかっただけに、②③と立て続けに聴いてみてまるで違うテイクを聴いているかのような錯覚に陥ってしまった。ホンマにテクノロジーの進化は凄いわ... (≧▽≦)
Def Leppard - High 'N' Dry #Saturday Night# #HQ#
①「ロック・ロック」
名作「パイロメニア」の1曲目を堂々と飾っていたのがこの「ロック・ロック」という曲。私は一連のビデオ・クリップでレップスを知り、「フォトグラフ」、「ロック・オブ・エイジズ」、「フーリン」といったシングル曲目当てで「パイロメニア」を買ったのだが、いきなり予想もしていなかったこの曲のパワーに圧倒されてブッ飛んだのを今でもよく覚えている。何と言ってもイントロのシンセを切り裂くように炸裂するギラギラしたギターがめちゃくちゃカッコイイし、若き日のジョー・エリオットのハイトーン・シャウトも生々しい。ノリ一発でガンガン攻める姿勢が名演を生んだのだろう。どこを切っても熱いロック・スピリットが迸り出るような、タイトル通りのストレートアヘッドな疾走系ロックンロールだ。
Def Leppard Rock! Rock! Till You Drop Music video
⑧「ウィミン」
この曲は「パイロメニア」の大ヒットを受けて4年ぶりにリリースされた待望のアルバム「ヒステリア」からの 1st シングルということで期待も大きかったのだが、全米チャートでは全くの不発(←何と80位までしか上がらんかった...)に終わってしまい、そのせいか過小評価されているキライがある。まぁ一般ピープルにとってはサウンドが余りにもヘヴィーすぎるし、 “女、女、女なしでは生きられない~♪” などというこっ恥ずかしい歌詞(笑)もラジオではかかりにくいのでシングルには向かないとは思うが、綿密に練り上げられた重厚でスケールのデカいサウンド・プロダクションといい、ブリティッシュ・ロックらしいエモーショナルなギター・ソロといい、私にとっては「ヒステリア」の中で5指に入る愛聴曲。特に後半部の盛り上がりようは凄まじく、幾重にも重なっていくリフレインのヘヴィーネスは痛快無比だ。
Def Leppard - Women
⑩「スラング」
1996年にリリースされたアルバム「スラング」は当時の音楽界を席巻していたグランジ/オルタナ・ロックに迎合したかのようなダークな作風や、収録曲のクオリティーが過去の作品群と比べて遥かに落ちるせいもあってあんまり好きになれないが、このタイトル曲だけは別。最初、ファンキーなリズム・カッティングが生み出すモダンなビートに乗ってジョー・エリオットのラップ調ヴォーカルが飛び出してきた時は “何じゃいコレは...(゜o゜)” と思ったが、何度も聴くうちに脳内リフレインを起こし、 “コレはコレでめっちゃオモロイやん!” とすっかり気に入ってしまった。ラップ/ヒップホップは私が生理的に受け付けない音楽ジャンルの一つなのだが、レップスの手にかかると楽しく聴けてしまうのだからあら不思議... 彼らならではのポップなメロディー・センスと美麗コーラス・ワーク、そして息もつかせぬパワー・コードの波状攻撃が、有象無象の凡百ヒップホップ・ロックとは激しく一線を画すカッコ良いダンサブル・ロック・ナンバーに仕上げているのだ。とにかく騙されたと思ってこの曲をリピート再生してみて下さい... 絶対にハマりまっせ(^o^)丿
Def Leppard - Slang Official Music Video 潤・1996