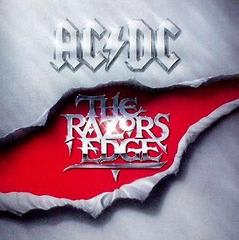
一昨日から我が朋友のサムは2週間のタイ旅行に出かけた。長いこと海外旅行に行っていない私としてはホンマに羨ましい限りだが、今日はそんな彼女の旅の安全を祈って(?)オーストラリアが生んだ最強のロックバンド、 AC/DC にしよう。
私は洋楽を聴き始めてすぐにレッド・ゼッペリンやディープ・パープルの洗礼を受け、70年代はキッスやエアロスミス、80年代に入ってもデフ・レパードやモトリー・クルーといったハードロック・バンドを聴きながら過ごしてきたのだが、AC/DC はそんな中でも特別な存在だった。ジャズに “スイング” が必須なようにロックに “ノリ” は欠かせない。十年一日のごとくヘビメタ特有の “様式美” に拘るバンドが多い中、AC/DC は原始的とも言える激しいタテノリ・グルーヴでロックの初期衝動を感じさせてくれる稀有なバンドなのだ。
彼らはロバート・ジョン・マット・ラングがプロデュースした「バック・イン・ブラック」(1980年)と「悪魔の招待状」(81年)という2枚の大ヒット・アルバムで80年代初頭に頂点を極めた感があったが、続く「征服者」(83年)と「フライ・オン・ザ・ウォール」(85年)はセルフ・プロデュースが裏目に出たのかキャッチーさに欠けるへヴィーな内容でセールス的にも苦戦した。しかし80年代後半に入ってバンドは不振を脱し、88年の「ブロウ・アップ・ユア・ビデオ」では70年代の彼らを想わせるような疾走系ロックンロールが復活、まだプロデュースに甘さは残るものの、シングル・カットされた「ヒートシーカー」と「ザッツ・ザ・ウェイ・アイ・ウォナ・ロックンロール」の2曲は私のロック魂のスイート・スポットを直撃し、私は久々の快作に大喜びしたものだった。
そうこうしているうちに80年代も終わり、1990年の9月にいきなりドッカーン!と登場したのがこの「ザ・レイザーズ・エッジ」だった。一聴して感じたのはライヴ感溢れる骨太な音作りがAC/DC の持ち味を巧く引き出しているということで、ボン・ジョヴィをスターダムに押し上げエアロスミスを復活させた必殺仕事人、ブルース・フェアバーンのプロデュースによってゴージャスでキャッチーなアルバムに仕上がっている。
個々の楽曲では何と言ってもアルバム冒頭に置かれた①「サンダーストラック」である。イントロの “テロレロテロレロ テロレロテロレロ~♪” という一度聴いたら忘れられないようなリフに “アァァア~アァ♪” というコーラスが被さり、 “サンダー!!!” の雄叫びが炸裂する時の快感を何と表現しよう! この風雲急を告げるムード、ワクワクするような高揚感、ただならぬ殺気を身体全体で感じ、その凄まじいグルーヴに身を委ねれば自然と頭が上下動してしまうという最高のヘッドバンギング・ナンバーだ。初めてこのアルバムを聴いた時、いきなりこの「サンダーストラック」にカンプなきまでに打ちのめされたのを今でもハッキリと覚えている。
②「ファイアー・ユア・ガンズ」もめっちゃスリリング。 “ジャララ ジャラララ ジャッジャジャッ♪” という超カッコ良いリフにシビレる痛快無比なロックンロールで、メロディアスに疾走するという一見誰にでも出来そうで中々出来ないことをやっているのが凄い。最高傑作アルバム「バック・イン・ブラック」に入っていた「シェイク・ア・レッグ」や「ギヴン・ザ・ドッグ・ア・ボーン」を彷彿とさせるようなテンションの高さもハンパではない。やっぱり AC/DC はこうでなくっちゃ(^o^)丿
①②のインパクトが強烈過ぎてどうしても残りの曲がやや地味に聞こえてしまうのだが、そんな中では⑥「ロック・ユア・ハート・アウト」がお気に入り。 “ジャンジャンジャン ジャッ ジャッ ジャッジャ♪” というリフと闊達なベースラインが印象的で、AC/DC らしさ全開の1曲だ。ミディアム・テンポの⑦「アー・ユー・レディ」は90年代の「悪魔の招待状」的なロック・アンセムでライヴでの大合唱にピッタリだし、⑨「ショット・オブ・ラヴ」もその後の「スティッフ・アッパー・リフ」へと繋がるようなグルーヴを持った佳曲だと思う。
90年代に入って完全に低迷期を脱した AC/DC はその後まさにロック・アイコンとして時代を超越した存在になっていくのだが、この「ザ・レイザーズ・エッジ」はそんな彼らの復活を強く印象付けた1枚なのだ。
AC/DC - Thunderstruck [HQ]
AC/DC - Fire your Guns (HQ)
AC/DC Rock Your Heart Out Music Video (Semi-Rare Video)
私は洋楽を聴き始めてすぐにレッド・ゼッペリンやディープ・パープルの洗礼を受け、70年代はキッスやエアロスミス、80年代に入ってもデフ・レパードやモトリー・クルーといったハードロック・バンドを聴きながら過ごしてきたのだが、AC/DC はそんな中でも特別な存在だった。ジャズに “スイング” が必須なようにロックに “ノリ” は欠かせない。十年一日のごとくヘビメタ特有の “様式美” に拘るバンドが多い中、AC/DC は原始的とも言える激しいタテノリ・グルーヴでロックの初期衝動を感じさせてくれる稀有なバンドなのだ。
彼らはロバート・ジョン・マット・ラングがプロデュースした「バック・イン・ブラック」(1980年)と「悪魔の招待状」(81年)という2枚の大ヒット・アルバムで80年代初頭に頂点を極めた感があったが、続く「征服者」(83年)と「フライ・オン・ザ・ウォール」(85年)はセルフ・プロデュースが裏目に出たのかキャッチーさに欠けるへヴィーな内容でセールス的にも苦戦した。しかし80年代後半に入ってバンドは不振を脱し、88年の「ブロウ・アップ・ユア・ビデオ」では70年代の彼らを想わせるような疾走系ロックンロールが復活、まだプロデュースに甘さは残るものの、シングル・カットされた「ヒートシーカー」と「ザッツ・ザ・ウェイ・アイ・ウォナ・ロックンロール」の2曲は私のロック魂のスイート・スポットを直撃し、私は久々の快作に大喜びしたものだった。
そうこうしているうちに80年代も終わり、1990年の9月にいきなりドッカーン!と登場したのがこの「ザ・レイザーズ・エッジ」だった。一聴して感じたのはライヴ感溢れる骨太な音作りがAC/DC の持ち味を巧く引き出しているということで、ボン・ジョヴィをスターダムに押し上げエアロスミスを復活させた必殺仕事人、ブルース・フェアバーンのプロデュースによってゴージャスでキャッチーなアルバムに仕上がっている。
個々の楽曲では何と言ってもアルバム冒頭に置かれた①「サンダーストラック」である。イントロの “テロレロテロレロ テロレロテロレロ~♪” という一度聴いたら忘れられないようなリフに “アァァア~アァ♪” というコーラスが被さり、 “サンダー!!!” の雄叫びが炸裂する時の快感を何と表現しよう! この風雲急を告げるムード、ワクワクするような高揚感、ただならぬ殺気を身体全体で感じ、その凄まじいグルーヴに身を委ねれば自然と頭が上下動してしまうという最高のヘッドバンギング・ナンバーだ。初めてこのアルバムを聴いた時、いきなりこの「サンダーストラック」にカンプなきまでに打ちのめされたのを今でもハッキリと覚えている。
②「ファイアー・ユア・ガンズ」もめっちゃスリリング。 “ジャララ ジャラララ ジャッジャジャッ♪” という超カッコ良いリフにシビレる痛快無比なロックンロールで、メロディアスに疾走するという一見誰にでも出来そうで中々出来ないことをやっているのが凄い。最高傑作アルバム「バック・イン・ブラック」に入っていた「シェイク・ア・レッグ」や「ギヴン・ザ・ドッグ・ア・ボーン」を彷彿とさせるようなテンションの高さもハンパではない。やっぱり AC/DC はこうでなくっちゃ(^o^)丿
①②のインパクトが強烈過ぎてどうしても残りの曲がやや地味に聞こえてしまうのだが、そんな中では⑥「ロック・ユア・ハート・アウト」がお気に入り。 “ジャンジャンジャン ジャッ ジャッ ジャッジャ♪” というリフと闊達なベースラインが印象的で、AC/DC らしさ全開の1曲だ。ミディアム・テンポの⑦「アー・ユー・レディ」は90年代の「悪魔の招待状」的なロック・アンセムでライヴでの大合唱にピッタリだし、⑨「ショット・オブ・ラヴ」もその後の「スティッフ・アッパー・リフ」へと繋がるようなグルーヴを持った佳曲だと思う。
90年代に入って完全に低迷期を脱した AC/DC はその後まさにロック・アイコンとして時代を超越した存在になっていくのだが、この「ザ・レイザーズ・エッジ」はそんな彼らの復活を強く印象付けた1枚なのだ。
AC/DC - Thunderstruck [HQ]
AC/DC - Fire your Guns (HQ)
AC/DC Rock Your Heart Out Music Video (Semi-Rare Video)
















