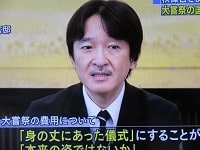23日報道された明仁天皇の最後の記者会見(誕生日会見。実施は20日)をメディアはこぞって最大限に賛美し、「感動した」などの「国民」の声(だけ)を報じました。
しかし、会見内容を分析すると、そうした「賛美」とはまったく逆に、多くの問題を含むきわめて政治的な重大発言であることが分かります。
問題点は少なくとも10あります(こうした政治的発言を行うこと自体、憲法第4条に抵触しますが、ここでは発言内容の問題に絞ります。引用した発言はすべて宮内庁のHPからです)。
① 日本が戦場にならなければ「平和」なのか
「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵しています」
メディアが大きく取り上げた言葉ですが、「平成」すなわち1989年~2018年に、世界で紛争・戦争が絶えなかったことは周知の事実です。にもかかわらず「平成」を「戦争のない時代」と言うのは、日本が戦場にならなかったという意味でしょう。自分の国が戦場にならなければ「戦争のない時代」なのでしょうか。あまりにも自国中心の閉鎖的利己的考えではないでしょうか。
② 日本の戦争加担(参戦)は棚上げするのか
「本土」が戦場にならなくても、日本はアメリカの戦争に加担してきました。米軍の後方基地になった朝鮮戦争やベトナム戦争は「昭和」のことですが、日本も資金提供し自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣した湾岸戦争は1991年(平成3年)のことです。その後、自衛隊の海外派兵は常態化しています。
また、沖縄などで多発している軍事基地被害は、間接的な戦争被害ではないでしょうか。
こうした事実を棚上げして「平成」を「戦争のない時代」というのは、戦争加担の加害責任にほうかむりするものです。
③ 「戦後」は「平和と繁栄」か
「我が国は国際社会の中で…平和と繁栄を築いてきました」「我が国の戦後の平和と繁栄が…築かれた」
「平成」だけでなく「昭和」も含めて「戦後」は「平和と繁栄」の時代だというわけです。ここでは朝鮮戦争やベトナム戦争への加担は完全に捨象されています。また、「繁栄」という言葉によって、深刻な貧困や格差拡大も隠ぺいされています。「戦後」を「平和と繁栄」と賛美するのは戦後政権の座に座り続けてきた自民党政治を美化するものです。
④ 「沖縄」に「心を寄せていく」は本当か
「沖縄は、先の大戦を含め実に長い苦難の歴史をたどってきました」「沖縄の人々が耐え続けた犠牲に心を寄せていく」
「先の大戦」で沖縄を「本土防衛」のための捨て石にしたのは他ならぬ明仁の父・裕仁です。敗戦後、「国体(天皇制)護持」のため沖縄をアメリカに売り渡したのも裕仁です(「沖縄メッセージ」)。
にもかかわらず、明仁天皇は「11回の沖縄訪問」でただの一度も県民に謝罪したことはありません。沖縄に「心を寄せる」というなら、今日に続く沖縄の「苦難」の元凶である裕仁天皇の所業について、子として、皇位を引き継いだ者として、まず謝罪することが出発点ではないでしょうか。
⑤ サ体制(サンフランシスコ「講和」条約・日米安保条約)が肯定できるのか
「その年(1952年・明仁18歳-引用者)にサンフランシスコ平和条約が発効し、日本は国際社会への復帰を遂げ、次々と我が国に各国大公使を迎えたことを覚えています」
こう述べてサ条約と日米安保条約によるサンフランシスコ体制を肯定しました。しかし、サ条約によって在日朝鮮人や台湾人は「外国人」として切り捨てられました。日米安保条約が米軍基地・沖縄の「苦難」の根源であることは言うまでもありません。サ体制を肯定してどうして「沖縄に心を寄せる」でしょうか。
⑥ アジア激戦地巡りは 「慰霊の旅」か
「戦後60年にサイパン島を、戦後70年にパラオのペリリュー島を、更にその翌年フィリピンのカリラヤを慰霊のため訪問したことは忘れられません」
メディアが天皇の「平和」への意思を示すものとして美化するいわゆる「慰霊の旅」です。しかし、天皇・皇后が東南アジアの激戦地を訪れて「慰霊」したのは、戦死した「日本兵」です。
それぞれの激戦地では多くの住民が犠牲になりました。「慰霊」というなら、戦争加害国としてまず日本が被害を与えた現地の人々の墓碑を訪れ、謝罪するのが先ではないでしょうか。しかし天皇・皇后が加害国として現地で謝罪したことはありません。
たとえば、フィリピンには「死の行進」で悪名高いバターン捕虜収容所がありましたが、天皇・皇后がそこを訪れることはありませんでした。
⑦ 日本に住む外国籍の人々は視界にあるのか
「国民皆の努力によって…平和と繁栄を築いてきました」「我が国の戦後の平和と繁栄が、このような多くの犠牲と国民のたゆみない努力によって築かれたものであることを忘れず…」
明仁天皇は「国民」という言葉を多用します。しかし、敗戦後、日本の復興に貢献したのは、「国民」すなわち日本国籍のある人間だけではありません。在日朝鮮人をはじめ、外国籍の人々も、日本で働き、税金を納めてきました。そうした在日外国人は天皇の視界に入っているのでしょうか?
天皇が「国民」という場合、「日本人」を念頭に置いていると思われますが、そうした「国民」の強調は、「単一民族国家」思想を流布するものと言わねばなりません(これは第1条をはじめ現憲法の欠陥でもあります)。
⑧ 天皇の交代で「時代」を区分するのは正当か
「来年春に私は譲位し、新しい時代が始まります」「新しい時代において、天皇となる皇太子と…」
天皇の交代がなぜ「新しい時代」の始まりなのでしょうか。なぜ天皇の交代で「時代」を区分するのでしょうか。天皇にはなんの政治的権限もありません。天皇によって「時代」が区分されるというのは戦前の絶対主義的天皇制・皇国史観の名残ではないでしょうか。
⑨ なぜ「退位」と言わず「譲位」と言うのか
「来年春の私の譲位の日も近づいてきています」「来年春に私は譲位し…」
天皇は「退位」と言わず「譲位」と言います。「退位」と「譲位」では意味が大きく違います。「譲位」とは天皇が自らの意思で天皇の位を皇太子に譲ることです。それは「主権在民」の憲法原則とは相いれません。だから法律名は「退位」であり、政府も「退位」と言わざるをえません。全国紙で「譲位」と言っているのは産経新聞だけです。
この違いにいち早く気付き、「退位」はおかしい、「譲位」と言うべきだと強硬に主張したのは美智子皇后です。明仁天皇はここでも美智子皇后にならって「譲位」という言葉を使っています。それが「主権在民」の憲法に反する発想であることは明白です。
⑩ 天皇が「象徴」の在り方を自分で考え、実行していいのか
「私は即位以来、日本国憲法の下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を求めながらその務めを行い、今日まで過ごしてきました」「天皇となる皇太子とそれを支える秋篠宮は…日々変わりゆく社会に応じつつ道を歩んでいくことと思います」
ここに「平成流」ともてはやされる明仁天皇の言動の根本的問題があります。すなわち彼は、憲法の「象徴天皇制」とはどうあるべきかを自分で考え行動してきたし、それを誇示さえしているのです。
しかし、それは憲法の規定を逸脱するものです。何の政治的権限もない天皇が憲法(「象徴天皇制」)の解釈を自分流に行い、それに基づいて行動することは、憲法前文、第1条、3条、4条、第7条(主権在民、政治的権能、内閣の助言と承認、国事行為)に明白に反します。
にもかかわらず、明仁天皇はそれをやってきた。結果、「公的行為」とか「象徴としての行為」などという脱法的言葉を生み、天皇の独断専行を許してきました。その行きついた果てが「生前退位」の「ビデオメッセージ」です。
しかも明仁天皇は、そうした憲法無視の「平成流」を皇太子や秋篠宮に引き継がせようとしているのです
以上10の問題点を見てきましたが、まとめて言えば、明仁天皇が行ってきたことは、戦争・植民地支配の加害責任の棚上げ・隠ぺいであり、自民党政治の美化であり、対米従属のサ体制・日米安保条約の肯定であり、「天皇君主化」に通じる天皇の独断専行です。今回の会見はその集大成といえるでしょう。
重要なのは、こうした明仁天皇・美智子皇后の言動が、「天皇崇拝」とともに「正しいこと」とされ、日本人の考え方・思想に大きな影響をあたえていることです。
ここに国家権力にとっての「象徴天皇制」の存在価値があり、だからこそ廃止しなければならない理由があります。