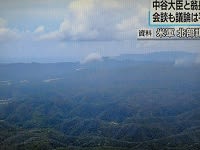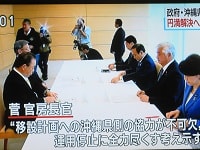歴史的出来事や政治家の評価は、事実に基づいて行われる必要があることは言うまでもありません。歴史の教訓を現在そして未来に生かすためにそれは不可欠です。
8日で翁長雄志前沖縄県知事が死去して1年になりました。沖縄タイムスは8日付の社説で、「命を削るように新基地反対を貫き、沖縄の自治と民主主義を守るため政府と対峙し続けた」と絶賛しました。琉球新報も9日付で、「身をていして沖縄の新たな夜明けを県民に見せてくれた」(呉屋守将・金秀グループ会長)など、翁長氏とゆかりの人々の談話を複数掲載して翁長氏を称えました。
政治家・翁長雄志氏へのこうした賛美は、果たして正当な評価でしょうか。
翁長氏は外見上「政府への抵抗姿勢」を取り続けたように見えますが、実際には辺野古新基地問題をはじめ、いくつもの重要問題で、政府(安倍政権)と正面からたたかわず、むしろ協調してきました。ここでは基地問題に限って、翁長県政の3年半を振り返ってみます(紙幅の関係で簡潔な指摘になります)。
① 辺野古新基地建設とのたたかい回避
a、 公約に反して承認撤回を不履行
翁長氏は「私が当選すれば撤回の理由になる」と公約して当選しましたが、当選後は「埋立承認撤回」を棚上げし続け、ついに在任期間中、自ら「撤回」することはありませんでした。
b、 大型ブロック投入による岩礁破砕を黙認(2015年11月17日)
c、 3つの訴訟をめぐり安倍政権と「和解」(2016年3月4日=写真左)
d、 辺野古の陸上工事を容認(2016年8月31日)
e、 「承認取消」を自ら取り消す(2016年12月26日)
f、 埋立石材搬入のための奥港、本部港、中城湾港の使用を相次いで許可(2017年9~11月)
g、 辺野古で市民を弾圧する機動隊を放置(県公安委員長の任免権は知事にあります)
② 高江ヘリパッド建設を容認
辺野古とともに新基地建設阻止の焦点である高江のヘリパッド(オスプレイ用)建設を、翁長氏は容認しました(2016年11月28日の記者会見)。琉球新報は1面トップで、「知事ヘリパッド容認 事実上の公約撤回」(2016年11月29日付=写真中)と報じました。
③ 浦添米軍基地の県内移設を容認・推進
浦添軍港の移設に市民は反対していますが、翁長氏は那覇市長当時から一貫して容認・推進してきました。米軍基地の県内移設という点では辺野古と変わらず、ダブルスタンダードの批判は免れません。
④ 与那国・宮古・石垣の自衛隊基地建設・増強を容認
県議会での再三の追及にもかかわらず、翁長氏は八重山地域への自衛隊増強について「住民の合意が重要」としながら、反対とは一言も言わず、事実上容認してきました。
⑤ 日米安保条約を一貫して絶賛
翁長氏は一貫して日米安保を賛美し、自らその擁護者であると公言してきました。例えば、辺野古訴訟の第1回口頭弁論(2015年12月2日)では、「日米安保体制を壊してはならない。日米安保を品格のあるものにする」と陳述しました。
在沖米軍トップのニコルソン四軍調整官(当時)との会談では、「日米が世界の人権と民主主義を守ろうというのが日米安保条約だ」(2017年11月21日付沖縄タイムス=写真右)とさえ言いました。
冒頭の翁長氏に対する賛美・評価が事実に反していることは明白ではないでしょうか。
重要なのは、こうした翁長県政に対する誤った評価は、「翁長県政を引き継ぐ」玉城デニー県政のもとでその弊害が増幅される危険性があることです。それは辺野古・高江に限らず、八重山諸島・本島への自衛隊増強、米軍と自衛隊の一体化が進む日米安保の深化に顕著に表れる恐れがあります。
沖縄のみならず日本の平和・民主主義の市民運動の前進にとって、3年7カ月の翁長県政を科学的に分析し、正確な評価は下すことがきわめて重要です。