













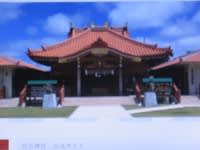
















朝日新聞デジタルは4日、独自記事として、太平洋戦争開戦時に天皇裕仁の側近(侍従長)だった百武三郎(ひゃくたけさぶろう)の日記が見つかったとして、その内容の一部を報じました(写真左、中。同記事より)
そこで明らかになっているのは、裕仁が開戦に「政府や軍部の進言でしぶしぶ同意した」(東京裁判)とされているのとは違い、木戸孝一内大臣らも戸惑うほど、開戦に意欲的で前のめりになっていたことです。
以下、同記事から抜粋します(太字は私)。
天皇は(1941年)9月ごろまでは開戦に慎重な姿勢を示し続けたとされるが、10月13日、百武は日記にこう記した。
宮相本日拝謁(中略)切迫の時機に対し已(すで)に覚悟あらせらるゝが如(ごと)き御様子に拝せらると 先頃来木戸内府も時々御先行を御引止め申上ぐる旨語れることあり 先頃来案外に明朗の龍顔(天皇の顔―私)を拝し稍(やや)不思議に思ふ
松平恒雄(まつだいらつねお)宮内大臣や木戸ら天皇に会った側近から、陛下がすでに覚悟を決め、気持ちが先行している様子だと聞いた。百武から見ても、先ごろから陛下の表情が明るいので不思議に思った――との内容だ。
木戸の日記にも同じ13日、天皇が「万一開戦となる場合、宣戦の詔勅(しょうちょく)を発することとなるだろう」と開戦に触れた発言が記されている。天皇は「開戦を決意する場合、戦争終結の手段を初めから研究しておく必要がある」とも語ったと木戸は書いている。
これに対し、その4日前の10月9日。
博恭(ひろやす)王殿下参内(さんだい)(中略)稍(やや)紅潮御昂奮(こうふん)あらせらるゝ様拝す
海軍軍令部総長を務めた皇族の伏見宮(ふしみのみや)博恭王と対面した後、天皇が顔を紅潮させて興奮した様子だったと百武は記す。議論の内容は翌10日、木戸が天皇から聞いた話として記された。
昨日伏見宮殿下は対米主戦論を主張せられ之れなくば陸軍に反乱起らんとまで申されたる由(中略)又(ま)た人民は皆開戦を希望すとも申されたりと
伏見宮が「米国と戦争しなければ陸軍に反乱が起きる」「人民は開戦を希望している」などと主戦論をぶったという。
さらに11月20日。
内府(木戸)曰(いわ)く上辺の決意行過ぎの如く見ゆ
百武は、天皇が開戦に傾く様子を木戸が懸念したとみられる「陛下の決意が行き過ぎのように見える」との発言を記した。これにつながる二つの出来事が、直前の15日の大本営政府連絡会議であった。
一つは図上で作戦を説明する「兵棋(へいぎ)演習」。真珠湾攻撃を含む作戦計画が天皇に提示されたという。
もう一つが「戦争終末促進に関する腹案」の決定だ。開戦にあたり、戦争をどう終わらせるか研究しておくべきだと考える天皇を説得し、決断を促すため軍部がつくったとみられる。(編集委員・北野隆一)
天皇裕仁は、慣例を破って御前会議で積極的に発言し、開戦を決意すると、「気持ちが先行」し、顔は「明朗」「紅潮興奮」し、木戸らを「決意行過ぎの如く見ゆ」と戸惑わせたというのです。
太平洋戦争開戦から80年。NHKは例年になく様々な番組で「太平洋戦争特集」を組んでいますが、東アジア・太平洋戦争の歴史で最も重要なのは、天皇裕仁の戦争・植民地支配責任であり、それが隠ぺい・棚上げされ、今日の「象徴天皇制」に繋がっている事実です。百武の日記はその一端を示しています。