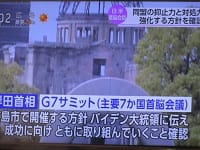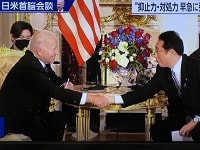

「防衛装備品、輸出を緩和 政府検討 戦闘機も対象に」―28日付日経新聞1面トップにこんな見出しが躍りました。
「政府は今年度内にも防衛装備品の輸出に関する規制を緩和する。戦闘機やミサイルなど大型の装備品でも、個別に協定を結んだ国なら提供できる案を検討する」
政府・自民党はかつての「武器輸出禁止三原則」を安倍晋三政権で撤廃し、「防衛装備移転三原則」(2014年)に変えて武器輸出に道を開きました。ただ、輸出できるものに制限があるため、「その規定を変えて攻撃型の装備も輸出できるようにする」(同「日経」)ものです。
武器とりわけ「攻撃型」兵器の輸出は日本が世界の紛争・戦争を煽る“死の商人”になることであり、絶対に許すことはできません。
見落とせないのは、その「狙い」が「国内防衛産業の維持」(28日付琉球新報=共同通信)にあることです。
「自衛隊しか顧客がなく利益率が低いため事業から撤退する企業が相次ぎ、防衛産業を維持できなくなるとの懸念が政府、与党内で広がったことが背景にある」(同琉球新報)
岸田政権は3月、「ウクライナ支援」として武器の範疇に入る「防弾チョッキ」「ヘルメット」を供与(輸出)しました。これに関し、「自民党では、侵略を受けた国には欧米のように殺傷力のある装備も提供すべきだとの声が上がり、自民党が4月にまとめた提言に三原則の見直しが盛り込まれた」(同)のです。
「ウクライナ戦争」は「NATO(北大西洋条約機構)の東方拡大」と密接に結びついていますが、そもそもNATOと軍事・兵器産業は切っても切れない関係にあります。
「NATOの舞台裏は、各国軍事産業にとって重要な意思疎通の空間なのだ。
軍事産業あるいは土木・建設・水道などインフラ産業界の眼から見るポスト冷戦は、われわれ市民の視点とはまったく違う。軍事産業や欧米のインフラ整備部門、エネルギー資源やそのパイプライン建設など大規模な産業には、地域紛争は新しいタイプの商機であり、有望なマーケットなのだ。
主要国が“マッチポンプ”で意図的に紛争を荒げることはなくても、結果的に“マッチポンプ”になってしまった例はある」(谷口長世著『NATO―変貌する地域安全保障―』岩波新書2000年)
自分で紛争に火をつけ、その鎮火を口実に軍事関与して兵器を売る“マッチポンプ”。ウクライナの「マイダンクーデター」(2014年)に対するアメリカ政府の関与は、意図的な“マッチポンプ”と言わざるをえません(3月28日のブログ参照)。
スウェーデンのストックホルム国際平和研究所が3月公表した「世界の兵器貿易に関する報告書(2017~21年)」によると、2014年以降、欧州各国の兵器輸入が増加し、前回報告書(12~16年)比19%増となっています。欧州各国に兵器を売却した最大の国はアメリカで50%以上を占めました。世界の兵器貿易の輸出全体をみると、米国が断トツで世界シェアの39%を占めています(3月14日の日経新聞デジタル)。
そして今回の「ウクライナ戦争」。
ゼレンスキー大統領は「徹底抗戦」を主張して米欧諸国に兵器の供与を要求し続け、アメリカはじめNATO加盟国・欧州諸国はこれに呼応して兵器を供給し、「兵器のNATO化」が進んでいます(5月17日のブログ参照)。
戦争の裏には軍事産業の商業戦略、国家権力との癒着があります。「ウクライナ戦争」ももちろん例外ではありません。それによって巨額の利益を得ているのはアメリカの軍事産業です。
岸田政権・自民党は軍事同盟(安保条約)でアメリカに従属して戦争国家化を急速に進めるとともに、軍事産業の育成・癒着においてもアメリカに倣おうとしているのです。