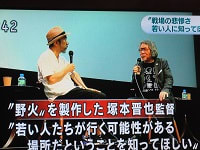山田洋次監督の最新作「母と暮せば」(吉永小百合主演)を観ました。
吉永さんはこの作品に「運命的な出会いを感じる」と語ったことがありますが、観ている方にもそれが伝わってくるようでした。
抑えた演技の中で、原爆・戦争への怒りと平和への祈りが重い光を放っていました。吉永さんの映画のひとつの集大成ではないでしょうか。若い二宮和也さん、黒木華さんの好演も光っていました。
吉永さんは胎内被爆の女性を演じた「夢千代日記」をきっかけに、1986年から各地で原爆詩の朗読を続けています。また、「3・11」以後は原発を告発した詩の朗読も行なっています。「いつまでも『戦後』が続きますように」。吉永さんがよく口にする言葉です。
そんな吉永さんが、この映画の公開直前に掲載された新聞インタビューで、こう述べています。
「でも今、戦争が近くなっているような気がします。とても怖く、何か胸騒ぎのするような」(12月6日付中国新聞=共同)
吉永さんの思いは、雑誌「世界」の最新(1月)号の座談会(山田監督、早野透桜美林大教授と)にいっそう鮮明に表れています。
日本の原発について、こう述べています。
「原発が五四基もつくられていく過程で、大きな声を出さなかったことに対し、私は恥じ入る気持があります」
そして注目されるのが、次の発言です。
「時間が経っても、忘れてはいけないことがあるということですよね。この先の世代の子どもたちには謝罪はどうこうとおっしゃっている方もいますけれども・・・」
明らかに安倍首相(「戦後70年談話」)への批判です。
戦争(安保)法案を強行し、原発を再稼働させ、侵略の歴史を「修正」しようとする安倍政権への厳しいまなざしが、この短い言葉に凝縮されています。
人気・実力ともに文字通り日本を代表する女優(文化人)である吉永さんの、叡智と勇気にあふれた発言に大きな拍手を送ります。
吉永さんにこの叡智と勇気を与えたのは、30年近く続けている原爆詩の朗読であり、その中で接し、知り合った多くの市井の市民ではないでしょうか。
そんな吉永さんに、そんな吉永さんだからこそ、要望・お願いがあります。
吉永さんは広島の被爆詩人・栗原貞子(1913~2005)の「生ましめんかな」を、「大変難しい」と言いながらよく朗読しています。被爆直後の惨状の中での新たな生命の誕生(出産)を詠んだ感動的な詩です。
吉永さんに、同じ栗原貞子の「ヒロシマというとき」をぜひ朗読していただきたいのです。
<ヒロシマ>といえば<パール・ハーバー>
<ヒロシマ>といえば<南京虐殺>
<ヒロシマ>といいえば 女や子供を 壕のなかにとじこめ ガソリンをかけて焼いたマニラの火刑
<ヒロシマ>といえば
血と炎のこだまが 返って来るのだ
(中略)
<ヒロシマ>といえば
<ああ ヒロシマ>と やさしいこたえがかえって来るためには
わたしたちは
わたしたちの汚れた手を きよめなければならない
「ヒロシマというとき」は、15年戦争の日本の加害責任を被爆者の立場から告発した、希有な詩なのです。(全文はこちらを参照ください。http://home.hiroshima-u.ac.jp/bngkkn/database/KURIHARA/hiroshimatoiutoki.html)
「夢千代日記」以来、吉永さんは原爆・戦争の悲惨さを告発し、平和の尊さを訴え続けてきました。そんな吉永さんだからこそ、原爆・戦争の被害だけでなく、日本の戦争・植民地支配の加害責任へも視点を向け、告発していただきたい。そんな作品にも出演していただきたい。
それはきっと、吉永さんの「こころ」にも沿うことだと思います。