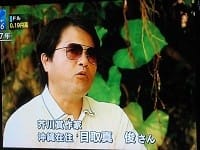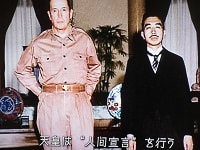天皇一家の沖縄訪問(4~5日)を絶賛した玉城デニー知事の発言については先に書きましたが(7日のブログ参照)、問題は玉城氏だけではありません。
仲地博・元沖縄大学長は、「平和への強い意志示す 寄り添う姿 愛子さまに継ぐ」の見出しで、「豊かで真摯なスケジュールが組まれている。…平和憲法下の象徴天皇たらんとする天皇の強い意志が見てとれるように思う」(6日付沖縄タイムス)と賛美しています。
しかし、もちろん賛美するコメントばかりではありません。
石原昌家・沖縄国際大名誉教授は、「戦後80年の年に(天皇)一家が来県したことは、国防の名の下に「沖縄の軍事強化は日本のためにやむを得ない」という全体主義的な国家体制を望む人たちが皇室を利用しようとする思惑も感じられる」(6日付沖縄タイムス)と指摘しています。
注目されたのは、田仲康博・元国際基督教大教授の視点です。5日付沖縄タイムスに「談」として掲載されました。
<日の丸を振っている子どもたちを見ると、自分の子ども時代を思い出す。復帰運動を担う「少国民」として動員された悔しさがよみがえる。一つの国家の体制になびいてしまう心証が現れており、沖縄はあまり変わっていないのではないか。1960年代ごろの復帰運動は姿や形を変えて今も続いている。天皇に対する沖縄の人たちのまなざしが気になる。
どのように天皇制がつくられ、戦争につながっていったのか、考え続けなければならない。天皇が代替わりする中で戦中、戦後の責任について言葉を発したことはなく、責任はないがしろになっている。
明治以降、国家の頂点にいたのが天皇で、戦時中は昭和天皇がその頂点にいた。(「近衛上奏文」「天皇メッセージ」の問題を指摘―略)
平成、令和に時代が移り変わったから、象徴天皇になったからと言って、国家が沖縄を支配する構造そのものは変わっていない。
戦後80年がたち…沖縄では米軍占領下の時代から、今や自衛隊が急速に増強される時代となった。その中での天皇来県である。天皇本人の思いとは別に、天皇制をうまく利用しようとする人たちもいる。歴史修正主義がどう動いていくのか注意深く見なければならない」(5日付沖縄タイムス=写真中)
「天皇に対する沖縄の人たちのまなざし」についてのウチナーンチュとしての警鐘です。
これに対し、「本土」の日本人はどうでしょうか。
今回の「天皇訪沖」を社説で取り上げた全国紙(東京新聞を含め)は産経新聞(もちろん大絶賛)だけでした。「本土」の識者からの論評も見られませんでした。
本来、「沖縄と天皇制」の関係、自衛隊が急速に増強されている沖縄に天皇が行く意味・危険性について論評しなければならないのは、「本土」のメディアであり学者・研究者の方です。
そして多くのヤマトンチュ(日本人)は、この問題に関心すら持っていないでしょう。
沈黙や無関心は、「国家が沖縄を支配する構造」に加担していることに他なりません。