
















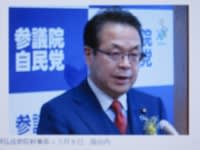









岸田文雄政権は3月31日、ウクライナの首都の呼称をロシア語由来の「キエフ」からウクライナ語読みの「キーウ」に変更すると発表しました。「チェルノブイリ」も「チョルノービリ」にすると。
日本のメディアはこの政府発表を受け、2日からいっせいに呼称を変更しました。政府の方針に忠実に従ったものです。ここには見過ごせない問題があります。
第1に、なぜ岸田政権は呼称変更したのでしょうか。
「国の象徴とも言える首都の呼称を変えることで、先進7カ国をはじめとする国際社会と連携し、ロシアによる侵攻が続くウクライナへの連帯を示す狙いがある」(1日付琉球新報=共同)
呼称変更は戦争の当事国であるウクライナと背後で操るアメリカはじめNATO(北大西洋条約機構)陣営との一体化を図るきわめて戦略的な狙いによるものです。
第2に、この戦略的呼称変更を主導したのが、防衛省だということです。
松野博一官房長官は3月15日の記者会見では、「ウクライナ側から問題があると申し入れを受けたわけでもない」と、呼称変更には消極的でした。
「ところが二週間後の二十九日、自民党の会合で「キーウ(キエフ)」と表した防衛省の資料が配られ、三十一日には各省庁の文書をウクライナ語読みに統一すると政府が発表した」(6日付東京新聞「こちら特報部」)。
呼称変更は防衛省が主導し、官邸がそれに続いたものです。
第3に、「ロシア語禁止」はウクライナの極右勢力の基本戦略だということです。
ウクライナは歴史的に多言語国家です。ところが、「マイダンクーデター(革命)」(2014年、写真)によって、親ロ政権を倒して権力を掌握した勢力がまずやったことの1つが、ロシア語を公用語として使えなくすることでした。
「国家権力は最高会議に移り、矢継ぎ早に重要決定が行われた。その中にはスヴォボーダが提出したロシア語を公用語から外す法案もあった。その後の東ウクライナの混乱を決定づけることになるこの愚かな法案は、すんなり可決されてしまった」(岡部芳彦・神戸学院大教授著『マイダン革命はなぜ起こったか』ドニエプル出版2016年)
「スヴォボーダ」とは、「ウクライナ語にこだわる極右政党」(岡部氏、前掲書)です。
今回の呼称変更は極右の「愚かな」ロシア語排除戦略の延長線上にあると言って過言ではないでしょう。
こうした政治的・戦略的問題を含む岸田政権による呼称変更。日本メディアはそれに唯々諾々追随し、それが日本社会に流布することになるのです。(私は、少なくともウクライナ戦争が終わるまでは、呼称変更しません)