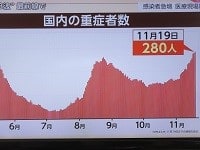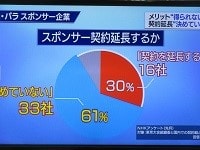第1回帝国議会開院式(1890年11月29日)から130年を祝う式典なるものが29日、国会内(参院本会議場)で、徳仁天皇・雅子皇后出席のもとで行われました。主権在民の日本国憲法の基本原則を何重にも蹂躙する明白な憲法違反であり、絶対に容認することはできません。
そもそも帝国議会は、天皇睦仁(明治天皇)の「勅諭」(1881年10月)によって開設されたもの。「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(大日本帝国憲法第1条)という天皇絶対主権の下で、帝国議会は、「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」(同第5条)と位置づけられた天皇の協賛機関にすぎませんでした。
さらに、「天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス」(同第7条)とされており、議会を開くも閉じるも解散するも天皇の思いのまま。まさに天皇の付属機関でした。
事実、天皇は帝国議会をそのように操りました。
「天皇は、天皇が任命し、天皇が信頼する政府に協賛するのが、議会の役目だと思いこんでいる。…議会と内閣がぬきさしならぬ対立にはいったとき、天皇はどうしたか。…にっちもさっちもいかなくなったとき、伝家の宝刀として抜くのが天皇の詔勅である」(宮地正人「政治史における天皇の機能」、『天皇と天皇制を考える』青木書店1986年所収)
その帝国議会の「開設祝賀式典」なるものを、敗戦後憲法で「国権の最高機関」(第41条)となった国会で、各党の国会議員出席のもとに行うこと自体、現行憲法の趣旨に反しています。
しかも、その場に天皇・皇后が出席し、最も高い位置から国会議員を見下ろす。さらに天皇は、「お言葉」なるものを発し、「決意を新たにして国民の信頼と期待に応えることを切に希望」するとして、国会議員に“新たな決意”を促す。それを受けて首相(菅義偉)が、「われわれは新しい時代の日本をつくり上げていかねばならない」と“決意表明”する。
まさに天皇主権下の帝国議会の再現と言わねばなりません。二重三重に憲法原則が蹂躙されていることは明白です。
この憲法違反の儀式に、日本共産党を除くすべての政党が出席し、天皇を見上げ、首(こうべ)を垂れました。これが現代日本の権力機構の実態、天皇制国家・日本の現実です。(象徴)天皇制がいかに民主主義に反するか、主権在民を蹂躙する存在であるかを白日の下に示しています。この一事をもってしても、天皇制を廃止する(憲法から天皇条項を削除する)ことが急務であることは明らかです。
共産党が「戦前の帝国議会を踏襲した天皇中心のやり方」(29日NHK)だとして式典を欠席したことは、当たり前とはいえ、評価されます。しかし、それならなぜ同党は、天皇が出席して「お言葉」を述べる(この日と同じ位置から)国会の開会式に出席するのでしょうか。「戦前の帝国議会を踏襲した天皇中心のやり方」であることは、国会開会式もまったく同じではありませんか。
にもかかわらず、共産党は2016年1月4日の通常国会から方針転換し、開会式に出席し始めました。これは明らかに今回の態度と矛盾し、憲法違反に加担する行為です。共産党はこの日の自らの言明に従って、国会開会式への出席をきっぱりやめねばなりません。





















 朝鮮学校が高校無償化制度から排除されている差別政策を卒業生らが訴えた裁判の広島高裁判決(10月16日)。そのルポが月刊「イオ」最新(12月)号の中村一成(イルソン)氏の連載にある。
朝鮮学校が高校無償化制度から排除されている差別政策を卒業生らが訴えた裁判の広島高裁判決(10月16日)。そのルポが月刊「イオ」最新(12月)号の中村一成(イルソン)氏の連載にある。