



 8日行われた日米首脳会談に対する日本の新聞の社説が(東京新聞を除き)9日出そろいました。あらためてこの国の論説の現状を示すものとして見過ごせません(「読売」「日経」「産経」は対象外)。
8日行われた日米首脳会談に対する日本の新聞の社説が(東京新聞を除き)9日出そろいました。あらためてこの国の論説の現状を示すものとして見過ごせません(「読売」「日経」「産経」は対象外)。





読売新聞は1月1日付社説でこう書いています(太字は引用者)。
「何もしなければ平和が保たれるなどというのは、危険な幻想である。…相手に「勝てる」という思い違いをさせないことが、最大の防衛策となるだろう。
そのためには、まずは日本自身の防衛努力、そして日米同盟関係の強化によって、もし日本や台湾を含めた地域の安全を脅かす行動に出れば自国にとって重大な損失となることを、相手にしっかり認識させることが重要だ」
続いて、3日付(2日付は休刊)の社説でもこう書いています。
「(米国は)「世界の警察官」として、全ての紛争を主導する意思と能力があるわけではない。…日本をはじめ、米国の同盟国と友好国が防衛力を拡充し、地域の安全保障体制を強化しなければならない。積極的な情報共有によって一体化を推進すべきだ」
まるで「戦争マニュアル」です。「相手」とはもちろん中国のこと。2日連続で、中国を敵国視し、日本の軍事力増強と日米軍事同盟の強化を強調した読売新聞の社説は、保守反動が何を今年の中心課題にしているかを示唆しています。
一方、朝日新聞、毎日新聞の1日、3日の社説は、「人権・民主主義」「新しい資本主義」「民主政治と市民社会」がテーマで、軍拡・日米軍事同盟、東アジアの平和に関する問題は取り上げていません。
これら全国紙3紙の新年の社説には、日本のメディアの危機的状況が表れています。
政権(国家権力)との一体化を強める読売が日本の軍拡、日米軍事同盟の強化を声高に主張するのに対し、朝日、毎日はそれに歯止めをかけるのではなく、黙して容認する。強弱の違いはあっても、自衛隊(日本軍)・日米軍事同盟(安保条約体制)支持では同一線上の安保翼賛体制です。
一方、岸田政権は新年早々、自衛隊とオーストラリア軍の軍事協力を促進する「円滑化協定」に署名し(6日、写真中)、日米「2プラス2」会談(7日、写真右)では、米軍のコロナ感染拡大の責任は棚上げして、「日米軍事同盟強化」を強調するなど、読売の社説が督促した道をひた走っています。
昨年、ノーベル平和賞を受賞したロシアのリベラル紙「ノーバヤ・ガゼータ」のドミトリー・ムラトフ編集長(写真左の右)は、受賞演説で旧ソ連の物理学者でノーベル平和賞を受賞したサハロフ氏の次の言葉を引用しました。
「国際的な信頼や軍縮、そして安全保障は、情報、良心、言論の自由を伴った開かれた社会なくしては考えられません。平和、進歩、人権。これら三つの目標は互いに不可分です」
そしてムラトフ氏はこう強調しました。
「私たちはジャーナリストであり、その使命は明確です。事実とフィクションを見分けることです」(2021年12月10日の朝日新聞デジタル)
日本はメディアに対する暴力的弾圧がないから「報道の自由」が保障されているかといえば、けっしてそうではありません。
「国境なき記者団」による「報道自由度ランキング」(2021年度)では、日本は180カ国中、67位という低さです。その理由として「国境なき記者団」は、「閉鎖的・差別的な記者クラブ制度」や「特定機密保護法」などを挙げています。
日本は、国家権力が法律や行政権限を背景にメディアに圧力をかけ、メディア自身が権力監視の本来の責務を自粛・放棄することで、「報道の自由」が大きく低下しているのです。
そして、中国、朝鮮民主主義人民共和国を敵視する日米両政府と同じ立場から、両国を一方的に批判する報道は、かつての「鬼畜米英」報道を彷彿とさせます。まさに「事実とフィクションを見分ける」報道が求められています。
今年は東アジアの平和問題が大きな焦点になることは間違いありません。その中で、日本のメディアの実態が根本から問われることになります。



「北朝鮮による度重なる挑発行為は断固容認できない」。菅官房長官は29日の会見で、北朝鮮の「ミサイル発射」に対しこう述べました。
「北朝鮮の挑発」。それは日本政府の常とう句であり、同時に、日本のメディアが1社の例外もなく繰り返し使っている言葉です。
それは果たして事実に基づいた「報道」でしょうか。
「挑発」とは、「相手を刺激して事件などが起こるようにしかけること」(『広辞苑』)です。
朝鮮半島の緊張を高めているこの間のアメリカ(トランプ政権)と日本(安倍政権)、そして北朝鮮の主な動きを振り返ってみましょう(日時は日本時間)。
★3・1 米韓合同軍事演習開始(過去最大規模。金正恩委員長の「斬首作戦」を含む)。
★4・7 トランプ大統領、シリアをミサイル攻撃(「アサド政権による化学兵器使用」の証拠示さず)。
★ 同 トランプ大統領、安倍首相との電話会談で「全ての選択肢がテーブルの上にある」。安倍氏「高く評価する」。
★4・9 トランプ大統領、原子力空母カール・ビンソンの朝鮮半島近海への展開を指示。
★4・10 米ティラーソン国務長官、シリア攻撃は北朝鮮をけん制したものと示唆。
★4・11 トランプ大統領「北朝鮮へ無敵艦隊を送っている」。
☆ 同 北朝鮮、最高人民会議(国会)で「外交委員会」を復活。
★4・13 トランプ大統領「(北朝鮮制裁を)中国がやらないなら、米国と同盟国でやる」。
★ 同 安倍首相「(北朝鮮は)サリンを(ミサイルの)弾頭に付けて着弾させる能力をすでに保有している可能性がある」(参院外交防衛委員会)。
★4・14 米、アフガニスタンで「大規模爆風爆弾(最強の爆弾)」を初使用。トランプ大統領「北朝鮮は問題だ。問題は対処される」。
★ 同 米NBCが「北朝鮮に核実験の兆候があればアメリカは先制攻撃する」と報道。
☆4・15 北朝鮮、「故金日成主席生誕記念日」で軍事パレード。「新型ミサイル」初公開。
☆4・16 北朝鮮、「ミサイル発射」(失敗)
★4・17、18 米ペンス副大統領、韓国と日本を相次いで訪れ、「平和は力によってもたらされる」。安倍氏「支持する」。
★4・23、24 カール・ビンソンと海上・航空自衛隊が共同「訓練」(写真右)。
☆4・25 北朝鮮、「朝鮮人民軍創建記念日」で砲撃訓練。
★4・26 米、最新鋭迎撃システム(THAAD)の発射台やレーダーを韓国に搬入。
★4・27 トランプ大統領、「北朝鮮政策」を上下両院の全議員に異例の説明。
★4・28 米、国連安保理で北朝鮮に対する「国際的包囲網」構築を訴え。
☆4・29 北朝鮮、「ミサイル発射」(失敗)。
★ 同 カール・ビンソン、日本海へ。日本海で日米・米韓共同「訓練」(予定)。
以上の事実経過を先入観抜きで見れば、どちらが「挑発」しているかは明白ではないでしょうか。圧倒的軍事力で「相手を刺激して事件などが起こるようにしかけ」ているのは、アメリカ=トランプ大統領であり、それに忠実に追随している日本政府=安倍首相です。
問題は北朝鮮の「核開発・保有」だ、と言うかもしれません。もちろん核開発・保有は許されるものではありません。しかし、その背景には、いまだに朝鮮戦争が終結していない(休戦中)状況で、北朝鮮が「平和協定」へ向けた対話を望んでいるにもかかわらず、アメリカがそれに耳を貸さず、韓国と一体となって北朝鮮に軍事圧力をかけ続けている(合同軍事演習の定例化など)実態があることを見落とすことはできません。
「核」についても、アメリカが自国の膨大な核兵器保有は棚上げし、またインドなどの「核保有」は容認しながら、北朝鮮にだけ「放棄」を迫るのは、大国主義以外の何ものでもありません。北朝鮮に「核放棄」を求めるなら、当然アメリカ自身も核兵器を放棄すべきでしょう。そもそも「核兵器禁止条約」に反対するアメリカや日本に北朝鮮を非難する資格があるでしょうか。
「北朝鮮の挑発」と言い続ける「報道」に正当性がないことは明らかです。自ら事実を検証することなく、政府の言い分(用語)を引き写しするのではメディアとしての基本的資格が問われます。
重大なのは、「北朝鮮の挑発」と繰り返すことは、正当性がないだけでなく、日米両政府の「北朝鮮敵視」に加担することになり、アメリカによって軍事衝突(戦争)が引き起こされた時には、米・日の責任を棚上げし北朝鮮を敵視することにつながることです。
それはかつて帝国日本の朝鮮・中国侵略・植民地化を新聞が賛美したことの二の舞いと言わねばなりません。
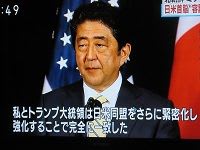


安倍首相とトランプ大統領の会談に対し、読売新聞や産経新聞はもちろん「日米同盟」を最大限賛美し、「日本も、米国に依存するだけでなく、『積極的平和主義』の下、自衛隊の国際的な役割を拡大することが大切である」(「読売」12日付社説)と安倍政権の背中を押しています。
「読売」や「産経」ほど露骨ではありませんが、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞なども一様に「日米同盟」を肯定・礼賛し、日本の新たな役割を主張しています(以下、引用はいずれも12日付各紙社説)
「『揺らぐことのない日米同盟』を確保するため、ただトランプ氏にすり寄るだけでは、日本は国際社会からの信頼を失いかねない」(毎日新聞)
「日本は(日米安保)条約で課せられた基地提供義務を誠実に果たし、条約の義務以上の在日米軍駐留経費を負担している。…大統領からアジア太平洋地域への米軍関与の継続と、日本の役割に対する理解が得られたことは意義がある」(東京新聞)
「共同声明は、日米同盟を『アジア太平洋地域における平和、繁栄及び自由の礎』だとうたった。ならばトランプ氏との関係も、旧来型の『日米蜜月』を超える必要がある」(朝日新聞)
「日米同盟を一層強化することでも一致し、米側は防衛面では日本側の要求をそのまま受け入れた形だ」(琉球新報)
「オール日米同盟」のメディアの姿が改めて浮き彫りになっています。これでいいのでしょうか。
明確にしなければならないのは、日米安保条約に基づく「日米同盟」とは軍事同盟にほかならないということです。自明のことですが、この点をはっきり書いているメディアは1つもありません。たんなる「同盟」という言葉を流布させることは、軍事同盟の本質・危険を見えなくさせる役割を果たします。
「日米同盟」がきわめて危険な軍事同盟であることは、今回の「共同声明」にもはっきり表れています。
「揺らぐことのない日米同盟はアジア太平洋地域における平和、繁栄および自由の礎である。 核および通常戦力の双方による、あらゆる種類の米国の軍事力を使った日本の防衛に対する米国のコミットメントは揺るぎない」
「日本の防衛」を口実に「核(兵器)」の使用を明記したことはきわめて重大です。「共同声明」に「核」が盛り込まれたことがかつてあったでしょうか。
しかしこの重大な「核」の明記を社説で取り上げた新聞はたった1社しかありません。「中国や北朝鮮を抑止する効果的なメッセージ」だと賛美した産経新聞だけです。さすが(?)「産経」です。
すべてのメディアは、「日米同盟はアジア太平洋地域における平和、繁栄および自由の礎である」という「共同声明」の文言を肯定しています。「核」の使用さえ公言する軍事同盟がどうして「平和、繁栄、自由」の礎なのでしょうか。メディアは「日米同盟」を当然の前提とするのでなく、その理由を明らかにする必要があります。
新外交イニシアチブ事務局長の猿田佐世さんは、「トランプ政権の登場は、日本が『対米従属』だけを判断指針にすることができなくなり、自ら外交安保について考えなければならなくなった戦後は初めての機会でもある」とし、「今後の日米外交と安全保障のあるべき姿を巡り提案がもっとなされるべきだ」(12日付共同配信)と指摘します。
「戦後初」かどうかはともかく、この限りでは基本的に同意です。しかしそこまで言いながら、なぜ肝心の日米軍事同盟=日米安保条約の是非について触れないのでしょうか。猿田さん(新外交イニシアチブ)は安保条約・日米軍事同盟についてどのような「提案」をするのでしょうか。
「日米同盟」=「日米軍事同盟」=「日米安保体制」が不動の前提であるかのようなタブーから脱却しようではありませんか。日米安保条約を廃棄し、どの国とも軍事同盟を結ばない、どの国も敵視しない、非同盟・中立の日本を実現し、文字通り非軍事的手段で世界の「平和、繁栄、自由」に貢献しましょう。そんな日本の「あるべき姿」を構想しようではありませんか。



「クリントン優勢」というアメリカ大手メディア世論調査がすべて外れたのはなぜか。
「隠れトランプ派」が数字に表れなかったなど、さまざま言われていますが、日本にも通じる興味深い指摘を2つ紹介します。
1つは、BS-TBSの「外国人記者は見た+」という番組の「トランプ氏勝利の真相」の回(20日夜)で、ニューヨークタイムス特派員はじめ複数の外国人記者が要旨次のように発言したことです。
世論調査が外れたのは、地方新聞(地方総局に相当か)が次々つぶれたことが大きい。
もともと世論調査の生の数字と実際に取材した実感との間には乖離がある。これまではそれを地方新聞の取材によって修正してきた。それが地方新聞がつぶれたためにできなかった。
アメリカでは「メディアを信頼している」という人の割合が年々大きく減少しているグラフも示されました(写真右)。
もう1つは、中国新聞に相次いで載った「識者評論」。
前田幸男東大教授は、「統計理論に基づく世論調査は不確実性を織り込んで議論すべきであるにもっかわらず、評論家や大手メディアが丁寧に解説しなかったこと」(18日付)がミスリードの原因の1つだと指摘します。「専門家は有権者が自分たちと同じ物差しでトランプ氏を見ていると楽観していたのだろう」
会田弘継青山学院大教授は、世論調査や評論家の予測が外れたのは「プロの敗北」であり、「そこにこそ『トランプ現象』の本質がある」(17日付)と言います。
「インテリと呼ばれる自分たちは、いかに下層中産階級である『普通の働く人たち』のものの考え方(価値観)を知らずに来たか。そこには高等教育を受けたリベラル(進歩派)と呼ばれる者の『おごり』がある」
「下層中産階級は経済的な抑圧だけでなく、文化的な抑圧も受けていると感じている。エリートは抑圧に無自覚だ。トランプ氏当選は白人下層中産階級による一種の『反動革命』である。トランプ氏が彼らを操ったように見えて、実は彼らが同氏を使って激しい異議申し立てをしたのだ」
関連して、フランスの学者エマニエル・トッド氏も、白人大卒外の層のトランプ支持が多かった(写真中)ことを示し、今回の結果は「教育格差が生んだ非教育階級による一種の革命」だと言います(25日放送の「報道ステーション」)
以上の指摘に共通しているのは、世論調査や評論家の予想が外れた根底には、「メディア」や「専門家」が現実から遊離し、独善に陥っている実態があるということです。
日本はどうでしょうか。
安倍首相が強権的に悪政を推し進めるのは、大手メディアの世論調査が「高い内閣支持率」を示しているからにほかなりません。世論調査の結果が政治を動かしていると言っても過言ではないでしょう。
ではその世論調査は、はたしてどれだけ実態を反映しているでしょうか。電話調査の生の数字を実際の取材で修正することは行われているでしょうか。「エリート」の学者・評論家・新聞記者は、どれだけ「下層中産階級」の生活・声を知っているでしょうか。
「普通の働く人たち」から遊離した虚構の「世論」を利用して国家権力が政治を動かす危険を凝視する必要があります。
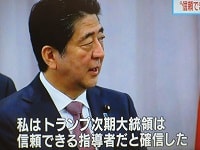

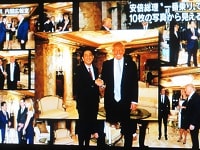
安倍首相とトランプ次期米大統領との「会談」(日本時間18日)は、異例・異常づくめでした。
第1の異常さは、トランプ氏が一切の取材を拒否したことです。報道陣は会談場所となったトランプ氏の私邸があるトランプタワーから締め出され、通りをはさんだ向こう側に待機せざるをえませんでした(写真中)。
この種の会談では少なくとも冒頭に写真撮影(頭撮り)が行われるのが普通ですが、トランプ氏をそれも拒否しました。そのため、日本政府は「内閣広報室提供」として10枚の写真を配布しました。
トランプ氏の取材拒否の背景に、選挙中からのメディア敵視があるのは間違いないでしょう。アメリカのメディアは取材拒否に抗議し、その意思を示すために主要なテレビ局はトランプ氏側から提供された写真は一切使わなかったといいます。
ところが日本のメディアはどうでしょうか。取材拒否に抗議するどころか、「内閣広報室提供」の写真をフルに使い、安倍氏とトランプファミリーの〝和やかさ”をあれこれ「解説」する始末です(写真右)。
アメリカと日本のメディアの違いは明瞭です。権力と対峙すべきメディアの姿勢としてどちらが妥当か、言うまでもないでしょう。
第2の異常さは、トランプ氏も安倍氏も「会談」の内容を一切明らかにしなかったことです。
「非公式な会談だから」(安倍氏)というのは言い訳になりません。たとえ「非公式」でも「公的」な首脳会談です。決して「私的」な訪問ではありません。あくまでも「トランプ氏の外交デビュー」(NHKニュース)なのです。90分間も話し合っておいて、その内容を一切明らかにしないなどということが許されるものではありません。
トランプ氏は当初、「会談」後に「声明」を出すとしていましたが、それも取りやめました。
安倍氏はトランプ氏を「信頼できる指導者だと確信した」と述べましたが、なぜ「信頼できる」のか、なぜそう「確信」したのか。安倍氏はその根拠を明らかにする必要があります。米軍経費やTPPなどについての会談内容を一切明らかにしないままで、「信頼できる」と強調するのは、デマゴギー(虚偽の宣伝)以外の何ものでもありません。
ところがこれに対しても、日本のメディアは、「非公式という位置づけで…具体的な内容は『差し控えたい』と説明を避けた。…首相がトランプ氏の発言内容を公表しなかったこと自体は理解できる」(19日付朝日新聞社説)などと、批判するどころか「理解」しているのです。
そもそも日本のメディアが「霧中に踏み出した一歩」(19日付毎日新聞社説)などとこぞって賛美する今回の「安倍・トランプ会談」とは何だったのでしょうか。
選挙中のトランプ氏の「日米同盟見直し」示唆発言にびっくり仰天した安倍氏が、日米同盟(安保条約による軍事同盟)を維持するために、50万円のゴルフクラブを土産にトランプ氏のもとにはせ参じ、「信頼できる指導者」と媚びを売っただけではありませんか。
トランプ氏はわが意を得たりとばかりに、さっそくフェイスブックに「安倍晋三総理に我が家に立ち寄ってもらったことをうれしく思う。グレートな友情の始まりだ」と書きました。国内外の不人気を少しでも挽回しようと、安倍氏を利用したことは明白です。それが「外交デビュー」に安倍氏を選んだトランプ氏の「ディール(取引)」だったのです。
核兵器使用、移民排斥、女性蔑視・差別はじめ数々の暴言で批判を浴びているトランプ氏に真っ先に会いに行き、「信頼できると」と世界に向かって公言したことは、安倍氏個人の問題にとどまらず、日本の恥です。
それを無批判に賛美する日本のメディアは、恥の上塗りと言わねばなりません。