






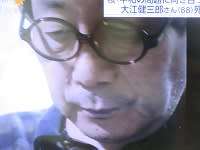




ゴルフの笹生優花選手(19)が全米女子オープンで優勝(7日)したことに対し、日本のメディアは「日本の女子選手の海外メジャー制覇は史上3人目」などと「日本人」を強調しました。スポーツの国際大会やノーベル賞報道の際に繰り返し唱えられる「日本人」。そこには見過ごすことができない問題が含まれています。
笹生選手は父親が日本人、母親がフィリピン人で、フィリピンでの生活が長く、フィリピンでは今回の優勝を「フィリピン人初の快挙」と祝福しているといいます。東京五輪が開催される場合は、フィリピン代表として出場すると報じられています。
笹生選手やテニスの大坂なおみ選手など、両親のどちらかが「日本人」で、活躍しているスポーツ選手は少なくありません。その場合、日本のメディアは「日本人選手」と報じます。何をもって「日本人」としているのでしょうか。そこには「日本国籍」の有無があると思われます(国籍は外国でも両親のどちらかが日本人なら「日本人」とする我田引水の報道もありますが)。
「日本人」が強調される背景には、意識的にせよ無意識的にせよ、「日本国籍」の存在があります。そしてこの日本の「国籍制度」こそ諸悪の根源なのです。
笹生選手は現在、日本とフィリピンの2つの国籍を持っています。しかし、22歳になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条)。日本の国籍法は原則的に多重国籍を認めていません(「国籍唯一の原則」)。これが在日コリアンへの差別、外国人労働者の無権利状態、反民主的な入管制度につながっています。
「グローバル化と価値観の多様化が進んだ現代社会において、旧態依然とした国籍法全体のオーバーホールが必要…。「国籍唯一の原則」自体を含んだ国籍法制全体の抜本的見直しが議論されなければならない」(国籍問題研究会編『二重国籍と日本』ちくま新書2019年)
現在の国籍法(1950年施行)は基本原則、個々の条項を含め、明治国籍法(1899年制定)を受け継いだものです。その明治国籍法は、「日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」とした大日本帝国憲法(明治憲法、1889年制定)に基づいて制定されました。
つまり現在の国籍法による「日本国民(日本人)」規定は、天皇制の支柱となった帝国憲法・国籍法を引き継いだものです。これが「旧態依然」たるゆえんです。
「近代国家としての統合を強化したい日本は、どうしても「国籍唯一の原則」神話をたてる必要があった。もともと多様であった人々に対し、戸籍制度によって天皇の赤子という「血統」幻想を与え、虚構の「民族」日本人が外国人排斥を通じ…「われわれ」意識をつくられた。排他的な忠誠を誓う者にのみ見返りとして国籍=市民権を与えるという大日本帝国下の国籍概念は、一方でまつろわぬ者を「非国民」として権利を奪ってきた。
そして日本国憲法にかわった現在でも、それは未だ生きている。戸籍=国籍=市民権を強固な一枚岩として維持し、それによって単一民族国家であるかのような虚像をつくり出し、巧みに近代国家としての統合を計ってきた日本。日本は明治以降ドイツに国家モデルを学んだが、国家統合の方法は多分に日本独自のものである」(チョン・ヨンヘ(鄭暎恵)大妻女子大教員『<民が代>斉唱』岩波書店2003年)
ここに日本の天皇制(戦前の絶対主義天皇制、戦後の象徴天皇制)の本質があります。
そして、こうした重大な背景・意味をもつ「日本人」呼称の大合唱が行われ、「われわれ」意識が刷り込まれる場が、「東京五輪」に他ならないことを改めて銘記する必要があります。



きょうは「海の日」(「東京五輪」で変則的になりましたが通常は7月の第3月曜日)。「海の日」とは何か、なぜ「海の日」ができたのか。それが明治以降の天皇制と深い関係にあることはこれまで何度か書いてきました(2019年7月15日、2017年7月18日のブログ参照)。ポイントを確認しておきましょう。
以上に関連して、「海の日」が皇民化教育とも深い関係にあったことも想起する必要があります。
〽 うみは ひろいな おおきいな つきが のぼるし ひが しずむ
小学校低学年の音楽の教科書に出てくる唱歌「うみ」です。いかにも無邪気でのどかな「海」の歌のようですが(私もそう思っていました)、実はこの歌は、「侵略の歌です。少なくとも帝国海軍への誘導の歌です」と、北村小夜さん(元教員)が指摘しています(『戦争は教室から始まる』現代書館2008年)
「この歌が初めて教科書に登場するのは一九四一年、小学校が国民学校に改称されたときです。学校の在り方を大きく転換し皇民教育を徹底させようというもので、『唱歌』は芸能科音楽になりました」(同書)
北村さんは「うみ」が「侵略の歌」であることを示すものとして、同じ1941年に改訂された初等科『修身二』(4年生用)を引用しています。
「八 日本は海の國
日本は海の國です。海の恵みを受け、海にまもられてきた國です。(中略)
今の日本は海國日本の名のとほり、世界いたるところの海洋に、日の丸の旗をかかげ て、國の光をかがやかしながら活動してゐます。
へさきに菊の御紋章を仰ぐ帝國軍艦は、み國のまもりもかたく、太平洋から印度洋にかけて、その威力を張っています。
海國日本のほまれをあげるぶたいは、かぎりなく大きいのです。その廣いぶたいに日の丸の旗をささげて進むのが、私たちの尊いつとめです」(同書より)
唱歌と皇民化教育の関係については、小村公次著『徹底検証 日本の軍歌』(学習の友社2011年)にもこうあります。
「唱歌教育の転換は、一九三一年の満州事変を前後して始まる戦争の時代とぴったり符合していた。…国民学校になってから芸能科音楽が『音楽は軍需品』と言う理由で『重視』された」
唱歌「うみ」の教科書掲載と「修身」の改訂は一体でした。戦時下の教師たちは子どもたちに「うみ」を歌わせ、「修身」を叩き込み、「菊の御紋章を仰ぐ帝國軍艦」による海外侵略を煽ったのです(写真中・右は戦艦大和<レプリカ>の菊の紋章=呉・大和ミュージアム)。
「うみ」の3番の歌詞はこうです。〽 うみに おふねを うかばせて いって みたいな よその くに
1941年に初めて教科書に載った「侵略の歌」=「うみ」が今も教科書に掲載され続け、同じ年に帝国日本が制定した「海の記念日」が「海の日」となって今日に続いている。これが日本の歴史、天皇裕仁が戦争・植民地支配責任から逃げ、敗戦後も天皇制が連綿と続いている日本の現実であることを、あらためて直視する必要があります。



先に共同通信の配信で大きく報じられた「小林忍侍従日記」について、裕仁天皇(昭和天皇)の戦争責任を隠ぺいし美化するするものだと書きましたが(8月27日のブログ参照)、そのような視点でこの「日記」報道を論評したものは、その後も日本のメディア・論壇では見ることができません。
そんな中、目を引いたのが朝鮮新報(8月31日付)の記事(「取材ノート」)です。タイトルは<「加害者」意識の欠如>。要点を抜粋します。
< 8月末、晩年の昭和天皇と側近のやりとりを記した日記が見つかった。日本の大手メディアは「心奥に触れる価値ある日記」「人間としての天皇の苦悩」と大々的に報じた。
「戦争責任のことを言われる」――戦争責任と向き合わず、逃げた者の厚顔無恥な一言。この発言を天皇があたかも戦争責任を感じていたかのように美化するメディア。ここに、戦後から現在まで通ずる日本の加害者意識の欠如を見る。
中国侵略、対米英決戦決定。戦争政策の絶対的な中枢として侵略戦争の拡大に関与した天皇。戦争末期には、無謀な戦争の継続により、多くの命を奪い、その責任は米国の覇権戦略の中でうやむやとなった。
テレビや新聞の「終戦」特集からは、日本の侵略戦争によって犠牲となった「被害者」の存在が抜け落ちた。戦争の実相をひた隠した戦後は、「強制連行はなかった」「慰安婦はねつ造」という「加害者」と「被害者」のすり替えを容認する。
隣国の脅威を煽り、軍備を拡大し、憲法改正をめざす現政権。侵略戦争へと突き進んだ過去の国家体制をしっかりと検証する姿勢が今、求められている。>
「加害者意識の欠如」した日本、日本のメディア、「国民」に対する厳しい指弾です。
日本には「加害者意識の欠如」と表裏一体の「菊(天皇)タブー」が、戦前・戦後一貫してあります。
そんな中でも「タブー」に「倚(よ)りかからない」識者は皆無ではありませんでした。その1人が、詩人の茨木のり子(1926~2006)です。
「小林日記」で裕仁が批判を気にしていたという「戦争責任は言葉のアヤ」発言(1975年10月31日)。実は裕仁が気にしていたほど「世間」はこの暴言を批判しなかったようです。そのことを茨木のり子はこう告発しています。
< 戦争責任を問われて その人は言った 「そういう言葉のアヤについて 文学方面はあまり研究していないので お答えできかねます」 思わず笑いが込みあげて どす黒い笑い吐血のように 噴きあげては 止り また噴きあげる (中略)
野ざらしのどくろさえ カタカタカタと笑ったのに 笑殺どころか 頼朝級のヤジひとつ飛ばず どこへ行ったか散じたか落首狂歌のスピリット 四海波静かにて 黙々の薄気味悪い群衆と 後白河以来の帝王学 無音のままに貼りついて ことしも耳すます除夜の鐘 >(「四海波静」、1977年刊行『自分の感受性くらい』所収)
茨木のり子にはこんな詩もあります。
< 日本の若い高校生ら 在日朝鮮高校生らに 乱暴狼藉 集団で 陰惨なやりかたで 虚をつかれるとはこのことか 頭にくわっと血がのぼる 手をこまねいて見てたのか その時 プラットフォームにいた大人たち
父母の世代に解決できなかったことどもは われらも手をこまねき 孫の世代でくりかえされた 盲目的に 田中正造が白髪ふりみだし 声を限りに呼ばはった足尾鉱毒事件 祖父母ら ちゃらんぽらんに聞き お茶を濁したことどもは いま拡大再生産されつつある
分別ざかりの大人たち ゆめ 思うな われわれの手にあまることどもは 孫子の代が切りひらいてくれるだろうなどと いま解決できなかったことは くりかえされる より悪質に より深く 広く これは厳たる法則のようだ (後略)>(「くりかえしのうた」、1971年刊行『人名詩集』所収)
祖父母・父母の世代に解決しなかった「天皇の戦争責任」追及。孫子の代へ先送りすることはできません。私たちの代でやるべきことをやらねばなりません。
年譜によれば、裕仁の「言葉のアヤ」発言の翌1976年、茨木のり子は「朝鮮語を習い始める」とあります。当時五十歳でした。



5日開幕した「第100回全国高校野球選手権大会」の開会式に皇太子夫妻が出席しました(写真中)。皇太子は「あいさつ」で、「これまで1世紀にわたり、青少年の夢を育み国民の大きな関心を集めてきた高校野球が果たしてきた役割は大きい」と述べました。
これに先立ち、主催の朝日新聞は7月30日付社会面で、「皇室 球児に寄り添う」という大見出しで、これまで明仁天皇や皇太子ら皇族がのべ7回「夏の甲子園を訪れている」など、皇室と高校野球の関係をアピールしました。
こうして「夏の甲子園」が「100回」=「1世紀」にわたり常に「青少年の夢を育み」、皇族が「球児に寄り添」ってきたかのように描くことは、高校野球と日本の歴史の重要な部分を捨象することになります。
第1回大会(当時は中等学校大会)が行われたのは1915年。今年2018年が「第100回」では計算が合いません。42年から45年までの4年間、戦争のために中止になったからです。41年も途中で中止になりましたが、回数(第27回)にはカウントされています。
「(1941年)7月に文部省から全国運動競技開催中止命令が発せられ、スポーツの全国大会はすべて禁止されました。甲子園出場をかけた地方大会の真っ只中。…いきなり発令された中止令に、球児や関係者はどんなに失望したでしょう」(小野祥之氏『高校野球100年を読む』ポプラ新書)
ところが政府は、41年大会を途中で中止させておいて、翌42年には文部省自らが主催者となって「夏の甲子園大会」を行っています。通算回数には数えられていないこの大会は「幻の甲子園」と言われています。それはどんなものだったか。以下、早坂隆氏(ルポライター)の『幻の甲子園 戦時下の球児たち』文芸春秋刊などを参考に振り返ってみます。
政府が中止にした直接的理由…戦争の深まりの中、学徒の移動に制限が設けられたのが、中止の直接的な原因。この時期、軍関係の人員や物資の輸送を優先的に行うため、交通機関に多くの規制が課せられ、全国的に旅行制限が設けられていた。
位置づけ…「大日本学徒体育振興大会」の中の一競技という位置づけ。大会の競技種目は野球のほか、柔道・剣道・相撲・陸上・水上・籠球・蹴球・射撃・「戦場運動」の10種目。「戦場運動」とは「手榴弾投擲突撃」「行軍競走」など。
開会式(1942年8月22日)…場所は奈良・橿原神宮(初代天皇とされる神武天皇宮)の外苑運動場(野球競技の実施は甲子園)。分列行進で始まり、周囲には、軍服姿の陸軍将校たちが並ぶ。時の東条英機首相も出席し、戦時色の強い祝辞を述べた。大会の謳い文句は、『戦時下に示さん、日本の底力』。橋田邦彦文相(のちA級戦犯容疑者)が裕仁天皇の「青少年学徒に賜はりたる勅語」を「奉読」。
特別ルール・呼称…文部省の通達によって、「選手」は「選士」に。「打者は投手の投球をよけてはならない(突撃精神に反する)」、「選士交代も認められない(最後まで死力を尽くして戦え)」などの特別ルール。
甲子園での開会式・閉会式…出場16校の主将がスコアボードの前に一列に並んで綱を引き、特大の「日の丸」を掲揚。宮城(皇居)遥拝、「君が代」斉唱、祈願黙とう。「戦士答辞(選手宣誓)」では「我らは…必勝不敗の信念を培い、皇国の次代を双肩にになうべき青年学徒として、あくまでも正々堂々と戦う」。閉会式では、選手、観客が一緒に「海ゆかば」(天皇のための死を賛美する歌)を歌う。
球場内スローガン…スコアボードの左上に「勝って兜の緒を締めよ」、右上に「戦ひ抜かう大東亜戦」(写真右)。スタンドにも「防諜は民一億の非常戦」のスローガン。
これでは野球大会というより、野球に名を借りた「学徒動員」であり「戦意高揚大会」です。
こうした、「球児に寄り添う」とは真逆な歴史が高校野球史にあったことを忘れることはできません。
その黒い歴史を刻んだ帝国日本の政府・軍の最高責任者が天皇だったことは言うまでもありません。

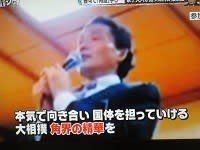

大相撲の女人禁制は天皇制・皇室典範の女性差別と密接な関係にあると先に書きましたが(4月7日のブログ参照)、それを証明するような事実がまた明らかになりました。
静岡市で8日行われた大相撲春巡業で、力士が土俵上で小学生らに稽古をつける「ちびっこ相撲」(写真左)から、女児が排除されたのです。静岡だけではありません。宝塚市(6日)でも、長野県(10、11日)でも同様のことが起こっています。
いずれも日本相撲協会から「女子を土俵に上げるのは遠慮してほしい」(13日付琉球新報)という「要請」があったからです。昨年までは女子も土俵に上がっていましたが、今年から禁止されました。
これについて日本相撲協会の芝田山広報部長(元横綱大乃国)はこう述べています。
「女の子が万一けがをして顔に傷がついたりするようなことがあっては困るということで、巡業部で検討して昨年9~10月ごろに決めた。安全確保がすべてで女人禁制とは関係ない」(13日付読売新聞)
「けが」はとってつけた口実でしょう。「けが」があるとすれば女子だけではありません。「顔に傷」云々にいたっては逆に女性差別と言わねばなりません。「ちびっこ相撲」からの女児排除が「女人禁制」の一環があることは疑いようがありません。
ここで注目されるのは、「巡業部で検討して昨年9~10月ごろ決めた」ということです。当時の巡業部長はだれだったか。貴乃花親方です(今年3月辞任)。今年から「ちびっこ相撲」で女児を排除するという相撲協会の決定は、貴乃花が中心に決めたものだということです。
この貴乃花の決定は、大相撲は「国体」=天皇制を支えるものだという彼の大相撲・天皇制観と無関係ではないでしょう。
貴乃花は常々、後援会など内輪の集まりでは、天皇制を支える大相撲の精神をうたった「角道の精華」(かつての力士研修所の教材)を賛美し、「『角道の精華』にウソをつくことなく、国体を担っていける大相撲角界の精華を」などと語っていました(写真中)。
昨年の「貴ノ岩暴行事件」で貴乃花のこうした「思想」があらためてクローズアップされました。中島岳志東京工業大教授はこう指摘していました。
「彼(貴乃花)の発する言動の中には、極端なナショナリズムが見え隠れする。『週刊朝日』」12月22日号の『貴乃花親方の逆襲』では、支援者に送ったメールが紹介されているが、そこでは相撲協会を『国体を担う団体』と位置づけ、『日本を取り戻すことのみ』が『私の大義であり大道』だと述べている。九州場所の千秋楽打ち上げでも『日本国体を担う相撲道の精神』という言葉を使ってスピーチを行っている。
『国体』とは、日本という国を『万世一系の天皇』によって支えられてきた特殊な国柄と捉えるもので…貴乃花親方は繰り返し天皇に言及し、力士は『陛下の御守護をいたす』ことに『天命』があると述べていることから、意識的に『国体』という言葉を使っていることがわかる」(2017年12月26日付東京新聞夕刊)
昨年は、天皇の「退位特例法」(6月9日成立)論議の中で、安倍首相らの「女帝」を認めない皇室典範の「皇統男系主義」があらためて強調された時です。9月3日には秋篠宮の長女・眞子氏の「婚約会見」が行われ、女性皇族のあり方が話題になりました。
皇室をめぐるこうした動きの中で、天皇主義者の貴乃花巡業部長が、「女人禁制」の「伝統」を固守するため、地方巡業の「ちびっこ相撲」から女児を排除することを決めた、と考えてもけっして不自然ではないでしょう。
貴乃花ほどであからさまではありませんが、日本相撲協会が天皇制と密接な関係にあることは周知の事実です。昨年の「暴行事件」の中で、八角理事長(写真右の中央)が力士に対する「講話」(11月28日)で、「日本の国技といわれる相撲、日本の文化そして誇りを背負っているんです」と述べ、「日本の国技を背負う力士であるという認識」を強調したのも、貴乃花が言う「国体を担う相撲道」と大同小異でしょう。
今回の「女性は土俵から下りてください」アナウンス(4日、舞鶴巡業)、「ちびっこ相撲」からの女児排除であらためて明らかになったのは、大相撲の女性排除(差別)の実態(伝統)であり、それが天皇制と深く結びついたものだということです。
そうした女性排除・差別が、私的な宗教観にとどまらず、日本相撲協会という公益法人の正式な運営方針になっているところに、無意識のうちに「(象徴)天皇制」が根を張っている日本社会の問題性があると言えるでしょう。



「人命が第一」「伝統より人命」は誰でもわかることです。にもかかわらず日本相撲協会の「若手行司」が「女性は土俵から下りてください」と繰り返し放送した(4日、舞鶴市の春巡業)のはなぜか。個人の問題ではありません。
それは、女性が大相撲の土俵に上がれないという「伝統」はたんなる「伝統」や「風習」ではなく、神道、そして天皇制と深く結びついたものだからです。大相撲・日本相撲協会は歴史的にも今日的にも天皇制と深く関係しています(写真右は大相撲を観戦する天皇・皇后)。
なぜ「女性は土俵に上がれない」のか。
「古くからの風習と観念に基づいて土俵は神聖な場所と見なされ、月ごとに生理がある女性を固く禁じてきました」(根間弘海専修大教授『ここまで知って大相撲通』グラフ社)
「不浄な存在の女性は、神聖な場所に立ち入れないという昔からのしきたり」(武田和衛・フリーライター『大相撲!』ローカス)
その意味をさらに突っ込んで説明しているのが、女性で初めて横綱審議委員になった作家の西館牧子氏です。
西館氏は、「土俵の女人禁制を男女差別と思っていない」「女が土俵にあがる必要はない」としながら、「なぜ女性は土俵にあがってはならないのか」としてこう述べています。
「それは、『土俵は俵で結界(魔物の侵入を防ぐ区域―引用者)された聖域』だからである。…つまり、過去、女性は障害物として見られて、結界内に入ることができなかった。それが今に伝わっており、土俵は女人禁制なのである」(『女はなぜ土俵にあがれないのか』幻冬舎新書)
「聖域」とは?
「大相撲における核は『神にかかわる部分』ではないか。…ことあるたびに、協会(日本相撲協会―引用者)が『聖なる土俵』『相撲は神事』と言うのは、土俵とその周辺に神がいるからである」(西館氏、同前)
「神」とは?
「相撲場の『中心』は結界された聖域であったが、それは天皇という現人神のための聖域であった」(西館氏、同前)
土俵に女性を上げないのは、「神の聖域」を汚さないためであり、その「神」とは「天皇という現人神」だというのです。
事実、大相撲と天皇(制)の関係は歴史的に根深く、特に相撲協会は裕仁天皇(昭和天皇)と強く結びついてきました(2016・3・26、2017・1・10のブログ参照https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20160326 https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20170110)。
女性を「不浄」として「女人禁制」にすることは差別であり、人権上許されないことは明白です。しかも、日本相撲協会は文科相が認可する財団法人です。大相撲はけっして私的な催しではありません。
さらに問題なのは、神道につながる「性差別」「男尊女卑」が国の法律になり、制度化されていることです。それは皇室典範の男系主義です。
現在の皇室典範(1947年5月3日施行)は第1条で「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」として、「女性天皇」を否定しています。これは明治の皇室典範(1889年2月11日発布)の第1条「大日本帝国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス」をそのまま引き継いだものです。
明治の皇室典範はなぜ「女帝」を禁じたのか。種々の理由がありますが、その一つは女性差別です。
「(明治皇室典範制定時の―引用者)女帝否定論者の議論には、見え隠れしながら、しかしきわめて決定的に、セクスィスト(性差別者)の立場が遍在しているということである」(奥平康弘東大名誉教授『「萬世一系」の研究』岩波現代文庫)
伊藤博文とともに皇室典範制定の中心になった井上毅は、明治天皇に進言した私案(「謹具意見」)の中で、「男を尊び、女を卑むの慣習、人民の脳髄を支配する我国に至ては、女帝を立て皇婿を置くの不可なるは、多弁を費すを要せざるべし」という女帝否定論者(沼間守一)の言葉をそのまま盛り込みました(鈴木正幸神戸大教授著『皇室制度』岩波新書より)。
現在の皇室典範の男系主義(女性天皇否定)の思想的基盤はこうした「男尊女卑」「女性蔑視」であり、それは天皇制イデオロギーの中心と言われます。
「萬世一系の皇統は、こうした異姓(女帝―引用者)によって汚損されてはならない!―そういった“家督”思想なのである。まさにこの思想こそ、明治支配層らが井上毅ら明治法制官僚たちをつうじて確保しようとした天皇制イデオロギーの中核であ(る)」(奥平氏、同前)
政府は来年の「新天皇即位」で、天皇の証しとされる「三種の神器」を引き継ぐ儀式(「剣璽等承継の儀」)に「女性皇族」は参加できないと決めました。皇室典範では女性に皇位継承権がないからというのが理由です。
「女性が土俵に上がれない」ことと、女性皇族が「即位儀式」の一部に参列できないことは、神道・天皇制(皇室典範)の「女性差別」「男尊女卑」において通底しているのです。
相撲協会に「伝統の見直し」を求めると同時に、皇室典範、さらに(象徴)天皇制自体を考え直す必要があります。



2月11日は「建国記念の日」という名前の祝日でした。各地で「護憲派」と「改憲派」の集会が行われました。広島市内では護国神社(天皇の名で戦没者を祀る神社)へ向けて女性や子どもによる「なでしこ行進」が行われたといいます。
「建国記念の日」は、「建国をしのび、国を愛する心を養う」という「趣旨」で1966年に制定が強行されました。「2月11日」は紀元前660年のこの日、神武天皇が即位したとする日で、旧「紀元節」をそのまま引き継いだものです。
しかし、「神武帝は六~七世紀の朝廷貴族が天皇の日本支配を権威づけるためにつくりだした架空の人物であり、また主権在民の憲法をもつ現代の日本国民が、二月一一日つまり古代天皇制の成立を祝日とすることはおそろしい時代錯誤」(藤原彰氏ら『天皇の昭和史』新日本新書)です。
その「建国記念の日」(旧「紀元節」)が、「東京オリンピック」とただならぬ関係があったことはあまり知られていないのではないでしょうか。
満州事変前年の1930年、当時の東京市長(現知事)永田秀次郎は10年後の1940年に開催される第12回オリンピックを東京で開催するよう招致運動することを決めました。40年に政府が全国で大々的に行う記念行事の目玉にするねらいです。
その記念とは、「紀元二千六百年」。1940年は神武天皇が即位したとする紀元前660年から2600年になるとして、政府は10年前の1930年から全国的キャンペーンを展開しました。
衆議院でも鳩山一郎(のちの首相)らによって、東京オリンピック開催を求める「建議案」が提出されました(1935年2月19日)。そこでこう述べています。「開催の年は二千六百年に該当し神武天皇の御偉業を景仰記念すると共に、日本建国三千年の文化を宣揚紹介し…画期的事業の達成を望む」(橋本一夫著『幻の東京オリンピック』講談社文庫より)
ムッソリーニ(イタリア)の協力もあって、1936年7月のIOC総会で第12回オリンピックを東京で開催することが決まりました。ポスターまでつくられました(写真中。神武天皇を描いていると思われます。『幻の東京オリンピック』より)
しかしその後、皇国日本の侵略戦争激化のため、オリンピックどころではなくなりました。
「1940年東京オリンピック」はこうして幻に終わりましたが、「紀元二千六百年」という皇国史観と「東京オリンピック招致」という国家主義の結合の歴史がここにありました。
「紀元二千六百年」をめぐって見過ごせない歴史がもう1つあります。
1940年の「紀元二千六百年祝典」に向け、天皇の政府は「皇国臣民」「内鮮一体」の名のもとに、植民地・朝鮮人による「朝鮮人建国奉仕隊」なるものを作り、神武天皇を祀っている橿原神宮(奈良、写真右)の拡張工事などに従事させたのです。
「朝鮮人建国奉仕隊」にはそれまでの朝鮮人強制連行とは違う意味合いがあったと言われています。
「1938年の国家総動員法体制の一環から、何よりも総動員の動機づけ=イデオロギー支配として、『皇国臣民』『内鮮一体』強化が意図されたなかでの朝鮮人建国奉仕隊の存在は、国家が直接介入した朝鮮人動員が始まったことを意味する」(川瀬俊治氏「「紀元二千六百年祝典」と朝鮮人建国奉仕隊」=「季刊戦争責任研究・第51号」)
架空の「神武天皇即位」からの「紀元二千六百年」という皇国史観は、こうして朝鮮人を「皇国臣民」に取り込み、植民支配を強化するテコになったのです。
敗戦後、1964年に「東京オリンピック」は現実となりました。その「名誉総裁」は天皇裕仁でした。
そして2020年。「朝鮮脅威」論がふりまかれ日米軍事同盟が強化される中で2回目の「東京オリンピック」が行われます。前年の19年に即位する新天皇徳仁の国際的お披露目舞台となり、安倍政権が「日本再興」(東京オリンピックの基本方針=2015年11月27日閣議決定)として「国威発揚」を図るのは必至です。
天皇制とオリンピック、そして民族差別。皇国史観と大国主義の結合は、けっして過去の話ではありません。
「2020年は紀元二千六百八十年」という安倍首相の声が聞こえてきそうです。



天皇・皇后は8日、大相撲初場所の初日を観戦しました(写真左)。天皇の「大相撲観戦」は恒例で、この3年は毎年行われています。昨年も初場所の初日でした。
天皇はなぜ大相撲を観戦するのでしょうか。
たんなる「趣味」ではありません。コンサートや展覧会へ行くのとは質的に違う意味を持っています。
「宮内庁は天皇の活動を『国事行為』『公的行為』『その他の行為』の三つに分類し、わずかな例を除き、ほとんどの活動を公務と位置付けている」(1日付中国新聞=共同)
宮内庁が憲法上の「国事行為」ではない「公的行為」「その他の行為」なるものも「公務」としているのは事実上の憲法違反です。それをそのまま紹介する記事もきわめてずさんですが、ここで注目したいのは、この記事の続きです。
「『その他の行為』は、芸術奨励を目的とした音楽や絵画鑑賞などが公務に含まれ、宮中祭祀や御用邸での静養、大相撲観戦は公務ではない純粋に私的な行為とされている」(同)
天皇の活動はほとんどが「公務」だが、「わずかな例外」がある、その1つが「大相撲観戦」だ、というのが宮内庁(国)の見解です。「音楽や絵画鑑賞」は「公務」だが「大相撲観戦」はそうではなく「純粋に私的な行為」だとは、なんとも不思議な解釈ではないでしょうか。
記事にはその理由は書かれていませんが、考えられることは1つ。「大相撲観戦」は「宮中祭祀」と同類の宗教活動、皇室神道にもとづく活動だということではないでしょうか。
事実、日本相撲協会はその「使命」を、「太古より五穀豊穣を祈り執り行われた神事(祭事)を起源とし、我が国固有の国技である相撲道の伝統と秩序を維持し継承発展させる」(協会HPより)ことだと規定しています。
毎年初場所が始まる前に、時の横綱はそろって外で土俵入りを披露(奉納)することになっています。今年も6日に行われました。その場所は、明治天皇を祀っている明治神宮です。(写真右)
土俵の屋根(写真中)は神明造という様式ですが、これは天照大神を祀っている伊勢神宮の神明社の様式に合わせたものです。
こうした天皇と大相撲の宗教的結びつきから、さすがの宮内庁も「大相撲観戦」を天皇の「公務」とすることはできないのではないでしょうか。
問題は、天皇と大相撲のこうした関係、宗教性をどれだけの人が理解しているかです。「大相撲観戦」が「音楽や絵画鑑賞」と違い、宮内庁も「公務」ではなくて「純粋に私的な行為」だと言わざるをえないほどの宗教的行為であることを知っている人がどれほどいるでしょうか。
こうした事実は隠されたまま、大相撲は「国技」とされ、天皇・皇后が観戦に訪れれば来場者は総起立して拍手を送る。これは天皇の「公務」と宗教活動の区別をなし崩しにし、無意識のうちに「天皇制」と神道を「国民」に浸透させるものではないでしょうか。
憲法上、天皇に認められている行為は何なのか。天皇の「私的行為」である宗教(神道)活動が公的粉飾をまとってまかり通っている実態はないか。それを明らかにすることは、「象徴天皇制」の是非、「天皇制」の今後を考えるうえで最小限必要なことではないでしょうか。