



 西田昌司・自民党参院議員の沖縄戦歴史改ざん発言をめぐり、作家の目取真俊氏が沖縄タイムスに寄稿した論稿の中でこう指摘しています。
西田昌司・自民党参院議員の沖縄戦歴史改ざん発言をめぐり、作家の目取真俊氏が沖縄タイムスに寄稿した論稿の中でこう指摘しています。
















沖縄の米軍キャンプ・ハンセンの新型コロナ感染者は、21日現在207人にのぼり、玉城デニー知事は同日、日米両政府に、「米本国からの軍人・軍属の移動停止、基地外への外出禁止」を要請しました(写真中)。沖縄・米軍基地の大規模クラスター(集団感染)はますます深刻な問題になっています。
しかし、こうした沖縄の窮状・訴えが、岸田政権はもちろん、日本のメディアの眼中にはまったくないことが、同じ21日夜の首相記者会見(写真左)で露呈しました。
会見では冒頭、岸田首相が約20分発言したのに続き、14人の記者が質問しました(大手メディア7人、地方紙(沖縄以外)4人、外国メディア2人、フリーランス1人=江川紹子氏)。
岸田氏はもちろん、14人の記者の中で、沖縄・米軍基地のクラスター問題に触れた記者は1人もいませんでした。
ここには、沖縄、基地問題に対する日本(「本土」)メディアの欠陥が象徴的に表れています。
第1に、米軍基地を沖縄に集中させ、犠牲を押しつけておきながら、その被害の実態には目を向けようとしない、沖縄に対する「構造的差別」が表れていることです。それは、辺野古新基地建設強行に対する無関心・軽視と同根です。
第2に、米軍基地がコロナ感染対策の大きな障害になっていることを追及する視点が皆無だということです。それは市民の命と健康を顧みない米軍を容認・免罪していることに他なりません。
このメディアの「米軍基地タブー」は、沖縄に限らず、「本土」の米軍基地にも対しても同じです。
第3に、以上の2つの問題の根底には、日本のメディアの日米安保条約(軍事同盟)支持・擁護の基本姿勢があることです。
玉城知事の要請に対し、米軍は、「移動停止に関しては「日米安保条約の義務履行を妨げずにどのように対処できるか考えたい」と回答した」(22日付沖縄タイムス)と報じられています。
言い換えれば、日米安保条約に基づいて活動しているのだから、移動停止の要請には応じられない、ということです。これは米軍基地がコロナ対策の抜け穴になっている元凶が日米安保条約であることを米軍自ら吐露したことにほかなりません。
しかし、日本のメディアはその根源にまったく目を向けようとしていません。
重要なのは、こうしたメディアの弱点・欠陥は、メディアの問題にとどまらず、そのまま日本の「世論」、「市民」に反映していることです。メディアが「沖縄差別」「米軍基地タブー」「日米安保条約支持」の「世論」を作り出しているのです。


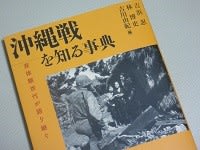
23日付の琉球新報、沖縄タイムスは、沖縄戦当時の島田叡(あきら)県知事(写真中)、荒井退造警察部長を描いた映画「島守の塔」(五十嵐匠監督)の「製作を応援する会沖縄」が22日結成されたと大きく報じました(沖縄タイムスは1面、写真左)。
結成式で五十嵐監督は「島田さん、荒井さんの偉人伝を作るつもりは全くない」(23日付琉球新報)と述べていますが、「極限状態の沖縄戦で、人間は他人を思うことができるのかということがテーマだ」(同)としており、島田知事や荒井部長が美化させるのは必至でしょう。琉球新報も島田知事を「沖縄戦当時、食糧確保や疎開に尽力したとされる」と好意的に紹介しています。
かつて島田知事と荒井部長を描いたテレビドラマが放送されたこともあり(2013年8月TBS系)、両氏を「偉人」とする見方は「本土」でも少なくありません。
しかし、これは事実に反した評価・美化であり、「本土」の帝国日本政府が任命した知事、県警部長(中央官僚)が沖縄戦で果たした歴史的役割に対する評価を誤らせるものです。
『沖縄戦を知る事典』(吉浜忍・林博史・吉川由紀編、吉川弘文館2019年、この項P70~73林博史氏執筆)から抜粋します。
< 内務省は「軍の司令官らと協調してやってくれる知事」として島田叡を選んだ(当時の警保局長の証言)。沖縄県民を犠牲にしようとする軍に対して県民を守ろうとするのではなく、軍の要求にこたえる知事として選ばれたのである。
知事のきわめて重大な行為の一つが、鉄血勤皇隊への学徒の動員である。第32軍司令官、沖縄連隊区司令官(徴兵業務を担当)、沖縄県知事の三者による覚書がある。14歳から17歳までの学徒の名簿を作成して、県知事を通じて軍に提出し、その名簿を基に軍が学徒を鉄血勤皇隊に軍人として防衛召集し、戦闘に参加させることが取り決められていた。県知事は本来兵士に召集される義務のない学徒を軍に提供した。いくつかの史料からこれは島田知事によるものと考えられる。
45年4月27日、市町村長会議が県庁壕で開催された。この会議で(島田は―引用者)米軍が住民まで皆殺しにすると恐怖を煽り、住民にも一人残らず竹やりなどを持って戦うように指示していた。>
以前(2013年)、琉球大学で行われたシンポジウムで、郷土史研究家の川満彰氏(名護市教育委員会)が、島田知事についてこう述べたことがあります。
「陸軍中野学校出身者の離島残置謀者(離島に残って諜報活動を行う日本兵)に(偽装のための)教員免許を公布したのは島田叡だ。その戦争責任はどうするのか」(2013年10月25日のブログ参照https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20131025)
島田叡と荒井退造は「本土」政府・大本営に忠実に従って沖縄戦を遂行する官僚として送り込まれ、事実その通り行動したのです。その島田、荒井を評価・美化することは、誤りであるだけでなくきわめて危険な意味を持ちます。
「今日、有事(戦時)法制を考えるとき、地域の戦争体制を作るのは自衛隊というより警察を含めた行政機関である。沖縄の戦時体制を作った行政・警察を美化することはこの問題から人々の目をそらせることになりかねない」(林博史氏、前掲『沖縄戦を知る事典』)
沖縄戦から75年。事実を正確に掘り起こし、教訓を導くことが改めて重要になっているいま、島田、荒井を美化することはまさにそれに逆行するものと言わねばなりません。
さらに重大なのは、この「映画『島守の塔』製作を応援する会沖縄」の「呼びかけ人」47人に、琉球新報、沖縄タイムス、琉球放送、沖縄テレビ、琉球朝日放送など、沖縄メディアの代表が揃って名を連ねていることです。沖縄メディアの見識が問われます。その責任はきわめて重いと言わざるをえません。



辺野古埋立の石材運搬に本部港を使用することが11日、許可されました。直接許可したのは本部町ですが、実質は港の所有権を持つ沖縄県・翁長雄志知事の許可です。
翁長知事は4日前の7日にも、中城湾港の使用を許可したばかりです。これで奥港(国頭村)の使用許可(9月上旬)に続いて「埋立石材運搬の港使用許可」3連発です。
奥港の許可以来、翁長氏に対し「公約違反」との批判が強まり、住民団体などから「使用許可撤回」要求が相次いで提出されている中での「使用許可」強行です。「公約違反」だけでなく翁長氏の「県民・住民無視」は顕著です。
翁長氏にもともと進んで辺野古新基地を阻止する意思がないことは、知事就任以来、再三指摘してきました。その地金が表れてきているわけです。
そんな翁長氏に「あらゆる知事権限」を行使させ、新基地阻止に向かわせるのは、世論の力以外にありません。その点で重要な役割を担っているのが、琉球新報と沖縄タイムスです。
ところが、県内で絶大な影響力をもつこの県紙2紙の姿勢が、このところ目に見えて後退してきています。
例えば、「本部港の使用許可」の報道(12日付、写真左、中)は、新報が1面3段と社会面に関連記事。タイムスも1面3段で2面と社会面に関連記事。いずれも1面トップではまく、社説もなく、この件での翁長氏に対する取材もありません。
「中城湾港の使用許可」報道(8日付)の後退ぶりはさらに顕著で、新報はかろうじて1面3段、2面に関連記事があるものの、タイムスにいたっては3面3段記事のみ。いくら「保育園への落下」というニュースがあったにせよ、この扱いはひどすぎます。両紙とも社説で取り上げていないのはもちろん、これまでなら節目節目に行っていた翁長氏への取材と「一問一答」はまったく影を潜めています。
それだけではありません。新基地阻止の切り札である「埋立承認撤回」について、タイムスは半年前の社説では、「埋め立てを強行し、新基地を建設することは、行政の公平・公正性からいっても、環境影響評価のあり方からしても、看過できない重大な問題をはらんでいる。それだけでも埋め立て承認を撤回する理由になる」(5月28日付沖縄タイムス社説)と主張してていたにもかかわらず、今では、「焦る民意…今すぐ撤回すべきだとの市民の主張には、基地建設阻止への論理的な主張が見えない」(10日付沖縄タイムス解説記事)と、撤回を求める市民に批判の矛先を向ける始末です。
「承認撤回」の主張を前面に出さなくなったのは、新報も同様です。
こうしたタイムス、新報の姿勢の後退(変質)(特にタイムスに顕著)の背景に何があるのかはわかりません。
しかし、言うまでもなく、辺野古新基地阻止のたたかいは終わったわけではありません。今がまさに正念場です。
この重要な局面で、翁長氏の「公約違反」や「承認撤回」の有効性を客観的に明らかにし、翁長氏に「公約」実行を迫ること、そして辺野古の現場で連日たたかっている人たちをはじめ、新基地阻止を求める県民・市民に寄り添い、その目線で報道すること。
それが今求められているジャーナリズムの使命ではないでしょうか。
<お知らせ>
『「象徴天皇制」を考える その過去、現在、未来』(B6判、187ページ)と題した本を自費出版しました。
これまで当ブログに書いてきた「天皇(制)」の関するものをまとめたものです(今年10月までの分)。「天皇タブー」が蔓延する中、そしてこれから「退位・即位」に向けて「天皇キャンペーン」がさらに大々的に繰り広げられることが予想される現状に、一石を投じたいとの思いです。
ご希望の方に1冊1000円(郵送料込み)でおわけします。郵便振り込みでお申し込みください。
口座番号 01350-8-106405
口座名称 鬼原悟
今後とも、当ブログをよろしくお願いいたします。