













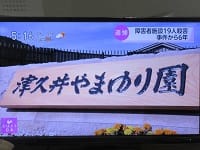
















終バスが行ったあとの渋谷バス停で、座って体を休める路上生活をしていた大林三佐子さん(当時64)が、近所の男に殴打され死亡(2020年11月6日)して、半年になります。
1日夜のNHK「事件の涙」はこれを追跡取材しました。ネット上ではいまも大林さんを悼む書き込みが絶えず、その多くは女性だといいます。「いつ自分が同じようになってもおかしくない」「彼女は私だ」
大林さんは広島市生まれ。小さい時から人と接するのが好きで、広島にいるときは劇団に所属していたこともある(写真右)。27歳で結婚して東京へ。しかし1年で離婚。理由は夫の暴力。コンピュータ関係の会社に勤めたが、30歳で退職。数年ごとに転職を繰り返した。
10年ほど前から、短期契約のスーパーなどの試食販売員で食いつないだ。日給約8000円。給料が出るとすぐにコンビニで電気代やガス代を払っていた、と親しかった同僚は言う。
毎年クリスマスには郷里の母親と首都圏に住むただ一人の弟にカードを送った。かわいいイラストを手書きして。そのカードが4年前から届かなくなった。同時期、大林さんはアパートから出た。家賃が払えなくなった。キャリーケースを持ち歩く生活になった。
「試食販売で自分で生活を立て直そうとしていた。けれど、頑張っても頑張っても、はい出せなかった。アパートを借りることもできなかった」(元同僚)
その試食販売の仕事も、コロナ禍でなくなった。
大林さんの死は、何を問いかけているのでしょうか。番組で紹介された関係者の言葉を手掛かりに考えたいと思います。
姉が路上生活をしていたことは事件後初めて知ったという弟―「なぜ助けを求めてくれなかったのか」
路上生活者を支援しているNPO代表―「路上生活者は助けを求めにくい。とくに女性は人に声をかけにくい。怖いから」
事件前からバス停で大林さんを見かけていたという近所の男性―「どうすることもできなかった。ちょっとした優しさが何になるかわからなかったし」
実父からの性暴力で家を出てホームレスになり、SNSで知り合った男性の家を転々として暮らしていた21歳のK さん。大林さんが亡くなったベンチに花を供え―「(路上生活者にとって周りは)別世界なんです。私はこの世界にはいない…。自己責任と言われる社会。その人(大林さんのような人)を見つけることができない社会なんです」(K さんは去年夏からSNSで見つけた支援団体の援助でアパートに入居)
番組ナレーション―「事件後、小さな変化が起きています。路上生活を支援する若者が増えているのです」
結婚から死に至るまで、大林さんの人生はこの社会の女性差別に貫かれていました。コロナ禍がそれを助長しました。
「なぜ助けを求めなかった」。残念な思いからつい言ってしまいそうな言葉ですが、それはベクトルが逆でしょう。「夜道は危険。痴漢に注意」の標語同様、被害と加害が逆転しているのではないでしょうか。
「ちょっとした優しさが何になる」。たとえ何もできなくても、「大丈夫ですか?」と声をかけるだけで、大林さんの孤立感はいくらかでも和らいだのではないでしょうか。
考えたいのは、「ちょっとした優しさ」をどこへ向けるかです。
大林さんの姿を見かけていた人の中で、行政(区役所)に知らせた人はいたのでしょうか。「路上で困っている人がいます。支援を」と。警察は巡回で大林さんを見かけていたはずです。知っていながら見て見ぬふりをしていたのではないでしょうか。
問うべきは行政・政治の責任です。市民の「ちょっとした優しさ」は行政・政治への突き上げに向かうべきです。路上生活を支援する若者が増えているのは素晴らしいことです。が、その気づき、「優しさ」は政治・行政へ向けられてこそ生かされるのではないでしょうか。
「自助」「共助」の危うさ。「自助」と「共助」は紙一重です。問われるべきは「公助」です。いいえ、「公助」という言葉自体、トリックです。公(政治・行政)が市民の命・生活を守るのは援助ではなく責務です。「公助」ではなく「公責」と言うべきです。
首相が就任後初の所信表明演説で「私が目指す社会像は、自助・共助・公助」(2020年10月26日、菅義偉首相)と、「公助」よりも「自助・共助」を前面に出してはばからない日本。大林さんの死が問いかけているのはそんなこの国のあり方です。