








11月3日は日本国憲法が公布(1946年)された「文化の日」とされていますが、もともとは「天長節」、睦仁天皇(明治天皇)の誕生日が起源です。今でも「文化の日」という名前とは裏腹に民主主義に反する天皇制と深くかかわっています(昨年11月4日のブログ「「文化の日」と天皇制」をご参照くださいhttps://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20191104)。
ここでは、74年前に天皇裕仁(昭和天皇)によって公布された日本国憲法の問題点を沖縄との関係で考えます。
菅義偉首相は学術会議推薦の6人を任命拒否した言い訳に、憲法15条第1項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」を持ち出しています。憲法にはいたるところに「国民」の言葉があります。この「国民」とはいったい誰のことでしょうか?その中に沖縄の人々は入っているでしょうか?
憲法改正(新憲法制定)を審議する国会議員を選出するための衆院議員選挙が1946年4月10日に行われました。そのための選挙法改正が1945年12月に成立しました。この選挙法で初めて女性の選挙権が認められ、教科書などでは「普通選挙法」と評価さています。
しかし、この選挙法には重大な問題がありました。「沖縄県民の選挙権を、台湾・朝鮮など旧植民地の出身者の選挙権とともに停止するという重大な欠陥を孕むものであった」(小林武著『沖縄憲法史考』日本評論社2020年9月、写真右)のです。
なぜ沖縄県民の選挙権は「停止」されたのでしょうか。
「沖縄は、一九四五年四月、米軍上陸と同時に発せられた「米海軍軍政府布告第一号」(いわゆる「ミニッツ布告」―引用者)によって「すべての政治および管轄権」が米国海軍の下におかれることになった。ここでは「日本帝国政府の総ての行政権の行使」が停止され、その後、八月に本土の戦闘が終結し、日本政府が降伏文書に調印した九月以降も、沖縄には日本政府の行政権は及ばなかったのである」(古関彰一著『平和憲法の深層』ちくま新書2015年)
沖縄は日本の敗戦以前から米軍に統治され、日本の行政権は及ばず、戦後も選挙権をはく奪。沖縄県民が排除された選挙で選ばれた国会議員たちによって現行憲法は審議・決定され、天皇が公布したのです。
さらに重大なのは、その異常性を指摘し異議を唱えた議員・政党が皆無だったことです。
「この憲法を審議する段階で、沖縄県民が「国民」であると考えれば、沖縄県民を除いて「全国民を代表する」(憲法43条―引用者)議員の選挙を実施することは…できなくなると考える議員が出てこなかったことが不思議でならない。
しかし、議員ばかりか、憲法学者も政治学者も、現実の沖縄県民は「全国民」ではないと判断して憲法四三条をつくったのであろうか。…憲法学者で貴族院議員の宮沢俊義も、政治学者で貴族院議員の南原繁も…なにひとつ語っていないのである。…当時共産党の書記長であった徳田球一もいた。徳田は沖縄名護市の出身であった(けれど何も異議を唱えなかった―引用者)(古関彰一氏、前掲書)
「本土」から沖縄に移住して言論・学究活動を行っている小林武氏もこう指摘します。
「国民主権を原理とする憲法の制定が主権者国民の一部(沖縄県民―引用者)の参加を拒否してなされたことは、今日においても改めて重大視しておくべき事項であると考える。あまつさえ、その重大事が当時も今日に至るまでも、学問的作業の中でさえほとんど等閑に付されてきたことが問題を一層深刻なものにしている、と思われるのである」(前掲書)
沖縄県民を排除して「全国民」と定義した憲法を制定した。そのことに誰一人異議を唱える議員、学者はいなかった。そしてその重大事は今日に至るも問題にされていない―このことの重大性、日本国憲法と沖縄、日本のこの関係を私たち日本人は肝に銘じる必要があります。
沖縄は「施政権返還」(1972年、写真中)によって日本国憲法下に入りました。しかし、辺野古新基地建設はじめ米軍基地が集中していることに端的に表れているように、沖縄は「構造的差別」におかれています。それは、沖縄県民を排除・差別して憲法を制定・公布した歴史がまったく清算されていないことを示しているのではないでしょうか。



8月2日のNHK「目撃ニッポン」で、沖縄の「幻の女流作家」といわれる久志芙沙子(くしふさこ・本名久志ツル、1903~1986、写真左)の存在を初めて知りました。沖縄と日本(ヤマト)の埋もれた歴史の一端です。
番組は、芙沙子の孫の加古淑(ひで)さん(写真中の左)が沖縄を訪れ、祖母の足跡をたどるというものでした。芙沙子の生涯は、直木賞作家・大島真寿美(写真中の右)の『ツタよ、ツタ』(小学館文庫、2019年)で(フィクションとはしながら)克明に描かれています。
芙沙子は祖父が琉球王朝で総理大臣級の重臣を務めたほどの名門中の名門の出身。それが日本による琉球併合(いわゆる「琉球処分」1879年)で没落。母と二人の困窮生活ののち、19歳で作家を目指して上京。結婚して台湾、名古屋に移ったあと離婚し、7歳年下の学生と駆け落ち同然に再び上京。そこで後に「幻の作家」と言われるようになる「筆禍事件」が起こります。
1932年、「婦人公論」の懸賞に応募し、同年6月号に、「滅びゆく琉球女の手記―地球の隅っこに押しやられた民族の歎(なげ)きをきいて頂きたい」と題した芙沙子の作品が掲載されました(連載の1回目。写真右)。タイトルは編集部が勝手につけたもので、芙沙子がつけたタイトルは「片隅の悲哀」でした。
「主人公の女性の視点を通して描かれていたのは、疲弊した琉球の現実や、琉球の出自を隠して(東京で―引用者)立身出世した叔父、そして故郷に残された老母たちの困窮である。うち棄てられた女たちに「琉球の現実」が象徴されている」(勝方=稲福恵子早稲田大名誉教授、前掲『ツタよ、ツタ』の解説)という作品でした。
これに対し、在京の「沖縄県学生会」が猛烈に抗議。編集部に押しかけ、謝罪と掲載中止を要求しました。学生らは「(琉球の現実は)就職や結婚の妨げとなる「恥」であるから蓋をすべきであると考え(た)」(勝方=稲福恵子氏、同)のです。
「婦人公論」編集部は抗議に屈し、翌7月号に「謝罪文」を掲載するとともに、連載を打ち切りました。そればかりか、芙沙子に「釋明文」を書かせて掲載しました。その内容は次のようなものでした(抜粋)。
「學生代表のお話ではあの文に使用した民族と云ふ語に、ひどく神経を尖らしてゐられる様子で、アイヌや朝鮮人と同一視されては迷惑するとの事でしたが今の時代に、アイヌ人種だの、朝鮮人だの、大和民族だのと、態々(わざわざ)階段を築いて、その何番目かの上位に陣取つて、優越を感じようとする御意見には、如何(どう)しても、私は同感する事が出来ません」(前掲、勝方=稲福恵子氏の解説より)
「釋明文」といいながら芙沙子はけっして「釈明」などしていません。逆に抗議した学生たちの誤りを鋭く批判しています。これが、1932年(満州事変の翌年)に沖縄出身の女性によって書かれた文章なのですから、目を見張ります。
芙沙子は抗議に屈しませんでした。しかし、これを機に再びペンを執ることはありませんでした。「幻の作家」といわれるのはそのためです。
それから41年後の1973年(「本土復帰」の翌年)、かねて芙沙子の「釋明文」に注目していた沖縄の月刊誌(「青い海」)の女性記者が芙沙子の居場所を突き止め、インタビューを申し込みました(同誌73年12月号に「四十年目の手記」が掲載)。困惑した芙沙子の思いを、『ツタよ、ツタ』はこう描いています。
「無名の女の、それも連載第一回のみしか発表されなかった小説を発端とする、あんな莫迦げた騒ぎが、なぜ、今になって注目されるのだろう?釈明文に至っては文学作品ですらない。…ようするに、四十年、この世界はなにも変わらなかったということか」
それからさらに47年。いま、沖縄と日本(ヤマト)の関係は、琉球、アイヌ、朝鮮など少数・異民族に対する日本社会の実態は、どれほど変わっているのでしょうか。
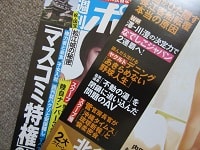


写真誌「フライデー」(6月26日号、講談社発行)に、「スクープ撮 菅官房長官が『沖縄タイムス』『琉球新報』と“懐柔密会”」という見出しの記事が出ました(写真中)。
6月8日夜、「都内超一流ホテルのロビー階にあるバーの個室」で、菅氏と「沖縄タイムス、琉球新報の幹部」が、「2時間以上」会談した。前の週に官房長官サイドから「地元紙との懇親をはかりたい」との打診があり、「場所等は、官邸側で準備した」、というのが記事の概要です。
同記事には、タイムス、新報の次のようなコメントが載っています。
「菅長官から直接話をうかがい、考えを聞く機会と捉え、取材方法の一環として参加しました。菅長官は基地移設計画を進める従来の政府方針を説明しただけで、理解を求める発言はなかったと記憶しております。会合によって、沖縄タイムスとしての立場に変更はありません」(沖縄タイムス社東京支社)
「日常の取材活動、取材源についてのコメントは差し控えます。辺野古新基地問題についての本紙の報道姿勢に変更はありません」(琉球新報社東京報道部)
両紙ともいまのところ「フライデー」に抗議はしていません。
この記事が事実なら、私が最も気になるのは、当日の飲食代を誰が出したのかということです。両紙が取材費として出したのか、菅氏が「官房機密費」から出したのか、それとも割り勘だったのか。
首相をはじめ時の政権幹部とメディアが、夜の料亭やホテルで飲食を共にしながら「懇談」するのは、新報、タイムスに限らず、残念ながら日本のメディアの宿痾です。
折しも、「週刊ポスト」(6月19日号、小学館発行)は、「『マスコミ特権』は世界の恥だ」と題する特集を組み、「安倍首相と大新聞・テレビ幹部&記者『夜の会食』完全リスト」(写真右)なるものを掲載しました。
第2次安倍政権の2013年1月から15年6月1日までの首相とメディアの「夜の会食」を、一覧表(表にあらわれているものだけ)にしたものです。
数えてみると、その回数は61回にのぼります。一覧表に出ている「参加者」を会社ごとに分類すると、のべ人・回数は次の通りとなります。
「読売」18、「時事」10、「産経」9、「毎日」7、「朝日」6、「フジテレビ」5、「日テレ」5、NHK4、「日経」4、「共同」4、「テレ朝」4、「中日(東京)」2、「中国」1、「西日本」1、「静岡」1。このほか、「報道関係者」3回、「内閣記者会キャップ」3回、「首相番記者」「報道各社の論説委員」「報道各社の政治部長」「女性記者」各1回など。ちなみに、個人で最も多かったのは、渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長で9回にのぼっています。
これらの「夜の会食」にかかった経費は官房機密費(もちろん税金)から出されるのが常です。この機密費というブラックボックス、民主党政権誕生時に「全容を解明する」と大見得を切りながら、雲散霧消してしまったのは記憶に新しいところです。
新報、タイムスがこうした「大手メディア」の悪弊の“仲間入り”をすることは、もちろん好ましいことではありません。
でも、新報、タイムスにいま最も問われていることは、はたしてこうした問題でしょうか。
沖縄タイムスは6月10日付で「翁長知事就任半年」の特集を組み、「辺野古強行国を追及」「痛烈な言葉、世論も支持」などの見出しで翁長知事の「半年」を賛美しました。琉球新報も翌11日付で「就任半年」をまとめ、「辺野古移設の考えを変えない国に、県行政としていかに対峙し、県民意思を実現していくかという命題に挑んでいる」と翁長氏を持ち上げました。
しかし、「就任半年」を振り返るなら、翁長氏が選挙で公約した「埋め立て承認の取り消し・撤回」に、半年たってもいまだに手を付けず、「視野に入れる」「選択肢」にとどめていることを、なぜ両紙は追及しないのでしょうか。
たとえば琉球新報は2月26日の社説で、「もやは許可取り消しの可能性を論じる段階ではない。…移設作業をこれ以上続けさせてはならない。翁長雄志知事は即刻、許可を取り消すべきだ」と主張しました。沖縄タイムスも3月8日の社説で、「これ以上のブロック投入やボーリング調査の再開を許してはならない。翁長知事には速やかに知事権限を行使してもらいたい。決断の時だ」と迫りました。
両紙のこうした主張はどこへ行ってしまったのでしょう。辺野古の事態はこれらの社説の時点よりさらに日々悪化していことは周知の通りです。両紙はなぜ当時の主張を引っ込めてしまったのでしょう。なぜ今こそ声を大ににて「取り消し・撤回」を求めないのでしょうか。そこに、「取り消し・撤回」を行わない翁長氏への配慮・迎合がないと言い切れるでしょうか。
翁長知事の言動を、メディアとしての曇りない目で見て判断・評価し、言うべきことを堂々と主張する。それがいま両紙に問われている最も重要な問題だと私は思います。

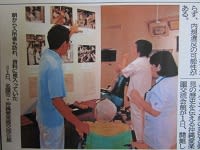

河直美監督(脚本も)の最新作「あん」(樹木希林主演)が、5月30日封切られました。ハンセン病元患者の生きることへの真摯な姿と、彼女と知り合ったことで再生する中年男性と少女の交流を描いた感動作です。原作はドリアン助川著『あん』(ポプラ文庫)。
奇しくもその2日後の6月1日、沖縄(名護市)の国立療養所・愛楽園内に、展示や映像でハンセン病隔離政策の歴史を後世に伝え、地域との交流を図る資料館、愛楽園交流館がオープンしました(写真中。2日付沖縄タイムスより)。
資料館開館に向け、2012年から企画運営委員会で20回以上熟議を重ねてきました。とくに、患者を屋外で解剖する映像や、強制堕胎による胎児標本の展示などをめぐっては、「衝撃的な事実が、逆にハンセン病に対する新たな偏見を生む可能性も考慮しながら、展示の在り方を判断した」(大城貞俊委員長、2日付沖縄タイムス)といいます。
全国のハンセン病患者が隔離されたのは、1931年の「らい予防法」から。その非科学的差別政策が解除(あくまで法律上)されたのは、1996年の同法廃止によって。ほんの19年前のことです。
全国のハンセン病患者と家族は、筆舌に尽くしがたい苦難を強いられましたが、沖縄ではさらに本土にない苦しみがのしかかりました。沖縄戦が差別を加重させたのです。
沖縄では日本軍による強制収容が1944年5月から本格化しました。収容された患者を待っていたのは、壕掘りという24時間体制の強制労働でした。
「末梢神経が麻痺している患者にとって壕掘りは苛酷な作業であり、傷を作っても気付かないことが多かった。気付いた頃には化膿し骨を痛め、切断以外に選択肢がない状態に追い込まれていた」(吉川由紀氏「ハンセン病患者の沖縄戦」-『友軍とガマ』より)
「病ゆえに家族と引き離されながら、治療らしい治療も受けられず強制労働に駆り立てられる。怪我をすれば手足を切断され、飢餓とマラリアに苦しむ中で、弱者がさらなる弱者の介護を強いられる。死者の埋葬や火葬にも無感覚になった」(同)
強制労働、米軍の空襲、非衛生による病気悪化、飢餓、マラリア・・・これは愛楽園とともに、沖縄のもう1つの施設、宮古島南静園(写真右)でもまったく同じでした。
国はなぜハンセン病患者を隔離したのか。
「その目的はハンセン病患者のない皇国建設のための『民族浄化』であった。らい予防法の制定も、患者ではなく、むしろ国民を『らい禍』から護るためのものであったのだ。戦争は隔離政策に拍車をかけ、無らい県運動の名のもと『祖国ヲ潔ムル為二!』患者を社会から締め出す方策が展開される。ハンセン病患者は皇軍の将兵になれない非国民であり、改めて、植民地をもつ一等国大日本帝国にとっての国辱とみなされた」(浜口稔氏「ハンセン病患者の語る戦世」-『沖縄と「戦世」の記憶』より)
「国辱の血の拡散を防ぐ終生隔離によって病根を断つための断種と堕胎を法制化した国家があり、その法律が許すがまま、彼らの人権を故意に、あるいは無知によって蹂躙したわたしたち日本国民がいたのである」(同)
天皇制国家によるハンセン病隔離政策は、日本だけでなく、植民地の韓国(更生園)、台湾(楽生園)、満州、パラオなどでも強行されたことを忘れてはなりません。
映画や原作の「あん」にはそうした背景は描かれていません。でも、「あん」では「聞く」という言葉がキーワードになっています。月の声を聞き、小豆の声を聞く主人公。「私たちはこの世を見るために、聞くために、生まれてきた。・・・だとすれば、何かになれなくても、私たちには生きる意味があるのよ」と語る主人公。
「聞く」ことは知ること、そして声なき声を想像することのにつながります。私たちは元患者さんたちが受けた差別の歴史、この国の暗い歴史を知らねばなりません。「無知」によって人を差別し人権を蹂躙しないために。
愛楽園資料館を訪れたら、館の内外にこだまする「いのち声」に耳を傾けたいと思います。



「明治産業革命遺産」(8県23施設)の「世界遺産登録」と安倍政権の関係については先に(5月7日)書きましたが、韓国はさらに具体的に、三菱長崎造船所(写真左)、高島炭鉱、三池炭鉱など、「7施設で5万7900人の朝鮮半島出身者が動員され、94人が死亡、5人が行方不明」(韓国国会報告)という数字をあげ、反対の姿勢を強めています。
日本政府はあくまでも、対象期間は「1853年から1910年(朝鮮併合)まで」だから韓国の批判は当たらない、と強弁しています。
これに対しては、次のような指摘があります。
「この枠組みは明治維新から日本の資本主義の核ができた時期までの近代化だけを賛美し、その後の強制労働などは一切見ない。これでは世界遺産に登録されても、歴史をきちんと検証できるか、韓国の人に疑問に思われても仕方がない。本当に後世に伝えるべきなのは、かつて日本の間違った政策で朝鮮や中国の人々が受けた痛みや悲しみの方ではないだろうか」(近代史研究家・竹内康人氏、東京新聞5月20日付)
同感です。そして、さらに付け加えなければならないのは、日本政府の植民地政策の犠牲になったのは、朝鮮、中国など東アジア諸国の人たちだけではなかったということです。琉球王国(沖縄)こそ日本の植民地政策の犠牲を真っ先に受けた国(民族)だったことを決して忘れてはなりません。
「琉球処分」です。それはまさに今回安倍政権が世界遺産登録申請の対象としている期間に強行されたことなのです。主な出来事を挙げます。
1854年 琉球王国、アメリカと独自に条約締結(琉米条約)
68年 明治維新。琉球は鹿児島の管轄下へ
71年 琉球船の台湾遭難事件(明治政府、琉球の日本領有と台湾進出を企てる)
72年 琉球王国を琉球藩とし明治政府の直轄下へ(「琉球処分」=廃琉置県のはじまり)
75年 処分官・松田道之を琉球に派遣し、琉球藩(琉球王国)廃止(沖縄県設置)の方針通告
79年 松田、歩兵400、警察官160を引き連れ、暴力的に「廃琉置県」強行(「琉球処分」完了)
80年 明治政府が清に「分島・増約案」提示(中国市場への参入と引き換えに宮古・八重山諸島を割譲)-不成立
「明治産業革命遺産」と「琉球処分」は年代が一致するだけではありません。
23施設の中には、鹿児島の集成館(写真中)関連施設が3つ含まれています。集成館とは、「1851年薩摩藩主に就任した島津斉彬が欧米列強による植民地化を防ぎ、日本を強く豊かな国にするため大砲鋳造や造船」(鹿児島県HP)を行った、薩摩版「富国強兵」の拠点です。その薩摩藩は1609年の武力侵攻以来、明治維新まで琉球を支配し続けました。島津斉彬自身、「琉球を拠点とした欧米諸国との貿易構想をうちたてた」(『沖縄から見える歴史風景』)人物です。
さらに、23施設には「松下村塾」が含まれ、吉田松陰門下、長州出身の明治政府官僚(安倍首相が「尊敬」してやまない)が美化されています。その筆頭は伊藤博文(写真右)ですが、伊藤こそ「琉球処分」の張本人の1人です。1875年の通告に従わない琉球王国に対し、松田に武力侵攻をけしかけたのが、当時内務卿だった伊藤です。
「ヤマト政府命令が一向に進展しないことに業を煮やした明治政権は、1878年に伊藤博文が松田道之に『琉球処分案』を起草させ強硬策をとることにした」(山本英治氏『沖縄と日本国家』)
「琉球処分」から130余年。琉球(沖縄)に対するヤマトの「植民地政策」は今日に続き、「辺野古新基地強行」として現象しています。この歴史と現実こそ、決して忘れてはならない「負の遺産」です。



自衛隊配備の是非を問う注目の与那国町住民投票が、あす22日行われます。
争われているのは、陸上自衛隊沿岸監視部隊(約150人)の駐屯、監視用レーダーや隊舎などの建設の是非です。
一昨年8月の町長選挙で政府・防衛省の支援を受けた誘致推進派の外間守吉町長が当選したため、工事はすでに昨年5月に着工していますが、今回の住民投票で「反対」が上回った場合、外間町長は、「配備は止められないが、町として国に非協力的な立場を取らざるを得ない」(15日付琉球新報)と明言しています。
「反対」の意思表示によって、陸自配備に事実上のストップをかけられるかどうか、たいへん注目されます。
与那国島への陸自配備には、少なくとも5つの重大な問題があります。
①「自衛隊票」が有権者の20%!与那国は軍隊(自衛隊)の意のままに
与那国の人口は約1500人。有権者(成人)は1187人です。自衛隊誘致などに対する島民の意見はほぼ2分されており、一昨年の町長選での外間氏と反対派の崎原正吉氏との票差はわずか47票にすぎませんでした。
そこに150人の自衛官が家族とともに「移住」してきたらどうなるか。「2人家族」だとしても約300票が「自衛隊票」となります。これは実に有権者の約20%です。キャスチングボートどころか、自衛隊(国家権力)の意向が与那国町の重要事項を決めてしまうことになりかねません。
沖縄防衛局の井上一徳局長は、今回の配備は「艦船や航空機を監視することが主な役割」(18日付沖縄タイムス)だとして「安心感」を振りまいていますが、いったん配備してしまえば、その後何をしようが自衛隊のやりたい放題になる危険性がきわめて大きいのです。
②レーダー・電磁波のへの不安消えず
今回の監視レーダーの設置自体も島民にとって重大です。それは電磁波による健康破壊の不安が消えないからです。レーダーはもっとも近い所では人家からわずか180㍍の場所に造られます。
住民の不安に対し、外間町長は今年1月、防衛省主催の「説明会」を開催して「安全」を強調しました。しかしその講師が防衛省から資金援助を受けているセンターの代表というお手盛りぶりで、不安はいっそう強まっています。
③軍事基地依存の経済・財政へ転落
誘致推進派の最大の理由は、「人口増加」とともに、「何十、何百億という国のお金が入ってくる」(「自衛隊に賛成する会」金城信浩会長、20日付沖縄タイムス)という「交付金」頼みです。
しかしこうした基地依存の経済・財政は、「バブル的な金で施設を造っても将来的に財政を圧迫する先例はいくつもある。活性化より財政規律を破壊する原因になる可能性の方が高い」(島袋純琉大教授、18日付沖縄タイムス)のです。
④破壊される自然
与那国はかつて人気ドラマ「Dr.コトーの診療所」(吉岡秀隆主演)の舞台になった島です。あの広大で青々とした牧場に、自衛隊のレーダーなどが建てられようとしているのです。
軍事施設が沖縄の貴重な自然を破壊する。海と陸の違いはあっても、その点では辺野古とまったく同じです。観光にも大きな障害となります。
⑤沖縄を前線基地化する安倍戦略の一環
もっとも重大なのは、与那国への陸自配備が「島しょ防衛」を口実にして対中国、北朝鮮との緊張を強め、沖縄全体を前線基地にしようとする安倍戦略の一環だということです。
辺野古をはじめ、宮古島の下地空港の自衛隊使用、第2那覇空港の自衛隊増強など、与那国と同時並行的に、安倍・防衛省が狙う重大事態が進行しています。
2007年6月24日、アメリカの掃海艇が突然与那国に入港・上陸しようとしたことがあります。これに対し、島のおじい、おばあら100人以上が座り込みで抗議し、しばらく上陸を阻止し、米軍を驚かせました。その年です、与那国に突然「防衛協会」がつくられたのは。これが陸自誘致運動の発端です。
いまも誘致反対の先頭にたっている「イソバの会」(イソバとは、昔与那国島を守ったという伝説の女酋長の名前)の女性が、ある集会でこう訴えたのを思い出します。
「『武器のない所に鉄砲玉は来ない』。これが島のおじい、おばあの教えです」
見過ごせないのは、こうした重大な与那国情勢に対し、翁長知事が沈黙を決め込んでいることです。
翁長氏は13日の記者会見で、与那国への陸自配備についての見解を問われ、こう答えました。
「近く住民投票が実施されるので私としてのコメントは差し控えたい。県としては今後に注視して議論するなかで、県としての対応を考えたい」(14日付沖縄タイムス)
町財政(金)のために自衛隊を誘致しようとしている「賛成派」に対し、翁長氏はなぜ持論(のはず)の「基地は沖縄経済の最大の阻害要因だ」と言えないのでしょうか。
辺野古新基地に本気で反対しているのなら、それと一体の与那国陸自配備にも「反対」だとなぜ言えないのでしょうか。
沖縄が直面している重大事態は辺野古だけではありません。
「辺野古新基地反対」と「与那国陸自配備反対」の一体化が求められています。
そのことは逆に「賛成派」の方がよく知っています。「賛成する会」の金城会長はこう言っています。「本島で辺野古の新基地建設への反対が盛り上がっているので、その影響だけが唯一の気掛かりだ」(20日付沖縄タイムス)
住民投票が行われるあす22日には、偶然にも辺野古で新基地に反対する県民大会が行われます。大会で、「辺野古新基地反対」とともに、「与那国陸自配備反対」のコールが起こることを切望します。



沖縄県の翁長雄志知事が16日、防衛局に対し辺野古沿岸部海底へのコンクリートブロック設置作業を停止するよう指示しました。「初の知事権限行使」(琉球新報17日付。以下、新報=琉球新報17日付、タイムス=沖縄タイムス17日付)です。
辺野古の現場でたたかっている市民からは、「ありがたい」「やっと動いてくれた」(タイムス)など「歓迎」の声が上がりました。これまでの翁長知事の“静観”にいかに市民が焦り、怒っていたか分かります。
しかし、今回の「停止指示」は、およそ「知事の本気度が示された」「大きな一歩だ」(新報)などと評価できるものではありません。
①「停止指示」の“効果”はあまりにも限定的
今回翁長知事が防衛局に指示したのは、次の3点です。
①新たなブロックの設置停止とすでに設置したブロックの移動停止
②海底面の現状変更停止
③設置したブロックの位置に関する図面や設置前後の海底の写真など必要資料の提出
(以上、タイムス)
つまり写真右の地図の黄色い〇の部分へのブロック投入を、これ以上やめよというものです。その範囲はきわめて限定的で、内側の「岩礁破砕許可区域」は不問に付されています。
しかも、黄色い〇部分への違法投入に対しても、「新たな設置」は停止せよというだけで、すでに投入されているものの撤去は求めていません。
撤去(原状回復)について翁長氏はいまだに、「調査で現状を把握して違反があれば、あり得る」(タイムス)と言うだけです。違反はすでに明白です。ジュゴンネットワーク沖縄の細川太郎事務局次長が、「許可区域外のコンクリートは即刻撤去を指示できるのではないか」(新報)と指摘している通りです。
②あまりにも遅い・・・コンクリート投入はほぼ終了
翁長氏の「停止指示」に対し、防衛局は、「ブロックの設置をほぼ終え、23日以降にボーリング調査や仮設岸壁の建設に入る」(タイムス)といいます。これに対し県も「許可区域内の海上作業は可能」(同)と認めています。結果、「防衛局は翁長知事の指示では、当面の作業への影響は出ないとみている」(同)。
作業がほぼ終わったころに、「新たな設置停止」を指示しても何の効果があるのでしょうか。事ここに至るまでに手を打たなかった(動かなかった)翁長氏の責任は不問にできません。
③あまりにも遅い・・・県の「調査」結果が出るのは3月10日ごろ
これまでの対処の遅さ(黙認)だけではありません。翁長氏が「違反」があるかどうか判断するという「県の調査」は、その結果が出るのがなんと来月10日ごろになるというのです。
「県は24日に業者と契約、27日から現場調査に乗り出す。・・・調査結果は1週間から10日程度で報告があるとして、その後に知事が許可(岩盤破砕許可―引用者)取り消しなどを判断する」(タイムス)
調査のスタートがなぜこんなに遅く、調査になぜこんなに時間がかかるのか。そもそも、サンゴや海底の損傷、違法性は複数の市民団体やメディアの独自調査ですでに明白です。その資料を活用すれば良いので、新たな調査など必要ありません。時間を浪費するだけです。その間にも、工事の既成事実化はどんどん進んでしまうのです。
④「本丸」は「埋め立て承認」。「本気」なら「即時撤回」を
カヌーで抗議を続けている市民の訴えです。
「(今回の指示は)許可区域外の話で、埋め立て中止などについては言っていない。もっと踏み込んでほしい」「作業は一日一日進む。知事がはっきりと中止や撤回を言ってくれないと作業は止まらない。県民は止めるために知事を選んだ」(タイムス)
その通りです。「知事の本丸は承認の効力をなくすこと」(仲地博・沖縄大学長、タイムス)です。「承認の効力をなくす」手段は、埋め立て承認の「取り消し」か「撤回」です。安倍政権が強権的に工事を強行している今にいたっては、「即時撤回」以外にありません。これが「本丸」です。
今回の翁長氏の「停止指示」は、「本丸」どころか、「外堀」のさらに外をどうするかという話なのです。
与党県議の一人は、「知事がようやく最初のジャブを打ってくれた。第2、第3の行動で『新基地を造らせない』材料を積み上げてほしい」(タイムス)と話しています。
事態が静止しているならそうした段階論も可能かもしれません。しかし、事態は刻々と動いています。というより、時間との勝負なのです。
「防衛局は18日にも大型スパット台船を使った海底ボーリング調査を再開・・・6月ごろまでに埋め立て工事に着手したい考え」(新報)
「知事の判断は当然だが、動きが鈍い。現場では次々とサンゴが破壊され、見るに堪えない」(細川太郎氏、新報)
辺野古新基地建設阻止に悠長な段階論は有害無益です。即時撤回しかありません。
県政野党の自民党幹部が言っています。「本気で辺野古に反対するのならば、埋め立て承認をすぐに撤回すればいい」(タイムス)
これは正論です。正論は誰が言っても正論です。言うことが自民党と同じだから言うのがはばかれると自粛したり、発言者を攻撃することは根本的に誤りです。それは、安倍政権を批判したら「テロ集団」と同じになるから批判するな、というようなものです。
翁長知事が「本気」で辺野古新基地建設を止めるつもりなら、埋め立て承認を即時撤回すべきです。



辺野古埋め立て工事のために政府・沖縄防衛局が大浦湾に投げ込んだ巨大なコンクリートブロック(アンカー。1基10㌧~45㌧を75基の予定)が、サンゴや岩礁を破壊していることが、10日の琉球新報、沖縄タイムスで報道され、大問題になっています。
本土の新聞の多くは無視していますが、11日の報道ステーションは報じました。ブロック投げ込み区域は、県の「許可」範囲外であることが明らかになっており、この点だけでも翁長雄志知事は直ちにブロック投げ込みを止めさせることができます(写真左のグリーンが「許可」区域、黄色の〇がブロック投げ込み区域。写真中央がアンカー。写真はいずれも報道ステーションから)
これに対し、元名護市議の宮城康博さん(写真右)が中心になり、「沖縄県民とすべての憂慮する市民有志一同」の名前で、10日、翁長知事に対し、「沖縄県は沖縄防衛局に対して、大浦湾内での『アンカー設置』作業を直ちに中断し岩礁破壊の許可申請をするよう勧告を」と題する「緊急要請」を行いました。
わずか2日で県内外2662人の賛同署名が集まった画期的な要請です。
要請文は事態の深刻さを指摘したうえで、県が「内容を精査し判断する」としていることに対し、「(その)間も大浦湾では『粛々』と巨大なアンカーが投下され環境が破壊され続けています」とし、「辺野古には新基地はつくらせない、を公約として当選された翁長県知事におかれましては、一刻も早く、沖縄防衛局に対して大浦湾内での『アンカー設置』作業を中断し、岩礁破砕の手続きに基づいた許可申請をするよう勧告してください」と要求しています。
一方、沖縄県内で憲法9条を守る活動を続けている6つの「9条の会」も10日、合同で、翁長知事に対し、第三者委員会の検証作業を急ぎ、「辺野古断念を求める政治的意思」を表明するよう要請しました。
「うるま市具志川九条の会の仲宗根勇共同代表は『第三者委は日程が間延びしている。県民の危機意識を共有すべきだ』と訴えた」(11日付沖縄タイムス)と報じられています。
辺野古の重大事態を事実上黙認し続けている翁長知事に対し、ようやく、要請、突き上げ、批判の声が公然化してきました。まさに不安や苛立ちが怒りに転化しようとしています。
さまざまな風当たりの中で、勇気ある声を上げはじめた人たちに心から敬意を表します。
同時に、あえて言いますが、まだ焦点が合っていないように思えます。
第1に、アンカー作業を止めることはまさに緊急に必要なことですが、それはあくまでも応急措置としての“止血”です。いま必要なのは“緊急手術”、すなわち「埋め立て承認の撤回」です。翁長知事にはそれができるのです、その気さえあれば。
「アンカー作業の中止要請」は、「翁長知事は直ちに承認を撤回せよ」という要求と同時に行われるべきです。
「9条の会」の申し入れも同様です。知事に「辺野古断念を求める政治的意思」の表明を求めていますが、いま必要なのは「意思の表明」ではなく、具体的な実効行為、すなわち即時撤回です。カラ文句の「意思表明」は聞き飽きました。
第2に、宮城さんたちが要請文を渡したのは「県海岸防災課」、「9条の会」は「基地防災統括監」。相手が違います。翁長知事に直接手渡し、直接申し入れるべきです。
おそらく県当局がそうさせたのでしょうが、断固として翁長氏本人への面会を求めるべきです。宮城さんたちも「9条の会」の人たちも、みんな選挙で翁長氏を応援した人たちです。翁長氏に直接会って申し入れる資格も権利もあります。翁長氏がそれに応じないとすれば、それは首相や官房長官が翁長氏に会おうとしないこと以上に問題ではないでしょうか。
宮城さんたちの申し入れに対し、翁長氏は何と言ったか。「事実だとしたら大変なことだ。事実関係について確認して県の対応を決める」(11日付琉球新報)
なんということでしょうか。事実に決まっているではないですか。これが県民の支持で当選した知事の言う言葉でしょうか。
宮城さんたちの「緊急要請」の最後の言葉を、翁長氏はかみしめるべきです。
「現地では、カヌーに乗って抗議する市民・県民に対する海上保安庁職員による暴力的排除行為が連日行われており、ことは市民・県民の生命を守るためにも大至急を要する事態です」



前回のこのブログで、沖縄の翁長雄志知事に、「公約」に基づいて直ちに「辺野古埋め立て承認」を撤回するよう求めました。
その際、海外の識者らが連名で翁長氏に書簡を送ったことに注目し、その一部を紹介しました。
大変重要なニュースですが、本土の新聞には載っていないようです。
「しんぶん赤旗」(日本共産党機関紙)はどうだろうかと、昨日図書館で見てみました。そして、目を疑うような驚きと怒りを禁じえませんでした。「書簡」の趣旨がまったく反対に歪曲されていたからです。
「赤旗」(1月28日付)は2面3段の囲み記事(写真右)で、「翁長知事に海外の連帯 識者15人 沖縄新基地反対」の見出でこう書いています(以下、全文)。
[ワシントン=洞口昇幸]沖縄県宜野湾市の米軍普天間基地の同県名護市辺野古への「移設」(新基地建設)に反対し、普天間基地の即時無条件撤去を求める昨年1月の声明に賛同した海外の識者・文化人のうち15人が23日、翁長雄志・県知事に連帯の意思を示す手紙を送りました。
送ったのは、ニューヨーク州立大のハーバート・ビックス名誉教授、シカゴ大のノーマ・フィールド名誉教授、アメリカフレンズ奉仕委員会のジョゼフ・ガーソン氏(政治学博士)、ジャン・ユンカーマン早稲田大教授・映画監督、米アメリカン大のピーター・カズニック教授、オーストラリア国立大のガバン・マコーマック名誉教授など。
手紙では、昨年11月の県知事選で翁長氏が勝利したことで新基地反対の民意が再確認され、辺野古を守るために長年取り組んできた人たちにとって、「大きな励ましとなった」と述べています。
この記事(見出し含め)がいかに「書簡」の趣旨を捻じ曲げているか。「書簡」を報じた沖縄県の2紙と比べれば明らかです。
琉球新報(1月25日付、写真左)は、1面で、「辺野古阻止へ『行動を』 海外識者15人、知事に手紙」の見出しで、「(海外の識者・文化人が)翁長雄志知事に手紙を送り、辺野古の新基地建設に向けた日本政府の作業を止めさせるために積極的な行動を取ることを求めた」と報じました。
沖縄タイムス(同日付、写真中)は、2面トップで、「知事に迅速行動要求 外国識者 辺野古に危機感」の見出しで、記事と解説を掲載しています。
この中で沖縄タイムスの平安名純代・米国特派記者は、「識者らは・・・『本格的埋め立て工事は間近に迫っており、残された時間は非常に限られている。遅すぎるという感を否めない』と危機感を表明。・・・『県民は法的検証よりも、翁長知事の政治的決断力に民意を委ねたのであり、その思いに応えてほしい』と訴える」と「書簡」の内容を紹介。「解説」でこう指摘しています。
「今回の要請の背景にあるのは、埋め立て承認の取り消し・撤回を掲げて当選した翁長知事の対応の遅さだ」
「書簡」はどういうものだったのしょうか。ここに全文を転記します。本土のみなさん、ぜひ読んでください。
2015年1月23日
沖縄県知事 翁長雄志様
私たちは主に、昨年1月に発表した「世界の識者、文化人、平和運動家による辺野古新基地建設反対と普天間基地返還を求める声明」の賛同人となった、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、欧州の市民グループです。私たちは 、沖縄の社会、政治、歴史の研究などを通じ沖縄に関わってきており、これまで十数年にわたり沖縄についての記事を英語で世界に発信してきた『アジア太平洋ジャーナル:ジャパンフォーカス』(japanfocus.org)の執筆者でもあります。
昨年の声明で私たちは、仲井眞前知事による民意に背いた辺野古埋め立て承認を批判し、沖縄の過重な基地負担の不当性を訴え、辺野古新基地建設反対を訴えました。そして11月、辺野古新基地を「造らせない」と公約した翁長知事が当選したことで新基地反対の民意が再確認されました。知事が現地に赴き基地建設反対を訴えたことは、大浦湾と辺野古を守るために長年たゆまぬ努力をしてきた人たちにとって、どんなに大きな励ましとなったことでしょう。
あれから2か月が過ぎました。現在、基地建設に向けての作業が強行されています。連日抵抗する市民と機動隊が衝突し、毎日のように怪我人が出ている様子は見るに堪えません。私たちの理解では、出動しているのは沖縄県警であり、県警は知事が任命する県公安委員会の管理下にあります。知事はその権限をもって、辺野古で抵抗する市民たちに暴力的な警備は行わないように、また機動隊は交通警察に交代させるよう県警に指示できるはずです。海上保安庁にも暴力的な警備を即刻やめるよう申し入れてください。
知事は、前知事による埋め立て承認の検証のための委員会を1月下旬には決定し、月に二度ほど会合し、早ければ4月に検証結果をまとめるよう作業を進めるとの報道があります。その結果埋め立て承認に法的瑕疵があれば取消、そうでなければ撤回を考えているとのこと。また、4月以降、訪米団を組んで米国政府に直接基地建設中止を訴えるという計画も聞いております。
しかし本格的埋め立て工事は間近に迫っており、残された時間は非常に限られています。遅すぎるという感を否めません。
今埋め立て作業を止める権限を持つのは日米政府と、埋め立て承認の取消か撤回という方法で作業を止めることができる翁長知事だけです。知事が、埋め立ての取消か撤回という権限を行使しないままに訪米しても、説得力を持たないのではないかと思います。逆に訪米前に少なくとも取消か撤回への明確なコミットメントをすれば、訪米行動は意味あるものとなります。その際は私たちも全力でバックアップします。
また、沖縄県民は、沖縄をこれ以上差別させず、自然環境を破壊する基地は造らせないという価値観のもとに知事を選んだのです。法的検証は確かに大事なことですが、法的側面にあまり重点を置くことは、埋め立て承認を「法的基準に適合している」と正当化した仲井眞氏と同じ土俵に立ってしまうのではないでしょうか。県民は法的検証よりも、翁長知事の政治的決断力に民意を委ねたのであり、その思いに応えてほしいと思います。
知事が取消か撤回を行うまでは、日米政府は前知事の承認に従って着々と作業を進めてしまいます。一度大浦湾が土砂やコンクリートで破壊されてからでは遅すぎます。検証委員会の判断が出るまで作業中止を求めることはもちろんですが、委員会は一刻も早く答申を出し、知事は取消か撤回の決定を下すことを期待します。
埋め立て承認の取消か撤回をせずこの基地が造られてしまったら、初めて沖縄県の合意に基づく新基地が造られたということが歴史に刻まれ、将来への重大な禍根が残ります。
外部からの口出しと批判されかねないことを申しましたが、私たちの目標は知事と、知事を選んだ沖縄県民の多数派と共通しており、それは辺野古の基地建設阻止です。そして私たち自身も日米政府を動かし基地建設を断念させる努力を続けていきます。
沖縄新基地建設反対!世界の声(No New Bases in Okinawa! Global Voices)
<以下、15人の氏名、肩書は省略。太字は引用者>
読めば歴然です。「書簡」を送った識者らは、辺野古新基地建設阻止を本当に願い、たたかっている県民と連帯するために、翁長氏に「迅速行動」を強く、厳しく要求しているのです。
「赤旗」の記事は前置きの一部を引用しただけで、肝心な本文の内容はまったく伝えていません。そして「識者」らがただ素朴に「翁長知事に連帯」を表明しているかのように描いています。
これは完全な「欠陥記事」であるだけでなく、なにがなんでも翁長知事を擁護したいというきわめて政治的な意図による事実の隠ぺい・改ざんと言わねばなりません。
事態は動いています。いまや、翁長氏への不満は海外識者らだけではありません。
「翁長氏は知事選で『あらゆる手段で新基地建設を阻止する』と表明していた。ある与党議員は『もう就任1カ月半だ。「あらゆる手段」が見えないことが県民に不安を与え、不安は怒りに変わりつつある』と不満を隠さない」(琉球新報1月28日付)
日本共産党が「翁長支持」を続けるのは、政治選択ですが、それは正確な情勢判断によってなされるべきであることはいうまでもありません。
そうであるなら、沖縄の正確な情勢を「赤旗」読者や党員・支持者に伝えることのは、政党として最低限の責務ではないでしょうか。
政治的思惑から、事実を隠ぺい・歪曲することは、絶対に許されることではありません。