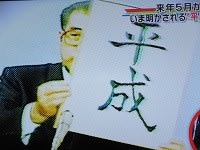1日開会した臨時国会では、本会議場などのバリアフリー化が注目されていますが、もう1つ、この国会には歴史的な意味があります。それは、天皇徳仁が天皇として初めて国会の開会式に出席した国会だということです(徳仁は皇太子時代の2003年、明仁天皇の代理として出席したことがあります)。
バリアフリー化も重要ですが、国会にはそれと同じように、いや、それ以上に早急に見直し撤去しなければならない“バリア”があります。それは天皇が議場の最上部から国会議員を見下ろし、「おことば」を述べる現在の開会式の在り方です。
これは主権在民の現憲法とはまったく相いれないもので、天皇主権の旧憲法(大日本帝国憲法)の継続にほかなりません。直ちにとりやめるべきです。
しかし、国会内はもちろん、メディア・「学者・識者」からも、この開会式に異議を唱える声はまったく聞こえてきません。そんな中、現憲法下で3人目の天皇となった徳仁天皇も、祖父・裕仁、父・明仁に従い、憲法に反する「国会開会式出席」を継承した意味はけっして小さくありません。
天皇の国会開会式出席がどういう意味を持っているか、確認しておきましょう。
天皇の国会開会式出席は、憲法(第6、7条)が定める「国事行為」ではなく、いわゆる「公的行為」として行われるものです。「公的行為」を憲法上認めるかどうかには諸説ありますが、重要なのは次の指摘です。
「大事なことは…どの説が有力であれ、政府の承認の下に、現に天皇は…公的行為を行っているという事実である。この結果、天皇が公的資格で登場する場面は、きわめて広汎なものとなっている。そしてそれらは、それぞれに天皇の権威を高めることに役立っている。
たとえば国会開会式への出席のように、旧憲法的天皇観を再生産するものがある。旧憲法の場合には、議会の召集は統治権の総覧者たる天皇の大権に属しており、天皇はその立場で議会に臨み、議員を見下ろす場から勅語を読んでいたが、現憲法における国会開会式は議会が主催するものとなり、天皇はただそれに招待され出席する立場であるに過ぎないにもかかわらず、現在も形式的には昔と同様の儀式が国会で行われ、天皇の『おことば』の前で、主権者国民の代表であり、国権の最高機関である国会の議員が、一部の議員を除いて、一斉に畏まって頭をたれている姿は、新旧の天皇の立場の相違を曖昧にするとともに、国民主権原理をぼかすことになっている」(横田耕一九州大名誉教授、『憲法と天皇制』岩波新書)
ここで注釈が必要なのは、横田氏の指摘にある「一部の議員を除いて」を、いまでは削除しなければならないということです。横田氏の著書が書かれたのは1990年ですが、2016年1月4日、日本共産党がそれまで欠席してきた方針を撤回し、開会式に出席し志位和夫委員長も天皇に頭を下げました(写真右)。これによって「一部の議員」もいなくなり、国会は文字通り天皇賛美の翼賛国会となってしまったのです。
1日徳仁天皇が述べた「おことば」は明仁天皇とほぼ同じで、内容に問題はないように思われています。しかし天皇はこの中で、「国会が、国権の最高機関として…その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します」と述べています。これは、「国権の最高機関」を見下す位置から、“しっかり働け”と言っているにほかなりません。
主権在民に反する、大日本帝国憲法の再現・継続である「天皇の開会式出席」は直ちに廃止すべきです。