

















12月13日は日本人が絶対に忘れてはならない日です。84年前、1937年のこの日、日本帝国軍隊は中国の首都(当時)、南京を侵略・陥落し、女性、子どもを含む30万人以上(中国側調査)の大虐殺とおびただしい性暴力という蛮行を行いました。いわゆる南京事件です。
天皇裕仁が南京侵略を命令し、陥落を称賛したことは、多くの資料で証明されています。たとえば―。
「一九三七年一二月一日…大本営は戦闘序列を発号し、そのうえで『中支那方面軍ハ海軍ト協同シテ敵国首都南京ヲ攻略スベシ』という大陸令をくだした。戦闘序列というのは天皇の令する軍の編成のことであり、大陸令というのは、大本営陸軍部の発する天皇の命令である。この大陸令で、はじめて中国を『敵国』と呼び、首都南京の攻略を正式に命令したのである」(藤原彰著『南京の日本軍 南京大虐殺とその背景』大月書店1997年)
「この日(1937年12月14日―引用者)、昭和天皇より南京占領を喜ぶ『御言葉』が下賜された。<陸海軍幕僚長に賜りたる大元帥陛下御言葉 中支那方面の陸海軍諸部隊が上海付近の作戦に引き続き勇猛果敢なる追撃をおこない、首都南京を陥れたることは深く満足に思う。この旨将兵に申伝えよ。(『南京戦史資料集Ⅱ』)>…現地軍の中央命令無視、独断専行による侵略戦争の拡大を、天皇が追認し鼓舞、激励するという構図がここにある」(笠原十九司著『南京事件』岩波新書1997年)
さらに、明白な国際法違反の虐殺・性暴力に対しても、裕仁が黙認したことも指摘されてきました。
「昭和天皇は皇軍による犯罪行為について沈黙をしていた事実が残る。皇軍が南京を陥落させた瞬間まで、天皇は軍の動静を詳細に追っていたのである。また、事件の前兆があった時期を通じて、あるいは殺戮、強姦のあった全期間に、天皇は不快、憤り、遺憾を公にすることよりは、むしろ、中国に『自省』を促すという国策のもとで、大勝利に向け臣下の将軍や提督を鼓舞していたという否定しがたい事実もある」(ハーバート・ビックス著『昭和天皇上』講談社学術文庫2005年)
裕仁が南京事件を黙認した事実を、当時の側近も日記に書いていたことが明らかになりました。侍従長だった百武三郎の日記です。ETV特集「開戦への道(後編)」(11日)が紹介しました。
それによると、南京の事態について、裕仁は「うすうす聞いていた」と自ら述べていたといいます。
そして、「南京で虐殺行為」と報じた英紙「マンチェスタガーディアン」(1938年1月29日付、写真右)に対する裕仁の反応を、百武はこう記しています。
「南京ニ於ケル陸兵暴行ニ関スル英紙情報ハ皇軍将来ノタメ、支那統治ノタメ大影響アルニ付敢テ聖鑑ニ呈ス」(写真中)
「皇軍将来のため」「支那統治のため」に「聖鑑」=黙認する、としたのです。
「百武日記」は、裕仁が内大臣・木戸幸一も驚くほど戦争に前のめりだった様子を伝えていますが(6日のブログ参照)、それに加え、裕仁が南京大虐殺を黙認した事実を示したもので、きわめて注目されます。
ところが同番組は、古川隆久日大教授や加藤陽子東大教授らのコメントで、裕仁は軍部を止められなかったのだという結論で締めくくりました。これは「(軍部の)勢いでああいうことになった」という裕仁の弁明を擁護するものと言わねばなりません。
裕仁は「止められなかった」のではなく、柳条湖事件(1931年9月18日)以降をとっても、自ら天皇・大元帥として軍部を鼓舞し、侵略戦争を先導したのです。
同番組が特集した「百武日記」も、そのことを示す資料の1つです。



月刊「文芸春秋」(8月号)が、「第二波に備えよ」という特集を組み、その中で「天皇と雅子皇后はなぜ沈黙しているのか」と題する論稿を載せています(写真左)。筆者がこれまで天皇のビデオメッセージなどを批判してきた原武史氏(放送大教授)だけに、「原氏までが」との思いで読みました。
論稿は単純にコロナ禍での天皇の「メッセージ」を求めているもの(例えばこれまで取り上げた御厨貴氏や赤坂真理氏など)と同類ではありません。副題が<コロナ禍で見えてきた「平成流」と「令和流」の“違い”>となっているように、ビデオで2回(2011年3月16日と2016年8月8日)メッセージを発した明仁天皇を「平成流」、コロナ禍でメッセージを発していない徳仁天皇を「令和流」として、その「違い」を指摘するというのが主題のようです。
しかし、一見客観的に「象徴天皇制」を分析しているようにみえる同論稿にも、見過ごすことができない重大な誤り・危険性があります。
第1に、原氏は「私自身は、ビデオメッセージが持つ『政治性』に関して、批判的に検証している立場です」としていますが、論稿は全体として明仁天皇(当時)のビデオメッセージを美化する結果になっています。
「あの時(2011年3月16日―引用者)の天皇の『おことば』に励まされた人も多かったのではないでしょうか」「あの震災の時のメッセージ…上皇(明仁―引用者)の強い意思を感じさせる言葉です。今回の天皇(徳仁―同)の『ご発言』には、そうした天皇自身の意思が感じられません」などの記述がそれを示しています。
第2に、原氏は「メッセージについては、私自身も『憲法が禁じた権力の主体に天皇がなっている』と著書で書きました」と天皇の「ビデオメッセージ」には批判的であるとしていますが、その点の論及がこの論稿ではほとんどないため、結果として、コロナ禍で天皇のメッセージを促すことになっている点です。
それは、国王がメッセージを発したイギリスやオランダの例を挙げながら、「天皇がひとたびそうしたメッセージを出せば、イギリスやオランダと同じように、国民は励まされ、歓迎する空気が生まれるのも間違いありません」と述べているところに端的に表れています。
詳述は省きますが、「天皇のビデオメッセージ」は重大な憲法違反です。
第3に、この論稿の主題であり結論ともいえる次の記述の問題点です。
「結局のところ、どのような力学が働いて、現在の(徳仁天皇の―引用者)『沈黙』が保たれているかはわかりません。ただ、一つ確かなことは、このコロナ禍によって、図らずも『平成』と『令和』における象徴天皇制の在り方の『変化』がはっきりしたことです」
「象徴天皇制の在り方」は「平成」と「令和」で、すなわち天皇の代替わりによって「変化」するものだとし、その「変化」を是認しています。それは次の記述にも表れています。
「明治以降の天皇は、前代の在り方について、継ぐべきは継ぎ、改めるべきは改めるということを繰り返してきたのです。令和の世もそれは変わらないでしょう。今はその新たなスタイルを模索している段階だと私は思います」
これは誤りです。
なぜなら、「象徴天皇制の在り方」は憲法(第3、4、6、7条)に規定されており、時の天皇が自分流に作ることができるものではない、作ってはいけないからです。それが現行憲法における象徴天皇制と大日本帝国憲法における絶対主義的天皇制の本質的な違いです。
象徴天皇制を「平成流」「令和流」と分類し、時の天皇による「変化」を是認することは、憲法を無視(超越)した天皇の独自行動(言動)を容認する危険な誤りに通じると言わねばなりません。
天皇制についてのまともな論者が決定的に少ない現在の日本において、原氏は注目される学者の1人です。慎重で的確な論考を期待したいものです。



2カ月前に「徳仁天皇は『ビデオメッセージ』を発してはならない」と書きましたが(4月9日のブログ参照)、その後も天皇は何も「メッセージ」を発していません。理由は分かりませんが、この状況はたいへん意味のあることです。
4月以降、「コロナ禍」に関連して徳仁天皇が雅子皇后とともに行ったことは次の通りです。
4月10日 専門家会議の尾身副座長から聴取(政府・宮内庁はこれを「ご進講」と称します)
4月15日 厚労省医務技監から聴取
5月20日 日本赤十字社長・副社長から聴取
6月3日 東京都葛飾区保健所長らと面会(専門家からの聴取はこれが5回目とか)
それぞれの場面で感想は述べていますが、「国民」に向けたメッセージは発していません。天皇主義者はこの状況に不満を募らせていると思われます。宮内庁はやむを得ず、専門家会議と日赤からの聴取で徳仁天皇が述べた感想をHPに掲載しています。
明仁上皇が天皇であればとっくに「ビデオメッセージ」を出していたでしょう。「天皇退位有識者会議」(2017年)で座長を務めた御厨貴氏(元東大教授)が、「東日本大震災の時に上皇さまはビデオメッセージを出した。陛下も国民に向けて何らかのパフォーマンスを見せてほしい」(4月14日付中国新聞=共同)と公言していましたが、徳仁天皇・雅子皇后にメッセージ(パフォーマンス)を求める声は少なくありません。
東京新聞の望月衣塑子記者が、「皇室が世界に本来進むべき道を指し示すというのは、理想的なウィジョン」(「波」5月号)とコロナ禍のいま天皇・皇后に発言・行動を求めていることは先にみましたが(6月2日のブログ参照)、同類の声はほかにもあります。
作家の赤坂真理氏は、ドイツ・メルケル首相のスピーチ(3月18日)を評価したのに続き、「日本で機能していないと思うものがある」としてこう述べています。
「それは『象徴』だ。この歴史的な時に、首相は統合を象徴する存在たり得ていない。残念なのは、憲法第1条に書かれた『象徴』もまたそうであることだ。『象徴』と書かれた存在が、もし本当にその役を引き受けるのなら、今、何かを言ってほしい。でなければいつ象徴的であられるのか?」(4月29日付地方各紙=共同配信)
こうした声にもかかわらず、徳仁天皇が何もメッセージを発していないのは、したいけれどできないのか、それとも何らかの判断であえてしないのか。それは分かりませんが、客観的にみれば、何もしないことこそ“無為の知恵”と言えるでしょう。
天皇が政治・社会情勢に関連して自らの意見を述べることは、憲法が二重三重に禁じています。何もしないことが「憲法第1条」に沿うものです。しかも、「コロナ禍」ではそれが一層重要です。
今回の「コロナ禍」あるいは「コロナ後」は、私たちに様々な選択を迫っています。その1つは、「全体主義的な監視(国家による監視と制限)か、市民に力を与えるエンパワーメント(自己決定力)か」(イスラエルの歴史学者・ユヴァン・ノア・ハラリ氏、4月4日NHK・ETV特集)です。言い換えれば、「国家主義」か「市民主義」かの選択です。私たちが目指すべきは当然後者、「市民の自己決定力」を強化することです。
天皇(象徴天皇)はいうまでもなく国家機構・体制の一部です。天皇が自らの言動によってその存在を強めることは、上からの権威によって「国民」を束ねる国家主義(全体主義)の強化にほかなりません。それは私たちが目指すべき「コロナ後」の社会に逆行するものです。
天皇は「コロナ禍」でも、いいえ「コロナ禍」だからこそ、メッセージを発するべきではありません。このまま「無為」を貫くことこそが市民のためです。
(写真中)が、「この危機の時代に、私たちは特に重要な2つの選択を迫られている」と提唱していることが紹介されました。
第1の選択…全体主義的な監視か、市民に力を与えるエンパワーメントか。
第2の選択…国家主義による孤立か、グローバルな連帯か。
「全体主義的な監視」は「国家による監視と制限」、「エンパワーメント」は「市民の自己決定力」とも言い換えられました。



5月3日が憲法記念日、73年前のこの日に日本国憲法が施行されたことは、おそらく多くの日本人が知っているでしょう。ではその前日に、憲法施行とかかわって行われた重大な出来事はどのくらい知られているでしょうか。
1947年5月2日、「外国人登録令」が天皇の勅令(勅令二〇七)として発布・施行されました。翌日の憲法施行で「象徴」となり、一切の政治権能がなくなる(はずだった)天皇裕仁が、最後の勅令として、駆け込み的に制定した法令です。
「外国人登録令」が目的としたものは何だったか。「台湾人および朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」(第11条)ことでした。
植民地支配していた間は「皇民化政策」で強権的に「日本人」にしておきながら、戦争に負けたとたんに「外国人とみなす」として切り捨て、戦後の補償から排除したのです。
その切り捨ては「当分の間」どころか、1952年4月28日のサンフランシスコ「講和」条約の施行に伴って出されたい「法務府(現法務省)民事局長通達」(52年4月17日)によって、「朝鮮人および台湾人は…すべて日本国籍を喪失する」として固定化されました。
これが今日に続く敗戦後の在日朝鮮人・台湾人の無権利、差別、迫害の元凶です。その出発点が最大の戦争責任者・天皇裕仁の「最後の勅令」であったことを、日本人は歴史の事実として銘記しなければなりません。
その裕仁の「最後の勅令」の被害をもろに受けた1人が、裴奉奇(ペ・ポンギ)さん(写真中)でした。
裴さん(1914~1991)は1943年、朝鮮半島の興南という町で、日本人と朝鮮人の「女紹介人」に「南の島では金が儲かる」と騙され、釜山から下関へ、さらに日本軍の輸送船で鹿児島を経て沖縄に連れてこられました(44年11月)。そして、「赤瓦の家」で日本軍の性奴隷(「慰安婦」)にされました。
敗戦によって裴さんは、言葉も分からず知る人もいない沖縄に放り出されました。行く当てもなく金もなく、夕方になると飲み屋を見つけ酔客に身を売りました。食べ物と寝る場所をえるためです。子守り、野菜売り、空き瓶などをしながら放浪し、なんとか生き延びました。「慰安所より辛かった」と裴さんは振り返っています。
そんな裴さんの地獄の生活は、朝鮮総連の金賢玉さん(写真右は裴さんと金さん)夫妻と出会うことによって、やっと終止符が打たれました。「慰安婦」にされたのも貧乏に生まれた自分の運命だと思っていましたが、金さん夫妻とつきあう中で、そうではなかったことを知らされました。
年をとり、からだを壊し、働けなくなって生活保護を受けようとしたとき、「日本人」でないという国籍の壁に阻まれました(以上、『軍隊は女性を守らない~沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力』参照)。
天皇制帝国日本の植民地支配による貧困の中で騙され、日本に連れてこられ、天皇の軍隊の性奴隷にされ、敗戦とともに放り出され、裕仁の勅令で国籍を奪われ、なんの補償もないまま、再び故郷の地を踏むこともなく、異郷の地(沖縄)で77年の苦難の生涯を閉じました。まさに、天皇裕仁によって、日本の天皇制によって徹底的に踏みにじられた人生でした。
裴さんは、裕仁の死(1989年1月)を聞いたとき、「いっぺんに怒って」、こう言いました。「なんで謝りもせんで逝きよったんか」。「どうすればよかったの?」「そりゃあ謝ってほしいさ」。「謝ってどうするの?」「補償もせんといかんよ」(金賢玉さんの証言映像=注釈より)。
「謝りもせんで」天皇裕仁を死なせたのは、私たち日本人です。
謝らないどころではありません。3日前の「祝日」、「昭和の日」とは何の日でしょうか。かつての「天皇誕生日」、戦前は「天長節」、すなわち裕仁の誕生日です。日本という国は、日本人は、最大の戦争責任者に謝罪もさせなかったばかりか、いまだにその誕生日を「祝日」にして祝っているのです。
天皇制のこの醜悪な事実・実態を、日本人は「知らない」ではすまないのです。
※在日本朝鮮人人権協会が金賢玉さんのインタビュー映像(「裴奉奇さんに出会って」ゆかりの地訪問編・証言編)をユーチューブで公開しています。「在日本朝鮮人人権協会」の検索で視聴できます。5月6日まで限定です。



徳仁天皇が即位して5月1日で1年になります。安倍政権は数々の憲法違反を犯して一連の「代替わり儀式」を繰り広げ(写真)、懸命に天皇制の維持を図ろうとしてきました。
しかし、そうした政府(国家権力)の思惑とは裏腹に、この1年は天皇制がこの社会に必要ない、いや、あってはならないものであることがあらためて証明された1年ではなかったでしょうか。
徳仁天皇は即位以来、何をしたでしょうか。ほとんど記憶に残ることはしていません。それは批判すべきことではなく、逆に歓迎すべきことです。
天皇の影が薄くなった理由の1つは、新型コロナウイルスによって諸行事が中止・延期になったことです。ざっと挙げても、天皇誕生日の一般祝賀、英国訪問、園遊会、全国植樹祭、春の褒章の親授式、そして秋篠宮の「立皇嗣の礼」などが軒並み中止・延期になりました。
これらの行事が中止・延期になって市民生活に何か影響が生じたでしょうか。何もありません。すなわち、天皇の「公務」といわれているものは、市民にとってはなくても困らない、まさに「不要不急」のものだということです。
天皇制が不要であることをよりはっきり示しているのは、コロナ禍に対する徳仁天皇の姿勢です。
4月9日の当ブログで、「徳仁天皇は『ビデオメッセージ』を発してはならない」と書きましたが(https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20200409)、幸い今現在それは発せられていません。
天皇制維持勢力にとってこれは忸怩たるものがあるようです。例えば、「天皇退位有識者会議」(2017年)で座長を務めた御厨貴氏(元東大教授)は、「気掛かりなのは、新型コロナで皇室の存在が希薄になっていることだ」と危機感をあらわにしたうえで、「東日本大震災の時に上皇さま(明仁―引用者)はビデオメッセージを出した。陛下(徳仁―同)も国民に向けて何らかのパフォーマンスを見せてほしい」(4月14日付中国新聞=共同)と切望しています。
しかし、天皇の「ビデオメッセージ」は憲法上多くの問題があり、行われてはならないものです。コロナ禍に対しは、天皇として何もしないことが正解です。それが憲法の象徴天皇制の趣旨であることを改めて銘記する必要があります。
もう1つこの間の注目すべきことは、天皇制に対する「国民」の支持が減退していることです。
徳仁即位1年を前に、共同通信は皇室に関する世論調査を行いました。その結果、天皇に「親しみを感じる」という回答は58%にすぎませんでした(4月26日付地方各紙)。しかもこの数字さえ額面通りにとることはできません。
なぜなら、有効回答が63・3%(3000人に調査票を郵送し有効回答は1899)だったからです。調査票に対し「親しみを感じる」と答えて返送した人(選挙の絶対得票率に相当)はわずか36・7%ということになります。「尊くて恐れ多い」「すてきだと思う」など天皇に対する好意的回答をすべて合わせても、調査票に対するその比率は50・6%にすぎません。すなわち、天皇に対する好意的感情を積極的に回答した人は「国民」の約半分にすぎないということです。
憲法第1条は、天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定しています。世論調査の流動性を考慮しても、今回の共同通信の調査結果は、現在の天皇制がおよそ「国民の総意」に基づいているものではないことを示しているのではないでしょうか。憲法第1条に従えば、徳仁天皇は天皇の地位にとどまることはできないのです。
コロナ禍は、様々な面で、日本が格差と差別の国であることをあらためて私たちに突き付けています。天皇制こそ日本の差別の「象徴」であり元凶です。コロナ感染によって社会の変容が不可避になっているいまこそ、天皇制廃止へ向かう好機ではないでしょうか。

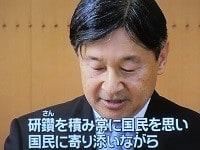
23日の誕生日に際して徳仁天皇が行った初めての「天皇誕生日会見」(21日実施)は、A4判にして8枚半(宮内庁のHP発表をコピー)にもおよぶ長いものでした。これまでの発言と比べ特筆すべきことはないように思えましたが、注意深く読むと、徳仁天皇、というより天皇制の本音・本質が露呈した場面がありました。
徳仁天皇は会見で、「国民に寄り添う」という言葉を4回口にしました。ほかに「被災者に寄り添う」が1回、「(国民に)心を寄せる」が3回。明仁前天皇を賛美し継承するという脈絡で連発したものですが、天皇(天皇制支持勢力)がいかにこの言葉を前面に出そうとしているかが改めて分かります。
では、天皇が「国民に寄り添う」「心を寄せる」とはどういうことでしょうか?
自衛隊のヘリで、入念に準備された「被災地」へ行き、選ばれた「被災者」に会うことが「寄り添う」ことになるのでしょうか。美辞麗句が躍る一方、天皇がどういう意味でその言葉使っているのかは不明です。
ところが、問わず語りにその意味が露見した場面がありました。記者が、「社会の片隅に暮らす人々」として、外国人労働者、在日外国人、外国にルーツを持つ日本人、障害者、LGBTなどを例にあげ、「陛下はこのような人々にどう寄り添い、光を当てていきたいとお考え」かと聞いたのに対し、徳仁天皇はこう答えました。
「本当にこの世界にはいろいろな方がおられ、そういった多様性に対して、私たちは寛容の心を持って受け入れていかなければいけないと常に思ってきました。私も引き続きそのような方々に対する理解も深めていきたいと思っております」
「社会の片隅に暮らす人々」とは記者の差別的表現ですが、それをマイノリティと言い換えると、徳仁天皇はそうしたマイノリティを、「寛容の心を持って受け入れていかねばならない」と言ったのです。
ここには明らかに上下関係があります。「寛容」には「人の過失をとがめない」(国語辞典)という意味があります。徳仁天皇の発言には、マイノリティを何か問題がある人間と見下し、受け入れてやるという上から目線があります。けっして平等ではありません。「生産性がない」発言と紙一重です。しかも徳仁天皇は「私たちは…」とその目線・立ち位置を「国民」にも要求したのです。
ここには天皇(制)の本質が表れているのではないでしょうか。天皇制は明白な身分制度です。現行憲法の下でも皇位継承を世襲にすることなどによって、身分制度としての天皇制が継続されています。
徳仁天皇がいくら「国民に寄り添う」「心を寄せる」を連発しても、それはこの身分制度の頂点に立つ者が、「国民」という下じもの者に対して情けをかける、慈悲の心を持つということにほかなりません。「寛容の心を持って受け入れる」という言葉はその本音を思わず吐露したものではないでしょうか。
平等であるべき人間社会に差別を持ち込み、固定化させる身分制度は廃止しなければなりません。それが人間の歴史の進歩です。したがって身分制度である天皇制は直ちに廃止しなければなりません。徳仁天皇初の「誕生日会見」はその思いを改めて強く抱かせるものでした。