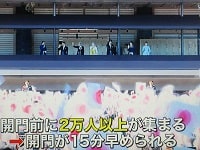衆議院の解散が強行された9日夜、NHKの「ニュースウォッチ9」は、「国会の舞台裏」として解散をめぐる衆議院事務局のあわただしいⅠ日を特集しました。この中で、驚くべき慣習があることを知りました。
この日午前、石破内閣は「解散」を閣議決定しました。それを浜田靖一衆院議院運営委員長は事務局の担当責任者に直接口頭で伝えました。
議運委員長室から出てきた担当者にNHKの記者が「解散ですか?」と聞くと、担当者は「お察しください」と答えました。
NHKによれば「解散詔書(写真左)が本会議場で読み上げられるまで、国会(事務局)では「解散」という言葉は使わないのが暗黙のルール」だというのです。
この件に関する放送はここまででした。この「暗黙のルール」の意味は何か。「解散」は憲法7条による天皇の「国事行為」であり、「詔書」が発せられた以上、その言葉を口にすることは畏れ多い、ということではないでしょうか。
これは「解散」に関する国会の知られざる“天皇タブー”だと思います。
衆院議長によって「解散詔書」が読み上げられると、議員たち(主に自民党議員)は「万歳」を三唱するのが慣例です。首を斬られてなぜ「万歳」なのでしょうか。推測ですが、これも天皇の「解散詔書」に対する敬意の表明ではないでしょうか。「天皇陛下万歳」の衆院解散版です。
天皇と国会の特別な関係はこれだけではありません。
国会議事堂を見学したことがある人はお分かりですが、議事堂正面の階段を上がると、一番先に目に入るのは議事堂の中心に置かれている「玉座」(天皇が来堂した際に座るとされているイス)です。
そもそも国会の開会は「国会招集」ではなく「国会召集」と表記されます。天皇が「召集」するという意味です。「召集令状」と同じです。きわめて不適切な表記ですが、全てのメディア、教科書が疑いもなく使っています。
天皇と国会の不適切な関係の典型は、天皇が開会式に出席し、最も高い壇上から「おことば」を読み上げることです。
衆院議長はその文書を天皇から受け取り、天皇に尻を向けないように前向きで頭を下げたまま後ずさりしなければなりません(写真右)。かつて福永健司衆院議長は体力の衰えからこの後ずさりができないといって議長を辞任しました(1985年1月)。
天皇の国会開会式における「おことば」はもちろん、出席すること自体「国事行為」ですらありません。完全に天皇主権の帝国議会の名残です。
「国権の最高機関」(憲法41条)であるはずの国会と天皇のこの不適切な関係は、現在の日本が明治憲法の天皇制から脱却できていないことを象徴的に示しています。
日本共産党は2016年1月、それまでの方針を転換して天皇が臨席する開会式に出席しました。そのことについての自己批判、方針の再転換はいまだに行われていません。
天皇タブーの悪しき慣例の廃止、天皇の開会式出席の取りやめなど、国会と天皇の不適切な関係を是正することは、憲法の主権在民原則にとって喫緊の課題です。