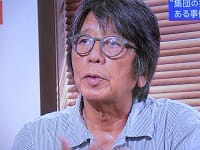


森達也監督の映画「福田村事件」が1日公開されました。NHKクローズアップ現代(8月30日)も取り上げるなど話題になっています。
「福田村事件」とは、関東大震災5日後の1923年9月6日、千葉県東葛飾郡福田村(現・野田市)で、通りがかった香川県三豊郡(現・観音寺市および三豊市)から来た薬売り行商団15人が朝鮮人と見なされ、幼児や妊婦を含む10人(お腹の子を含め)が、在郷軍人などの自警団などによって惨殺された事件です。
知る人の少ない事件ですが、森氏は2001年ころ、慰霊碑建立に関する地元紙の小さな記事に目が留まり、映像化の企画を温めてきたといいます。
優れた映画です。森氏が「キーワード」という「集団心理」の危険性がよく描かれています。しかもたんに流言飛語の問題にせず、「韓国併合」(1910年)、「三・一独立運動弾圧」(1919年)などの背景にも触れています(十分とは言えませんが)。
とりわけ評価したい点を2点挙げます。
1つは、森氏が「朝鮮人と誤って日本人が殺された事件ととらえられるのには強い違和感を覚える」とし、惨殺される直前に行商団のリーダーが村人らに訴えた言葉に「全ての思いを込めた」(8月28日付京都新聞)という、その言葉です(写真右がそのシーン)。
それは、「鮮人ならええんか。朝鮮人なら殺してもええんか」
この言葉(セリフ)がなかったら、森氏の意図に反して、とんでもない曲解を与える危険性があったでしょう。
もう1つは、虐殺された行商団は、被差別部落の人々でした。福田村事件の底流には、朝鮮人差別と部落差別の二重の差別があったのです。事件が埋もれた(フタをされた)のも、「被害者が被差別部落出身で声を上げられなかった」(8月30日付琉球新報=共同)のが大きな理由の1つだと思われます。
この点を映画はきちんと描くのだろうか。それが注目点の1つでした。なぜなら「クローズアップ現代」ではそのことは一言も触れられなかったからです。
杞憂でした。森氏は「水平社宣言」(1922年)も含め丁寧に描いていました。それがこの映画をとりわけ素晴らしいものにしたと言えるでしょう。
優れた映画ですが、疑問を1つ。
森氏は新聞の取材にこう述べています。「社会派と銘打つが、娯楽作品として見てほしい」(8月28日付京都新聞)
どういう意味で「娯楽作品」と言ったのか分かりませんが、強い違和感を禁じ得ません。このテーマが「娯楽作品」になるわけがありません。「娯楽作品」にしてはいけません。
そういえば、こういうシーン(展開)は必要なのかと首をかしげる場面がいくつかありました。それがもし「娯楽作品」を意図した結果だとしたら、不自然・不必要なばかりか、作品の質を落とすものと言わざるをえません。
最後に、森氏のインタビューやメディアの映画評では触れられていないけれど、きわめて重要な“見どころ”を挙げます。
それは、最後の字幕です。そこには次の一節があります。福田村事件の加害者らは、「大正天皇死去による恩赦」によって釈放された。
そうです。「この事件では…自警団員7人に有罪判決が下されたものの、昭和天皇即位による恩赦で釈放された」(畑中章宏著『関東大震災 その100年の呪縛』幻冬舎新書2023年7月)のです。
天皇制国家の朝鮮侵略・植民地支配・植民地戦争の延長線上で起きた虐殺事件。その加害者らが、大正天皇死去(昭和天皇即位)の「恩赦」で釈放された。「福田村事件」の本質を象徴する顛末です。






































